オフショア開発とは?メリット・デメリットと失敗しない進め方を解説


こんにちは。Wakka Inc.のWebディレクターの中垣です。
近年、日本のエンジニアが不足している背景から、オフショア開発が注目されています。
オフショア開発を行う前に、「オフショア開発のメリット・デメリットを把握したい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
オフショア開発には一長一短があるため、それぞれを理解して進め方を検討することが重要です。
本記事ではオフショア開発のメリット・デメリットと失敗しない進め方を解説します。今後、オフショア開発に着手を検討されている方は、ぜひご参照ください。
オフショア開発のうち、Wakka Inc.ではオフショアラボ型開発サービスを提供しています。
ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。
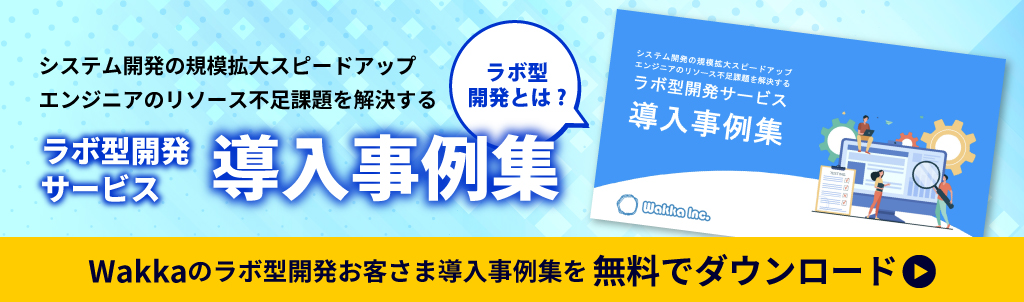
【基礎知識】オフショア開発とは

オフショア開発とは、海外の子会社や企業に開発業務の一部をアウトソーシングする手法です。
継続的に開発リソースを必要とする企業や、国内の開発コストを抑えたい企業に向いています。
オフショア開発の歴史は1970年代の米国にまで遡ります。
当時からインドを主な拠点として、低コストの人材確保や時差を活用した効率的な開発体制が構築されていました。
以前までは、日本は地理的な近接性から中国企業への発注が主流でした。
しかし、昨今は中国における人材不足や人件費高騰により、ベトナムやフィリピンへアウトソースする企業が増えつつあります。
また、総務省の調査では元請け・開発元の企業のうち、48.2%がオフショア開発を導入していることが判明しています。
参照:我が国企業の海外企業活用の実態把握に関する調査|総務省
オフショア開発の意味と国内動向
オフショア(offshore)とは、自分の国から離れた地域を意味する言葉です。
したがって、自国から離れた地域で行う開発はオフショア開発と呼ばれます。
昨今、オフショア開発の利用目的が、コストの削減からリソースの確保に移行しつつあります。
そして現在、海外の優秀なエンジニアを長期にわたって確保する、ラボ型開発が注目されているためです。
オフショア開発が注目されている理由
オフショア開発が注目されている理由は、主に以下の2つです。
- 国内におけるIT人材の不足
- オフショア開発の環境が整備されたこと
国内におけるIT人材の不足
オフショア開発が注目されている理由は、国内におけるIT人材が不足しているからです。
経済産業省の統計により算出された数字では、人材の伸び率が低かった場合、2030年に約79万人ものエンジニアが不足すると指摘されています。
特に不足しているのは、先端技術に関する知見のあるエンジニアや、現場で即戦力としてプロジェクトに参画できるエンジニアです。
また、世界全体では約2137万人もの人材が存在するとされています。
国内で不足しているリソースを補うために、海外へ目を向けるのは自然な流れです。
なお、エンジニア不足の原因とその打開策を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
オフショア開発の環境が整備されたこと
オフショア開発が注目される2つ目の理由は、環境が整備され中小企業でも海外展開が容易になったからです。
以前のオフショア開発では、自社にて現地へのコネクションを確立する必要があり、多くのコストがかかりました。
また、物理的に離れた地域でプロジェクトを推進するため、タイムラグの発生や管理の難しさなどの障壁がありました。
しかし近年は、インターネットが普及したり、オフショア開発の支援サービスが登場したりしたことで、中小企業でも容易にグローバル展開ができるようになったのです。
このように、国内でのIT人材不足と障壁が取り除かれたことで、多くのIT企業がオフショア開発に注目しています。
日本が進出しているオフショア開発先の国
オフショア開発が注目されはじめた当初は、開発費を大きく抑えられることもあって中国が人気の開発先国でした。
しかし中国の経済成長とともに、現地の人件費が高騰したこともあり、想定よりコストを抑えにくくなりました。
これに伴い、オフショア開発の進出先を中国から別国へ移行する動きが活発化しています。
中でも注目されているのが、発展途上にある東南アジアの国々です。
現在、多くの日本企業が進出している開発先国は、下記の5カ国が挙げられます。
| 国名 | 特徴 |
| ベトナム | ・日本語教育が盛んで、日本との交流が活発な国 ・IT人材が豊富 |
| バングラデシュ | ・英語が普及しているのでコミュニケーションがしやすい |
| ミャンマー | ・勤勉な人材が多く、日本企業との協業実績もある |
| フィリピン | ・英語が公用語なのでコミュニケーションがしやすい ・日本企業の多くが進出している |
| インド | ・オフショア開発の実績がトップクラス ・IT人材が豊富 |
参照:【2024年最新】オフショア開発の人月単価の目安は?最新動向から今後の見通しを解説|Wakka、IT人材に関する各国比較調査結果報告書|経済産業省
最初に挙げたベトナムは、東南アジアの中でも人気の高いオフショア先です。
ベトナムは政府が主体となってIT教育に力を入れているため、優秀なエンジニアが多く、さまざまな企業から注目されています。
オフショア開発のメリット

オフショア開発の代表的なメリットとして、以下のものが挙げられます。
- 開発コストの削減
- 時差を活用した開発体制
- 開発リソースの柔軟な調整
- 開発スピードの向上
- 国内リソースのコア業務への集中
- IT人材の確保
それぞれのメリットについて、順番に解説します。
開発コストの削減
オフショア開発の最大の魅力は、開発コストの削減ができることです。
先述したように、国内ではIT人材の需要増加と人手不足が重なり、人件費が高騰しています。
経済産業省の調査では、国内におけるIT人材の平均年収が約400~600万円といわれています。
オフショア開発は国内開発よりも人件費を抑えられる点から、安いコストでシステムの開発が可能です。
また、オフショア先のリソースを活用するだけで開発体制を強化でき、新たに人材や開発スペースを確保する必要がありません。
そのため、開発体制の拡大を国内で行う場合と比べて、低コストで進めることができます。
参照:我が国におけるIT人材の動向|経済産業省、IT人材に関する各国比較調査結果報告書|経済産業省
時差を活用した開発体制
オフショア開発のメリットは、時差を活用した開発体制を構築できることです。
オフショア開発の歴史で紹介したアメリカとインドでは、10時間30分の時差があり、アメリカが夜間稼働していない時間帯に昼間のインドが開発を進めるという体制の構築が可能です。
日本の場合、オフショア先となるアジア各国と距離が近い影響もあり、アメリカほど大胆な時差の活用は困難です。
しかし、そのような状況でも2~3時間ほどの時差があれば十分活用できます。
例えば、日本と現地のエンジニアの勤務時間が重なる時間帯にコミュニケーションを取り、日本側の勤務終了後も現地のエンジニアが2〜3時間ほど稼働することで、国内のみの開発体制と比べてより効率的な体制を構築できます。
時差の活用は、国内のエンジニアが稼働できない時間帯でも作業を進められるうえに、十分なリソースの確保も可能です。
そのため、着手できる開発プロジェクトの幅が広がります。
開発リソースの柔軟な調整
オフショア開発は開発リソースを柔軟に調整できる点もメリットです。
オフショア開発を実施すれば、オフショア先と自社双方のリソースを開発に活用できます。
自社にはない人材や設備を活用しながら開発を進めることにより、自社単体では実現できないプロジェクトにも着手しやすくなります。
また、開発を通じてオフショア先のノウハウや技術を自社に取り入れることにより、自社のさらなる発展にもつなげられるのもオフショア開発の強みです。
適切に活用すれば、自社の開発体制を強化できるだけでなく、国際的なマーケットでの競争力の強化も実現できます。
開発スピードの向上
オフショア開発は、開発スピードの向上が期待できる点も魅力です。
時差を活用することで、国内だけで開発する場合よりも長い時間帯で作業を進めることが可能となり、場合によっては24時間体制に近い開発も実現できます。
さらに人件費を抑えたうえで多数のエンジニアを動員することにより、作業も分担できるので、開発スピードが向上し、納期の短縮を実現しやすくなります。
自社だけでは長期化しやすいプロジェクトでも、オフショア開発によって開発スピードを向上すれば対応が可能です。
国内リソースのコア業務への集中
オフショア開発は、国内リソースをコア業務に集中するきっかけになります。
開発に伴うさまざまな作業をオフショア先に委託すれば、自社はコア業務に集中しやすい体制の構築が可能です。
当然、自社のリソースを開発に割く必要がなくなるため、新規の開発プロジェクトを抱えることで生じるコア業務への影響を抑制できます。
リソースを国内に集中できれば、企業の競争力を保持できるうえに、新たなビジネスチャンスにも対応できるでしょう。
IT人材の確保
オフショア先を通じてIT人材を確保できる点も、オフショア開発のメリットです。
オフショア開発は優れたIT人材がいるチームを、そのまま自社の開発に取り入れられます。
採用などのプロセスを経る必要がないため、スムーズな人材の確保が可能です。
経産省調査によると、少子化・高齢化が進む日本のIT人材の平均年齢は30代後半といわれています。
また、今後はさらに平均年齢が高まってくると予想されており、IT人材の確保の重要性はより一層高まっているのが現実です。
しかし、アジアのオフショア先では依然として労働人口が増加している国も多く、ベトナムでは若い世代のIT人材が多く活躍しています。
さらに、ベトナムのようなIT系人材の育成を国策として掲げている国では、義務教育から大学・専門学校まで充実したIT教育を提供しており、幅広い世代の優秀な人材が多いというメリットがあります。
IT人材の確保に悩んでいる企業にとって、オフショア開発は打開策となる手法です。
参照:Vietnam IT Market Report 2023

オフショア開発のデメリット
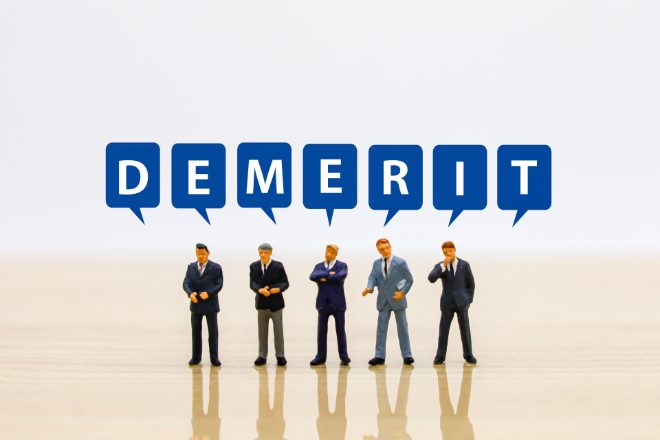
一方、オフショア開発のデメリットとして、以下が挙げられます。
- 価値観や文化の違い
- 言語によるコミュニケーションの課題
- 品質管理の難しさ
- セキュリティリスク
- 契約・法制度の違い
- 時差による連携の難しさ
- 仕様変更への対応
オフショア開発はメリットが多い一方で、注意すべきデメリットもあるものです。
それらを事前に把握しておくことで、開発におけるリスクを回避できます。
価値観や文化の違い
やはり国によって文化や価値観は異なります。
そのため、オフショア開発を実施すると、さまざまな場面で考え方や慣習の違いを実感する場面は少なくありません。
特に日本は、事細かに言語化せず文脈や前後関係で察するようなコミュニケーション文化といわれています。
しかし、国外で同じコミュニケーションが通じるとは限りません。
日本人同士では明文化しなくても察していたことが、オフショア先のエンジニアには伝わらない状況が発生することは十分に想定されます。
また、オフショア開発を始めた直後は、まずオフショア先に自社の開発プロセスの理解を得ることから始めましょう。
特に導入初期には通常の開発委託以上に、コミュニケーションコストが発生することを念頭に置くことをおすすめします。
言語によるコミュニケーションの課題
オフショア開発では先程の文化の違いに加えて、言語の違いも障壁となりがちです。
特に母国語が通じない相手の場合、会話に消極的になったり、発言が少なくなったりする方も少なくありません。
しかし、言語の壁を意識しすぎて現地のエンジニアとのコミュニケーションを控えめにしてしまうと、信頼関係の構築が遅れ、開発に関する重要な情報の伝達漏れが起きやすくなります。
コミュニケーションの齟齬を放置すると、開発が遅延したり、予期せぬトラブルが発生したりする事態になりかねません。
そのため、初めてのオフショア開発では、現地での豊富な経験を持つ人材とともに拠点を設立することが重要です。
コミュニケーションの課題はさまざまなリスクを回避するうえでも、解決しなければなりません。
「日本語や英語は利用できるか」「ブリッジSEは設置する必要があるか」など、さまざまな観点から対応策を検討しましょう。
品質管理の難しさ
オフショア開発は品質管理が難しい点に注意しなければなりません。
オフショア開発の経験者に話を聞くと、「開発の品質管理に苦労している」「品質が良くないのでオフショアから撤退した」という声が少なくありません。
確かに、細かい部分の仕様が伝わらずに想定したものとは違う内容で納品されたり、納期が遅延したりすることも一定数発生してきます。
このようなケースは、安い人件費だけを求めて仕事を丸投げする場合に特に起きやすいですが、他にも要件定義や管理体制の不備など、さまざまな要因が関与することがあります。
オフショア先と丁寧にコミュニケーションを取れば、品質に問題が生じるリスクは格段に減らせます。
そのため、オフショア先の企業は欠かせないパートナーであるという意識を持って、日々の開発定例などで開発の背景や全体スケジュール、品質の目線合わせを続けることが大切です。
理想的な品質管理を実現するには、適切な開発プロセスや品質管理体制を構築する必要があります。
品質管理チームを構築し、開発の初期段階からプロジェクトに参加させるなど、早期から品質管理を徹底すれば、クオリティの維持が可能です。
セキュリティリスク
オフショア対策を実施する際はセキュリティリスクに注意しましょう。
開発を委託する国によっては、セキュリティに対する認識が日本と異なる場合があります。
また、オフショア先の企業のリソースが不足している事情から、十分なセキュリティ対策が実施されていないケースも少なくありません。
加えて、オフショア開発は自社とオフショア先で情報やシステムなどを共有することもあります。
適切なセキュリティ対策を講じないと、自社の機密情報が漏洩するリスクが高まります。
セキュリティリスクを回避するためにも、機密情報の取り扱いやセキュリティ対策について、オフショア先と入念に協議しておくことが重要です。
契約・法制度の違い
国外に開発を委託するとなれば、契約や法制度の違いを意識しなければなりません。
国によっては日本とは異なる税制度があったり、その国ならではの法手続きを行ったりすることが想定されます。
また、日本と異なる法律制度の理解が不十分なまま契約を締結すると、オフショア先との間でトラブルが発生するリスクがあります。
契約・法制度によるトラブルはオフショア開発の成否を左右するものです。
オフショア先の国の法制度に詳しい専門家からアドバイスを得るなど、法的なリスクを回避するように心がけましょう。
時差による連携の難しさ
時差は開発に活用できる一方、連携を困難にする可能性があります。
例えば開発途中でトラブルが発生したり、プロジェクトの軌道修正をしたりする際に緊急で連絡を取りたくても、時差の影響で連絡が取れなくなるケースは珍しくありません。
オフショア先によっては勤務時間外は連絡を一切取れない場合もあり、緊急時の対応が遅れるリスクが生じます。
また、時差を考慮せずにスケジュールを進行すると、開発の遅延が生じた場合に納期を守れなくなるリスクが高くなります。
自社とオフショア先が円滑に連携するためには、時差を考慮した体制作りが不可欠です。
緊急時の対応についてもマニュアル化し、互いに対応策を共有しておけば、トラブルが発生しても開発への影響を最大限抑えられます。
仕様変更への対応
オフショア開発は仕様変更の対応が難しい点にも注意が必要です。
物理的な距離や時差がある以上、オフショア開発は進捗の管理が困難です。
加えて、オフショア先以外にもさまざまな企業が関わっている状況だと、プロジェクト自体が複雑化し、管理が煩雑になります。
そのため、開発しているプロダクトに仕様変更が生じた場合、対応しにくくなる恐れがあります。
最悪な場合、スケジュールに大きな狂いが生じ、納期に遅れる事態になりかねません。
オフショア開発を実施する際は、仕様変更が生じる事態も想定して開発体制を整えましょう。
また、オフショア先とのコミュニケーションを密に行い、プロジェクトに対する共通認識を擦り合わせておくことも重要です。
オフショア開発が向いているプロジェクト・向いていないプロジェクト
オフショア開発はコスト削減や人材確保など多くのメリットがある一方で、コミュニケーションや品質管理、セキュリティ、法制度の違いなど、さまざまな課題も存在します。
プロジェクトの特性を考慮し、適切に判断することが重要です。
一般的に、以下に当てはまるプロジェクトはオフショア開発に適していると考えられます。
- 仕様が明確で変更が少ない
- 大規模で人手が必要
- 開発プロセスや成果物の管理がしやすい
- 繰り返し性の高い定型業務や保守・運用
- コスト削減が最重要課題
具体的には、基幹システムの新規開発、Webサービスのバックエンド開発、ECサイト構築、CMS導入などが挙げられます。
一方で、以下のようなプロジェクトはオフショア開発には不向き、又は慎重な検討が必要と考えられます。
- 仕様が不明確で頻繁に変更が発生する
- 高度な専門知識を要し、属人性が高い
- リアルタイムでの密なコミュニケーションが不可欠
- 機密情報やセキュリティ要件が非常に厳しい
- 短期間での開発が求められる
具体的には、新規事業のMVP開発、組み込み系システム、UI/UXデザインの擦り合わせなどが挙げられます。
プロジェクトの特性を十分に理解し、適切なパートナー選定、綿密なコミュニケーション計画、そして明確な進捗・品質管理体制を構築することが不可欠です。
オフショア開発におけるブリッジSEの役割

オフショア開発をスムーズに進めるうえで、重要な役割となるのがブリッジSEです。
ブリッジSEは、オフショア開発において日本と海外の開発チームをつなぐ役割を担当します。
文字通り、橋渡しを担当するブリッジSEの業務は以下の通りです。
- コミュニケーションの円滑化
- プロジェクトの進捗管理
- 技術的なサポート
以下ではブリッジSEの役割について、それぞれ順番に解説します。
コミュニケーションの円滑化
委託先となる海外の企業と委託元のコミュニケーションを円滑化することは、ブリッジSEの主な役割です。
ブリッジSEが委託先の国の言語・文化・習慣などを把握してサポートすると、チーム同士の円滑なコミュニケーションが実現します。
その結果、コミュニケーションの誤解や行き違いが減少し、開発スピードの向上が期待できます。
また、自国の文化や習慣を理解してくれるスタッフの存在は、委託先の開発チームのモチベーション向上にも貢献するはずです。
プロジェクトの進捗管理
ブリッジSEにとって、プロジェクトの進捗管理は重要です。
オフショア開発に限らず、作業上のミスにより進捗の遅延は起こり得るものです。
特にオフショア開発では、物理的な距離や時差があるため、遅延への対応が遅れるリスクが高くなります。
そのため、ブリッジSEは委託先と綿密にコミュニケーションを取り、進捗を徹底的に管理することでプロジェクトの遅延を防止します。
また、こまめに進捗を管理するだけでなく、委託元へ定期的に報告したり、新たな要望を委託先に伝えたりすることもブリッジSEの役割です。
技術的なサポート
SEである以上、ブリッジSEも技術的なサポートを実施します。
ブリッジSEは委託先が開発したプロダクトの品質管理も担当しますが、その際に機能の検証や修正の指示も行う場面も少なくありません。
機能の検証や修正の指示は、技術的な知見がなければできないことであるため、ブリッジSEにもさまざまな知識やスキルが求められます。
オフショア開発のリスクを軽減する進め方

オフショア開発は優秀なIT人材を確保でき、さらに開発にかかるコストを全体的に抑えられる点が魅力です。
しかし、オフショア開発の進め方を理解していないと、オフショア開発のメリットを十分に活かしきれません。
オフショア開発で失敗しないための進め方は、以下の通りです。
- 最終的な成果物・自社の課題を明確にする
- オフショア開発企業を比較
- 開発方法・管理体制を決定する
- 進捗状況・品質を管理
なお、オフショア開発では法律に関する知識が求められる場面もあります。
特に委託契約はトラブルを避けるうえでも、あらかじめ法律の専門家の協力を仰ぎましょう。
手順1.最終的な成果物・自社の課題を明確にする
まずは「アプリの実証実験を完了させる」「プロダクトの特定の機能を完成させる」など、最終的な成果物・自社の課題を明確にしましょう。
国内でプロジェクトを進めるとしても最終的な成果物・自社の課題を明確にするのは重要です。
自社の課題が明確でないと、システム開発の目的や最終的な成果物も決まらずプロジェクトが成功しにくくなるからです。
また、オフショア開発は言語や文化の違いから意思疎通が難しくなる可能性もあるため、成果物・課題が明確になっていない場合、委託先の企業との連携もより難易度が上がります。
より密な連携を取るうえでも、成果物・自社の課題を明確にして、オフショア先の開発チームに伝わるように準備しておきましょう。
手順2.オフショア開発企業を比較
次にオフショア開発企業を比較して、委託する企業を選定します。
オフショア開発企業を選ぶ際は、自社の課題が解決できるか、開発の目的にあっているかなどを確認します。
特に確認すべきなのが相手の開発実績です。
企業によって得意な開発プロジェクトが異なるため、自社が開発したいものと近い開発実績があるかを確認しましょう。
自社の近い分野を扱っている開発会社であれば、ノウハウを共有しやすくなります。
また、複数社から見積もりを取得することで、自社に適した企業を見つけやすくなります。
手順3.開発方法・管理体制を決定する
次に開発方法・管理体制を決定します。
主な開発方法は、以下の2種類です。
| ウォーターフォール開発 | 仕様を明確にしてから上流工程から順番に開発を行う |
|---|---|
| アジャイル開発 | 機能ごとに開発プロセスを細分化したうえで開発を行う |
上記の開発方法はプロダクトの規模や内容によって使い分ける必要があります。
当然、開発方法が変われば開発プロセスも大きく変わるので注意しましょう。
また、管理体制として下記の方法があります。
- 継続的にリソースを確保するラボ型
- 成果物を納品する請負型
- 開発を依頼する企業と現地のベンダーとの間に入る仲介型
どの開発方法・管理体制が適しているかは、開発の目的や成果物によって変わるため、それぞれのメリットとデメリットなどを比較し、自社に合った方法があるか検討しましょう。
手順4.進捗状況・品質を管理
開発方法・管理体制まで決定したら、次は進捗状況と品質を管理します。
オフショア開発で失敗しないためには、プロジェクトの進捗管理が重要です。
なぜなら、異なる文化・習慣や言語によるコミュニケーションの難しさ、そして時差の存在により、国内開発と比べて業務管理がより複雑になるためです。
また、委託元と委託先で成果物に対する認識が異なるケースも珍しくありません。
業務目標とのズレが発生する可能性があると想定しておく必要があります。
進捗・品質管理が適切に行われていないと、作業遅延やミスに気づくのが遅くなり、人件費の増大につながります。
作業進捗を適切に行うには、業務の目標設定と現状把握を徹底しましょう。
進捗管理のポイントをより詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
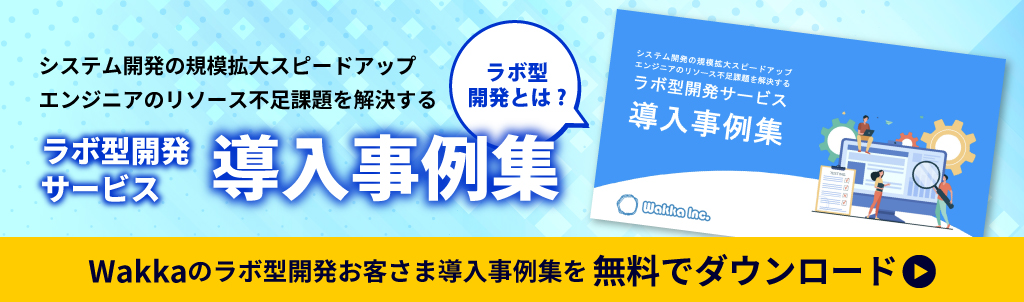
オフショア開発を成功させるための4つのポイント

オフショア開発を成功させるためのポイントは、下記の4つがあります。
- チームの一員として稼働してもらう
- プロジェクトのコスト管理を怠らない
- 発注前に準備を万全にしておく
- プロジェクトに適した開発企業を選定
順番に詳しく解説します。
また、オフショア開発で起こりがちなトラブル事例とその対応策を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

チームの一員として稼働してもらう
オフショア開発を行う際は、オフショア先にチームの一員として稼働してもらう意識を持たせるように心がけましょう。
オフショア開発でよく見られる課題の一つに、現地エンジニアの稼働率が想定よりも低くなるケースがあります。
そのため、現地のエンジニアに、自社のチームの一員としてしっかりと稼働してもらうことがポイントです。
チームの一員として稼働してもらうには、現地のベンダーやブリッジSEに丸投げせずタスクを適切に分配しましょう。
日本からのタスクが少ない場合は、現地エンジニアのやることがなくなり、費用対効果が減少してしまいます。
チームの一員として稼働してもらえるように、国内で業務をする以上に細かくコミュニケーションを取り、関係性を築きましょう。
プロジェクトのコスト管理を怠らない
2つ目のポイントはプロジェクトのコスト管理を怠らないことです。
オフショア開発でありがちな失敗として、開発コストが想定以上に膨らむことがあります。
開発のスケジュール管理などに問題があると、開発期間が伸びてしまい、納期に間に合わなくなる恐れがあります。
特にラボ型開発のように一定期間エンジニアを確保する契約の場合、開発期間が延長されると追加で費用がかかり、想定以上のコストが発生しかねません。
費用対効果を減少させないためにも、スケジュールをコントロールし、コスト管理を徹底しましょう。
発注前に準備を万全にしておく
3つ目のポイントは開発の発注前に準備を万全にしておくことです。
オフショア開発では、国内での業務と違って業務管理の難易度が高まります。
また、言語や考え方の違いにより、細かなニュアンスが伝わりづらく、委託元とオフショア先との間でコミュニケーションがスムーズに進まないことも珍しくありません。
コミュニケーションの齟齬を放置すると、開発途中でトラブルが発生し、スケジュールの遅延につながる可能性があります。
要件定義や詳細設計を日本でしっかり行い、開発にかかる時間の見積もりも徹底的にしましょう。
起こりうるミスを想定して、対処法も考えておくと開発をスムーズに進められます。
プロジェクトに適した開発企業を選定
4つ目のポイントはプロジェクトに適した開発企業を選定することです。
適切な開発企業を選定することで、プロジェクトの成功率が高まり、開発をよりスムーズに進めることができます。
当然、開発企業によって、得意分野は異なります。
AI開発に長けた企業もあれば、アプリ開発に特化した企業もあるため、オフショア開発を行う際はプロジェクトに合わせて開発企業を選択しましょう。
プロジェクトに適していない企業を選ぶと開発期間が長引いたり、品質が想定より低くなったりする恐れがあります。
見積もりを依頼する際は、企業の開発実績や活用できるノウハウ・設備などを確認しましょう。
なお、オフショア開発の経験が少ない企業は、優れた技術力があっても円滑な連携が難しくなる可能性があります。
特に日本語や英語に対応できない開発企業の場合、別途ブリッジSEの手配が必要です。
オフショア先となる開発企業の選択は、プロジェクトのプロセスや人員配置にも大きな影響を与えます。
現地の企業に詳しい専門家のアドバイスを仰ぐなどして、慎重に吟味しましょう。
オフショア開発の成功事例:ベトナムでラボ拠点を設立
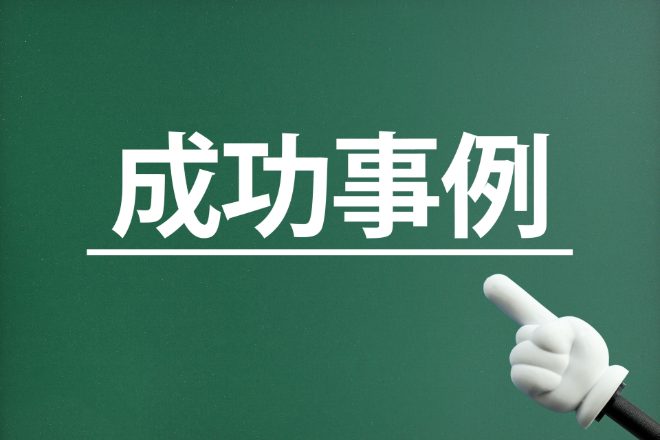
ベトナムでラボ拠点を設立し、オフショア開発で成功したLaichi.LLCの事例を紹介します。
Laichi.LLCはWebサイト制作やWebアプリ開発などを行っている企業です。
日本のグループ会社において、人手不足により優秀なエンジニアの採用が困難であったことから、海外のエンジニア人材に着目しました。
そこで、充実した開発環境を備えるベトナムにラボ拠点を設立したのです。
ベトナムではオフショア開発の支援拠点を持つ専門家と相談しながら、業務フローを作成しました。
現地でエンジニアの採用を進めながら、受託業務を徐々に増やしていき、ラボ拠点の運営に成功した事例です。
参照:成長企業が語る、海外子会社設立の魅力。ジーピーオンライングループの多様な人材が紡ぐ、次の成長の一手とは?
メリット・デメリットを理解しオフショア開発を成功させよう

オフショア開発は、時差を活用した開発やエンジニア不足の補完といったメリットがある一方で、コミュニケーションと品質管理の難しさというデメリットも抱えています。
オフショア開発に慣れないうちは、国内のプロジェクトよりも入念に計画を行う必要があります。
また、現地ベンダーへの業務の丸投げは適切な意思疎通を妨げ、オフショア開発のメリットを活かせないだけでなく、想定している成果も十分に得られなくなります。
オフショア開発では信頼できるパートナーを見つけ、必要な情報を集められるかが成功の鍵となります。
オフショア開発をスムーズに進めるなら、Wakka Inc.のサポートをご検討ください。
Wakka Inc.は多数のオフショア開発の実績があるうえに、スタートアップ支援・長期プロジェクト支援両方に対応できます。
さらに短期間で進めるオフショア開発や、ベトナムでの法人設立の支援も行っているなど、多角的なサポートを実践しています。
さまざまな関連資料もご用意していますので、この機会にぜひお問い合わせください。
ラボ型開発のご相談はWakka Inc.まで
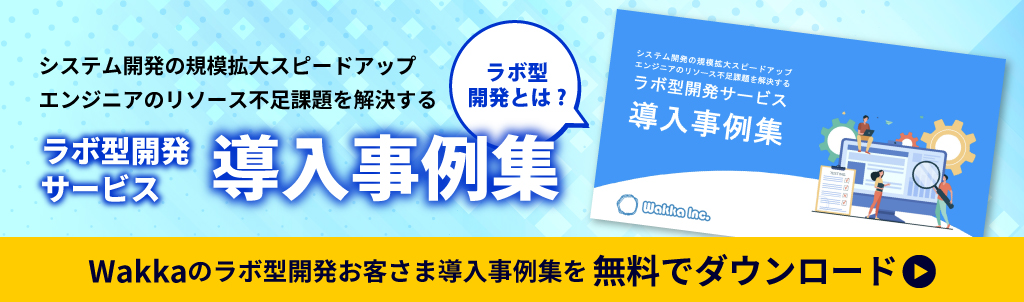

WebメディアでPGから管理職まで幅広く経験し、Wakka Inc.に参画。Wakka Inc.のオフショア開発拠点でラボマネジャーを担当し、2013年よりベトナムホーチミンシティに駐在中。最近では自粛生活のなかでベトナム語の勉強にハマっています。

















