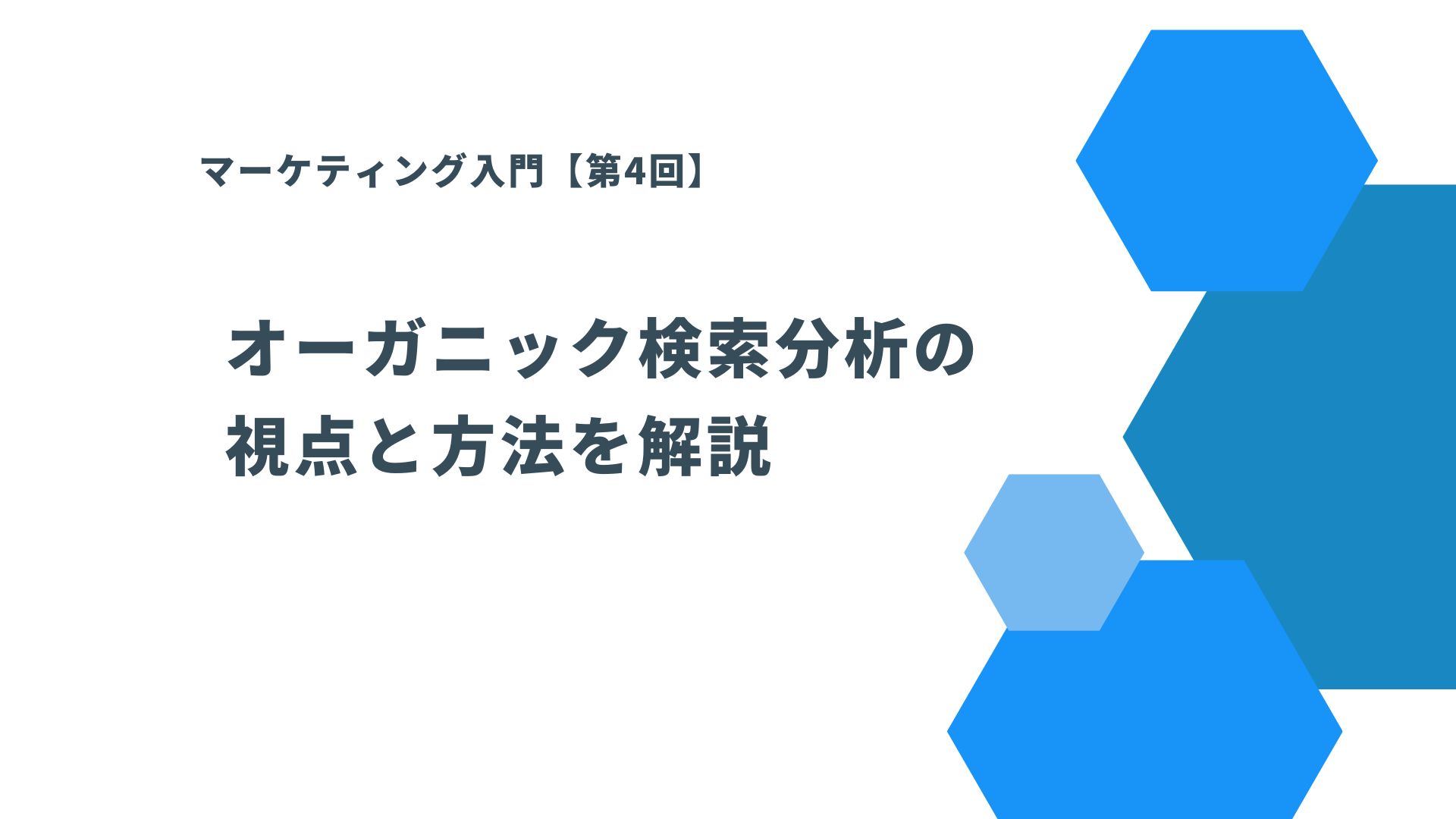食品サブスク:BtoB市場における多様なビジネスモデル


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
近年注目を集めている食品サブスクリプションサービス(以下、食品サブスク)は、ビジネスモデルが多様化しています。
そのため、どのモデルが自社に適しているのか、どのように導入すれば成功するのか、悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、食品サブスクの多様なビジネスモデル・市場規模・メリットやデメリットなどについて解説します。
また、食品サブスクの事例も紹介するので、自社に最適な食品サブスク戦略を構築するためのヒントにしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
食品ECのトレンド調査
食品ECサイトの構築/改修を
食品サブスクとは

本章では、食品サブスクの基本的な知識について解説します。
収益構造や市場規模を理解するための参考にしてください。
食品サブスクの収益構造
食品サブスクの収益構造は、大きく分けて以下の2種類に分類できます。
| 収益構造 | 説明 | 例 |
| 定期購入型 | 顧客が定期的に一定料金を支払うことで、商品を受け取るモデル。 顧客数と継続率が収益に直結する。 | 毎月一定量の野菜セットを配送するサービス、定期的にコーヒー豆を届けるサービスなど |
| ポイント制 | 顧客がポイントを購入し、そのポイントを使って商品と交換するモデル。 ポイントの販売数と利用率が収益に影響する。 | 一定量のポイントを購入し、好きな商品と交換できるサービスなど |
いずれのモデルも、顧客の継続率を高めることが収益最大化の鍵となります。
そのため、顧客満足度を高めるための工夫が不可欠です。
食品サブスクのビジネスモデル
食品サブスクのビジネスモデルは、さまざまなニーズに対応するため、非常に多様化しています。
代表的なモデルをいくつか紹介します。
| ビジネスモデル | 説明 | メリット | デメリット |
| 定期宅配型 | 顧客のニーズに合わせた商品を定期的に宅配するモデル。 ミールキットや食材セットなどが該当。 | 顧客の囲い込みが容易で、売上予測が立てやすい。 | 顧客の嗜好変化への対応が重要。 在庫管理が必要。 |
| キュレーション型 | 専門家が厳選した商品を定期的に届けるモデル。 ワインやコーヒー豆などが該当。 | 付加価値が高く、顧客ロイヤルティを高めやすい。 | 商品選定に専門知識が必要。 仕入れコストが高い可能性がある。 |
| カスタマイズ型 | 顧客が自由に商品を選べるモデル。 顧客の選択肢が多く、柔軟な対応が求められる。 | 顧客満足度が高く、リピート率向上につながる。 | システム構築が複雑化し、在庫管理が困難になる可能性がある。 |
| 組合せ型 | 複数のモデルを組み合わせたモデル。 (例)定期宅配にカスタマイズ要素を加える | 顧客ニーズへの対応力が高く、顧客層を広げやすい。 | システム構築が複雑化し、運用コストが高くなる可能性がある。 |
自社が持つ強み・リソース・ターゲット顧客層などを考慮し、最適なビジネスモデルを選択することが重要です。
食品サブスクは複数のモデルを組み合わせることで、より多くの顧客層を獲得できる可能性も秘めています。
食品サブスクの市場規模

食品サブスク市場は、近年急速に拡大しています。
以下の資料を見てみましょう。
上記の資料で分かるように、サブスクや食品関連のECサイトの市場規模は年々拡大しており、今後も成長を続けることが予想されています。
生鮮食品は品質の維持など課題が多いため、ECサイトやサブスクにおいては難易度が高い分野として認識されていました。
しかし、昨今は技術の発展や、多くの企業の努力もあり、さまざまな形態の食品サブスクが実現しています。
参考:サブスクリプションサービス市場に関する調査を実施(2023年)|株式会社矢野経済研究所
食品サブスクの4つのメリット

BtoB企業が食品サブスクを導入するメリットは多岐に渡ります。
特に以下の4つのメリットは、事業成長に大きく貢献するものです。
- 売上が安定化する
- 売り上げの予測が容易にできる
- 入荷量を調整できる
- 新商品を投入しやすい
それぞれのメリットについて、順番に解説します。
売上が安定化する
食品サブスクは、安定的な売上を確保できるビジネスモデルです。
顧客が契約を継続する限り、毎月安定したストック収益が見込めるからです。
季節変動の激しい食品業界においては、安定した売上は企業の経営基盤を強化するうえで非常に重要です。
売上の予測が容易にできる
食品サブスクは、顧客数と契約内容に基づいて、将来の売上を容易に予測できます。
精度の高い売上予測は、事業計画策定や投資判断にも役立ちます。
さらに在庫管理や生産計画を効率的に立てられるようになり、無駄な在庫を抱えるリスクの軽減が可能です。
また、資金繰り計画もスムーズに行えるため、安定した経営を実現できます。
入荷量を調整できる
食品サブスクは契約状況を把握することで、入荷量を適切に調整できます。
需要予測に基づいた発注が可能となるため、在庫ロスを最小限に抑え、コストの削減が可能です。
また、需要の変動にも柔軟に対応できるため、市場の変化に迅速に対応した事業運営を実現できます。
食品業界特有の鮮度管理や賞味期限の問題にも対応しやすくなります。
新商品を投入しやすい
定期的に商品が届く特性を活かし、新商品を試してもらえる機会を増やせる点も食品サブスクのメリットです。
食品サブスクは既存顧客へのアプローチが容易なため、新商品のテストマーケティングやフィードバック収集が効率的に行えます。
顧客の嗜好を把握しながら新商品開発を進めることで、顧客満足度を高め、リピート率の向上につなげられます。
積極的な新食品の投入は、顧客のリピート率の向上にもつながる重要な施策です。
WaGAZINE読者さま限定!
食品ECのトレンド調査
食品ECサイトの構築/改修を
家庭・BtoC向け食品サブスクの事例6選

本章では、家庭・BtoC向け食品サブスクとして、以下のような事例を紹介します。
紹介する事例は以下の通りです。
- Oisix|品質の高さで話題の食材の宅配サブスク
- snaq.me|独自のアルゴリズムを使ったおやつ特化のサブスク
- AIR SPICE|きめ細かいサービスで初心者でも使いやすい
- POTLUCK|手軽な操作で手作り料理を受け取れる
- Fun Fan chikuha!|限定商品やキャンペーンで集客に成功
- Otomoni|カスタマイズ機能などで顧客ニーズに対応
家庭・BtoC向けの食品サブスクを検討する際の参考にしてください。
Oisix|品質の高さで話題の食材の宅配サブスク
Oisixは食品・ミールキット・総菜などを提供する家庭向けの食品宅配サブスクとして、高い人気を集めています。
質の高い食材を扱うだけでなく、配送希望日や納品先の変更に柔軟に対応できるなど、使いやすさにもこだわっている点が特徴です。
参照:Oisix公式サイト
snaq.me|独自のアルゴリズムを使ったおやつ特化のサブスク
snaq.meは「おやつ」に特化したお菓子専門の食品サブスクです。
ユーザーの好みに合わせ、独自のアルゴリズムで選んだ最適なお菓子の詰め合わせを提供しています。
ただユーザーの好みに合わせるだけでなく、バリエーションを増やすために、あえてスタッフが選んだおすすめのお菓子も入れるなどさまざまな工夫を行っています。
参照:snaq.me公式サイト
AIR SPICE|きめ細かいサービスで初心者でも使いやすい
AIR SPICEはスパイスを専門的に扱う食品サブスクです。
さまざまな味のカレーに利用できる本格的なスパイスを扱っており、多くのファンを獲得しています。
AIR SPICEは初心者向けにきめ細かいサービスを展開しており、レシピやエッセイなどで調理に必要な情報を提供しています。
そのため、初めてスパイスを購入するユーザーでも手軽に利用できる点が魅力です。
POTLUCK|手軽な操作で手作り料理を受け取れる
POTLUCKはさまざまな飲食店と連携し、手作り料理を事前予約してテイクアウトできるサブスクです。
POTLUCKは簡単な操作で料理のテイクアウトができるため、多忙なユーザーでも手軽に利用できます。
加えて、利用頻度に合わせてプランを設定しているため、無駄な出費を抑えられます。
参照:POTLUCK公式サイト
Fun Fan chikuha!|限定商品やキャンペーンで集客に成功
Fun Fan chikuha!は石川県能登半島にある酒造が展開している、日本酒に特化した食品サブスクです。
季節に合わせた良質な日本酒だけでなく、能登半島にちなんだおまけも提供するなど、独特なサービスが人気を集めています。
Fun Fan chikuha!はローカル色が強いサービスに加え、限定商品やキャンペーンを積極的に実施しています。
そのため、ほかの食品サブスクとは異なる個性を確立できている点が特徴です。
Otomoni|カスタマイズ機能などで顧客ニーズに対応
クラフトビールに特化したOtomoniは、日本全国・世界各地から厳選した銘柄のビールを提供しているサブスクです。
Otomoniはビールに慣れていないユーザーでも利用できるように、1本単位で好みのビールをカスタマイズできる機能を搭載しています。
さらに「苦手なもの」に登録しておけば、好みではない銘柄を避けられるなど、ユーザーに寄り添ったサービスを展開しています。
参照:Otomoni公式サイト
法人・BtoB向け食品サブスクの事例4選

近年は、法人・BtoB向けの食品サブスクも人気です。
本章では、以下の事例を紹介します。
- OFFICE DE YASAI|社食に特化した食品サブスクで注目を集める
- TABETE|店舗と連携してフードロス削減に貢献
- オフィスおかん|人数規模に合わせたきめ細かいプランが好評
- ES KITCHEN|手軽に導入できる食品サブスクが人気
それぞれ順番に解説します。
OFFICE DE YASAI|社食に特化した食品サブスクで注目を集める
OFFICE DE YASAIは野菜をふんだんに使った健康的な食事を提供する食品サブスクです。
冷蔵庫を設置するだけで、24時間いつでも健康に配慮した料理を購入できるなど、手軽に利用できることから高い人気を集めています。
OFFICE DE YASAIは、新鮮さを楽しめる冷蔵食品のプランだけでなく、賞味期限を気にしなくてすむ冷凍食品のプランがあるなど、ユーザーのニーズに合わせたサービスを提供しています。
加えて、長めのトライアル期間を設定するなど、使用感をしっかり確かめられる配慮をしている点も人気の秘訣です。
TABETE|店舗と連携してフードロス削減に貢献
TABETEはさまざまな店舗と連携し、余剰食品の販売情報を提供することにより、フードロス削減に貢献している食品サブスクです。
TABETEはただお得に余剰食品を提供するだけでなく、ユーザーと店舗が出会うプラットフォームとしても機能しています。
近年は地方自治体や大手ホテルと連携するなど、全国的にサービスを展開しています。
参照:TABETE公式サイト
オフィスおかん|人数規模に合わせたきめ細かいプランが好評
オフィスおかんは、事業所の人数規模に合わせたきめ細かいプランを提供している社食用のサブスクです。
10人未満から10万人以上まで、さまざまな規模の企業に対応してるため、自社の状況に合わせて手軽に導入できます。
導入時に手厚いサポートを受けられることもあり、オフィスおかんは多くの企業から導入されています。
参照:オフィスおかん公式サイト
ES KITCHEN|手軽に導入できる食品サブスクが人気
ES KITCHENは「オフィス100円社食サービス」を展開するなど、リーズナブルで導入しやすいサービスを展開している食品サブスクです。
ES KITCHENは他社からの乗り換え割や無料トライアルを積極的に実践しており、導入のハードルを下げています。
定期的に新商品を提供していることもあり、継続率が高い点も特徴です。
食品サブスクの課題

食品サブスクビジネスは魅力的な反面、成功のためには乗り越えるべき課題が数多く存在します。
注意すべき課題は以下の通りです。
- 先行投資が不可欠
- 1人あたりの客単価の向上
- サブスクに適したシステムの構築
- サービスの刷新による解約の防止
特にBtoB市場では、顧客企業のニーズを的確に捉え、安定したサービス提供を実現することが重要です。
それぞれの課題を知り、適切な対策を講じましょう。
先行投資が不可欠
食品サブスクビジネスを始めるには、初期投資が不可欠です。
具体的には、以下のような費用が発生します。
| 項目 | 具体的な内容 |
| システム構築費用 | ECサイト構築・在庫管理システム・顧客管理システム・決済システムなどの導入費用。 既存システムとの連携も考慮する必要があるため、費用は変動しやすい。 |
| 在庫費用 | 商品を保管するための倉庫費用や、冷蔵・冷凍設備費用など。 鮮度管理が重要な食品サブスクでは、適切な保管環境の確保が必須となる。 |
| 物流費用 | 商品の配送費用・梱包資材費用など。 配送エリアや配送頻度によって費用が大きく変動する。 |
| マーケティング費用 | 顧客獲得のための広告宣伝費用・販促費用など。 ターゲット層を明確にし、効果的なマーケティング戦略が必要となる。 |
| 人件費 | システム管理・顧客対応・商品仕入れ・配送業務などを行うためのスタッフの人件費。 業務効率化のためのシステム導入も検討すべき。 |
上記の費用を賄うためには、十分な資金計画と、収益化までの期間を見越した戦略が重要です。
特に、初期段階では赤字を覚悟し、長期的な視点で事業展開を行う必要があります。
1人あたりの客単価の向上
食品サブスクビジネスの収益性を高めるためには、1人あたりの客単価の向上も重要な課題です。
単価向上のためには、以下の施策が有効です。
| 施策 | 具体的な方法 |
| 付加価値の提供 | レシピ提供・栄養士による食事指導・専任コンシェルジュサービスなど、顧客にとって魅力的な付加価値を提供することで、顧客の満足度を高め、解約率を下げる。 |
| 商品ラインナップの拡充 | 顧客のニーズに合わせた多様な商品を提供することで、選択の幅を広げ、購買意欲を高める。 季節限定商品やプレミアム商品などを導入するのも有効。 |
| 価格帯の見直し | 顧客層や市場価格を分析し、最適な価格帯を設定する。 高価格帯の商品を導入することで、平均客単価を向上させる。 |
| アップセル・クロスセルの促進 | 顧客の購買履歴や嗜好を分析し、関連商品を提案することで、追加購入を促す。 |
| ロイヤルカスタマーへの優待 | 長期間利用している顧客への割引や特典を提供することで、顧客の継続利用を促し、顧客生涯価値(CLTV)を高める。 |
上記の施策を効果的に組み合わせることで、顧客満足度を高めながら客単価の向上を実現できます。
サブスクに適したシステムの構築
食品サブスクビジネスでは、スムーズな運営を行うために、適切なシステム構築が不可欠です。
特に、以下のような機能を持つシステムが求められます。
| 機能 | 詳細 |
| 在庫管理システム | リアルタイムでの在庫状況把握・発注管理、賞味期限管理など。 食品の鮮度管理には特に重要。 |
| 顧客管理システム(CRM) | 顧客情報の管理・購買履歴の分析・顧客セグメンテーション、パーソナライズされたコミュニケーションなど。 顧客のニーズを把握し、最適なサービスを提供するために必要。 |
| 配送管理システム | 配送ルートの最適化・配送状況の追跡・配送遅延の対応など。 迅速かつ正確な配送を実現するために重要。 |
| 決済システム | 安全かつスムーズな決済処理・請求書発行・売上管理など。 多様な決済方法に対応することが望ましい。 |
| ECサイト | 商品情報の掲載・注文受付・顧客サポートなど。 ユーザーフレンドリーなデザインと機能が重要。 |
いずれのシステムも、それぞれ連携して機能する必要があるため、システム選定や構築には専門家の協力を得ることが推奨されます。
サービスの刷新による解約の防止
食品サブスクは、顧客の継続利用を確保することが重要です。
そのためには、定期的なサービスの刷新が不可欠です。
例えば、季節に応じた商品の入れ替え・新商品の開発・キャンペーンの実施などを通じて、継続的な利用意欲を高める必要があります。
顧客からのフィードバックを積極的に収集し、サービス改善に反映させることも重要です。
また、解約者へのアンケートを実施し、解約理由を分析することで、サービス改善の具体的な方向性を明確にできます。
これらの取り組みを通じて、顧客満足度を高め、長期的な顧客関係を構築することが重要です。
食品サブスクのECサイト構築

食品サブスクを実現するなら、業態に合ったECサイトの構築が欠かせません。
本章では食品サブスクのECサイトを構築するうえで、重要なポイントについて解説します。
テクノロジーの活用
食品サブスクECサイトの構築において、テクノロジーの活用は不可欠です。
適切なシステムを選ぶことで、効率的な運営と顧客満足度の向上を実現できます。
具体的には、以下のテクノロジーが有効です。
| テクノロジー | 効果 | 具体的な活用例 |
| ECプラットフォーム | サイト構築・商品管理・決済処理・顧客管理を一元化し、効率的な運営を支援 | Shopify・Magento・BASEなどのプラットフォームを活用できる。 食品特化型のプラットフォームも利用できる。 |
| CRMシステム | 顧客データの管理・顧客セグメンテーション・パーソナライズされたコミュニケーションの実現。 | SalesforceやHubSpotなどのツールを活用できる。 顧客の嗜好や購入履歴に基づいた商品提案が可能になる。 |
| 在庫管理システム | リアルタイムでの在庫状況把握・発注管理の自動化・食品ロス削減。 | さまざまな在庫管理システムが存在する。 ECプラットフォームと連携できるものも活用できる。 |
| 配送管理システム | 配送業者の選択・配送ルートの最適化・配送状況のリアルタイム追跡。 | Ship&Coなどが活用できる。 特に生鮮食品など、温度管理が重要な食品サブスクでは必須。 |
| 決済システム | クレジットカード決済・キャリア決済・銀行振込など、多様な決済手段に対応。 | Stripe・PayPalなどがある。 サブスク特有の定期課金機能に対応しているシステムを選択する。 |
| データ分析ツール | 顧客行動の分析・売上予測・マーケティング戦略の最適化。 | Google Analyticsなどがある。 顧客の購買パターンを分析すれば、商品開発やプロモーションに応用できる。 |
上記のテクノロジーを効果的に活用することで、業務効率・顧客満足度・収益性の向上を実現できます。
導入にあたっては、自社の規模・予算・顧客のニーズに最適なシステムを選択することが重要です。
顧客体験の向上
食品サブスクにおいて、顧客体験の向上はリピート率向上に直結します。
顧客が継続してサービスを利用し続けるためには、満足度の高い体験を提供することが不可欠です。
顧客のリピートにつながる施策には、以下のようなものがあります。
| 顧客体験向上のための施策 | 具体的な方法 |
| パーソナライズされたサービス | ・顧客の嗜好やライフスタイルに合わせた商品提案 ・定期配送日の柔軟な変更 ・商品のカスタマイズオプションの提供 |
| スムーズな注文・配送プロセス | ・分かりやすいWebサイト ・簡単な注文手続き ・迅速な配送 ・配送状況のリアルタイム追跡 |
| 優れたカスタマーサポート | ・迅速かつ丁寧な対応 ・問い合わせへの迅速な回答 ・チャットサポートや電話サポートの提供 |
| コミュニティの構築 | ・SNSを活用した情報発信 ・顧客同士の交流の場の提供 ・会員限定イベントの実施 |
| 継続的なフィードバックの収集 | ・アンケートの実施 ・レビューの活用 ・顧客からの意見を積極的に取り入れる体制の構築 |
顧客体験を向上させるためには、顧客の声に耳を傾け、継続的に改善していく姿勢が欠かせません。
顧客満足度を高めることで、高い顧客ロイヤルティを構築し、長期的なビジネス成長を実現できます。
有効的なシステムを構築して、理想的な食品サブスクを実現しよう

食品サブスクの成功は、魅力的な商品提供だけでなく、それを支える堅牢なシステムの構築に大きく依存します。
特に、食品サブスクは鮮度管理や配送の正確性が求められるため、システムの信頼性と安定性は非常に重要です。
自社の規模やビジネスモデルに最適なシステムを選び、継続的な改善を繰り返すことで、理想的な食品サブスクを実現しましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
食品ECのトレンド調査
食品ECサイトの構築/改修を