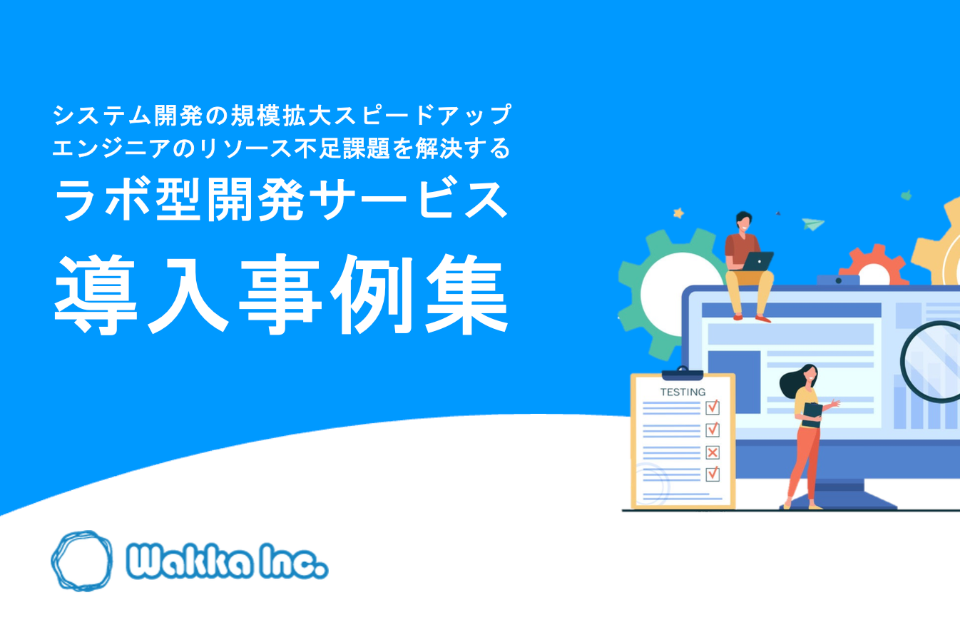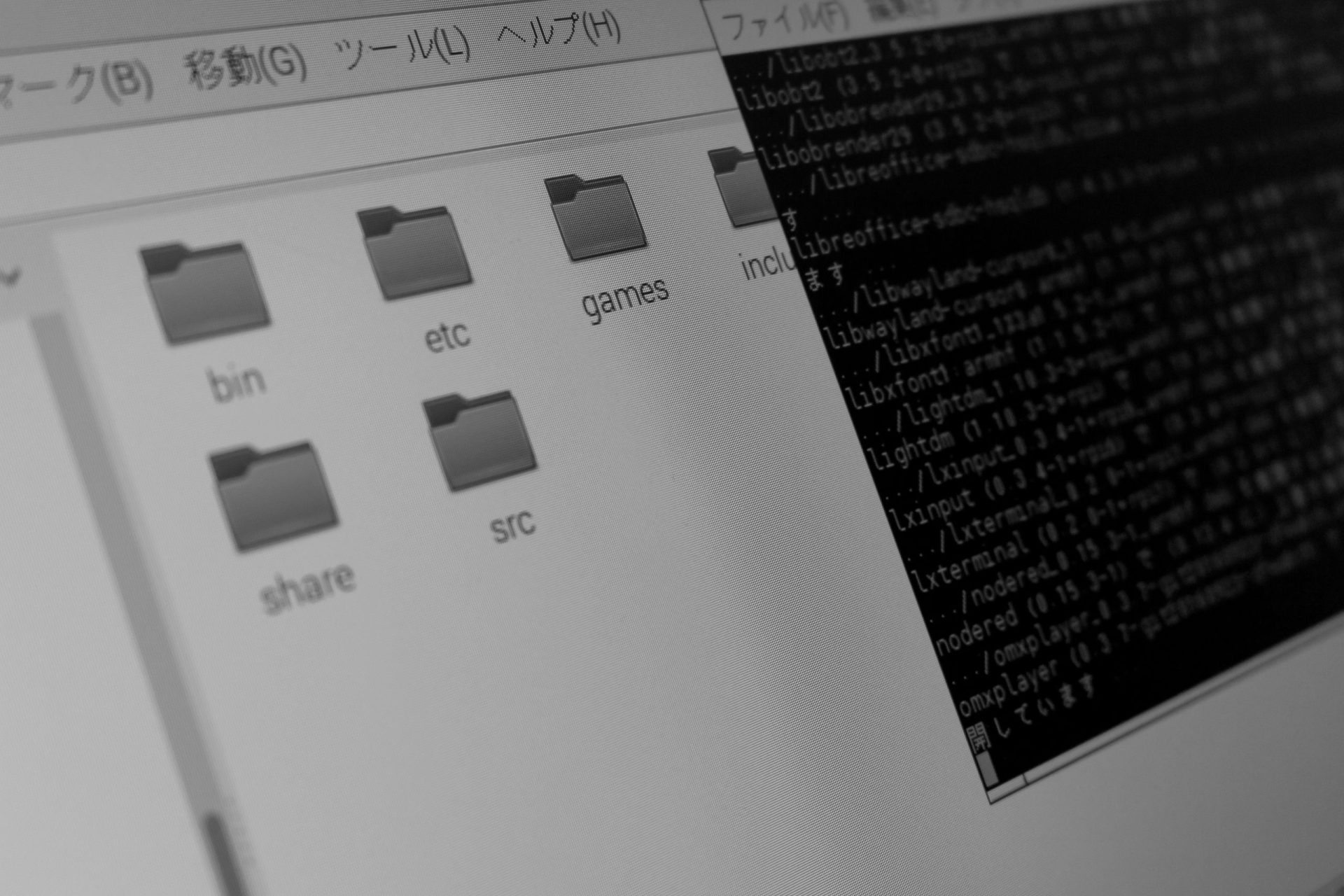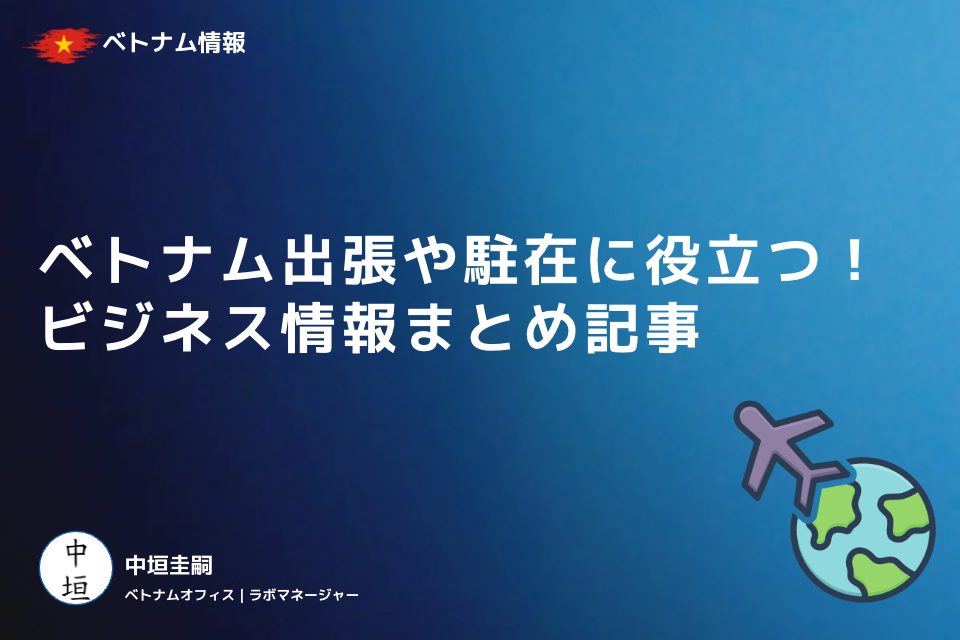ITアウトソーシングとは?業務の種類、メリットやデメリット、導入事例手順まで解説


こんにちは。Wakka Inc.のWebディレクターの安藤です。
現在、多くの企業でITアウトソーシングが活用されています。
なぜなら、ITアウトソーシングの導入によるコスト削減や業務の大幅な効率化に期待できるからです。
本記事では、ITアウトソーシングの現状や活用される理由・メリット・デメリット導入手順を解説します。
ITアウトソーシングについて理解し、自社に最適な導入方法を知りたい方はぜひご覧ください。
開発リソース不足が課題の場合はラボ型開発がおすすめです。
最適なプロジェクト体制で優秀な人材を低コストで確保できます。ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
ITアウトソーシングとは?

ITアウトソーシングとは、IT業務を外部委託することです。
ITOと略して呼ばれることもあります。
ITアウトソーシングの導入形態は、おもに下記の2つです。
- 企画から開発・運用まですべてを委託するケース
- 業務の一部のみを委託するケース
ITアウトソーシングの導入形態は、委託する範囲や業務内容などに応じて検討するのが一般的です。
委託する業務の内容は仕様書や業務一覧表で自由に決定できます。
ただし、委託する範囲や業務内容が多いほど委託料は増加します。
ITアウトソーシングを実施する際は、予算と兼ね合いを見ながら委託する内容を具体化することが重要です。
ITアウトソーシングの現状と市場規模

ITアウトソーシングの需要は年々増加しています。
理由としてIT業務の拡大や高度化が進み、IT人材の需要が高まっているにもかかわらず、国内の人材不足が深刻化しているためです。
経済産業省では、以下のような報告が出されています。
IT需要が今後拡大する一方で、我が国の労働人口(特に若年人口)は減少が見込まれ、IT 人材の需要と供給の差(需給ギャップ)は、需要が供給を上回り、2030年には、最大で約79万人に拡大する可能性があると試算されている。
近年はAIなどの導入によってIT関連業務の効率化が進められていますが、そのような対策もIT人材がいなければ実現できません。
一般企業においても、ビッグデータやAIの活用、オンライン上の顧客情報の管理など、企業にとってのIT業務の重要性はますます高まっています。
多くの企業においてIT業務は今後も増え続け、必要性はさらに高まる見込みです。
このような状況に伴い、ITアウトソーシングはより重要な施策として注目されています。
IT人材が少ない状況でも、ITアウトソーシングを通じて専門性が高い企業のサポートを受ければ、自社のIT戦略を実現できる可能性が高まります。
ITアウトソーシングのメリット

ITアウトソーシングは、さまざまな課題を解決する糸口として期待されるようになりました。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 業務の効率化
- 人材不足解消
- コア業務に集中可能な体制構築
- IT技術の進化への対応
- コスト削減
- ITシステムのセキュリティ強化
- 体制変更の場合でも対応できる
- 事業継続性の確保
- 24時間365日の安定したシステム運用
- ITアウトソーシングによるグローバル展開の実現
順番に詳しく解説します。
業務の効率化
IT業務は高度化しており、従業員のITスキル不足は業務の生産性に大きく影響します。
しかし、非効率化している業務が発生してしまう場面も珍しくありません。
IT業務が非効率化すると、人件費などのコストが高騰し、収益を圧迫する恐れがあります。
しかし、IT業務の効率化は専門的知識が不可欠であり、ノウハウがない企業では実現が困難です。
非効率なIT業務をノウハウを持つ企業にアウトソーシングすることで、リソースに余裕が生まれるため、人材育成の充実化を図れます。
また、専門家に業務を委託することにより、プロセスの見直しも可能です。
その結果、業務効率化とITスキル不足の解消が期待できます。
人材不足解消
労働人口の減少により、IT業務の担い手が不足傾向にあることも、ITアウトソーシングが増えている要因です。
経済産業省の商務情報政策局情報処理振興課の「参考資料(IT人材育成の状況等について)」によると、2030年までのIT人材の不足数を推計した場合に、将来的には40~80万人の規模での不足が懸念されています。
そのため、IT人材の確保は企業にとって重要な課題となりつつあります。
IT人材がいなければ、自社の業務の遂行だけでなく、DX化など重要なIT戦略の推進が難しくなるでしょう。
深刻化する人材不足への対策として、ITアウトソーシングは有用な施策です。
自社にはない人材やノウハウを他社のサポートで補うことにより、重要なIT戦略を実践しやすくなります。
コア業務に集中可能な体制構築
IT業界では、多くのリソースが求められる一方で、トラブル発生時はコア業務に割くリソースが不足しがちなのが現状です。
さらに、下記のような定型業務も遂行しなければなりません。
- 日々の問い合わせ対応
- システムの保守管理
- システムのバージョンアップ
コア業務の停滞は、売り上げへの影響も懸念されるため、必要に応じてITアウトソーシングの活用を検討する必要があります。
ITアウトソーシングによってノンコア業務に割く時間や労力を削減すれば、コア業務に割くリソースを確保できます。
IT技術の進化への対応
IT技術は常に高度化しており、相応のスキルを持った人員の確保や育成が難しいケースが増えています。
企業として技術の進化に対応できなければ、さまざまな課題が発生する事態になりかねません。
例えば、以下のような状況が挙げられます。
- 5Gの高速通信により多くの端末で同時接続が可能になり、維持管理コストが増える
- ビッグデータの発展で、より膨大なデータを管理する必要がある
ITアウトソーシングには、ITのプロが在籍しているため、進歩を続けるIT技術への対応の速さと専門性の高さに期待できます。
彼らのノウハウを活用すれば、新たなIT技術の導入がスムーズにいく上に、必要なノウハウの共有も可能です。
新たなIT技術に導入に成功すれば、事業の成長だけでなく、業務の効率化や従業員の負担も実現できる可能性が高まります。
つまり、ITアウトソーシングは、ITの専門家ではない従業員の負担を軽減し、働きやすい環境を構築する上でも有用です。
コスト削減
ITアウトソーシングはコストの削減にもつながる施策です。
IT人材の雇用によって自社でIT業務に実施する際、以下のようなコストが必要になります。
- 人件費
- 人材育成費
- サーバーの固定費・管理運用費
上記に加えて、繁忙期を意識した人員確保を想定した場合では、人件費が大幅に膨れ上がる可能性があります。
加えて、ノウハウが不足している企業だと業務プロセスが非効率化し、想定以上にコストが発生する事態になることも珍しくありません。
一方で、ITアウトソーシングを活用した場合を考えてみましょう。
IT業務をアウトソーシングすることにより、自社でIT人材を抱える必要がなくなり、自社サーバーを維持管理する必要もありません。
繁忙期の際の残業の発生による人件費増加の負担もなくなるので、自社のリソースをコア業務に集中させやすくなります。
ITアウトソーシングは、IT化による課題解決を低コストで実現するために有効な手段のひとつです。
ITシステムのセキュリティ強化
セキュリティ強化はITシステムを導入している企業すべてにとって、非常に重要な課題です。
IT業務は常にセキュリティやシステム障害などのリスクと隣り合わせのため、自社の従業員のみでは対応が困難な場合も少なくありません。
プログラミングやセキュリティに関する高度なスキルを持ったエンジニアが自社にいない場合、リスク管理などの課題が残り、トラブルが発生すればそれだけ従業員の負担も増えます。
また、不正アクセスやウイルス感染などによってシステムに致命的なエラーが生じれば、事業の継続に支障をきたす恐れがあります。
しかし、セキュリティの強化にはITのノウハウが不可欠です。
自社でセキュリティの強化が難しければ、ITアウトソーシングを実施しましょう。
専門家に委託すれば、自社のシステムの安全性をより高められます。
ITアウトソーシングの活用によって適切なシステムを導入できれば、ガバナンスの強化にもつながります。
ただし、ITアウトソーシングには、外部委託ゆえのリスクが潜んでいる点に注意が必要です。
情報の公開範囲や用途など、認識のズレが生じた場合には、情報漏えいやプライバシーの問題に発展しかねません。
ITアウトソーシングを活用する際は、秘密保持契約など情報の取り扱いに関する綿密な協議を実施し、最大限の注意を払ってください。
体制変更の場合でも対応できる
IT業務では導入するシステムの急な変更に伴う体制変更が頻繁に起こります。
急な体制変更により、コア業務に支障が出るケースも珍しくありません。
ITアウトソーシングを活用できれば、自社の体制を変えず、新しいシステムの導入時も安心して外部に一任できます。
新システムの導入に際して必要な対応のアドバイスも受けられるので、混乱を最小限に抑えられる点もメリットです。
ただし、体制の変更によって業務プロセスが変更される場合は、正確な情報共有が欠かせません。
委託先に任せきりだと、業務が属人化する恐れがあります。
事業継続性の確保
近年では、地震や洪水などの大規模な災害が多発しており、ITシステムにおいても事業継続計画(BCP)の策定が求められます。
BCPがあれば、非常時でも事業の停滞を防ぎ、損失を最小限に抑制する効果が期待できます。
しかし、BCPのためにIT人材を雇用するのは、人件費や育成費などを考慮すると現実的ではありません。
参照:BCP(事業継続計画)とは|中小企業庁
ITアウトソーシングは、ビジネスへの影響を軽減することを目的とした「ITサービス継続性管理」にも活用でき、効果的なBCPの策定が可能です。
ITシステムにおけるBCP策定は、自社のガバナンス強化といった観点からも有効です。
24時間365日の安定したシステム運用
ITアウトソーシングの対応可能時間は、24時間365日としているケースが一般的です。
そのため、ITシステムの24時間体制の監視対応・障害対応を実現でき、安定したシステム運用を実現できます。
自社だけでは24時間体制の構築は困難ですが、ITアウトソーシングならいつでもトラブル時の対応が可能です。
システムの安定運用を実現した先には、コア業務の安定化やエンゲージメント向上などの効果が期待できます。
ITアウトソーシングの活用は、最終的には企業価値の向上にもつながります。
ITアウトソーシングによるグローバル展開の実現
自社においてグローバル展開を検討する際に、海外拠点のIT環境構築や多言語対応などが課題となるケースは少なくありません。
ITアウトソーシング企業には、グローバルに展開していたり、海外拠点を持っていたりするところもあります。
海外展開している企業であれば、言語はもちろん、現地の商慣習や法規制も把握しているため、グローバル展開を実施する上での助けになります。
そのため、ITアウトソーシングの活用によって、自社のグローバル展開の加速が可能です。
ITアウトソーシングは、海外でも24時間365日体制のシステム運用ができるため、時差による影響抑制としても効果的です。
ITアウトソーシングのデメリット

ITアウトソーシングは、進め方によってはデメリットが生じる可能性もあります。
具体的には下記の通りです。
- 想定以上にコストが必要なケースがある
- セキュリティ面でトラブルの可能性がある
- ノウハウが残らない
- 生産性が低下する可能性がある
順に解説します。
想定以上にコストが必要なケースがある
ITアウトソーシングには、想定以上にコストがかかってしまう恐れがあります。
理由として、自社に本当に必要なサービスかの判断が曖昧になり、余計なサービスまで依頼してしまうケースがあるためです。
事前に自社の状況を細かく把握して「本当に導入が必要かどうか?」を慎重に判断しましょう。
同様に、委託先との連携に時間と労力を要するため、コミュニケーションコストについても検討してください。
コミュニケーションコストの削減には、コミュニケーションの手法や頻度などを事前に明確にしておくことが有効です。
生産性が低下する可能性がある
ITアウトソーシングのデメリットとして、生産性が低下する可能性も見逃せません。
委託先によっては、自社システムへの知見が不足しており、かえって時間がかかる場合もあります。
ホームページに掲載される事例や問い合わせを活用して、委託先の専門分野や遂行能力は事前に確認しておきましょう。
また、新規のプロジェクトを委託先と立ち上げる場合、業務プロセスや人員が確定するまで生産性が安定しないケースもあります。
そのような状況では、委託先と綿密に協議し、長期的な視点で取り組むことが重要です。
ノウハウが残らない
ノウハウが残らないのは、ITアウトソーシングの無視できないデメリットです。
IT業務の過程で得られるノウハウは、競合に対する優位性につながる武器となる可能性があります。
ITアウトソーシングの委託先によっては、業務の細かな過程は確認せず、結果のみ共有される場合も少なくありません。
そのため、委託契約で取り決めがない限り、システムの開発や運用のノウハウが自社の従業員に共有されることはほとんどありません。
ノウハウが残らない状況を放置すると、委託先との契約が終了すると、途端に業務が回らなくなるリスクが高まります。
一部の業務を社内に戻す予定がある場合には、自社の専任担当者を決めるなど、業務内容に深く関わっていく必要もあります。
3年後・5年後の状況まで社内でよく検討し、業務ごとに臨機応変に対応しましょう。
また、自社のシステム運用やIT業務に関するノウハウであれば、委託先に依頼することで共有してもらえる場合があります。
ただし、委託先が持つノウハウすべてを伝授してもらえることはないので注意しましょう。
あるいは、途中から開発チームを移管して、自社の海外開発子会社として設立可能なラボ型開発を導入するのもおすすめです。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
ITアウトソーシングできる業務の種類

ITアウトソーシングで委託できる業務は以下の通りです。
- システムの開発・運用
- ITインフラの構築や運用
- セキュリティ強化
- 社外・社内向けのヘルプデスク
- データ分析・運用
- 情報システム関連業務
- バックオフィス業務
- ITコンサルティング
それぞれの業務内容について、順番に解説します。

ITアウトソーシングは、形態により依頼できる業務内容が異なります。
下記は、それぞれの業務形態と内容の一覧表です。
| 形態 | 業務内容 |
|---|---|
| 開発アウトソーシング | システムの企画・設計・開発・テストを実施 |
| フルアウトソーシング | IT関連業務の企画から運用まですべて |
| 運用アウトソーシング | 導入したシステム・インフラ部分の運用やネットワーク保守など |
| ホスティング | 外部のサーバーやストレージの準備や運用、保守 |
| ヘルプデスク | コールセンターなどのように、顧客からの問い合わせ対応 |
| ハウジング | 自社のサーバーや通信機器を外部ベンダーのデータセンターに間借りする |
| 常駐サービス | 提供先に常駐し、業務への協力やサポート |
本章では、形態ごとに解説します。
開発アウトソーシング
開発アウトソーシングは、システムの企画・開発・テスト・実装までを委託する形態です。
運用は委託しないため、業務期間は限定的です。
開発アウトソーシングは、ある程度のITリテラシーがある人材がいる場合や、コストを削減したい場合などで活用されます。
ただし、開発アウトソーシングは、運用開始後に十分なサポートを受けられない可能性がある点に注意が必要です。
運用開始後に、社内のみでは対応が困難だった場合のサポート体制を確認しましょう。
フルアウトソーシング
IT業務の一部だけでなく、企画や開発・運用まですべての業務を委託する形態を、フルアウトソーシングと呼びます。
IT業務は多くのリソースを要するため、下記のような場合には、フルアウトソーシングが選ばれる傾向にあります。
- 必要な人員の確保が難しい
- 人件費を抑えたい
フルアウトソーシングの活用で、空いたリソースをコア業務へ投入し、事業拡大に取り組むケースにおいても有用です。
なお、すべての業務を委託する性質上、委託先への依存度が高まる点には注意が必要です。
運用アウトソーシング
運用アウトソーシングには、インフラ運用アウトソーシング・システム運用アウトソーシング・ネットワーク保守アウトソーシングの3種類があり、それぞれの違いは下記の通りです。
| アウトソーシングの種類 | インフラ運用アウトソーシング | システム運用アウトソーシング | ネットワーク保守アウトソーシング |
|---|---|---|---|
| 対象 | ITインフラ(ネットワーク・サーバーなど) | ITシステム(基幹システム・アプリケーションなど) | ネットワーク機器・ファームウェアなど |
| 目的 | ITインフラの安定稼働 | ITシステムの安定稼働による業務の正常な遂行 | ITインフラの健全性確保 |
| 業務内容 | ITインフラの監視・管理など | ITシステムの運用・監視・保守など | ネットワーク機器の点検とメンテナンス・ハードウェアの修理や交換・ファームウェアやソフトウェアの更新・障害発生時対応 |
自社で開発したシステムを運用するために、インフラ運用を委託するケースが増えている一方で、システム導入後の運用に課題を抱える場合もあります。
上記の場合では、結果的にシステム運用も委託する方向で検討する企業が少なくありません。
自社で使いこなせないシステムを放置すると、セキュリティの問題が発生するリスクも高まります。
セキュリティリスクを解消するには、インフラ・システムの運用の一括委託が効果的な場合があります。
ホスティング
ホスティングとは、データセンター内に設置されたサーバーを借りることです。
レンタルサーバーとも呼ばれ、通信事業者やISP(インターネットサービスプロバイダ)が提供しています。
ホスティングはサーバーの運用からメンテナンスまでレンタル先の管理となり、手間が省けるのがメリットです。
自社でサーバーを管理する企業は、メンテナンスやセキュリティ面で大きなリスクがある上に、管理コストも大きな負担となります。
セキュリティ面や管理コストを考慮するなら、ホスティングを活用するのも、業務改善に役立つ手段です。
ヘルプデスク
ヘルプデスクとは、顧客への電話・メール対応や、夜間・休日対応のサポートを委託する形態です。
顧客からの問い合わせのように、想定以上の時間と人員を割かれるケースでは、業務効率化の観点から有効です。
特に、繁忙期のような場面では、コア業務に人員を集中させながら顧客対応を充実化できます。
コア業務に人員を集中できる点においては、生産性の向上も期待できます。
ハウジング
サーバーなど必要機器は自社で用意し、設置場所を間借りする形態がハウジングです。
ハウジングは、サーバー・冷却装置などの設置スペースや備品の準備・管理にかかる労力を削減できるのがメリットです。
また、サーバーを自社で管理する場合は、セキュリティ面のリスクも抱えてしまいます。
ハウジングには、プロによる監視やバックアップがサービスに含まれているケースもあるため、セキュリティ強化においても有効です。
常駐サービス
常駐サービスとは、依頼元の企業に必要なスキルを備えた人材を派遣し、問題解決を行うサービスです。
個人情報や機密性の高いデータを扱っているなど、社外に情報を持ち出せない業務や企業で活用されます。
派遣された期間は、適切な人材が常駐し、業務への協力やコンサルティングなどのサービスが提供されます。
常に担当者が常駐していることもあり、トラブルが発生してもスピーディーに解決できるのが特徴です。
常駐サービスには、サービス提供側が指揮命令を行う委託型と、依頼元が指揮命令を行う派遣型の2種類があります。
委託型と派遣サービス型は、自社の状況や受けたいサービスに基づいて検討しましょう。
ITアウトソーシングの委託先の選び方

ITアウトソーシングの効果を十全に発揮し、十分なコストパフォーマンスを得るには、下記のような考慮すべきポイントがあります。
- 対応する業務
- 専門性や実績
- コスト
- セキュリティ面
順番に解説するので、ぜひ参考にしてください。
対応する業務
アウトソーシングの依頼先が、対応できる業務の範囲は、事前に確認しましょう。
依頼先によって対応できる業務範囲が異なり、場合によっては契約後に支障をきたすこともあり得ます。
トラブルを予防するには、依頼予定の業務を洗い出して、綿密にすり合わせることが大切です。
「どの業務を依頼すれば良いのか?」といった根本的な部分から支援してくれる企業もあるため、まずは自社の課題やニーズを相談してみましょう。
なお、ITアウトソーシングの費用は業務の種類や量によって変動します。
委託する業務が広範囲になると、それだけ予算が高騰するので注意しましょう。
専門性や実績
専門性や実績は、アウトソーシング先を決める際に重要な情報です。
アウトソーシング先が、依頼した業務への知見やスキルを持っていない場合もあるでしょう。
例えば、特定の業務形態しか対応できなかった場合は、自社に必要なサービスを受けられない可能性があります。
このようなトラブルを回避するために、ITアウトソーシング先の候補は複数用意し、自社に最適なパートナーを選びましょう。
コスト
コストも、アウトソーシング先を決める際に欠かせない要素です。
価格の安さだけで決めてしまうと、依頼先の業務や提供サービスの品質が低く、結果的にコストが増えるリスクもあります。
また依頼した業務へのスキル不足が原因で、トラブルに発展するリスクも無視できません。
自社の環境や、依頼する業務への遂行能力を双方で確認し、慎重に進めましょう。
セキュリティ面
セキュリティ面も、アウトソーシング先の選択において重要な要素です。IT業務では多くの顧客情報を抱え、情報漏えいのリスクがあります。
実際に「サイバー攻撃や不正アクセスにより、顧客の個人情報が流出した」といったニュースは後を絶ちません。
また、委託先が業務を再委託しているケースもあります。
信頼できるアウトソーシング先を見定めることが大切なため、アウトソーシング先の情報の管理方法や体制はよく確認しましょう。
ITアウトソーシングで効率化しやすい業務

本章では、ITアウトソーシングで効率化しやすい業務を解説します。
具体的には、次の通りです。
- IT業務全般
- 管理業務やシステム運用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
IT業務全般
IT業務全般は、アウトソーシングの導入で効率化しやすい業務の一つです。
IT業務は常に高度化し、求められるスキルの変化も早く、企業によっては対応が難しい場合もあります。
例えば、5Gの普及やAIの発達により、扱うシステムが変化し、求められるスキルもどんどん高度になっています。
コア業務でリソースに余裕のない企業では、IT業務への増員は困難です。
また、属人性が高い業務だと、担当者が離職することによってシステムや業務そのものがブラックボックス化するケースもあります。
ITにより自動化できる業務を洗い出し、ビジネスの効率化を図りましょう。
管理業務やシステム運用
管理業務やシステム運用も、ITアウトソーシングで効率化しやすい業務です。
コア業務が忙しい場合、多くの企業で管理業務やシステム運用が疎かになりがちです。
アウトソーシングを活用した提携業務や雑務を外部委託することにより、コア業務へ投入できるリソースが増大し、企業の成長につながります。
IT業務には、利益に直結するコア業務と、直結しないノンコア業務があります。
ノンコア業務である管理業務やシステム運用をアウトソーシングすることで、コア業務に集中でき売上の向上も見込めるでしょう。
ITアウトソーシングの導入手順

ITアウトソーシングを導入する上では、手順の理解が大切です。
下記のように導入手順を明確にすることで、導入の効率化やトラブル防止につながります。
- 課題の把握と目的設定
- 委託に必要な情報の整理と予算の確保
- 具体的な運用設計
- 導入
順番に見ていきましょう。
課題の把握と目的設定
ITの専門家と情報を洗い出して改善すべき課題を明確化して、適切な目的を設定する工程です。
第三者の客観的な視点が入ることで、より優先度の高い課題の見極めが可能になります。
自社の目的や課題が明確になれば、よりスムーズにアウトソーシングを導入できるはずです。
逆に課題を把握する過程で、自社で解決する見込みが立った場合は、そのまま対策を講じられます。
そうすれば、無駄なアウトソーシングが実施する必要がなくなります。
委託に必要な情報の整理と予算の確保
次に、委託する際に必要な情報を整理し、予算を確保しましょう。
具体的には、業務遂行に必要な人員や予算、必要な工程を決めます。
トラブルにならないよう、必要な情報や予算はしっかりと洗い出すことが大切です。
洗い出しが徹底されていれば、委託先に提出する仕様書がブラッシュアップできる上に、アウトソーシングを開始した際の引き継ぎもスムーズに進められます。
具体的な運用設計
スキルチェック表や作業手順書、作業フロー図などを作成する工程です。
運用設計の作成により、メンバー間の認識共有の促進や的確な人員配置が可能となるため、より効率的な業務遂行が期待できます。
運用設計に不備があると、アウトソーシング後に不備が発生しやすくなります。
委託先とは綿密にコミュニケーションを取り、情報の齟齬がないようにしましょう。
導入
ITアウトソーシングは、導入して終わりではありません。
導入後は、新たに生じた課題や改善点などを共有・分析し、その後のスムーズな運用に活用すると効果的です。
ITアウトソーシングは、導入後も継続的な連携を図り、改善に取り組みましょう。
なお、アウトソーシング後に運用設計の時点で想定されていなかった課題が判明することは珍しくありません。
その際は、委託先とどのように対処すべきか協議しましょう。
場合によっては、仕様書に業務を追加する必要が生じる場合があります。
ITアウトソーシングを導入する際の注意点

ITアウトソーシングを導入する際の注意点は、確認を怠れば、求めるサービス品質が得られなかったり、セキュリティリスクが高くなったりするリスクがあります。
具体的に、導入する際の注意点は次の通りです。
- ITアウトソーシング戦略を策定する
- 業務の柔軟性
- 業務範囲・サービス品質の明確化
- セキュリティレベルの確認
順番に解説します。
ITアウトソーシング戦略を策定する
ITアウトソーシング戦略を策定する上で大切なのは、以下3つのポイントです。
- ITアウトソーシングで得られるメリットはデメリットを上回っているか
- ITアウトソーシングの活用で目指す目標の数値化
- 専門性の高いIT人材の確保によって可能となる事業の今後の展望
上記の中でも、目標の数値化は特に大切です。
目標を数値化することで、ゴールが明確化し、達成できなかった場合の分析と計画の見直しなどに役立ちます。
業務の柔軟性
ITアウトソーシングを導入する際には「業務に柔軟に対応してくれる委託先かどうか」を確認しましょう。
例えば、事前に業務範囲を明確にした場合でも、細かな業務が発生するケースがあります。
そのたびに自社で対応していては、従業員の負担も減らず、アウトソーシングの意味が薄れてしまいます。
自社がITアウトソーシングに求める内容と、依頼先の柔軟性をすり合わせ、実現可能な範囲かどうかを確認するのが大切です。
業務範囲・サービス品質の明確化
業務範囲・サービス品質の明確化も重要です。
なぜなら、業務範囲とサービス品質を明確にしなければ、品質低下につながる恐れがあるためです。
例えば、業務範囲やサービス品質を明確にするSLA※などの取り決めを交わすことが、有効な対策として挙げられます。
SLAを取り決める際に、トラブルや事故発生時の対応についても話し合えば、スムーズな問題解決につながります。
※SLA(Service Level Agreement)・・・サービス提供者と利用者間で、業務範囲やサービス内容の取り決めを交わし、品質を保証する合意文書
セキュリティレベルの確認
ITアウトソーシングは、外部の企業が顧客情報を扱うため、自社で完結する業務と比べ、漏えいのリスクは格段に高まる点に注意が必要です。
セキュリティレベルは、以下2つの有無をチェックしてください。
- 国際的なセキュリティ基準を満たしたことを示すISMS認証
- 事業者間の個人情報の取り扱いが適切である証明のプライバシーマーク
また、前述したSLAにて顧客情報の取り扱いも明確にすれば、さらにリスクは減ります。
顧客情報の漏えいによる企業の損害は計り知れないため、セキュリティレベルは、ITアウトソーシング先を選ぶ際の最重要な指標の1つです。
ITアウトソーシングの事例
本章では、以下のようなITアウトソーシングの事例を紹介します。
- 社内で使用するシステムの開発と運用をアウトソーシング
- ヘルプデスク部門を外部に委託
- システム構築をアウトソーシングすることで属人性を解消
- 専門家のサポートを得てサイバーセキュリティを強化
実際にITアウトソーシングを利用する際の参考にしてください。
Q.ITアウトソーシングとSESの違いは何ですか?
ITアウトソーシングとは、IT関連業務を外部の専門業者に委託する仕組みです。
対して、SESは「System Engineering Service」の略称であり、企業の要望に応じてエンジニアを提供するサービスを意味します。
ITアウトソーシングが業務そのものを委託するのに対し、SESは依頼した企業にエンジニアを時間単位で常駐させる点が異なります。
いずれも外部委託の形態ですが、SESは準委任契約を採用するケースが一般的です。
Q.ITアウトソーシングにはどのような例がありますか?
ITアウトソーシングにはさまざまな形態がありますが、代表的な例としては以下が挙げられます。
・システムの開発や運用
・ITインフラの構築や運用
・セキュリティ強化
・社外や社内向けのヘルプデスクの委託
・データ分析や運用
・情報システム関連業務の委託
・バックオフィス業務の委託
・ITコンサルティング
ITアウトソーシングには、業務単位で委託する場合もあれば、部門ごと包括的に外部へ委託するケースもあります。
Q.ITアウトソーシングのメリット・デメリットは何ですか?
ITアウトソーシングのメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
・業務の効率化
・人材不足解消
・コア業務に集中可能な体制構築
・IT技術の進化への対応
・コスト削減
・ITシステムのセキュリティ強化
・人員や体制の変更にも柔軟に対応できる
・事業継続性の確保
・24時間365日の安定したシステム運用
・ITアウトソーシングによるグローバル展開の実現
【デメリット】
・想定以上にコストが必要なケースがある
・セキュリティ面でトラブルの可能性がある
・自社内にノウハウが蓄積されにくい
・委託先との連携が不十分な場合、生産性が下がる可能性がある
ITアウトソーシングで事業を成長させよう

本記事では、ITアウトソーシングのメリット・デメリット・導入手順を解説しました。
ITアウトソーシングは、導入する際の注意点や正しい手順を理解することで、多くのメリットを得られます。
ぜひこの機会に、ITアウトソーシングによる業務効率化やコスト削減を検討してみてはいかがでしょうか。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、

学生時代にWebサイトを自作したことがきっかけでWebの世界に。制作会社でデザイン、WordPressテーマ開発の実務を経て、テクニカル・ディレクターとして大規模サイト構築のディレクションを経験。2021年からWakka Inc.の日本拠点でWebディレクターとして参画。最近はブロックエディタになったWordPressをもう一度、勉強しています。