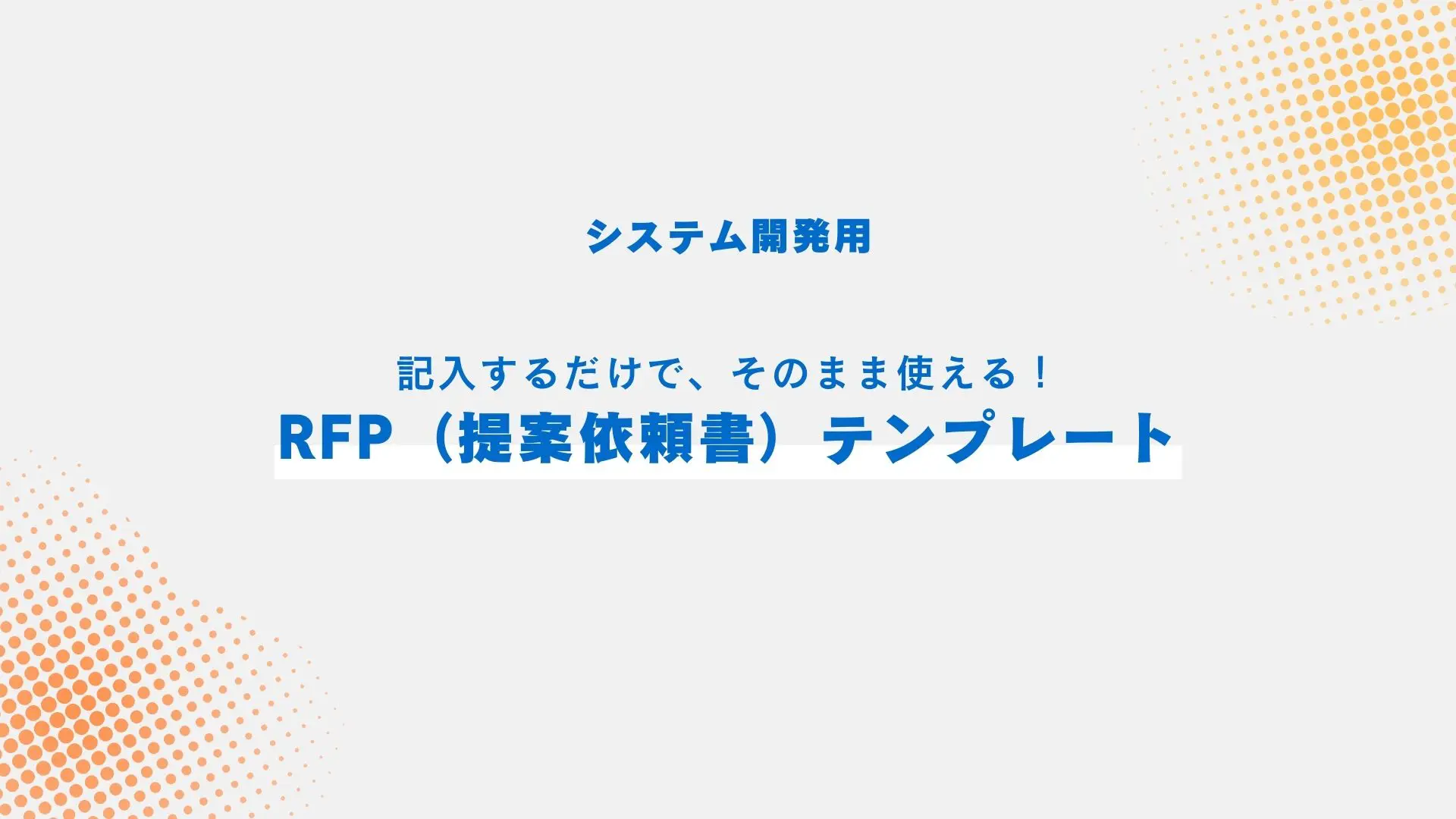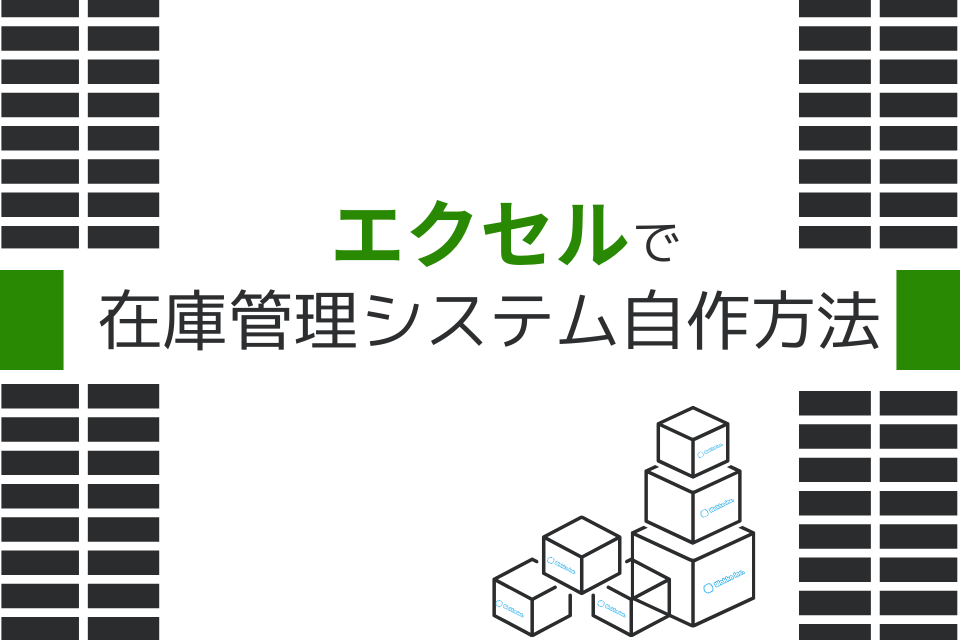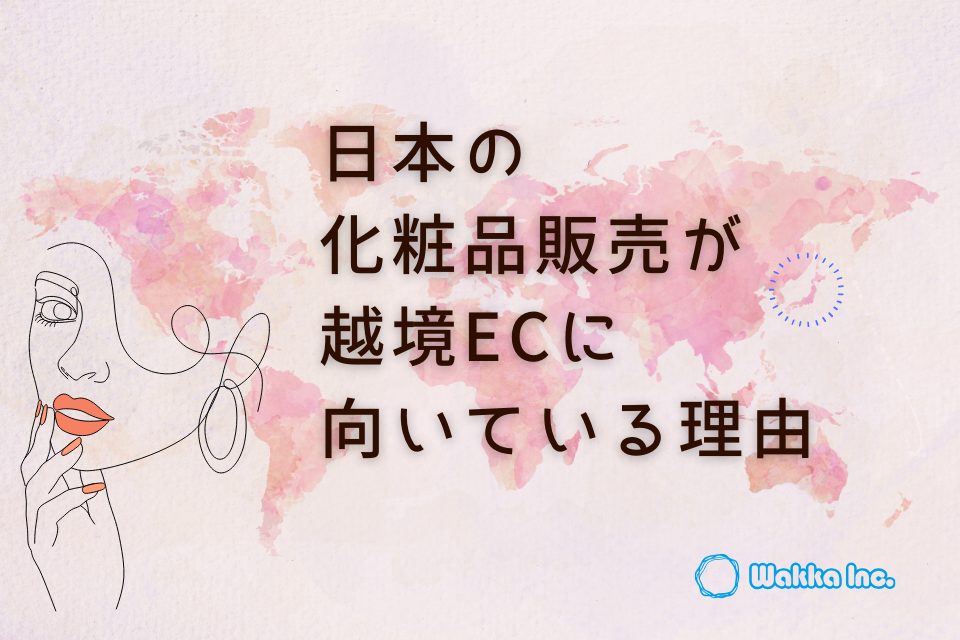基幹系システムとは?役割や情報系システムとの違いなどを解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
基幹系システムとは、企業が業務を運営するうえで欠かせないシステムです。
適切な基幹系システムが導入できなければ、業務に支障をきたすだけでなく、事業の運営にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
なお、「業務系システム」という言葉が基幹系システムを含む広い概念として用いられる場合もあります。
業務系システムという言葉の使われ方には幅があり、一般的には基幹系システムと同義で使われることも少なくありません。
本記事では「基幹系システム」と表現し、その役割や他の情報系システムとの違いなどについて解説します。
基幹系システムの導入や運営に役立つ情報もご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
基幹系システムの概要

企業活動を円滑に進めるうえで、さまざまなシステムが活用されていますが、そのなかでも基幹系システムは事業運営の根幹を支える重要な役割を担っています。
本章では基幹系システムについて、基本的な知識を解説します。
基幹系システムの役割と必要性
基幹系システムとは、企業の主要業務に不可欠な情報システムのことです。
具体的には、販売・購買・在庫・生産・会計・人事といった、事業の根幹に関わる業務を支えます。
基幹系システムは経営や業務の中枢を担い、万が一停止すると企業活動そのものに大きな支障をきたす可能性があります。
したがって、高い信頼性や安定的な稼働が求められるのが特徴です。
現代の企業経営において、基幹系システムは業務効率化や迅速な意思決定に不可欠な存在です。
業務系システムとの違い
業務系システムという言葉もよく耳にしますが、これは基幹系システムとほぼ同義で使われるケースがほとんどです。
ただし、文脈によっては基幹系システムを「企業の根幹業務を支えるシステム」とより狭義に捉え、業務系システムを「特定の業務を支援するシステム全般」と広義に捉える場合もあります。
それぞれの違いは以下の通りです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 基幹系システム | 企業の主要業務(販売・会計・人事など)を処理する、事業継続に不可欠なシステム。 |
| 業務系システム | 特定の業務を効率化・支援するためのシステム全般。 基幹系システムも含まれる。 |
このように、両者の定義には重複する部分も多く、厳密な区別が難しい場合もあります。
重要なのは、「システムが企業のどの業務を支えているか」という実態を理解することです。
情報系システムとの違い
基幹系システムと対比される概念として、情報系システムがあります。
情報系システムは、主にコミュニケーション・情報共有・意思決定支援などを目的としたシステムです。
それぞれのシステムの違いを以下でまとめました。
| 項目 | 基幹系システム | 情報系システム |
|---|---|---|
| 主な目的 | 業務処理の遂行・記録・管理 | 情報共有・コミュニケーション・意思決定支援 |
| 対象業務 | 販売・会計・生産など事業の根幹業務 | メール・スケジュール管理・社内SNS・グループウェアなど |
| システムが停止した際の影響 | 事業継続に致命的な影響を与える可能性が高い | 業務効率は低下するが、ただちに事業停止には至らない |
| 取り扱うデータ特性 | 定型的なトランザクションデータが中心 | 非定型的なドキュメントやコミュニケーションデータが多い |
基幹系システムは事業継続に直結するため、停止すると売上や生産活動が止まるなど重大な影響が生じます。
一方、情報系システムは業務効率には影響しますが、即座に事業が停止するとは限りません。
両者は連携することもありますが、その役割や特性は大きく異なるため、混同しないようご注意ください。
基幹系システムの主な種類

基幹系システムは、企業のさまざまな業務領域に対応するために、多様な種類が存在します。
基幹系システムの代表的な種類は以下の通りです。
- 会計システム
- 人事システム
- 生産管理システム
- 販売管理システム
- 購買管理システム
- 在庫管理システム
- その他基幹系システム
それぞれのシステムが専門的な機能を持ち、企業の業務効率化やデータ管理を支援します。
本章では、代表的な基幹系システムの種類とその概要を紹介します。
会計システム
会計システムは、企業の財務状況を管理するためのシステムです。
日々の取引記録から、試算表・貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を作成します。
主な機能としては、以下のようなものがあります。
- 仕訳入力
- 帳簿作成
- 決算処理
- 固定資産管理
- 支払管理
会計システムは税法や会計基準の変更にも対応する必要があり、正確性と信頼性が求められるシステムです。
決算や税務に大きく影響するため、企業は会計システムを適切に運用する必要があります。
人事システム
人事システムは、従業員の情報を一元管理し、人事関連業務を効率化するシステムです。
採用から退職までの人事データを管理し、給与計算や勤怠管理なども行います。
人事システムは、以下のような機能で構成されることが一般的です。
- 人事情報管理
- 給与計算
- 勤怠管理
- 評価管理
- 労務管理
適切に運用すれば、人事システムは従業員のモチベーション向上や適材適所の人員配置にも貢献します。
また、より良い人事評価や残業の削減など、さまざまな課題を解決するうえでも役立てられるシステムです。
生産管理システム
生産管理システムは、製造業において生産活動全体を計画・管理・統制するためのシステムです。
需要予測から生産計画・資材調達・工程管理・品質管理までをカバーします。
このシステムは、製造プロセスの効率化とコスト削減を目指すうえで重要です。
主な機能は以下の通りです。
- 生産計画立案
- 所要量計算(MRP)
- 工程進捗管理
- 品質情報管理
- 原価計算
生産管理システムによって、リードタイムの短縮や在庫の最適化が期待できます。
生産の効率化を果たすうえで、優れた生産管理システムは不可欠です。
販売管理システム
販売管理システムは、見積もりから受注・出荷・請求・入金に至るまでの一連の販売プロセスを管理します。
顧客情報や商品情報と連携し、販売活動の効率化と売上データの正確な把握を支援するためのシステムです。
このシステムには、以下のような機能が含まれます。
- 見積作成
- 受注登録
- 出荷指示
- 売上計上
- 請求書発行
- 入金消込
販売管理システムは販売実績の分析や営業戦略の立案にも活用されます。
購買管理システム
購買管理システムは、原材料・部品・副資材などの調達業務を管理するシステムです。
発注から入荷・検収・支払までのプロセスを効率化し、購買コストの適正化を図ります。
さらにサプライヤー情報や契約条件なども管理します。
主な機能は以下の通りです。
- 発注依頼
- 見積取得・比較
- 発注処理
- 納期管理
- 入荷・検収処理
- 支払処理
適正な購買活動は、企業の収益性向上に直結するため、製造業において購買管理システムは非常に重要です。
在庫管理システム
在庫管理システムは、原材料・仕掛品・製品などの在庫情報を正確に把握し、管理するためのシステムです。
入出庫管理や棚卸機能を持ち、欠品や過剰在庫を防ぎ、在庫の最適化を目指します。
在庫管理システムは、以下のような目的で導入されます。
- 在庫数量のリアルタイム把握
- 適正在庫レベルの維持
- 滞留在庫の削減
- 保管コストの削減
正確な在庫情報は、生産計画や販売計画の精度向上にも寄与するものです。
また、在庫の適正化はコストを削減し、収益の圧迫を防ぐうえでも重要です。
その他基幹系システム
ここまで紹介した種類以外にも、特定の業種や業務に特化した基幹系システムが存在します。
例えば、以下のようなシステムが挙げられます。
| システムの種類 | 機能 |
|---|---|
| 固定資産管理システム | 企業が所有する土地・建物・機械設備などの固定資産を管理します。 |
| 債権債務管理システム | 売掛金や買掛金などの債権・債務情報を管理します。 |
| 物流管理システム | 商品の輸送や保管など、物流プロセス全体を管理します。 |
自社の業務内容に応じて、必要なシステムを選択・導入することが重要です。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
ERP(統合系基幹システム)との関係性

近年、基幹系システムと並んでERPという言葉が頻繁に登場します。
ERPはEnterprise Resource Planningの略で、日本語では企業資源計画と訳されます。
つまり、企業の持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を統合的に管理し、経営の効率化を図るためのシステムです。
従来、会計・人事・生産・販売などの基幹系システムは個別に構築されたり、運用されたりすることが多くありました。
しかし、ERPは各機能を一つのシステムに統合し、データの一元管理とリアルタイムな情報共有を実現します。
これにより、部門間の連携強化や経営判断の迅速化が期待できます。
ERPのメリット
ERPを導入することで、企業はさまざまなメリットを享受できます。
代表的なメリットは以下の通りです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 経営情報の可視化 | 企業全体の情報をリアルタイムに把握でき、迅速かつ正確な経営判断が可能になります。 |
| 業務プロセスの標準化 | 統一されたシステムを利用することで、業務プロセスが標準化され、効率が向上します。 |
| データの一元管理 | 各部門のデータが一元的に管理されるため、情報の整合性が保たれ、重複入力の手間が省けます。 |
| 内部統制の強化 | 業務プロセスの透明性が向上し、アクセス権限管理などにより内部統制の強化につながります。 |
| コスト削減 | 情報システムの運用保守コストや、業務効率化による間接コストの削減が期待できます。 |
上記のメリットは、企業の競争力強化に大きく貢献します。
ERPのデメリット
一方で、ERP導入にはデメリットや注意点も存在するので注意しましょう。
導入を検討する際には、以下のようなデメリットを十分に理解しておく必要があります。
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 高額な導入コスト | システムのライセンス費用や導入コンサルティング費用など、初期投資が大きくなる傾向があります。 |
| 導入期間の長期化 | 現状業務の分析やカスタマイズ、データ移行などに時間がかかり、導入期間が長くなることがあります。 |
| 業務改革の必要性 | ERPの標準機能に合わせて業務プロセスを変更する必要が生じ、現場の抵抗に遭う可能性があります。 |
| カスタマイズの制約 | 過度なカスタマイズは、バージョンアップ時のコスト増やシステムの複雑化を招くことがあります。 |
| ベンダーロックインのリスク | 特定のERPベンダーに依存する形となり、将来的な選択肢が狭まる可能性があります。 |
ERPの導入は上記のデメリットを考慮し、慎重な計画と準備が求められます。
基幹系システムの形態

主にクラウド型とオンプレミス型の2種類に大別されますが、近年では両者を組み合わせたハイブリッド型なども登場しています
企業の規模や予算、セキュリティポリシーなどを考慮して、最適な形態を選びましょう。
以下では、基本の分類としてクラウド型とオンプレミス型について説明します。
クラウド型
クラウド型システムは、インターネット経由でサービス提供者が管理するサーバー上のシステムを利用する形態です。
利用企業は自社でサーバーやソフトウェアを保有・管理する必要がありません。
クラウド型の主な特徴は以下の通りです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用の抑制 | 自社でサーバー機器を購入する必要がないため、初期費用を抑えられます。 |
| 導入期間の短縮 | 環境構築が比較的容易なため、短期間での導入が可能です。 |
| 運用保守の負担軽減 | システムの維持管理やアップデートはサービス提供者が行うため、運用負担が軽減されます。 |
| 場所を選ばないアクセス | インターネット環境があれば、どこからでもシステムにアクセスできます。 |
| 拡張性 | 利用状況に応じてリソースを柔軟に増減できます。 |
クラウド型はスムーズに導入でき、コストも抑えられるため、容易に活用することが可能です。
オンプレミス型
オンプレミス型システムは、自社内にサーバーを設置し、ソフトウェアをインストールしてシステムを構築・運用する形態です。
企業がシステム全体を直接管理下に置けるうえに、設定によってはオフラインで運用できます。
オンプレミス型の主な特徴は以下の通りです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| カスタマイズの自由度 | 自社の業務プロセスに合わせて、柔軟にシステムをカスタマイズできます。 |
| セキュリティのコントロール | 自社ネットワーク内でシステムを運用するため、セキュリティポリシーを厳格に適用できます。 |
| 他システムとの連携 | 既存の社内システムとの連携が比較的容易な場合があります。 |
| オフラインでの利用可能性 | 構成によってはネットワーク環境に左右されずに利用できる場合があります。 |
| 資産としての保有 | ソフトウェアやハードウェアを自社の資産として保有します。 |
デメリットとしては、高いコストと、導入・運用における専門知識の必要性が挙げられます。
しかし、自社の業態に合わせてカスタマイズできるため、特殊性が高い業界にも適応できます。
基幹系システムの導入プロセス

本章では、一般的な基幹系システムの導入プロセスを解説します。
基幹系システムを導入する際の手順は以下の通りです。
- 課題の抽出とニーズの分析
- ベンダーの選定
- 要件定義
- 導入計画の策定
- システム設計
- 開発
- テスト・検証
- 移行準備
- 運用・保守
基幹系システムの導入は、企業の業務効率や経営戦略に大きな影響を与えるプロジェクトであるため、成功させるには、段階的かつ計画的に進めることが不可欠です。
1.課題の抽出とニーズの分析
まず、現状の業務プロセスにおける課題点を明確にします。
- どの業務に時間がかかっているか
- どのような情報が不足しているか
- 手作業や重複作業は発生していないか
上記の課題を基に、新しいシステムに求める機能や要件を具体的に洗い出します。
関係各部署へのヒアリングや現状業務の可視化が重要です。
2.ベンダーの選定
課題とニーズに適したシステムを提供できるベンダーを選定します。
複数のベンダーから提案を受け、機能・コスト・実績・サポート体制などを比較検討します。
選定のポイントは以下の通りです。
- 自社の業種・業態への理解度
- 導入実績の豊富さ
- 提案内容の実現可能性
- アフターサポートの充実度
- 将来的な拡張性
基幹系システムの導入において、信頼できるパートナー選びがプロジェクト成功の鍵となります。
3.要件定義
選定したベンダーとともに、システムの具体的な仕様や機能を詳細に決定する工程です。
業務プロセスをどのようにシステムに落とし込むか、必要な帳票や画面は何かなどを明確にします。
要件定義が曖昧だと、後の工程で手戻りが発生し、コストやスケジュールの遅延につながります。
ユーザー部門とIT部門、ベンダー間で綿密なコミュニケーションを取り、認識の齟齬がないように進めましょう。
4.導入計画の策定
要件定義で決定した内容に基づき、具体的な導入スケジュール・体制・予算などを計画します。
導入計画の策定では、タスクの洗い出し・担当者の割り当て・マイルストーンの設定などを行います。
リスク管理計画もこの段階で策定し、潜在的な問題への対応策を準備しておきましょう。
関係者全員が導入計画を共有すれば、目標に向かって進むためのロードマップとなります。
5.システム設計
要件定義で定められた機能を、実際にどのようにシステムとして実現するかを設計する工程です。
システム設計には、大きく分けて外部設計と内部設計があります。
| システム設計の方式 | 内容 |
|---|---|
| 外部設計 | ユーザーから見える画面や帳票のレイアウト、操作方法などを設計します。 |
| 内部設計 | データベース構造やプログラムの処理ロジックなど、システム内部の仕組みを設計します。 この設計書に基づいて、次の開発工程が進められます。 |
6.開発
システム設計書に基づいて、プログラマーが実際にプログラムを作成(コーディング)する工程です。
必要に応じて、既存のパッケージソフトウェアのカスタマイズも行われます。
大規模なシステム開発では、複数の開発者が分担して作業を進めることが一般的です。
開発においては、進捗管理や品質管理が重要となります。
7.テスト・検証
開発されたシステムが、要件定義や設計通りに正しく動作するかを検証する工程です。
単体テスト・結合テスト・総合テスト・受け入れテストなど、段階的にテストを実施します。
それぞれのテストの内容は以下の通りです。
| テストの種類 | 内容 |
|---|---|
| 単体テスト | 個々のプログラム(モジュール)が正しく動作するかを確認します。 |
| 結合テスト | 複数のモジュールを組み合わせた際に、連携がうまくいくかを確認します。 |
| 総合テスト | システム全体が業務シナリオに沿って正しく動作するかを確認します。 |
| 受け入れテスト | 実際にシステムを利用するユーザー部門が、要求通りかを確認します。 |
テストを通じて発見された不具合は修正し、品質を高めていきます。
8.移行準備
現行システムから新しいシステムへデータを移行するための準備を行います。
移行する際は、対象となるデータの範囲・移行方法・移行スケジュールなどをあらかじめ計画しておきましょう。
データクレンジング(不正確なデータの修正や整理)も重要な作業です。
また、ユーザーへの操作研修やマニュアル作成もこの段階で進めます。
9.運用・保守
システムが本稼働した後の運用と保守のフェーズです。
日々のシステム監視・障害発生時の対応・定期的なメンテナンスなどを行います。
ユーザーからの問い合わせ対応や、法改正・業務変更に伴うシステムの改修も含まれます。
安定稼働を維持し、システムの価値を最大限に引き出すためには継続的な活動が不可欠です。
新たな不具合や運用の課題が見つかった際は、速やかに対処しましょう。
基幹系システムの選び方

本章では、基幹系システムの選び方について解説します。
基幹系システムを選ぶ際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 導入する目的を明確にする
- 導入する際にバッファを確保する
- 業態に合ったものを選ぶ
- 他のシステムとの連携性を確認する
- 運用のしやすさを意識する
- セキュリティ対策を徹底する
- ノウハウを持つ人材を確保する
基幹系システムの導入は大きな投資であり、企業の将来を左右する可能性もあります。
そのため、ポイントを踏まえて自社に最適なシステムを慎重に選ばなければなりません。
導入する目的を明確にする
まず、基幹系システムを導入する目的を明確にしましょう。
導入する目的を明確にする際は、以下の点を意識してください。
- 業務効率をどの程度向上させたいのか
- コストをどれくらい削減したいのか
- どのような経営課題を解決したいのか
目的が明確であれば、必要な機能やシステムの規模もおのずと見えてきます。
目的が曖昧なままシステムを選定すると、導入後に十分な効果が得られない、あるいは期待に沿わない結果となる可能性があります。
また、不要な機能を搭載したシステムを導入したことにより、無駄なコストが発生するリスクが高まります。
導入する際にバッファを確保する
基幹系システムを導入する際は、バッファを確保しましょう。
システム導入には、予期せぬ問題や追加の要望が発生することがあります。
そのため、スケジュールや予算にはある程度のバッファ(余裕)を持たせておくことが賢明です。
余裕のないタイトな計画では、小さなトラブルが大きな遅延やコストの増加につながる可能性があります。
特に、初めて基幹系システムを導入する場合や、大規模な刷新の場合は注意が必要です。
業態に合ったものを選ぶ
基幹系システムは業態に合ったものを選ぶことが重要です。
企業には、製造業・小売業・サービス業など、さまざまな業種・業態があります。
当然、それぞれの業態で求められる機能や業務プロセスは異なります。
基幹系システムは、自社の業種・業態に特化した機能を持つシステムや、導入実績が豊富なシステムを選ぶことが成功のポイントです。
業界特有の慣習や法規制に対応しているかも確認しましょう。
もし業態に合わない部分や、より拡張したい機能があった際は、カスタマイズも視野に入れる必要があります。
他のシステムとの連携性を確認する
他のシステムとの連携性を確認することも、基幹系システムを選ぶうえで無視できないポイントです。
多くの企業では、基幹系システム以外にもさまざまなシステムを利用しています。
例えば、情報系システム(グループウェアなど)や、特定の業務に特化した専門システムなどです。
新しい基幹系システムが、これらの既存システムとスムーズにデータ連携できるかを確認することは非常に重要です。
連携がうまくいかないと、データの二重入力が発生したり、情報が分断されたりする可能性があります。
その結果、基幹系システムを導入したことでかえって業務に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
運用のしやすさを意識する
運用のしやすさは、基幹系システムにおいて重要なポイントです。
高機能なシステムであっても、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。
運用が難しいシステムだと、業務の停滞を招くだけでなく、かえってコストを増加させる事態につながる恐れがあります。
基幹系システムを導入する際は、実際に利用する従業員にとって直感的で分かりやすい操作性であるかを確認しましょう。
デモンストレーションを受けたり、トライアル版を利用したりして、使用感を確かめることが推奨されます。
また、マニュアルやサポート体制が充実しているかも選定のポイントです。
セキュリティ対策を徹底する
基幹系システムのセキュリティ対策は徹底しましょう。
基幹系システムは、企業の機密情報や個人情報など、重要なデータを扱います。
そのため、セキュリティ対策は万全でなければなりません。
不正アクセス・情報漏洩・データ改ざんなどを防ぐ機能が十分に備わっているかを確認しましょう。
アクセス権限管理・暗号化・ログ監視などのセキュリティ対策があると、リスクを格段に下げられます。
クラウド型の場合は、サービス提供者のセキュリティポリシーや認証取得状況も確認しましょう。
ノウハウを持つ人材を確保する
ノウハウを持つ人材の確保も積極的に実践しましょう。
基幹系システムの導入・運用では、システム導入プロジェクトの推進・要件定義・ベンダーコントロール・運用保守など、各フェーズで専門性が求められます。
そのため、専門的な知識や経験を持つ人材が必要です。
社内に適切な人材がいない場合は、外部のコンサルタントを活用したり、ベンダーのサポートを十分に受けられる体制を整えたりしましょう。
もちろん、従業員のITスキル・ITリテラシーの向上も不可欠です。
人材育成計画を策定し、ノウハウを持つ人材の育成にも取り組みましょう。
まとめ:基幹系システムは企業に不可欠な投資

基幹系システムは、単なる業務効率化ツールではありません。
導入によって、データに基づく経営判断や新規事業展開のスピードが向上し、競争優位性を確立できるため、成長戦略の実現にも不可欠となります。
変化の激しい現代において、企業が持続的に成長していくためにも、柔軟かつ堅牢な基幹系システムを整備しましょう。
自社の現状と将来像を見据え、最適なシステム投資を行うことが、競争優位性を確立するうえで重要な鍵となります。
本記事で紹介したポイントを参考に、理想的な基幹系システムの導入を実現していただければ幸いです。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、