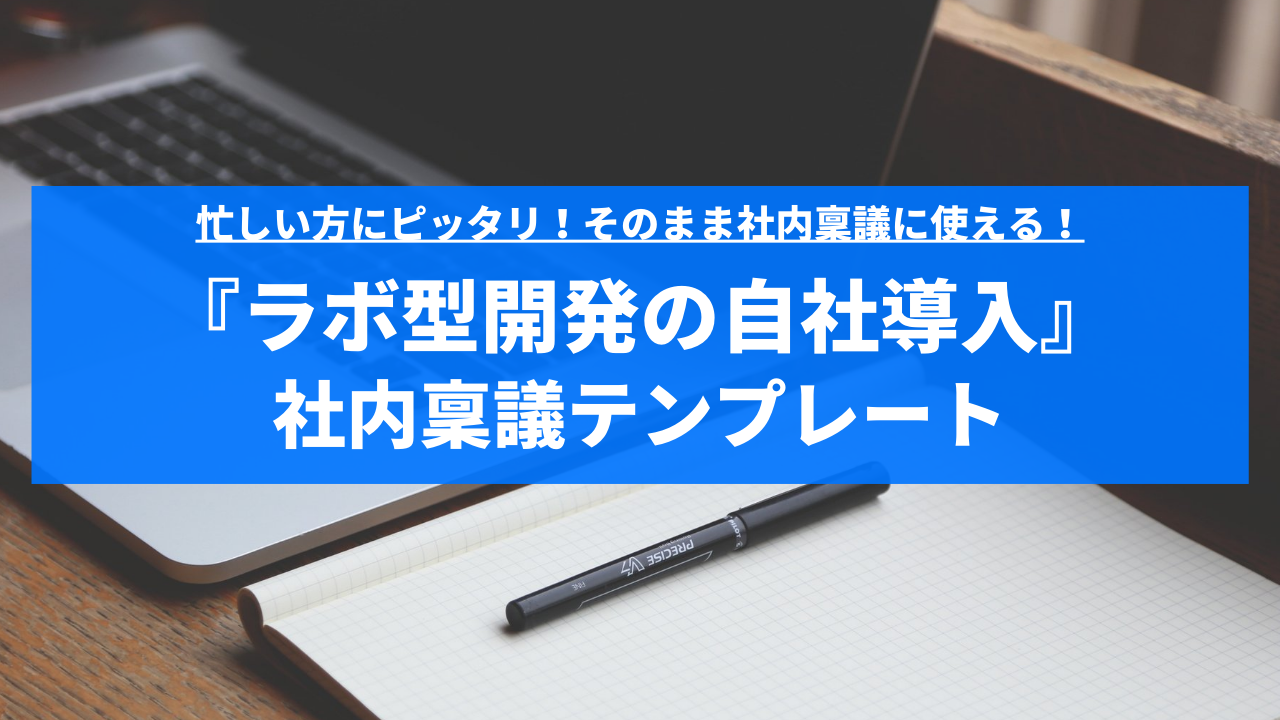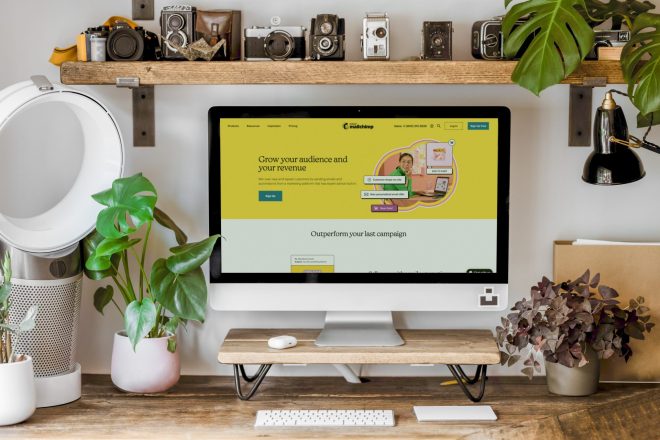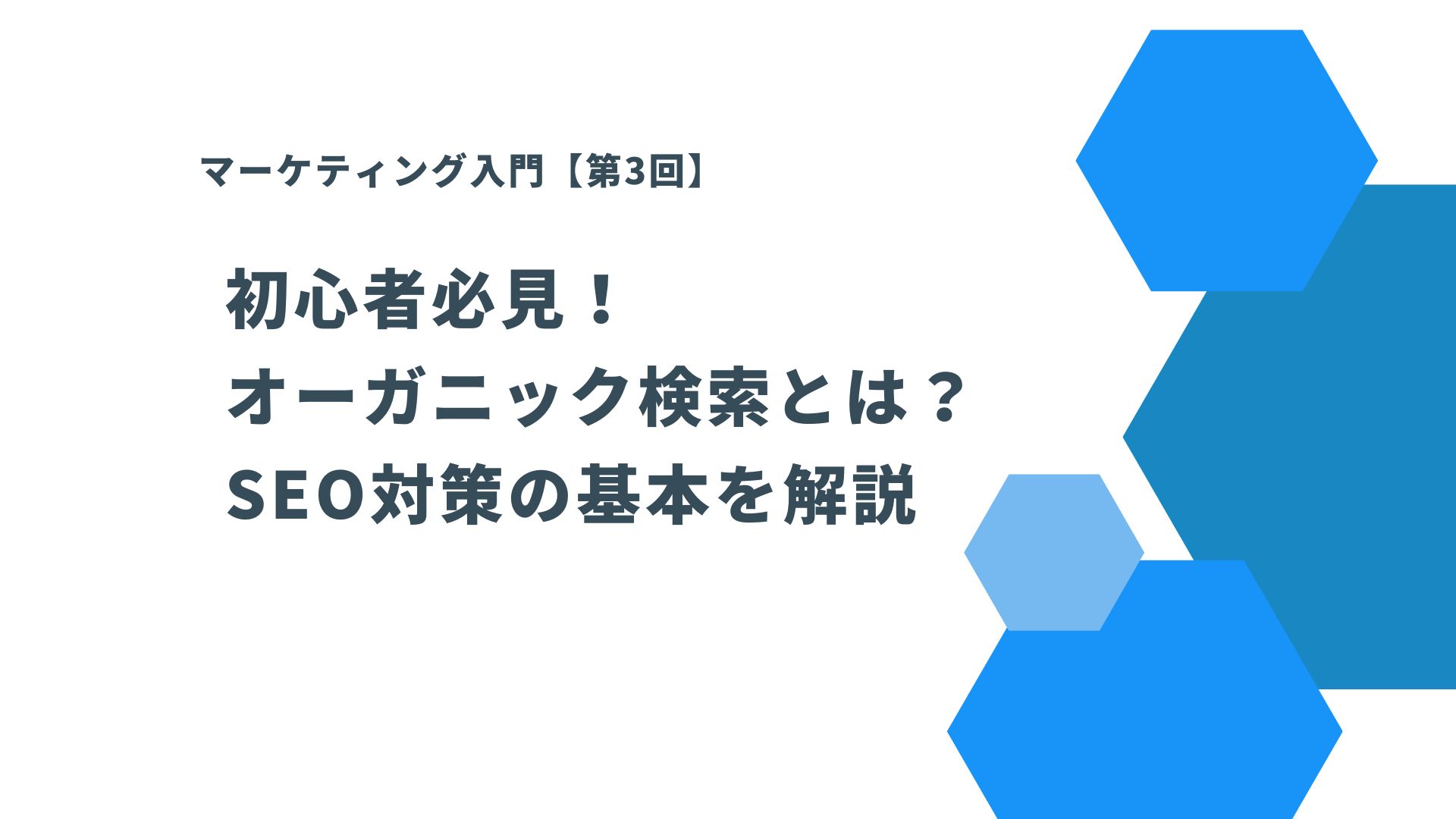システム開発における稟議書の書き方|内容と作成のポイントを解説


こんにちは。Wakka Inc.のWebディレクターの安藤です。
DX推進に伴い、社内システムのIT化に取り組む企業も多いでしょう。
しかし、新たなシステムの導入・開発は、自身の裁量権のみで進めることが難しく、上層部の承認を求められるケースもあります。
上層部の承認を得るために作成し、提出するのが稟議書です。
しかし、稟議書がスムーズに通らないために苦労していたり、企業によっては稟議書のフォーマットが決まっていなかったり、そもそも書き方が分からなかったりとお困りの方もいるのではないでしょうか。
企業によっては稟議書のフォーマットが決まっていなかったり、そもそも書き方がわからない方も。
本記事では稟議書の作成方法や問題点、スムーズに社内稟議を通す方法について解説いたします。
稟議書について悩まれている方や、スムーズに稟議を通す方法を詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
自社で使える『ラボ型開発 社内稟議テンプレート』
稟議書作成に手が回らない方や、
システム開発の社内稟議・稟議書とは

稟議書とは、関係各所に伺いを立てて、承認を得るための書類です。
新規システムの開発は、会社や部署に大きな影響を及ぼすため、1人の裁量権のみで進められないケースが一般的です。
そのため、予算やシステムの概要、開発目的や効果などをまとめた稟議書を作成し、複数の決裁者に承認を仰ぎます。
稟議書の作成から、決裁者の承認を受けるまでの一連の流れを稟議と呼びます。
システム開発の場合、稟議書はプロダクトの開発目的・機能・費用対効果などを明確にしなければなりません。
システムは高度なものであるほど、経営陣と開発陣の間で認識の齟齬が生まれやすいものです。
開発を順調に進行させるには、経営陣から理解を得られるように稟議書の記載を工夫する必要があります。
本章では、稟議書を作成する必要性と管理の在り方を紹介します。
稟議書はなぜ必要とされるか
稟議書は、企業内でのさまざまな手間を省くために必要とされています。
例えば稟議書で承認を受ける場合、関係者による会議を省略できます。
稟議書がなければ、一つの物事を決める際に複数の関係者を集め、その場で承認を得なければなりません。
また、稟議がなく独善的に導入してしまったシステムで、会社全体に悪影響が発生しないとも限りません。
複数の目が入ることで、本当に会社に必要なシステムかを判断できます。
稟議書の作成には、時間と手間がかかりますが、物事を合理的に進めるために重要です。
稟議が必要な業務
稟議が必要な業務にはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に稟議書に分類されるものは、以下のものがあります。
| 購入稟議 | 新たな物品を購入する際に作成 |
| 人事採用稟議 | 中途社員など突発的な採用や、新規採用計画の立案時に作成 |
| 外部企業との契約稟議 | サービスを外部と締結する際に必要 |
| 出張稟議 | 営業活動などで費用が発生する際に伺いを立てる |
主に、実行によりコストが発生するものに対して、稟議が必要となるケースが多いです。
稟議書は合理的に物事を進めるためや、業務に透明性を持たせるためにも必要なのです。
社内稟議を管理する理由
社内稟議は法的に保存を義務付けられた書類ではありませんが、適切に管理される必要があります。
仮に稟議書を廃棄してしまうと、なぜ稟議が通ったか把握できない事態になりかねません。
社内稟議は稟議書だけでなく、必要な添付書類も含めて保存期間、場所を決めて管理する必要があります。
システム開発の稟議書に含める内容

システム開発の稟議書には、以下のような内容を含めましょう。
| 項目 | 内容 |
| システム概要 | 開発するシステムの内容や仕様を記載する。 |
| 開発目的と目標 | 開発する目的や開発に伴う目標を記載する。 |
| 開発体制とスケジュール | システムの開発体制や、開発のスケジュールを記載する。 必要な人員の数や期間も明記する。 |
| 費用と見積もり | 開発に必要な費用の一覧と、各金額の見積もりを記載する。 |
| 費用対効果 | 開発したシステムによって得られる利益や、削減できるコストを網羅し、費用対効果を記載する。 |
| 想定リスクと対策 | 開発に際して想定されるリスクと、当該リスクへの対策を記載する。 |
| 期待される効果 | 開発したシステムに期待できる効果を記載する。 |
| 添付資料 | 必要があれば資料を添付する。 同様のシステムを開発した他社の事例や、市場の動向などを記載した資料のように、稟議書の内容の必要性に説得力を持たせるものが良い。 |
稟議書の記載方法や求められる内容は企業によって異なりますが、システム開発の必要性を伝えられるように記載することがポイントです。
社内のフォーマットの中で、開発の意図を具体的かつ分かりやすく伝える記載を心がけましょう。
システム開発の稟議書を準備する流れ

システム開発の稟議書は以下の流れで準備しましょう。
- 目的と背景を明らかにする
- 現状の課題と解決策を述べる
- 開発体制とスケジュールを組み立てる
- 費用対効果を算出する
- 想定リスクの洗い出しと対策を行う
それぞれのプロセスについて、順番に解説します。
1.目的と背景を明らかにする
まずはシステム開発の目的と背景を明らかにしましょう。
「なぜシステム開発が必要なのか」「開発したシステムで何を得たいか」など、開発の目的や背景を明記すれば、プロジェクトを行う意義を伝えられます。
また、この時点でシステムの要件定義を行えば、読み手が持つイメージのさらなる具体化が可能です。
なお、この時点で開発するシステムの目的を明確にしておくと、他項目の記載を定めやすくなります。
2.現状の課題と解決策を述べる
開発の目的や背景と並行して、現状の課題と解決策も洗い出しておきましょう。
現状の課題に対して、開発したシステムがどのような解決策になるかを明確にしておけば、プロジェクトの有益性を証明できます。
特に現場のニーズでシステムを開発する場合、業務の遂行や収益などに関わる課題の解決策となることを提示しましょう。
自社が抱える課題にアプローチできるシステムであると認められれば、承認される可能性が高まります。
3.開発体制とスケジュールを組み立てる
稟議書の時点でシステムの開発体制やスケジュールを組み立てておくことも重要です。
どれだけ優れたシステムでも、自社の人員やリソースが不足していたり、開発期間が長すぎたりすると実現は困難です。
開発したいシステムの実現可能性を確認するうえでも、開発体制とスケジュールの組み立ては正確に行う必要があります。
なお、開発に際して新しい開発手法を取り入れる際は、新たな手法を導入する意義を説明できるようにしましょう。
最先端の開発手法を取り入れる場合、前例がないため上層部の理解を得られない事態が想定されるためです。
4.費用対効果を算出する
システム開発によって得られる費用対効果の算出は、開発によって得られる利益を可視化するうえで重要です。
特に予算規模が大きいプロジェクトほど、上層部が納得する費用対効果を示さなければなりません。
費用対効果は開発に要するコストや、想定される利益をそれぞれ算定してから算出します。
コストを算定する際はただ金額を記載するだけでなく、それだけのコストが発生する理由も明記しておくと、理解を得やすくなります。
5.想定リスクの洗い出しと対策を行う
開発に際して想定されるリスクの洗い出しや、対策の実施も欠かせません。
あらかじめリスクを洗い出し、対策も決定しておけば、プロジェクトの成功率の高さを明示できます。
加えて、開発に着手する際にも、トラブルへの対応がスムーズになり、プロジェクトの遅延や中断を防止できます。
必要があれば、リスクと対策を網羅したマニュアルを作成しておきましょう。
システム開発の稟議書を作成するコツ

稟議書がスムーズに承認されるためには、書き方のコツを意識することが大切です。
承認者だけではなく、第三者にも分かりやすい稟議書を目指しましょう。
結論を先に述べる
稟議書は、結論から記載することがポイントです。
日頃から多くの書類を目にする承認者にとって、内容が分かりにくい稟議書は敬遠されがちだからです。
実は文章を作成する際はフレームワークがあり、当てはめると比較的簡単に文章を作成できます。
代表的なフレームワークはPREP法です。
| P(Point) | 結論 |
| R(Reason) | 理由 |
| E(Example) | 具体例 |
| P(結論) | 結論 |
まず、単刀直入に結論を述べ、それに理由付けをし、理由に対する具体例を挙げ、結論で締めくくるフレームワークです。
ビジネスシーンではまず結論を求められることが多いので、PREP法による稟議書の作成は理にかなっています。
稟議書のフォーマットが定まっていない場合は、PREP法で稟議書を作成しましょう。
図表やグラフを活用する
図表やグラフを活用し、視覚的にアピールすると、より分かりやすい稟議書を作成できます。
例えば開発したシステムで得られるメリットを図表にしたり、数値の表をグラフ化したりすることで、書き手の意図をスムーズに伝えられます。
読み手からしても、伝わりやすい図表やグラフがあると、内容を把握しやすくなります。
ただし、あまりに多くの図表やグラフを入れ込むと稟議書のボリュームが増加し、かえって読みにくくなりかねません。
図表やグラフは煩雑な情報を分かりやすくしたり、要点を明確にしたりする際に活用するようにしましょう。
メリットを具体的に
稟議の内容について、想定される企業のメリットを記載しましょう。
メリットが不明確であれば、上層部の承認を得るのが難しいからです。
例えば、会社のプロセスをどのように改善するのか、システムの導入で会社が具体的にどのような利益を得られるのかを記載します。
その際は稟議を承認するメリットを定量的に説明できるようにしてきましょう。
定量的なメリットの記載は、稟議の内容により具体性を持たせられるからです。
仮に、導入したいシステムが勤怠管理システムだとします。
勤怠管理システムを導入すれば、事務員の集計作業がトータルで月に30時間ほど削減できるようなメリットがあれば、上層部の同意を得やすくなります。
メリットを具体的、かつ定量的に記載すると通りやすくなる稟議書になる可能性が高まります。
デメリットを省かない
稟議書にはデメリットも記載しましょう。
メリットしかない稟議は、承認者に信頼されにくくなるからです。
また、デメリットやリスクを省略すると、後々問題になる可能性があるので省略は避ける必要があります。
導入する稟議にどのような欠点があり、それをどのように軽減する計画なのかのを記載しておきましょう。
この稟議に対するあらゆる側面が考慮され、問題が発生した場合に対処する用意があることを承認者に示せます。
ビジネスモデルを提示する
稟議書には、詳細なビジネスモデルを提示するとより信頼感が増します。
ビジネスモデルには、以下の項目が含まれていることが望ましいです。
- 誰に対するプロジェクトなのか
- 利益が生まれるならば期間内に生まれる利益の割合
- どのように利益を確保するのか
- プロジェクトの監督・管理者
- 目的に対する評価やチェック事項
- プロジェクトの期限
これらの項目を詳細に記載すると稟議の具体性が高まります。
ビジネスモデルの提示は信頼される稟議書になるだけでなく、複数の関係者の理解が深まるのもメリットの一つです。
これは詳細な項目を設けることで、問題点の発見がしやすくなるためです。
もちろん、項目ごとに問題点があれば、関係者からの指摘を受けやすくもなります。
しかし、指摘を訂正した結果、さらに信頼される稟議書を作成できます。
ビジネスモデルを明確に示すことは上層部の承認を得るためだけでなく、自身の考えを整理するためにも必要不可欠です。
テンプレートを利用する
企業によっては稟議書のテンプレートが用意されている場合があるので、テンプレートにしたがって稟議書を作成しましょう。
公式の書式に従うことでプロジェクトが最適な形で提示され、承認される可能性が高くなるからです。
また、稟議書が同じフォーマットで提出されることで、承認者が稟議書を確認しやすくなります。
現状、社内にテンプレートが用意されていないのであれば、以下の3項目を基本とした稟議書をテンプレートとして作成すると、合理性と理解度が高まります。
- PREP法の各項目を作成
- メリット・デメリットの記載
- ビジネスモデルの提示
システム開発における稟議書の問題点

稟議書は業務を合理的に進めていくために必要なものですが、そのうえではいくつかの懸念点や注意点も生じます。
ここからは、稟議書における具体的な問題を確認していきましょう。
時間がかかる
稟議書の問題点として一番に挙げられるのは、承認までの時間がかかることです。
なぜなら稟議書は基本的には複数の担当者の承認が必要なためです。
直属の上司には承認されたのに、上級管理職には承認されず、稟議書を作り直したケースも珍しくありません。
また、稟議の内容が複雑、又は費用が多額な場合は、承認に数日から数週間かかることもあります。
稟議書は合理性・透明性を確保するには必要なものですが、スピード感が犠牲になっているのは問題になりがちです。
事前の調整や根回しが必要
稟議をスムーズに通すには、関係各部署との事前調整や根回しが必要なケースもあります。
物事が承認されやすくなるためには、稟議書の質がすべてではないからです。
稟議書に書かれている物事のインパクトが大きい場合などは、事前に受け止められるように説明を関係部署に働きかけるほうが無難です。
いざ稟議書を目にした場合、拒否反応が強く出るケースがあるため、前もって下準備をしておくことで、承認を得られる可能性が高められます。
稟議書で動かす金額が大きければ大きいほど、関係部署を詳細に調べ、担当者との綿密な打ち合わせが必要です。
システム開発の稟議を通すためのポイント

システム開発の稟議を通す際は、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 関係部署との事前調整
- 承認者の立場を理解する
- 質疑応答の対策
それぞれのポイントを意識すれば、上層部から稟議の承認を得られる可能性が高まります。
関係部署との事前調整
関係部署との事前調整は、稟議を通すうえで積極的に実施すべき取り組みです。
開発するシステムについて、関係部署とあらかじめ認識を合わせておけば、必要性を理解してもらえるだけでなく、上層部を説得する材料を得るきっかけになります。
また、関係部署が抱える課題やアイデアを取り込むことにより、システムのさらなるブラッシュアップも可能です。
関係部署との事前調整は、基幹システムのような複数の部署を横断して利用するシステムほど重要です。
関係部署から理解を得ていれば、開発後のシステムがスムーズに定着しやすくなります。
承認者の立場を理解する
稟議書を通すなら、承認者の立場を理解することも大切です。
開発陣側の都合だけを訴えても、稟議書は通りません。
上層部が疑問を抱いたり、否定的になったりする理由を予測し、理解してもらうようにしなければ稟議書に説得力を持たせにくくなります。
また、承認者の立場を理解することは、稟議書をさらにブラッシュアップするチャンスです。
承認者が管轄している部署の事情や、自社の収益などを踏まえるなど、上層部の視点に立って作成すれば、より説得力のある稟議書を実現できます。
質疑応答の対策
稟議書を提出する際は、必ず質疑応答の対策を立てましょう。
稟議書の審査を受ける過程で上層部から質問されることは珍しくありません。
場合によっては稟議の内容を覆すような厳しい質問を受ける可能性もあります。
確実に稟議書を通すなら、上層部から受ける可能性がある質問をあらかじめ想定し、適切な回答ができるように準備しましょう。
どのような質問をされるかは上層部の傾向にもよりますが、費用対効果や開発の実現可能性など、承認者が気にするポイントはあらかじめチェックしましょう。
システム開発の稟議後に行うこと

システム開発の稟議が無事に完了したら、いよいよ開発に取りかかります。
その際、以下のような業務も実施しましょう。
- 開発状況の報告と進捗管理
- 費用対効果の検証と改善
それぞれの業務について、順番に解説します。
開発状況の報告と進捗管理
開発状況の報告と進捗管理は、開発プロジェクトが問題なく進行しているか上層部に示すうえで重要な業務です。
稟議書に記載した通りに開発が進み、進捗にも問題がなければ上層部から評価を受けやすくなり、今後もシステム開発を任せられる可能性が高まります。
逆に開発状況が適切に報告されていなかったり、進捗が遅れている状況が続いたりすると、上層部からの評価が低下します。
万が一、プロジェクトの進行に支障が出るレベルで開発が遅れていたり、重大なトラブルが発生したりした場合は、上層部の判断で中断させられる事態になりかねません。
システム開発を成功させるうえでも、開発状況の報告や進捗管理は入念に行いましょう。
費用対効果の検証と改善
費用対効果の検証と改善は、プロジェクトの成果を示すうえで不可欠なプロセスです。
稟議書の通りにシステムが開発できても、必ずしも想定したパフォーマンスを発揮できるとは限りません。
想定外のトラブルが発生したり、新たな課題が生じたりすることにより、期待通りの効果が出ていない状態は十分にあり得ます。
そのため、開発したシステムの費用対効果が発揮されているか検証することは重要です。
パフォーマンス低下の要因が発見された際は、早急に改善を実施しましょう。
PDCAサイクルを回し、開発後も改善をし続けることで、システムの効果を最大化できます。
WaGAZINE読者さま限定!
自社で使える『ラボ型開発 社内稟議テンプレート』
稟議書作成に手が回らない方や、
社内稟議をシステム化するメリット

社内稟議の問題点を解消するには、承認フローのシステム化を図ることが効果的です。
承認手順や稟議書のフォーマットのシステム化で、プロセスの効率性と信頼性を向上させられるからです。
システム化によって得られる具体的なメリットを紹介します。
ペーパーレス化
社内稟議をシステム化する最大のメリットは、ペーパーレス化です。
ペーパーレス化により以下のメリットが得られます。
- 稟議書の印刷コストの軽減
- 該当する稟議書の迅速な検索
- 書類の保管や管理コストの軽減
システムを活用すると、稟議書の作成日などタグ付けされた項目から検索できるので、必要な情報を見つけやすくなります。
また、紙面のように稟議書自体を紛失する恐れもありません。
紛失や検索コストを削減できるのは、ペーパーレス化の大きなメリットです。
承認までの期間短縮
稟議のシステム化によるもう一つのメリットは、承認までの時間が短縮できることです。
紙面管理の場合、該当者が企業にいる間しか稟議書の確認、承認作業ができません。
稟議書は大事な書類のため、社外に持ち出すのを禁止している企業も少なくないからです。
システム化の仕様にもよりますが、PCなどのデバイスがあれば稟議の内容を確認できます。
承認者が出張などで社外にいる場合でも、承認フローが途切れる心配がありません。
また、稟議が差し戻された場合でも、素早く訂正できるため、稟議に関する作業時間の短縮が可能です。
稟議書の問題点とされていた承認時間は、システム化すると解消できる可能性が高まります。
ミスの軽減
稟議書をシステム化すれば、ミスの軽減にもつながります。
承認フローをシステム化する際は、稟議書のフォーマットをテンプレート化するのが一般的です。そのため、記載に必要な項目をもれなく記載できます。
また、承認フローでのミスも軽減されます。
紙面管理の場合、承認フローの途中で稟議書自体を紛失してしまうケースも珍しくありません。
システム化を行うと、デジタルデータが削除されない限りデータは保存されるため、承認フローでのミスも軽減されます。
セキュリティ強化
稟議書のシステム化は、セキュリティの強化にもつながる取り組みです。
システム化された稟議書には、デジタル署名や指紋スキャンの機能を実装できます。
これにより不正行為や、不正確なデータの提出の防止が可能です。
承認フローも可視化されるため、社内の不正防止に大きな役割を果たします。
稟議書のシステム化はオリジナルシステムがおすすめ
稟議書の承認フローをまとめたワークフローシステムは、各社がリリースしています。
しかし、企業独自の仕様に当てはまるシステムは意外と少ないのではないでしょうか。
稟議書の仕様や承認フローのヒアリングからシステムの実装、自社の基幹システムとの連携など超えるべき課題は企業によりさまざまです。
既存のシステムを利用するよりも、オリジナルでシステムを開発したほうが費用、人的リソースの両面でメリットが大きい場合もあるため、新規でシステム化する場合はベンダーへの相談も選択肢に入れましょう。
まとめ:社内稟議のシステム化はベンダーに相談を

社内稟議や稟議書のシステム化は、企業によって取り入れるべき仕様が異なります。
また、システム化を実装すれば必ずしも業務が楽になるとは限りません。
企業の細かい仕様をヒアリングできるのがベンダーの良いところです。
自社の仕様にあったシステムは効率化につながります。
良いシステムの開発は、開発経験がモノを言います。
システム化を行う際は、開発経験が豊富なベンダーに相談するのはいかがでしょうか。
WaGAZINE読者さま限定!
自社で使える『ラボ型開発 社内稟議テンプレート』
稟議書作成に手が回らない方や、

学生時代にWebサイトを自作したことがきっかけでWebの世界に。制作会社でデザイン、WordPressテーマ開発の実務を経て、テクニカル・ディレクターとして大規模サイト構築のディレクションを経験。2021年からWakka Inc.の日本拠点でWebディレクターとして参画。最近はブロックエディタになったWordPressをもう一度、勉強しています。