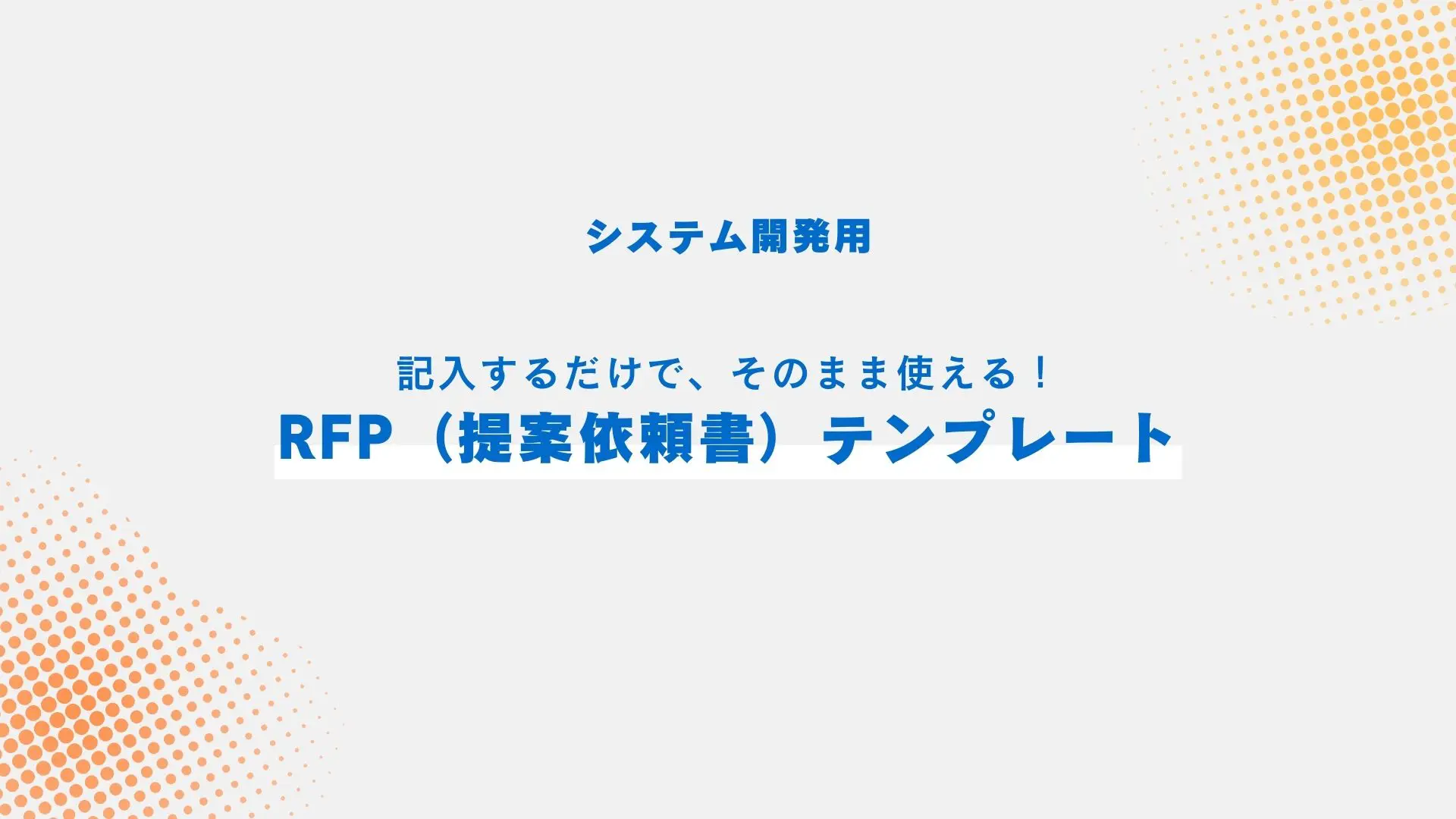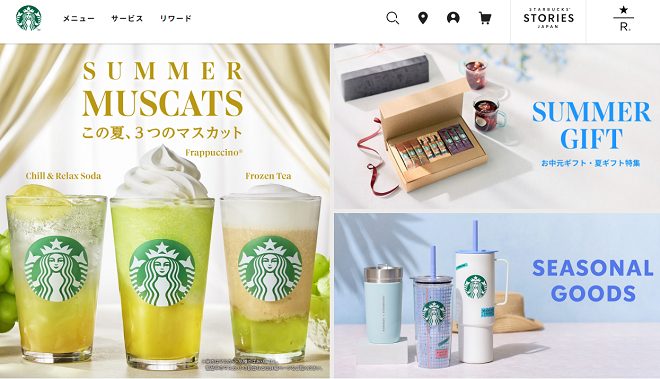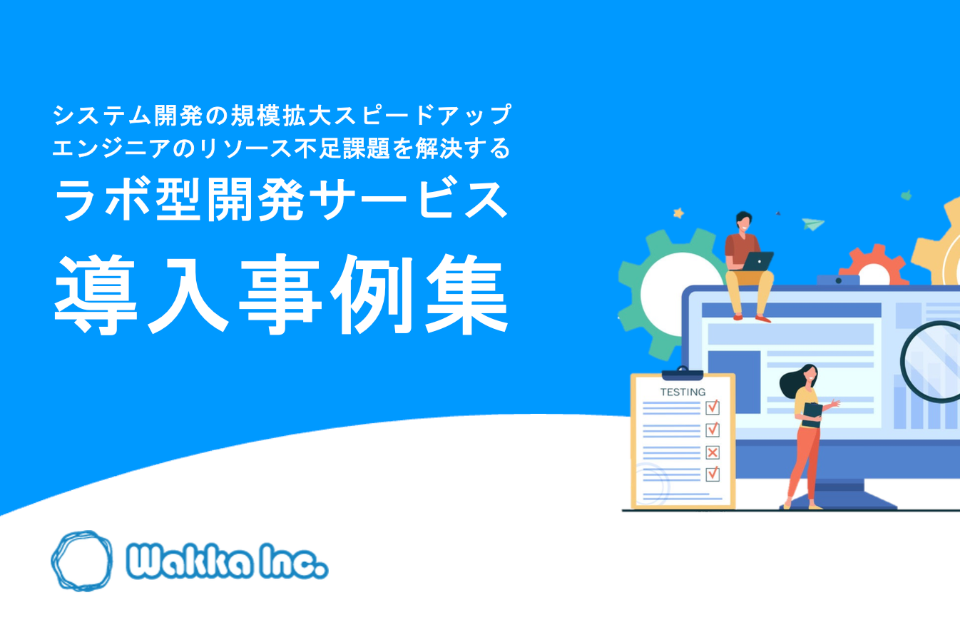バリューチェーン分析とは?やるべき理由や具体的なやり方を解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
バリューチェーン分析は、事業内容の改善や競争力を獲得するために活用できるフレームワークです。
しかし、どこから手を付けるべきかが分からず、もどかしい思いをしている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、バリューチェーン分析の基礎知識や具体的な手順、活用事例などを解説します。
バリューチェーン分析と併用できるフレームワークも、あわせてご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
バリューチェーン分析とは

バリューチェーン分析とは、企業の事業活動を「価値(Value)の連鎖(Chain)」として捉え、どの工程で付加価値が生み出されているかを分析するフレームワークです。
バリューチェーン分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱したもので、企業の競争戦略を考える上で非常に重要な手法とされています。
事業活動の全体像を俯瞰し、自社の強みと弱みを明確に把握するために用いられます。
価値創造のプロセスを可視化するフレームワーク
バリューチェーン分析の核心は、製品やサービスが顧客の手に届くまでの全プロセスを分解し、それぞれの活動が最終的な価値にどう貢献しているかを可視化することです。
原材料の調達から製造・販売・アフターサービスに至るまで、各段階でどれだけの価値が加えられ、どれだけのコストが発生しているのかを明らかにします。
バリューチェーン分析を通じて、企業は自社の競争優位性がどこから生まれているのかを特定できます。
バリューチェーン分析の構成要素
バリューチェーンは、大きく主活動と支援活動の2つに分類されます。
主活動は製品やサービスが顧客に届くまでの直接的な流れを、支援活動は主活動を支える間接的な活動を指すことが特徴です。
主活動と支援活動は相互に連携し、企業全体の価値を生み出しています。
| 分類 | 活動内容 | 概要 |
|---|---|---|
| 主活動 | 購買物流・製造・出荷物流・販売・マーケティング・サービス | 製品やサービスが顧客に直接届けられるまでの一連のプロセス。 モノや価値の創出に直接関わります。 |
| 支援活動 | 全般管理・人事・労務管理・技術開発・調達活動 | 主活動が円滑に進むようにサポートする活動。 企業全体の基盤を支えます。 |
主活動の具体的な内容は以下の通りです。
| 主活動の分類 | 具体的な活動内容の例 |
|---|---|
| 購買物流 | 原材料の調達・検品・保管・在庫管理 |
| 製造 | 製品の加工・組立・品質検査・設備のメンテナンス |
| 出荷物流 | 製品の梱包・在庫管理・倉庫からの出荷と配送 |
| 販売・マーケティング | 広告宣伝・販売チャネルの開拓・価格設定・営業活動 |
| サービス | アフターサービス・顧客サポート・修理・問い合わせ対応 |
続いて、支援活動の具体的な内容です。
| 支援活動の分類 | 具体的な活動内容の例 |
|---|---|
| 全般管理 | 経営企画・財務・会計・法務などのインフラ管理 |
| 人事・労務管理 | 採用・教育・研修・人事評価・労務管理 |
| 技術開発 | 研究開発・製品設計・生産技術の改善・DX(デジタルトランスフォーメーション)推進 |
| 調達活動 | 原材料・設備・備品などの購買活動全般 |
サプライチェーン分析との違い
バリューチェーン分析とサプライチェーン分析は、密接に関連していますが、焦点や目的が異なります。
サプライチェーンが「モノの流れの効率化」に主眼を置くのに対し、バリューチェーンは「価値の創造」に焦点を当てています。
バリューチェーン分析とサプライチェーン分析の項目ごとの違いを見てみましょう。
| 比較項目 | バリューチェーン | サプライチェーン |
|---|---|---|
| 目的 | 付加価値の最大化、競争優位性の構築 | モノや情報の効率的な供給、コスト削減 |
| 視点 | 企業内部の活動が中心 | 企業間の連携(供給者から最終顧客まで) |
| 焦点 | 各活動で生まれる「価値」 | モノやサービスの物理的な「流れ」 |
| 分析範囲 | 自社内の全活動(主活動・支援活動) | 原材料調達から販売までのモノの流れ |
| 意味合い | 価値の連鎖 | 供給の連鎖 |
サプライチェーンはバリューチェーンの主活動の一部、特に購買物流や製造、出荷物流と深く関わります。
バリューチェーンはマーケティングや人事、技術開発といった支援活動まで含めた、より広範な概念です。
バリューチェーン分析が重要な3つの理由

近年では、市場の成熟化やグローバル競争の激化により、単に良い製品を作るだけでは生き残れない時代になっています。
自社の活動を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための有効な手段として、バリューチェーン分析の価値はますます高まっています。
競争優位性を把握できる
バリューチェーン分析を行う最大の目的は、自社の「強み」と「弱み」を客観的に把握することです。
各事業活動を詳細に分解し、競合他社と比較することで、どの活動が自社の競争力の源泉となっているのか(コア・コンピタンス)を明確化できます。
バリューチェーン分析により、感覚的な経営判断ではなく、事実に基づいた戦略的な強みの強化や弱みの克服に取り組むことが可能です。
利益率を改善できる
事業活動を可視化することで、これまで見過ごされてきた非効率なプロセスや無駄なコストの発見が可能です。
例えば、特定の製造工程に過剰な時間がかかっている、あるいはマーケティング費用が十分な効果を生んでいない、といった問題点を明らかにできます。
問題点のコスト要因を特定して改善策を講じることで、事業全体のコスト構造を最適化できるため、直接的に利益率の向上につながります。
経営資源の最適化と全社的な連携強化
バリューチェーン分析によって自社の強みが明らかになれば、そこに経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を集中投下するという戦略的な意思決定が可能です。
一方で、付加価値の低い活動からは資源を引き上げ、外部委託(アウトソーシング)を検討するなど、より効率的なリソース配分が可能となります。
また、分析プロセスを通じて各部署の役割と他部署との関連性が明確になるため、部門間の壁を越えた全社的な連携が促進されるという組織的なメリットも期待できます。
バリューチェーン分析の手順4ステップ

本章では、バリューチェーン分析を実践するための具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。
この手順に沿って進めることで、誰でも体系的に分析を行うことができます。
自社のバリューチェーンを洗い出す
自社の事業活動を主活動と支援活動に分類し、具体的な業務内容をすべて書き出します。
自社のバリューチェーンを洗い出すときは、自社の業界特性を考慮することが重要です。
例えば、販売・マーケティング活動でも、製造業とサービス業ではその内容が大きく異なります。
業界別の活動内容の例は以下の通りです。
| 業界 | 主活動の例 |
|---|---|
| 製造業 | 部品調達 → 設計 → 製造・組立 → 出荷 → 販売 → アフターサービス |
| サービス業(例:ホテル) | 予約受付 → フロント業務 → 客室サービス → レストラン運営 → チェックアウト |
| 小売業(例:アパレル) | 商品企画・仕入 → 店舗運営・接客 → 在庫管理 → マーケティング → ECサイト運営 |
上記のように、自社のビジネスモデルに合わせて活動を具体的に定義することで、分析の精度が高まります。
各活動のコストと価値(強み)を分析する
洗い出した各活動について、かかっているコストと、生み出している価値(強み)を分析しましょう。
コスト分析では、財務諸表や会計データを用いて、各活動にどれだけの人件費や経費が配分されているかを算出します。
価値(強み)の分析では、定量的な指標と定性的な情報の両面から評価します。
分析対象と定量的な評価指標の例は以下の通りです。
| 分析対象 | 定量的な評価指標の例 |
|---|---|
| コスト | 人件費、原材料費、減価償却費、広告宣伝費 |
| 価値(強み) | KPI(顧客満足度、リピート率、不良品率) |
各活動のコストと価値を分析するステップでは、客観的なデータに基づいて、各活動の現状を冷静に評価することが求められます。
強みと弱みを評価する
各活動のコストと価値の分析結果をもとに、各活動が自社の競争力にとって「強み」となっているのか、それとも「弱み」となっているのかを判断します。
評価の際の主な着眼点は、コストと差別化の2つです。
競合他社と比較して、その活動をより低コストで運営できているか、あるいは他社にはない独自の価値を提供できているか、という観点で評価します。
| 評価 | 判断基準の例 |
|---|---|
| 強み | 競合よりもコストが低い・顧客満足度が非常に高い・独自の技術やノウハウがある |
| 弱み | 競合よりもコストが高い・頻繁にボトルネックが発生する・顧客からのクレームが多い |
強みと弱みを分類して評価することで、自社が重点的に投資すべき領域や、早急に改善すべき領域を明確にできます。
VRIO分析で競争優位性を評価する
VRIO分析とは、以下の4つの問いに答える形で強みの質を評価するフレームワークです。
| VRIOの要素 | 評価の問い |
|---|---|
| Value(経済的価値) | その強みは、市場の機会を活かし、外部の脅威を乗り越えるのに役立つか? |
| Rarity(希少性) | その強みを持っている競合他社は少ないか? |
| Imitability(模倣困難性) | 競合他社がその強みを模倣するのは難しいか?(コスト・時間・技術的に) |
| Organization(組織) | その強みを最大限に活用するための組織体制やプロセスが整っているか? |
VRIO分析により、バリューチェーンの中でどこに注力すべきかが明確になります。
自社の資源や能力のどれが持続的な競争優位性の源泉となるかを把握し、適切に取り組みましょう。
バリューチェーン分析の活用事例

バリューチェーン分析の活用事例からは、どのような観点から、どのような結果を目指すべきかのイメージを具体化できます。
本章では、バリューチェーン分析の活用事例を3つ紹介します。
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社|第三の場所という価値を創造
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、購買力とマーケティングという2つの強みをブラッシュアップしています。
高い購買力によって高品質のコーヒー豆を仕入れ、すぐれたマーケティングによって「スターバックスはおしゃれ」というイメージを与えています。
さらに、店舗で提供されているコーヒーカップや紙袋は、顧客にとって一種のステータスです。
バリューチェーン分析によって自社の強みを見出し、競合他社との差別化に成功しているのです。
トヨタ自動車株式会社|トヨタ生産方式による効率化
トヨタ自動車株式会社のバリューチェーン分析とは、原材料調達・生産・販売・アフターサービスなどの一連のプロセスに分解し、プロセスごとの価値創造を分析することです。
代表的なのは、ジャストインタイム・自働化などを追求したトヨタ生産方式(TPS)です。
トヨタ生産方式によって、生産プロセスの効率化と製品の低コスト化を実現しています。
株式会社ユニクロ|SPAモデルによる一気通貫の価値提供
株式会社ユニクロは、おもに下記4つの工程にバリューチェーン分析を活用しています。
| 工程 | 詳細 |
|---|---|
| 調達・製造 | サプライチェーンマネジメントの導入によって原材料調達から納品までを効率化しています。 また、独自の品質管理システムを導入し、高品質で低コストな商品の提供を実現しました。 |
| 商品開発 | 商品企画・デザイン・生産技術・マーケティングなど、部門横断的な商品開発体制を構築しています。 |
| 販売・マーケティング | 直営店・ECサイトとマルチチャネルで商品を販売し、広告・プロモーション・SNSなどを活用しています。 また、直営店を増やすことでブランドイメージの統一性を確保しています。 |
| アフターサービス | 品質保証や不良品に対する交換・返品を受け付けています。 カスタマーサポートを設置し、顧客の声に応えています。 |
上記のように、株式会社ユニクロは、バリューチェーン分析の結果に基づいて市場環境の変化に対応しています。

バリューチェーン分析に活用できる6つのフレームワーク

バリューチェーン分析は、ほかのフレームワークと併用することで、より高い効果を見込めます。
本章では、バリューチェーン分析に活用できる6つのフレームワークを解説します。
PEST分析
PEST分析とは、自社を取り巻く外部環境を4つの視点に分類して分析するフレームワークです。
PEST分析の4つの視点は下記の通りです。
| 視点 | 詳細 |
|---|---|
| 政治(Politics) | 法規制・税制・政権交代などの要素 |
| 経済(Economy) | 景気・金利・為替レートなどの要素 |
| 社会(Society) | 人口増減・ライフスタイル・価値観などの要素 |
| 技術(Technology) | 技術革新・新技術登場などの要素 |
上記4つの視点から分析を進めることで、外部環境に適した戦略策定の立案に役立ちます。
PEST分析で外部環境を俯瞰的に捉え、バリューチェーン分析で内部活動を分析することで、より包括的で戦略的な分析を実現可能です。
5フォース分析
5フォース分析とは、自社の収益性に影響を与える5つの競争要因を分析し、業界の理解を深めるためのフレームワークです。
5フォース分析で用いる要因の詳細は下記の通りです。
| 要因 | 詳細 |
|---|---|
| 競合他社の脅威 | 業界内の既存企業間の競争の激しさ |
| 新規参入者の脅威 | 業界への新規参入が容易かどうか・参入障壁の高さ |
| 代替品の脅威 | 顧客が選択できる代替製品の存在 |
| 売り手の交渉力 | 部品や原材料のサプライヤーからの要求の強さ |
| 買い手の交渉力 | 顧客が価格や品質に与える影響の強さ |
5フォース分析とバリューチェーン分析は、異なる視点から競争環境を分析しつつ、互いに補完しあう関係です。
5フォース分析で外部環境を、バリューチェーン分析で内部環境を分析することで、競争優位性を高めるための戦略を立案できます。
3C分析
3C分析とは、マーケティング戦略や事業計画を立案する際に現状を分析するためのフレームワークです。
3C分析で用いる要素は下記の3つです。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 市場・顧客(Customer) | ターゲットの顧客層のニーズ・購買行動・購買動機などを分析します。 市場規模・成長性・顧客の価値観などを把握し、自社製品がどのように受け入れられるかの理解を深めます。 |
| 競合(Competitor) | 競合他社の強み・弱み・戦略・市場シェアなどを分析します。 競合と比較することで、自社の相対的な立ち位置や差別化すべきポイントを明確化します。 |
| 自社(Company) | 自社の経営資源・強み・弱み・技術力・ブランドイメージなどを分析します。 自社の現状を客観的に把握でき、市場や競合に対する対応力を評価します。 |
3C分析を実施した後にバリューチェーン分析を実施することで、自社の強み・弱みのより詳細な分析が実現でき、効果的な戦略を策定できます。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社の現状を分析するためのフレームワークです。
SWOT分析を構成する要素は下記の通りです。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 強み(Strengths) | 自社の競争優位性や競合他社に勝る特徴。 |
| 弱み(Weakness) | 自社が抱える課題や改善点。 |
| 機会(Opportunities) | 自社にとって有利な外部環境の変化。 |
| 脅威(Threats) | 自社にとって不利な外部環境の変化。 |
バリューチェーン分析で特定した自社の強み・弱みをSWOT分析に落とし込むことで、より効果的に分析できます。
SWOT分析の機会・脅威といった要素と組み合わせて、より適した戦略立案に役立てましょう。
STP分析
STP分析とは、マーケティング戦略を立案する際に用いるフレームワークで、市場の全体像把握・市場発見・競合との差別化などが目的です。
STP分析を構成する要素は下記の通りです。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| セグメンテーション(Segmentation) | 市場を、年齢・性別・所得・ライフスタイル・価値観などのさまざまな軸で細分化する。 |
| ターゲティング(Targeting) | 細分化した市場から、自社製品の投入に適した市場を選定する。 |
| ポジショニング(Positioning) | 市場における競合他社と比較して、自社製品の立ち位置を明確にする。 |
市場と顧客にフォーカスしたSTP分析と自社の状況把握にフォーカスしたバリューチェーン分析は、相互に補完しあう関係です。
例えば、STP分析でターゲットを明確化し、バリューチェーン分析でターゲットに最適な製品を提供するためのコスト構造や効率性を分析するといったように活用できます。
マーケティングミックス(4P・4C)
マーケティングミックスとは、複数のフレームワークを用いて戦略を立てる手法で、4C分析と4P分析を組み合わせるのが一般的です。
まずは4P分析を構成する要素を見てみましょう。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 製品・サービス(Product) | 顧客のニーズを満たす製品やサービスの内容・品質・デザインなどを検討します。 |
| 価格(Price) | コスト・競合・顧客の価値観を踏まえて、価格戦略を検討します。 |
| 流通(Place) | 店舗・オンライン・卸売など、製品やサービスを顧客に届けるために適した流通経路や流通チャネルを検討します。 |
| プロモーション(Promotion) | 製品やサービスの認知度を高めて購買を促進するための広告・宣伝・販売促進活動を検討します。 |
続いて、4C分析を構成する要素です。
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 顧客価値(Customer Value) | 顧客が製品やサービスから得られる価値を検討します。 |
| 顧客コスト(Cost) | 顧客が製品やサービスを購入する際に負担する費用(時間や労力も含む)を検討します。 |
| 利便性(Convenience) | 顧客にとって購入しやすい環境を検討します。 |
| コミュニケーション(Communication) | 顧客と良好なコミュニケーションをとるための方法を検討します。 |
バリューチェーン分析とマーケティングミックスを併用した場合は、価格の適正化や配送システムの改善などにつながります。
なぜなら、バリューチェーン分析によって原材料のコストや物流にかかる時間などを把握でき、マーケティングミックスに落とし込めるためです。
バリューチェーン分析に活用できるテンプレート

より効率的にバリューチェーン分析を実施するために、テンプレートを活用するのも有効です。
実際に、Web上には多くのテンプレートが存在します。
テンプレートを選ぶときは、操作性の良さや項目が自社に適しているかなどのほか、操作する社員の意見を聞くのも大切です。
操作する社員の意見を取り入れることで、テンプレートが定着しやすくなり、最終的に活用されなくなるといった事態を防ぐことができます。
バリューチェーン分析で持続的な競争優位性を築こう

本記事では、バリューチェーン分析の基礎知識とともに、具体的な手順や活用事例などを解説しました。
バリューチェーン分析を活用することで、市場での優位性や競争力を高め、持続的な成長も期待できます。
バリューチェーン分析を活用し、ビジネスのさらなる飛躍を目指しましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、