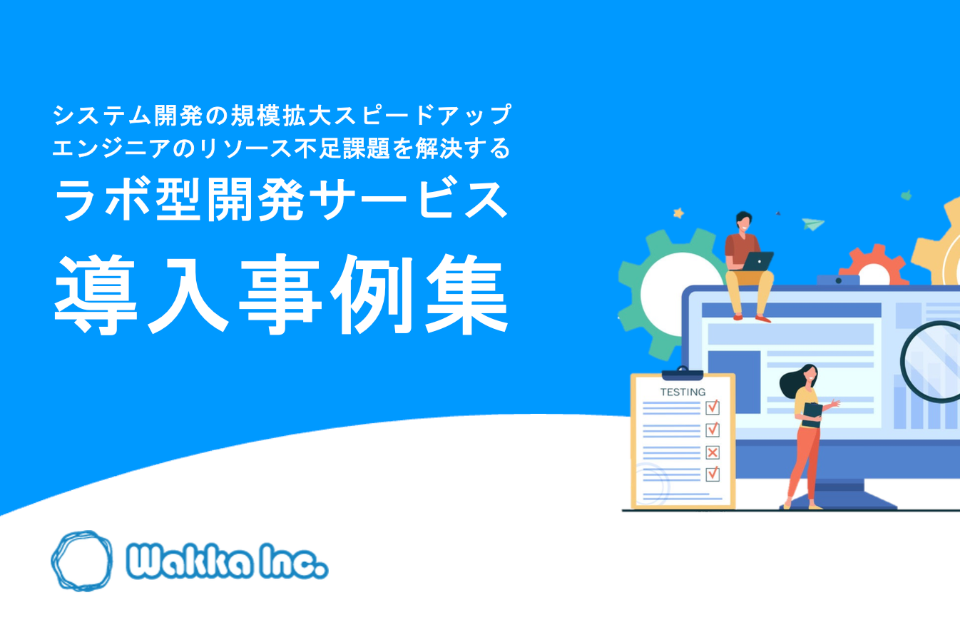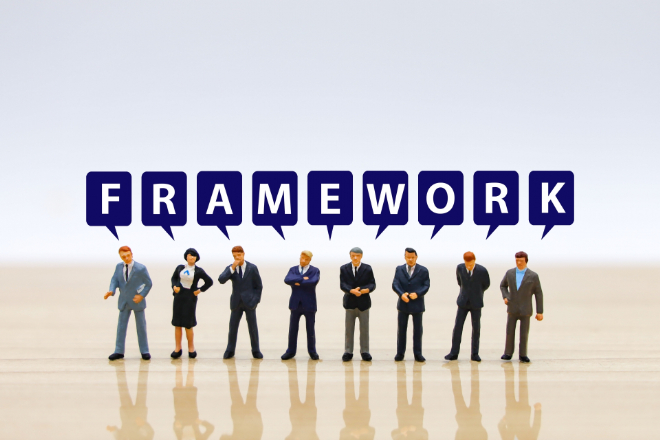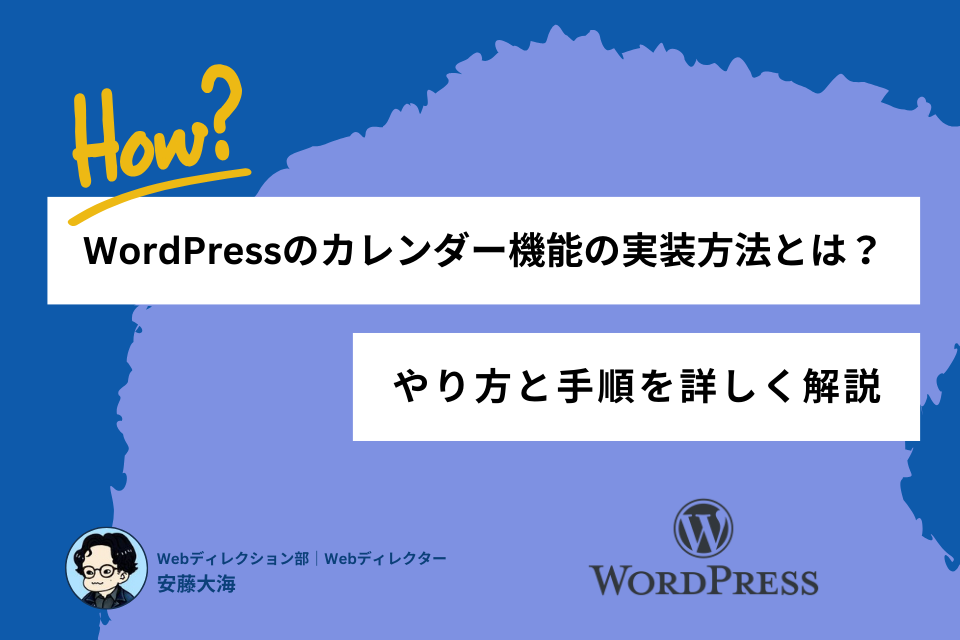AIでシステム開発は可能?具体的なコツ・メリットデメリットと成功のポイントを解説

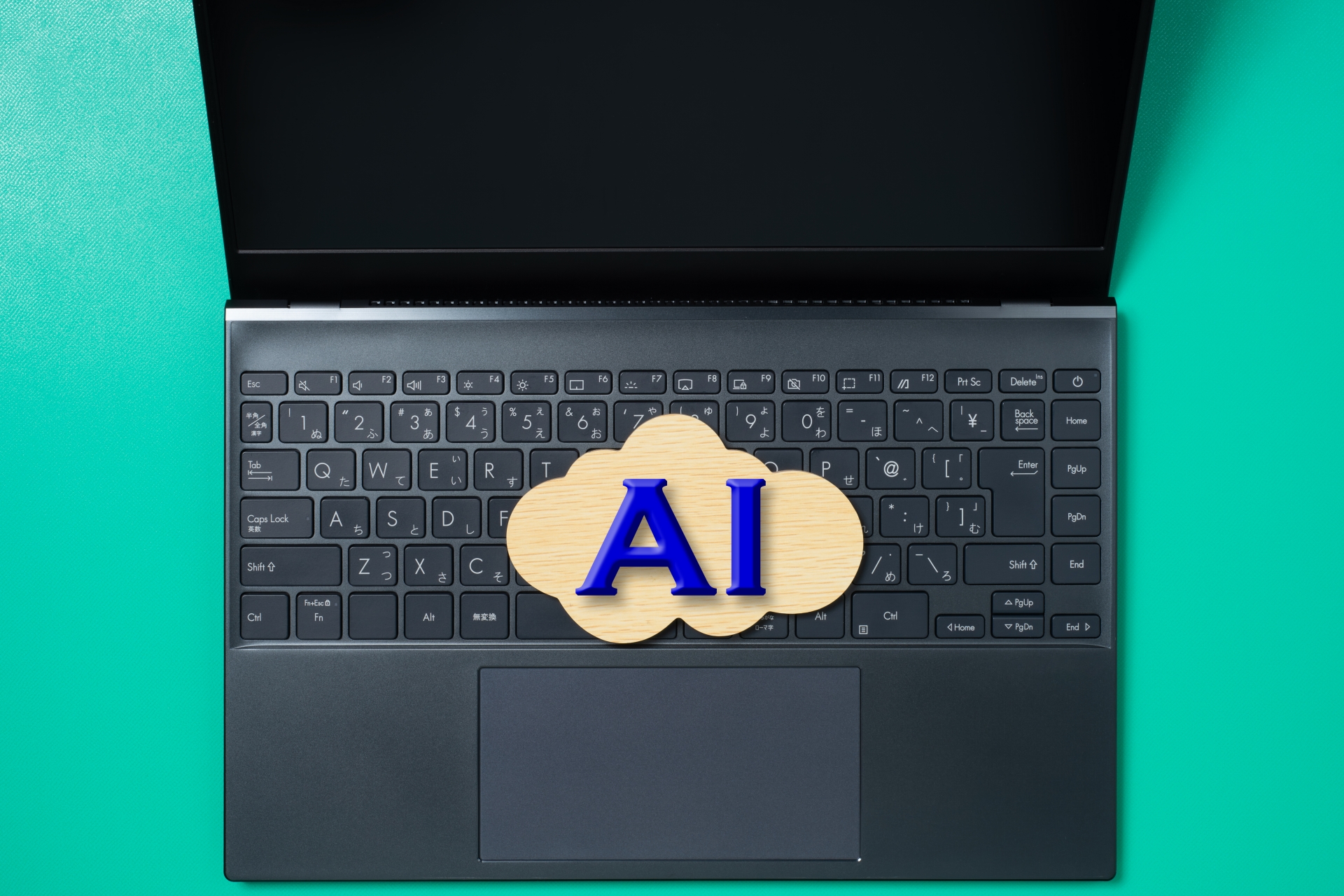
こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
「AIを使えば自分でシステム開発ができるのではないか」
「生成AIをどう活用すれば効率的に開発できるのか」
確かにAIは強力なツールですが、コツを押さえないと成功につなげるのは難しく、最終的には上流工程の設計が不可欠です。
本記事では、AIを活用したシステム開発における可能性と限界、具体的なコツやメリット・デメリットなど成功に導くためのプロの関わり方を解説します。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
AIでシステム開発はどこまで可能か
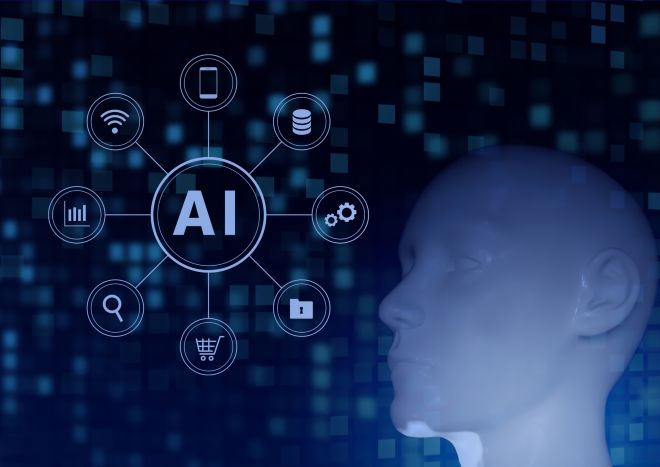
IT人材の不足が深刻化し、市場の競争が激化する中で、システム開発の現場には常に「より速く・より高品質に・より低コストで」といったプレッシャーがかかっています。
こうした状況において、AIは単なる作業自動化ツールにとどまりません。
開発プロセスそのものを根本から変革し、新たな価値を創造する可能性を秘めています。
従来の開発は人間が手作業を重ねる形でしたが、AIを取り入れた開発では、設計・コーディング・テストなどの知的工程をAIが補助します。
AIの支援によって、エンジニアは単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになるのです。
それでは、具体的にAIは開発工程をどのように変えるのでしょうか。
コード自動生成
Google Gemini、GitHub Copilot、OpenAI ChatGPTといったAIツールを使えば、自然言語で指示するだけでコードの断片を自動生成できます。
例えば「PythonでCSVを読み込んでデータを整形する関数を書いて」と入力するだけで、一般的なコード例を提示してくれます。
上記のAIは、よく使われるライブラリやフレームワークとの親和性が高く、ReactやDjango、Flask、Springといった開発環境でも効率的な利用が可能です。
結果として、定型的なコードや ボイラープレート(boilerplate)の記述を大幅に削減でき、開発者は本質的なロジック設計や機能の検討に集中できるようになります。
参考:Gemini・Copilot・ChatGPT・React・Django・Flask・Spring
テストコード・書類生成
AIは、実装された関数やクラスをもとにユニットテストやテストケースを自動生成することも可能です。
AIの自動生成により、従来は時間がかかっていたテストコードの記述作業を効率化できるため、品質を担保しつつスピードを高められます。
また、AIはコードの解説やAPIリファレンスをAIが生成してくれるため、開発チーム内でのナレッジ共有や新規メンバーのオンボーディングが容易です。
結果として、学習コストを削減し、開発スピードと品質の両立を実現できます。
プロトタイプ作成の効率化
新しいサービスやアプリを構想する際には、MVP(Minimum Viable Product)やPoC(Proof of Concept)の段階で、迅速に試作品を用意することが重要です。
AIを活用すれば、モックアップやデモ画面のコードを短期間で生成でき、アイデア検証や社内プレゼン用のデモをスピーディに構築できます。
AIの活用により、プロトタイプ開発にかかる時間が大幅に短縮できるケースもあり、事業の意思決定スピードを大幅に向上させることができます。
本格的な業務システム開発の難しさ
AIはコード生成やテスト作成に有効ですが、本格的な業務システムの開発には限界があります。
複雑な要件定義やアーキテクチャ設計はAIが不得意とする領域であり、ビジネス要件を踏まえた全体設計には人間の知見が欠かせません。
また、長期運用を前提とするシステムでは、セキュリティ・拡張性・保守性の確保が求められ、AIが出力するコードだけでは不十分です。
さらに、UI/UXの改善や仕様検討はユーザーとの対話や人間の洞察が求められる重要な工程です。
AIを使ってシステム開発する具体的なコツ

AIの能力を最大限に引き出すためには、いくつかのコツを押さえておく必要があります。
単にツールを導入するだけでは、期待したような成果は得られません。
AIを真のパートナーとして活用するための、具体的なテクニックを見ていきましょう。
プロンプト設計を工夫する
AIにコードを生成させる際は、曖昧な指示では期待する成果が得られません。
使用する言語やフレームワーク、実現したい処理内容を明確に書くことが重要です。
例えば、PythonでFlaskを使い、「ログイン認証を行うAPIを関数単位で記述して、テストコードも付けてほしい」といった形で成果物の形式まで指定すると生成精度が向上します。
指示を具体化し、検証可能な粒度で依頼するのがコツです。
小さな単位で生成と検証を繰り返す
いきなり大規模なコードを生成させると、不具合の特定や修正が難しくなります。
モジュール単位や関数単位など、小規模に区切って生成し、その都度人間がレビューを行うことで、バグを早期に発見できます。
AIと開発者が協力して、試行錯誤を積み重ねながら品質を高めるプロセスが理想です。
既存の開発フレームワークと併用する
RailsやLaravel、Springといった主要フレームワークと組み合わせて活用することで、AIが生成したコードを効率的に組み込むことができます。
特に定型処理や繰り返しが多い部分ではAIが強みを発揮するため、人間は設計やカスタマイズなど本質的な開発に集中できます。
既存の開発基盤をうまく活かすことで、実運用に耐えうるプロジェクトも進めやすくなるのです。
セキュリティ・規約面を必ず人がチェックする
AIが生成したコードには、思わぬ脆弱性や法的リスクが含まれる可能性があります。
そのため、セキュリティ担当者による精査や、ライセンスや著作権に関するチェックが不可欠です。
さらに、個人情報保護法などの法規制に適合しているかはAIが自動で判断できないため、人間が責任を持って確認する必要があります。
安全性とコンプライアンスを確保することで、安心してAIを活用できます。
AI開発のメリット

AIをシステム開発に導入することには、多くのメリットがあります。
以下の利点を理解し、自社の課題解決にどう活かすかを考えることが重要です。
主なメリットを以下の表にまとめました。
※表は、横にスクロールできます
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 開発スピードの向上 | コードやテストの自動生成により、開発期間を大幅に短縮できる。 |
| 学習コストの削減 | 専門知識がなくても簡単な開発が可能になり、教育負担が軽減される。 |
| プロトタイプを素早く試せる | 事業アイデアを短期間で形にし、提案や検証を迅速に行える。 |
| テストや書類の自動化による効率化 | テストコードや仕様書を自動生成し、工数削減と品質向上を実現できる。 |
開発スピードの向上
AIを活用すれば、定型的なコーディング作業を短時間で自動生成することができます。
こうしたAIの自動生成により、開発者は設計や本質的なロジック構築に集中できます。
初期実装や試作品の開発も大幅にスピードアップし、数日かかっていた作業が数時間で終えることも可能です。
結果として、新規プロジェクトや改修業務の立ち上げが迅速に進められます。
学習コストの削減
従来は専門知識が必要だったプログラミングも、AIを使えば自然言語の指示で実現可能です。
非エンジニアでも簡単なアプリや業務効率化ツールを作れるようになります。
学習コストが下がることで、プログラミング教育に多くの時間を割かずとも成果を上げられるようになります。
社内のIT活用範囲が広がり、現場主体でのシステム導入が進みやすくなることがメリットです。
プロトタイプを素早く試せる
AIのコード生成を活用すれば、新しい事業アイデアを短期間で形にできます。
MVPやPoCといった試作品を素早く作れるため、検証と改善のサイクルも高速で回せるようになるのです。
さらに、経営層へのプレゼン用デモも効率的に準備できます。
意思決定や投資判断を迅速化するうえで、AIは非常に有効な手段と言えます。
テストや書類の自動化による効率化
AIはテストコードを自動で生成でき、品質保証の初期段階を効率化します。
仕様書やコード解説といった書類も自動生成できるため、工数削減に直結します。
AIの自動生成によって、開発者はより付加価値の高い業務に時間を使えるようになるのです。
また、ナレッジ共有や新規メンバーの教育にも役立ち、チーム全体の生産性向上につながります。
AI開発のデメリット・課題

多くのメリットがある一方で、AI開発には注意すべきデメリットや課題も存在します。
以下のリスクを正しく理解し、対策を講じることが、AI導入を成功させる上で不可欠です。
※表は、横にスクロールできます
| デメリット・課題 | 具体的な内容 |
|---|---|
| システム全体設計はできない | 複雑なビジネス要件を理解し、システム全体の最適な構造を設計することはAIにはまだ難しい。 |
| 生成コードの品質・セキュリティリスク | AIが生成したコードに、バグや脆弱性が含まれている可能性がある。 |
| 著作権やライセンスの問題 | 学習データに由来するコードが、意図せず著作権を侵害するリスクがある。 |
| 運用・改善を継続する仕組みがAI単独では作れない | AI単独では、リリース後のユーザーフィードバックをもとにした継続的な改善は行えない。 |
システム全体設計はできない(要件定義・アーキテクチャ設計が弱い)
AIはコードの断片生成には強みを持ちますが、システム全体の要件定義やアーキテクチャ設計は不得意です。
ビジネス要件を理解し、業務フローを踏まえた構造設計を行うのは人間の役割です。
特にゴールが曖昧なままAIに依頼すると、不適切な成果物が出力されやすく、後工程で修正コストが膨らむリスクがあります。
そのため、設計段階では人間が主体となり、AIは補助的に活用することが望ましいです。
生成コードの品質・セキュリティリスク
AIが生成するコードにはバグや冗長な処理が含まれることがあり、品質にばらつきがあります。
また、SQLインジェクションや不十分な認証処理など、セキュリティ上のリスクが潜んでいます。
そのまま運用に組み込むと重大なトラブルにつながる可能性があるため、エンジニアによるレビューとテストが必須です。
さらに、生成コードはプロジェクトの特定要件や既存システムとの整合性も確認する必要があり、単純な置き換えでは十分な安全性や性能を保証できません。
著作権やライセンスの問題
AI生成コードには学習データ由来の知的財産リスクが存在します。
特にオープンソースのコードが混入する場合、商用利用時にライセンス違反となる危険性があります。
GPLなど制約の厳しいライセンスが含まれるケースもあるため、生成コードの出所や使用条件を確認し、法的リスクを回避する体制を人間が整えましょう。
加えて、社内規程や契約条件に照らした運用ルールの整備も不可欠です。
運用・改善を継続する仕組みがAI単独では作れない
システム開発は完成後の運用や改善が不可欠ですが、AIだけでは運用体制の設計やトラブル対応を行うことはできません。
さらに、モデルの精度を維持するには、継続的なデータの更新や再学習が必要です。
そのため、安定した運用や改善サイクルの構築は、人間が主体となって監視・改善計画を策定することが求められます。
また、運用中に発生する予期せぬ問題や仕様変更への対応も、人間が判断と調整を行うことで初めて継続的なシステム安定性が確保されます。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
AIを使ったシステム開発を成功させるコツ

これまで見てきた課題を乗り越え、AIを効果的に活用してシステム開発を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。
技術的な側面だけでなく、プロジェクトの進め方や組織体制にも目を向ける必要があります。
目的・KPIを明確化する
AIを活用したシステム開発を成功させるには、まず何を解決するためのシステムかを明確にすることが重要です。
単に「AIを使う」だけでは方向性がぶれてしまい、期待する成果が得られません。
また、工数削減率やエラー削減率など具体的な成果指標(KPI)の設定によって、導入効果を定量的に評価できるため、改善や拡張の判断もしやすくなります。
さらに、KPIはチーム全員で共有し進捗や結果を定期的に確認すれば、目的達成に向けたスムーズな軌道修正ができます。
データや利用環境を踏まえて設計する
AIの性能は学習データの量と質に大きく依存します。
そのため、どういったデータを使い、どのように学習させるかを事前に確認しましょう。
さらに、ユーザーが利用する環境や既存システムとの連携も考慮し、現場で実運用可能な設計を行うことが成功の鍵です。
加えて、データの偏りや欠損がないかセキュリティやプライバシーに配慮した取り扱いが行われているかも確認し、安心して運用できるよう、設計段階から配慮することが重要です。
PoCで効果検証する
AIを活用したシステム開発では、導入前に小規模なPoC(Proof of Concept)を実施し、効果を確認しましょう。
試作を作り性能や精度、業務上の有効性を検証することで、課題や改善点を早期に把握できます。
PoCの結果を踏まえて段階的に機能を拡張すれば、リスクを最小化しつつ本格運用に移行可能です。
また、ユーザーや関係者のフィードバックを反映させることで、現場ニーズに即した実用的なシステム設計が可能となり、導入後の運用もスムーズになります。
AIと人間の役割分担を決める
AIを活用した開発では、AIの『生成・補助』と人間の『判断・設計・検証』を明確に分担することが成功の鍵です。
AIはコード生成や定型作業の効率化を担当し、人間はシステム全体の設計や品質チェック、意思決定を担います。
こうした役割分担を事前にガイドラインとして整備しておくことで、チーム全体が効率的に作業を進められるのです。
さらに、役割を明確化することで品質の担保やトラブル対応も迅速に行え、AIの強みを最大限に活かしながら、安定した開発プロセスを維持できます。
※表は、横にスクロールできます
| 役割 | AI | 人間 |
|---|---|---|
| 担当範囲 | コード生成、定型作業の効率化 | システム全体の設計、品質チェック、意思決定 |
| 目的 | 開発効率の向上 | 品質担保、トラブル対応、AI活用による安定した開発プロセス維持 |
プロにシステム開発を任せるメリット

AIを活用したシステム開発には、プロンプトエンジニアリングやAIモデルの選定、セキュリティ管理など多くの専門知識と実務経験が求められます。
こうしたスキルを持つ人材を自社だけで確保するのが難しい場合は、AI開発実績が豊富な専門企業へ依頼することも有効な選択肢です。
業界知識を踏まえた要件定義が可能
システム開発の初期段階である要件定義は、成功の鍵を握る重要なプロセスです。
プロは、多様な業界で培った実績をもとに、業界特有の課題や商習慣を理解しています。
そのため、自社では見落としがちな業務フロー上の課題や潜在的リスクを整理し、最適な要件として落とし込むことが可能です。
さらに、単なる業務効率化にとどまらずビジネスモデルや収益構造に沿ったシステム設計を行えるため、長期的にビジネスを支える仕組みとして機能します。
最適なAIモデル・技術選定が可能
AIを活用する際には、機械学習・ディープラーニング・生成AIなど多様な手法があります。
ただし、技術選定の違いによって開発コストや成果の出やすさには大きな差が生じます。
プロに依頼すれば、課題に適したAIモデルの選定だけでなく、インフラやフレームワークの最適化も含めた総合的な提案を受けることが可能です。
実現性とコストのバランスを見極めつつ、開発スピードや精度、運用負荷を考慮した判断が可能になるため安心してプロジェクトを進められます。
セキュリティ・法規制の担保が可能
現代のシステム開発では、セキュリティと法規制への対応は避けて通れないテーマです。
特に、個人情報を扱うサービスや金融・医療などの規制産業では、設計段階から法令遵守を意識する必要があります。
プロは、個人情報保護法やGDPRをはじめとする国際規制、さらに業界特有のセキュリティ要件に対応した経験を備えているため安心して任せられます。
また、脆弱性診断や監査対応などのノウハウも備えているため、リリース後もリスクを最小化し、安定した運用を実現可能です。
開発後の運用・改善フェーズまで支援が可能
システムは導入して終わりではなく、運用や改善を繰り返すことで価値を高めていきます。
プロに任せることで、導入後も継続的なサポートを受けられるのが大きな強みです。
具体的にはAIやデータ分析を用いたチューニング、トラブル発生時の迅速な対応、ユーザーの声を反映した機能追加などが挙げられます。
自社だけではリソース不足になりがちな運用・保守フェーズをプロに委託することで、安定したシステム活用が可能になり、社内はコア業務に集中できる環境を整えられます。
Wakka Inc.のラボ型開発なら安心してAIを活用できる

私たち株式会社Wakka Inc.では、お客様のAIを活用したシステム開発を成功に導くため、「ラボ型開発」サービスをご提供しています。
ラボ型開発のメリットを最大限に活かしつつ、お客様に寄り添う伴走型の開発体制を整えています。
ラボ型開発の特徴(柔軟・長期的に専属チームを確保)
ラボ型開発の大きな特徴は、専属チームを長期的に確保できる点です。
単発の受託開発とは異なり、継続的に同じメンバーが関わることで、知識やノウハウがチーム内に蓄積され、効率的に開発を進められます。
また、事業の成長や市場環境の変化に応じて開発リソースや体制を柔軟に調整できるため、改善や機能追加にも迅速に対応可能です。
システムを継続的に進化させたい企業にとって、長期的な安心感を得られる開発スタイルと言えます。
AIを含む先端技術を取り入れた開発体制
Wakka Inc.は、AIを含む先端技術を積極的に取り入れた開発体制を整えています。
自然言語処理や画像認識、生成AIなどの最新技術を取り入れ、課題に応じた最適な技術を選定・実装可能です。
さらに、海外エンジニアを含めたグローバルな体制を構築しており、多様な知見やスキルを活用しながら柔軟に開発を進められます。
最新技術と国際的なリソースを組み合わせることで、他社にはない、先進的かつ柔軟なシステム開発を実現します。
上流工程から伴走するディレクション力
システム開発では、上流工程である要件定義や設計がプロジェクトの成否を左右します。
Wakka Inc.のラボ型開発は、要件整理の段階から伴走できるディレクション力が強みです。
ビジネスの目的や課題を深く理解した上で、最適なアーキテクチャを設計し、プロジェクト全体をマネジメントします。
進捗管理や品質管理を徹底しながら、開発フェーズでも柔軟に対応できるため、安定した成果を得られます。
コスト効率とスピードを両立できる体制
Wakka Inc.では、国内外のエンジニアを組み合わせた開発体制により、コスト効率の向上とスピードアップが実現できます。
高度な技術を要する部分は国内エンジニアが担当し、運用や定型作業は海外拠点を活用するなど、適材適所で役割を最適化しています。
こうした分業化によって、品質を維持しながらも効率的な開発が可能となるのです。
短期間でのリリースや段階的な改善にも柔軟に対応できるため、限られた予算と時間の中で成果を最大化したい企業にとって最適な選択肢です。
まとめ:AIとプロの伴走を組み合わせて、システム開発を成功させよう

本記事では、AIを活用したシステム開発の可能性から具体的なコツやメリット・デメリット、そして成功のポイントまでを解説しました。
AIは開発効率を高める強力な手段ですが、すべてを任せるのはリスクを伴います。
大切なのは、ポイントを押さえてAIを補助的に活用することです。
いずれにせよ、上流工程の設計やプロジェクトマネジメントには、人間の知見が不可欠です。
Wakka Inc.のラボ型開発なら、専属チームによる長期的な伴走と、AIを最大限に活用したシステム開発が実現できます。
事業成長に直結する開発パートナーをお探しの企業にとって、最適な選択肢として期待できます。
本記事が、皆様にとってAI活用の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、