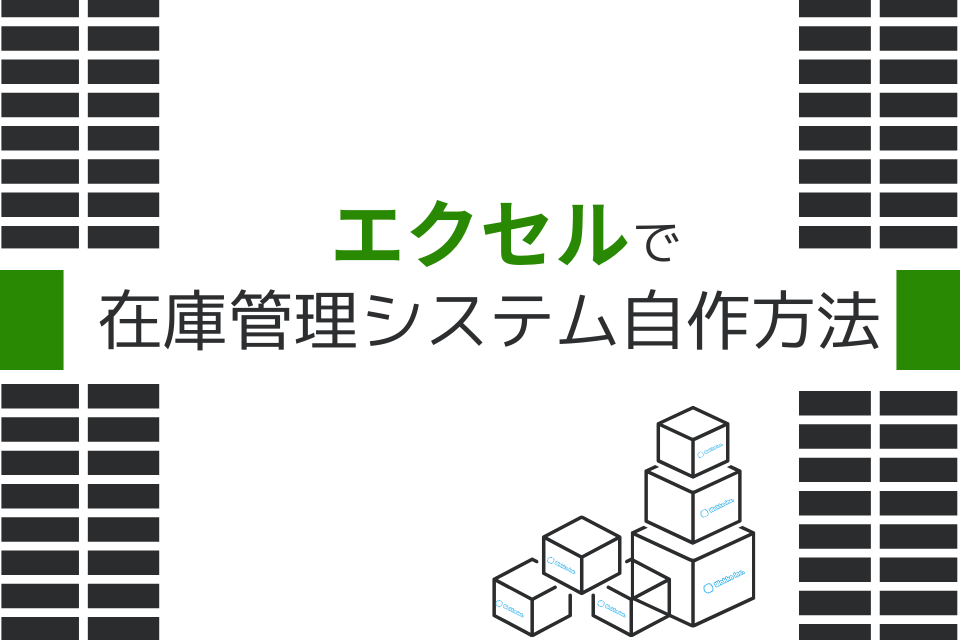入出庫管理とは?基本の流れ・よくある課題・効率化の方法をわかりやすく解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
在庫管理業務の中でも、入出庫管理は重要な業務です。
受注・出荷・仕入管理など関連する業務にも大きく影響するため、入出庫管理は常に正確に行わなければなりません。
なかには、自社の入出庫管理業務を改善したいけれど、どのようなポイントに着目して対策していくべきか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、下記について詳しく解説します。
- 入出庫管理の概要
- 入出庫管理の具体的なやり方
- 問題を解決するためのポイント
自社で適切な入出庫管理を実施するために、ぜひとも本記事をお役立てください。
「システム開発ハンドブックvol.2 在庫管理システム」では、入出庫管理を含むコストと販売機会の効率化を図るための在庫管理について、システムの選び方や導入時の注意点などを解説しています。ぜひ、あわせてご確認ください。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブックvol.2
在庫管理の最適化やシステム化を検討している方にオススメ
入出庫管理の基本と業務の流れ

本章ではまず基礎知識として、入出庫管理の概要について簡単に見ておきます。
入出庫管理とは「倉庫などの在庫状況を管理する業務」
入出庫管理とは、倉庫などの在庫状況を管理する業務です。
倉庫に入ってきた商品、出ていく商品の量を逐一記録して管理します。
そのように聞くと一見、単純な作業のように捉えられます。
しかし、入出庫管理でミスが起きるとその後の生産や販売の業務にも影響します。
そのため、入出庫管理は迅速かつ正確な管理が求められる業務です。
入庫・出庫・在庫管理の違い
入出庫管理では、「入庫管理」「出庫管理」「在庫管理」が密接に関わり合いながら倉庫運用を支えていますが、それぞれの役割は明確に異なります。
- 入庫管理(倉庫に入れる作業の管理)
入庫管理とは、商品や資材が倉庫へ入る際に行う一連の確認・登録作業です。
納品内容のチェック、数量・品番の照合、ラベル付与、棚入れまでが含まれます。誤入庫を防ぎ、正確な在庫データを作るための最初の工程です。 - 出庫管理(倉庫から出す作業の管理)
出庫管理とは、受注や発送指示に基づいて商品を倉庫から取り出し、梱包・出荷するまでの工程を管理する業務です。
誤出荷防止やリードタイム短縮に直結するため、倉庫運営の中でも特に精度が求められます。 - 在庫管理(倉庫内の数量・状態を管理)
在庫管理とは、入庫・出庫の結果として倉庫に残る商品の数量や品質、保管場所などを正しく把握・更新する業務です。
棚卸し、不良品管理、適正在庫の維持などが含まれ、過剰在庫や欠品の防止に欠かせません。
入出庫管理の基本フロー(受注〜出荷まで)
一般的に受注から出荷までの作業は、以下の流れで行われます。
- 見積もり
- 受注
- 受注内容の確認
- 出荷準備
- 出荷
- 納品
- 請求
業態や業種によって多少の違いはありますが、受注から出荷までの作業はおおむね上記のフローで実施されます。
一連のフローをスムーズに実行するには、それぞれの作業を効率的に実施するだけでなく、正確な入出庫管理が不可欠です。
入出庫管理が適切に実施されていないと、在庫数を正確に把握できず、受注しても商品を納品できなくなる事態になりかねません。
機会損失によって利益を失うだけでなく、顧客からの信頼を損なうリスクが高まります。
出庫と出荷の違い
出庫と出荷はよく似た用語ですが、実際は意味が異なります。
一般的に出庫は「需要に応じて倉庫から商品を出すこと」を意味します。
顧客の注文に応じて商品をピッキングし、倉庫から取り出すことはもちろん、別の倉庫や支部に送付するために商品を取り出すことも出庫として扱われます。
つまり、出庫は必ずしも顧客との取引に限定して行われる作業ではありません。
対して出荷は顧客に向けて商品を取り出し、運送業者に引き渡す作業を意味します。
出荷は顧客向けて発送する段階も含んでおり、基本的に外部との取引に際して実施されます。
なお、出庫の定義は企業によって異なる場合がある点には注意しましょう。
企業によっては別の拠点に商品を発送する作業のみを出庫とする場合もあれば、発送先を問わず「倉庫から出す段階」を指して出庫と呼ぶ場合もあります。
入出庫管理はなぜ重要か
入出庫管理を適切に実施できれば、倉庫に商品の在庫がどれくらいあるかを正確に把握できます。
在庫が適切に管理されていることで、商品の出荷や製造においてミスが発生するリスクの低減が可能です。
特に入庫業務は重要です。
在庫の入り口である入庫が正確に行われるかどうかが、在庫管理の質を決めると言っても過言ではありません。
正確な入出庫管理ができていないと、実在庫数とシステム上のデータにずれが生じます。
システムで管理する数値が合っていないと、その先の業務にさまざまな影響が出てきます。
例えば、以下のようなミスにつながる懸念が生じます。
- 出荷業務が円滑に進まず納期が遅れる
- 計画どおりに商品の生産ができない
このように、後続の業務でミスを発生させないためにも、入出庫管理を正確に実施することは重要です。
入出庫管理の方法3つを比較(Excel・ハンディターミナル・システム)
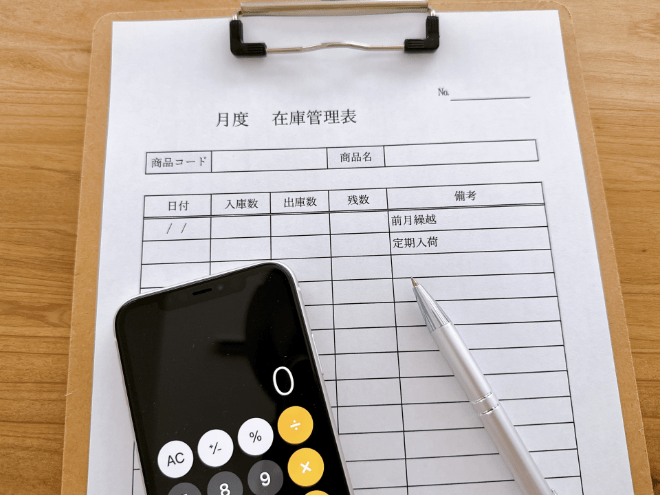
ここでは、入出庫管理の方法を3つご紹介します。
それぞれメリット・デメリットがあるため、自社の状況に適した手法を選びましょう。
| 手書き・Excel | ハンディターミナル | 在庫管理システム | |
|---|---|---|---|
| 導入にかかるコスト | ◎ | △ | △ |
| ミスの防ぎやすさ | △ | 〇 | ◎ |
| 現場での使いやすさ | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ共有のしやすさ | △ | 〇 | ◎ |
【方法1】手書き・Excelで管理する
手書きやExcelを使った入出庫管理は、シンプルで導入しやすい管理方法です。
いずれも、下記のような品目を記入した「在庫管理表」を作成し、入庫・出庫のたびに担当者が数量・検品結果を記録して管理します。
- 保管場所(ロケーション)
- 入庫数
- 出庫数
- 在庫数
- 担当者名
Excel管理は手書きと同じ運用イメージですが、計算式を設定しておけば在庫数の自動計算できるため、手書きより負担が軽減できます。
手書きやExcelで入出庫管理するメリット・デメリットは、下記の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で始められる | 人の手での記入が前提のため、入力ミスが起きやすい |
| 誰でも扱えるため、すぐに運用できる | 複数拠点・大量SKUには不向き |
| フォーマット変更が容易で改善しやすい | リアルタイム更新が難しく、在庫ズレが発生しやすい |
ハンディターミナル・バーコードで管理する
あらかじめ在庫の商品にバーコードを付与し、ハンディターミナルを使用する方法も多くの企業で導入されています。
ハンディターミナルを使用すれば、効率的に入出庫を管理できます。
商品のバーコードやQRコードを読み取ることで、手作業による入力が不要になるためです。
バーコードやQRコードから読み取った情報は、自動的にデジタル化されます。
スキャンするだけで在庫数の把握ができるため、手書きやExcelの在庫管理表と比べて、手入力の手間や入力ミスを減らせます。
在庫管理システムで管理する
より効率的かつ正確に入出庫管理を行うなら、在庫管理システムの導入が効果的です。
バーコードやハンディターミナルを使い、その後のデータ処理・在庫更新までをすべてデジタルで一元管理できる点が強みです。
在庫データはリアルタイムでデータベースに反映されるため、入庫・出庫のタイミングで瞬時に在庫数が更新され、担当者全員が最新情報を共有できます。
また、入力ミスを防ぐチェック機能や、自動計算・自動アラートなどの仕組みも備わっているため、人的負担が大幅に軽減されます。
在庫管理システムで管理するメリットは、下記の通りです。
- 多拠点・多人数でも管理しやすい
全拠点のデータがクラウド上で統合されるため、どこからでも同じ最新データを参照でき、拠点ごとの在庫差異や重複発注のリスクが大幅に減ります。
また、複数の担当者が同時に作業してもデータが衝突しにくく、属人化も防げるため、大人数での運用にも向いています。 - 自動化とリアルタイム管理が可能
入出庫のスキャン後はシステムが自動で在庫数を更新し、棚卸・発注点管理・ロケーション管理なども自動化できます。
リアルタイムで数量が反映されるため、在庫ズレの早期発見や欠品・過剰在庫の防止にもつながります。
入出庫管理でよく起こる課題
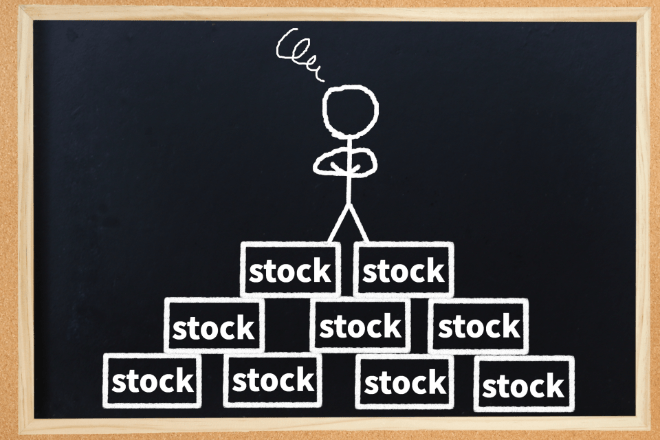
本章では、入出庫管理業務を実施する中でよく起こる、代表的な問題を解説します。
対策もあわせて説明するので、ぜひ参考にしてください。
在庫差異が生じる
入出庫管理が適切にできていないと、在庫差異が生じる可能性が高まります。
在庫差異とは、在庫と帳簿データがずれることです。
具体的には、記録タイミングがバラバラだったり、記入漏れが発生したりすることで在庫差異が生じます。
誤出荷やピッキングミスが起こる
誤出荷やピッキングミスは、顧客や取引先からの信頼を損なう重大なミスです。
商品の選択ミスや数量の誤認などは、確認不足や勘違いなどのヒューマンエラーによって発生します。
また、入出庫管理が適切にできておらず、正確な在庫数が分かっていない状況も、誤出荷やピッキングミスを誘発するため要注意です。
滞留在庫ができてしまう
入出庫管理が不適切だと、滞留在庫が発生するリスクを高めます。
滞留在庫とは、売れ行きや品質に関わらず、出荷の見込みがないまま長期間在庫に滞留している状態の商品です。
入出庫管理を手作業で行っている場合、情報がリアルタイムで更新されないため、滞留在庫が生じてしまいます。
属人化しやすい
入出庫の業務は、管理担当者の情報やノウハウが依存すると、業務が属人化してしまいます。
属人化が進むと、現場業務をスムーズに回すために特定の担当者が必要不可欠になり、異動や離職が起きた場合は業務が停滞します。
業務の属人化は、個人のメモやローカルでの管理に依存して、全員に情報・ノウハウを共有できていない場合に起きやすいです。
在庫情報がリアルタイムに更新されない
入出庫が頻繁に行われると、在庫数は常に変動していきます。
そのため、手書きやExcelによる在庫管理表を作成して運用していると、在庫がリアルタイムで更新されないことが問題です。
例えば、受注から出荷までのタイムラグ、入荷から入庫までのタイムラグが適切に管理できていない場合、次のような事態が発生する可能性が高まります。
- 在庫が引き当てられているのに気づかず重複して受注してしまう
- 入庫によって在庫が増えているのに気づかず受注機会をロスしてしまう
また、入出庫の業務を行っているその場で情報を入力できないために、在庫情報がリアルタイムに更新されない事態も課題です。
例えば、入庫時の検品結果をメモで控えておいて、あとから事務所のPCで結果を更新する場合などが当てはまります。
なるべく在庫情報がリアルタイムに把握できるよう、課題を解決していく取り組みが必要です。
入出庫管理の課題を解決するための対策
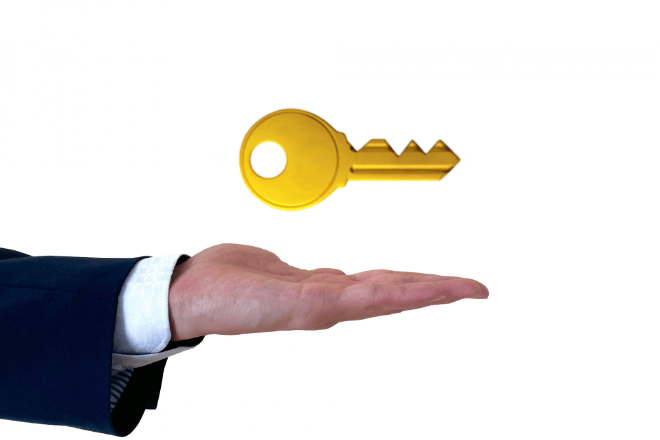
本章では、入出庫管理の問題を解決する方法を解説します。
業務フローやルールを統一する
入出庫管理の精度を高めるには、業務フローを見える化するだけでなく、「全員が同じルールで動く状態」をつくりましょう。
部署や担当者ごとにやり方が異なっていると、どれだけフローを整えても、ミスや在庫差異はなくなりません。まずは、入出庫に関わる業務について、次の点を洗い出し、標準フローとして整理しましょう。
- どのようなタスクが、いつ・どの順番で実施されているか
- 誰が、何の目的でそのタスクを担当しているか
- 具体的にどの手順で作業を行うべきか
そのうえで、作成したフローとルールを組織内で、次のような観点で共通化できているかを確認しましょう。
- 特定の担当者だけに過度な負荷や判断が集中していないか
- 必要なタイミングで必ずチェックが入る仕組みになっているか
- エラー・破損・数量不一致などのイレギュラー発生時の対応手順が決まっているか
入出庫管理の業務フローをできるだけ具体的に可視化し、マニュアルやチェックリストとして統一ルールに落とし込むことが、入出庫管理の課題解決につながる対処法です。
作業動線を改善する
作業動線の改善は、入出庫管理やピッキング作業の改善において不可欠な施策です。
作業動線が不明瞭な状態だと、入出庫管理やピッキング作業の非効率化を招きます。
特に在庫数が多い企業の場合、作業動線を改善しないとヒューマンエラーが発生しやすくなり、パフォーマンスが悪化する恐れがあります。
作業動線を改善する際は、入出庫管理・ピッキング作業・出荷準備など、一連のフロー全体を整理し、課題の洗い出しを行いましょう。
各プロセスの課題を洗い出し、それぞれに応じた対策を講じれば、作業動線を最適化できます。
バーコードなどで自動化する
入出庫管理の精度と効率を高めるには、バーコードやQRコードを活用した自動化が効果的です。
手書きやExcelでは、ヒューマンエラーのリスクが発生しやすいですが、バーコードを読み取る方式なら、数量・品番・ロケーションなどの情報を正確に登録できます。
また、バーコードスキャンは誰が担当しても同じ手順で作業できるため、属人化を防ぎ、全員で統一ルールを徹底しやすくなる点も魅力です。
さらに、読み取ったデータはそのままシステムに反映されるため、リアルタイムに在庫数が更新され、出荷残や欠品リスクの早期発見できます。
在庫管理システムを導入する
在庫管理システムを導入し、搭載された機能を有効活用すれば、入出庫管理業務の精度の向上が可能です。
入力チェックや登録結果の確認機能など、在庫管理システムには人の手による操作でミスを起こすリスクを低くするための機能が搭載されています。
システムの利用方法や手順が関係者に共有されるため、業務の属人化解消にもつながります。
また、登録された入出庫情報などはデータベースに反映して一元管理されます。
そのため、常に正確な在庫状況の把握が可能です。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブックvol.2
在庫管理の最適化やシステム化を検討している方にオススメ
正確な入出庫管理がもたらすメリット
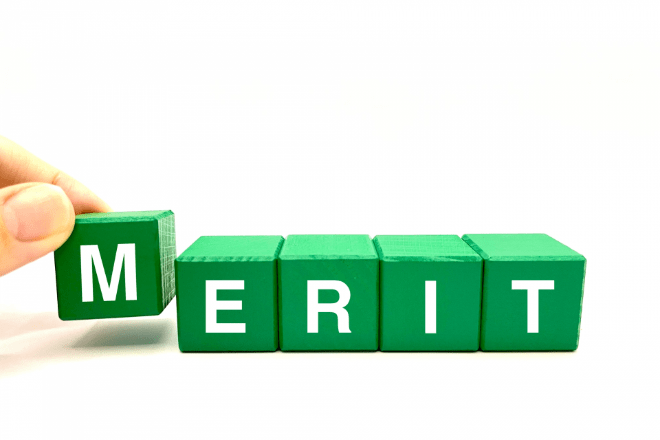
本章では、正確な入出庫管理を行うことでどのようなメリットが得られるか、詳しく見ていきましょう。
業務が効率化できる
まず直接的なメリットとして、業務を効率化できることが挙げられます。
正確な入出庫管理ができているかどうかは、在庫データの正確性に現れるものです。
つまり、入出庫管理が適切であれば、データ上の在庫データと倉庫や店舗の実在庫は一致します。
もし、正確な入出庫管理ができていなければ、データ上の在庫データと倉庫や店舗の実在庫が一致しません。
データ上の在庫と実在庫がずれた状態で放置されると、下記の課題が生じます。
- 在庫棚卸の業務で在庫数の補正や原因の調査に手間がかかる
- 受注や出荷の業務でイレギュラーな対応が増える
例えば、理論在庫と実在庫がずれている状態では、受注時に引き当てたはずの在庫が出荷時にはなく、次のようなイレギュラー対応が必要です。
- 次回の入荷日を確認して納期を調整する
- 商品を注文した顧客に納期遅れのお詫び連絡を出す
最悪のケースでは受注が取り消され、販売機会のロスになりかねません。
しかし、入出庫管理が正確にできていれば、イレギュラーな対応が減るため、業務全体として効率化が期待できます。
在庫状況をリアルタイムに把握できる
入出庫管理がリアルタイムで正確に実施されるようになれば、在庫データの正確さが保証されます。
常に正しい在庫状況を把握できれば、イレギュラーな対応が減って業務は効率化されます。
もちろん、在庫データの信頼性も上がるため、在庫データを利用した業務品質の向上が可能です。
無駄なコストを削減できる
正確な入出庫管理の実現は無駄なコストの削減にもつながります。
入出庫管理によって在庫を適正化することにより、滞留在庫を防げるため、管理コストの削減が可能です。
さらに在庫数のずれをなくすと、ずれが生じるたびに確認する必要がなくなるので、人件費の抑制にもつながります。
また、入出庫管理を自動化できる在庫管理システムを導入すれば、人件費の削減にもつながります。
在庫管理システムは手入力や手書きによる入出庫管理よりもスピーディーに記録できるうえに、情報共有も手間がかかりません。
結果的に作業を効率化できるため、入出庫管理にかかる人件費を減らし、さらなるコストダウンが実現できます。
キャッシュフローの健全化につながる
正確な入出庫管理ができていないと、前述したようにデータ上の在庫と実在庫で差異が生まれ、受発注や生産業務にも影響が出てきます。
不正確な在庫データをもとに受発注や生産計画が作成されると、以下のトラブルが発生するため、在庫データは常に適正化しなければなりません。
- 誤受注による販売機会の損失
- 実態と合わない生産計画の作成
入出庫管理が正確に実施されていると、受発注業務や生産計画も精度が高まります。
データ上の在庫と実在庫の差異が発生せず、在庫データの正確性が向上するためです。
正確な在庫データを運用できれば、受注・出荷・生産のための部品の仕入れなども適切なタイミングで実施でき、最終的には自社のキャッシュフローの健全化が可能です。
在庫管理システムの導入方法

在庫管理システムを導入する代表的な方法について解説します。
無料の在庫管理システムを利用する
在庫管理システムには、フリーソフトや無料プランで利用できるものがあります。
コストをかけずに利用できるため、試験的に在庫管理システムを導入したいときにおすすめです。
また、オープンソースで提供されている在庫管理システムもあります。
自社にある程度のプログラミングスキルを持った人材がいれば、自社向けにカスタマイズしたうえで導入できます。
なお、無料プランで利用できる在庫管理システムは、有料プランへの切り替えを前提としているものが少なくありません。
そのため、一部の機能しか利用できなかったり、機能に制限がかかっていたりすることが多いので注意が必要です。
有料の在庫管理システムを利用する
無料で利用できるフリーソフトや、在庫管理システムの無料プランでは、機能やユーザー数などに制限が設けられています。
また、オープンソースを利用して在庫管理システムを構築するには、技術力と開発期間が欠かせません。
トータルのコストやメリットを考えると、有料の在庫管理システムの導入が適切な場合もあります。
したがって、有料の在庫管理システムも視野に入れて検討しましょう。
有料の在庫管理システムであれば、機能の制約がなく、導入期間も短くて済みます。
追加料金を支払えば機能の追加や拡張も可能です。
入出庫業務の知見があるシステム開発会社に発注する
無料や有料の在庫管理システムで自社に適した製品が見つからなければ、システム開発会社に発注して自社オリジナルの在庫管理システムを開発する方法もあります。
システム開発会社に発注して開発する場合、フルスクラッチと呼ばれる開発手法を使用して開発を進めるケースが一般的です。
フルスクラッチ開発のメリットは、オーダーメイドで自由にシステムの機能を設計できる点です。
自社の業態や従業員のスキルに合わせて設計できるため、自社の業務に合わせた使い勝手の良いシステムが導入できます。
ただし、フルスクラッチ開発はゼロから開発を進めるため、既製品の在庫管理システムを利用するよりも、導入期間が長期になる点には注意しましょう。
また、開発費用が高額になることも留意してください。
システム開発会社に発注する場合、会社によって得意とする業務分野が異なる点にも注意が必要です。
できるだけ、入出庫業務に関する知識や在庫管理システムの開発実績が豊富な会社を選びましょう。
在庫管理システムを選ぶポイント

在庫管理システムはさまざまな種類が出ていますが、自社に最適なシステムを選ぶにはどのようにすれば良いでしょうか。
本章では、在庫管理システムを選ぶ際に考慮しておきたいポイントを解説します。
自社の業務内容に合っているか
導入する在庫管理システムを選ぶ際にまず確認しておきたいのは、自社の業務内容に合っているかです。
自社の業務内容と合っているかを確認する際は、以下を重視しましょう。
- 自社の商品に適しているか
- 在庫管理の対象範囲に適しているか
加えて、商品の点数やシステムを利用する拠点数などによっても、適したシステムは変わる点にも注意が必要です。
アパレル製品・雑貨・賞味期限の短い食品など、取り扱う商品によっても必要な機能が変わります。
また、在庫管理の対象範囲とは主に以下を指しており、在庫管理の対象範囲によって適したシステムは変わります。
- 店舗の在庫を管理するのか
- 製品や部品の倉庫の在庫を管理するのか
- ECサイトで取り扱う商品の在庫を管理するのか
さらに、自社で抱えている入出庫管理に関する課題を明確にし、自社の課題を解決するのに役立つ機能を備えているかも見ておきましょう。
カスタマイズが可能か
自社の商品・サービスや業務内容と照らし合わせて在庫管理システムの機能を確認しても、なかなかぴったり合うシステムは見つからない可能性があります。
しかし、自社の状況に合わせてカスタマイズできるシステムなら、自社の業務に合わせて運用できます。
そのようなケースにも対応するためには、どの程度柔軟にカスタマイズができるかという点も確認しておきたいところです。
既存システムと連携できるか
自社ですでに運用している既存システムがあれば、既存システムとの連携が可能かも確認しておきましょう。
既存システムとデータを連携できれば、業務の自動化や効率化が期待できます。
受発注管理・販売管理のシステムや、ECサイトと連携して在庫情報をリアルタイムに自動更新できれば、在庫管理を円滑に進められます。
セキュリティ対策ができているか
在庫管理システムを導入する際は、セキュリティ対策も確認しましょう。
セキュリティ対策に不備があると、在庫データなどのような自社の重要な情報が漏洩するリスクがあります。
ほかのシステムと連携している場合だと、取引上の機密や顧客の個人情報が流出する事態にもなりかねません。
在庫管理システムを選定する際は、どのようなセキュリティ対策が施されているかチェックしましょう。
製品によってはインターネットに接続しなくても使用できるものがあるため、不正アクセスによる情報漏洩を防止できます。
また、在庫管理システムの導入と合わせて、自社で利用しているネットワーク機器の確認も重要です。
セキュリティが脆弱なネットワーク機器を利用していると、そこを踏み台にした不正アクセスを受けるリスクが高まります。
スマートフォンで使いやすいか
在庫管理システムを選ぶうえで重要な比較ポイントが、スマートフォンでの操作性です。
現場の入出庫作業は倉庫内・店舗内・工場内など、PCを開けない環境で行われることが多いため、スマートフォンで直観的に操作できるシステムを選びましょう。
スマートフォン対応の在庫管理システムであれば、バーコードの読み取り・数量入力・ロケーション変更・棚卸などの作業をその場で完結できます。
現場でメモを取ってからPCに転記する手間がなくなるため、記録漏れや入力ミスを大幅に削減でき、リアルタイムな在庫更新が実現します。
自社に合った入出庫管理で業務を効率化しましょう

本記事では入出庫管理の方法・よく起こる問題点・解決のポイント・在庫管理システムの導入方法などについて解説しました。
入出庫管理を最適化する際は、まず自社で解決したい課題を明確にして、課題を解決するために効果的なアプローチをしましょう。
さらに、自社の業務や、取り扱う商品に合ったシステムの導入方法を選ぶことも重要です。
自社に合った入出庫管理の改善を実施し、在庫管理業務の効率化を目指しましょう。
この記事をご覧くださった方限定で、在庫管理システムを選ぶ際のノウハウを凝縮した特別資料をご提供します。
生産性向上・在庫管理の手間削減を図るために、ぜひ以下のフォームからダウンロードしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブックvol.2
在庫管理の最適化やシステム化を検討している方にオススメ