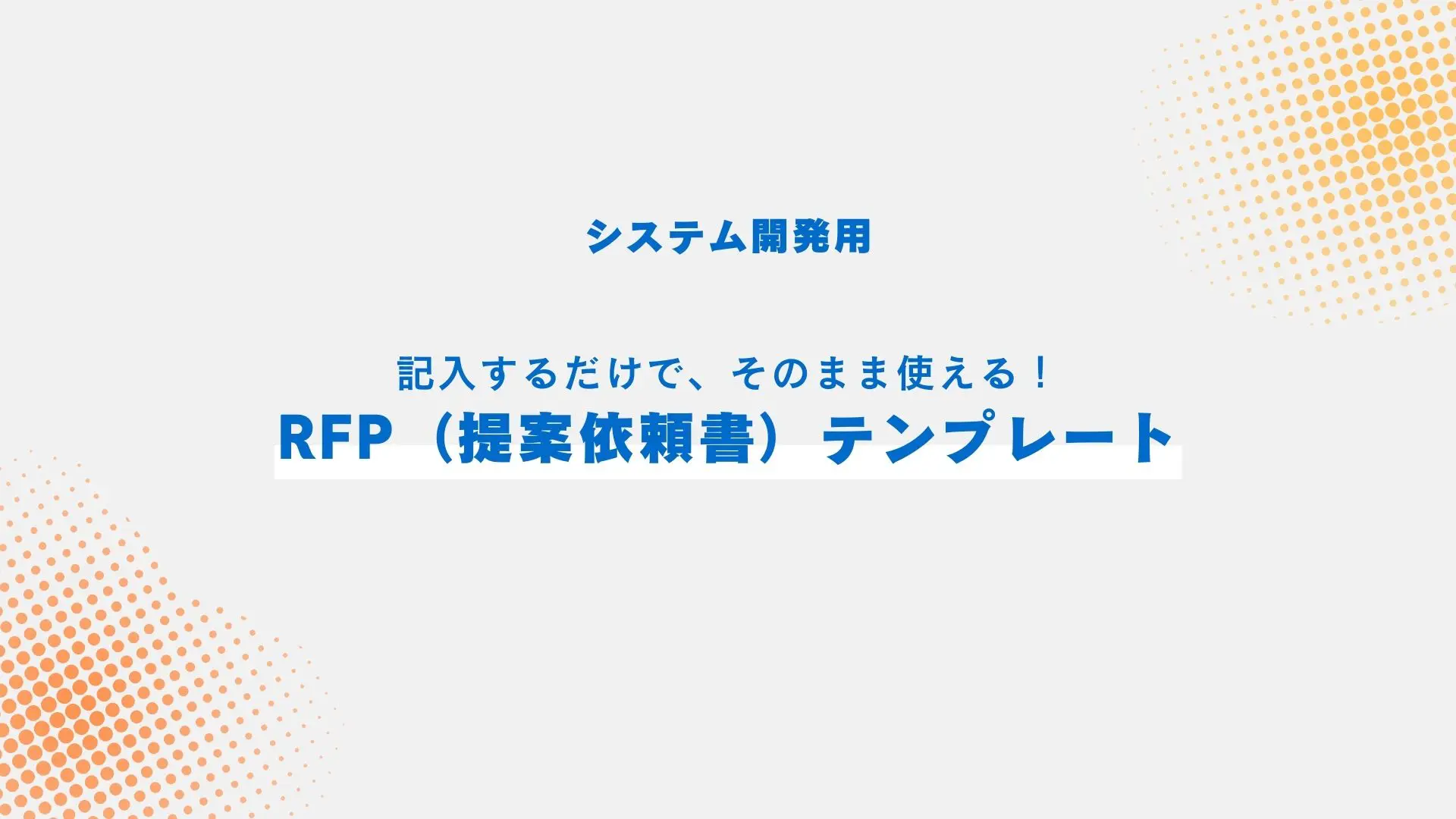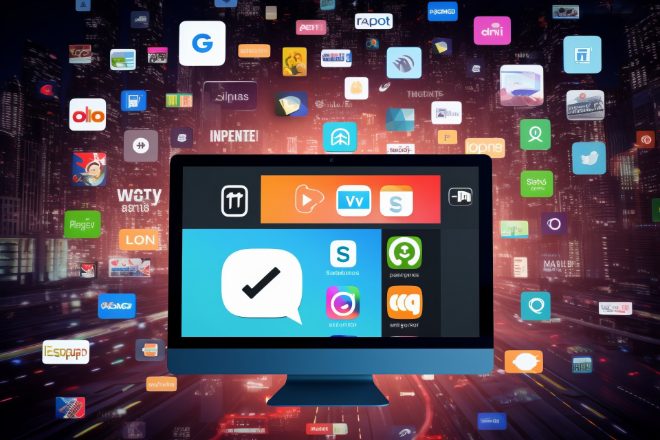UAT(受け入れテスト)とは?目的・進め方などについて解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
システム開発では、重要なプロセスが多くあります。
特に受け入れテストであるUAT(User Acceptance Test)は、システムのエラーや不具合の有無を確認するうえで不可欠な作業であり、最終的な品質を左右する取り組みです。
しかし、UATにはさまざまな種類があり、適切に実施するうえで注意すべきポイントもあります。
より有意義なUATを実施するためにも、その目的や進め方を把握しましょう。
本記事では、UATを実施する目的や進め方などについて解説します。
スムーズなシステム開発を実現するためにも、ぜひ参考にしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
UAT(受け入れテスト)とは

UATとは、システム開発の終盤(稼働前・納品前)に実施する検証作業です。
システムの稼働・運用に際し、重大な不具合がないかを見極めるうえで、UATは不可欠なプロセスです。
なお、一般的にUATは「受け入れテスト」と訳されますが、「ユーザー受け入れテスト」「承認テスト」「運用テスト」「検証テスト」など、別の呼び方をする場合があります。
UATはシステム開発のテストの最終段階に位置づけられるテストです。
UATは以下のテストを完了した後に実施されます。
| 単体テスト(コンポーネントテスト・ユニットテスト) | 初期段階で実施されるテストソフトウェアを構成する最小単位で適切に機能するか確認する |
| 結合テスト | コンポーネントやシステムを組み合わせたうえで適切に機能するか確認する |
| 総合テスト | システムの内容が要件定義と合致しているか・運用や保守管理に問題がないか確認する |
UATを含めた上記のテストを完了して、初めてシステム開発はリリースを実行できます。
UAT(受け入れテスト)を実施する目的

一般的に、UATは「稼働前・納品前に潜在的な欠陥はないか」「求められている要件を満たしているか」を確認することを目的に実施されます。
システム開発におけるUATは、最終的なテスト工程に位置付けられるものです。
そのため、UATが不十分だと、稼働後・納品後に致命的な欠陥や深刻な不具合が見つかるリスクが高まります。
UATはシステムの品質を保証し、ユーザーからの信頼損失を防ぐために不可欠なプロセスです。
企業は適切な手順でUATを実施し、リスクや不具合を最大限除去しなければなりません。
UAT(受け入れテスト)の主な項目

UAT(受け入れテスト)の主な項目は、次の通りです。
- 機能要件
- 非機能要件
- 業務要件
それぞれの項目を確認して、UATを実施する際の参考にしてください。
機能要件
まずUATでは、重要な機能に要件を絞ってテストを実施します。
「どの機能を優先してテストするか」を決めるために、各機能の優先順位を見極める必要があります。
システムの基幹的な機能や不具合を起こしてはならない機能を洗い出し、要件どおりに機能するかテストしましょう。
なお、テストの際は通常業務だけでなく、急遽のトラブル対応やイベント時の臨時業務など、さまざまなシチュエーションを想定して動作確認することが大切です。
非機能要件
非機能要件とは、性能・セキュリティ・使いやすさなど機能以外の要件を指します。
どれだけ機能性に優れていても、セキュリティ性や操作性が不十分では、思い通りの動作を実現できません。
機能要件がシステムのコアとなる機能をテストするのに対して、非機能要件は機能以外の項目をテストします。
非機能要件は、システムの機能とは異なる信頼性や信用性などを確認するためにテストを実施します。
業務要件
業務要件とは、実際の業務プロセスに必要な要件を満たしているか検証するテストです。
通常業務だけでなく、エラー発生時に対応や例外的な操作がシステムにどのような影響を与えるか検証します。
テストが不十分な状態で本稼働した場合、テスト環境とは異なる業務環境では、思わぬトラブルやエラーが発生する可能性があります。
業務要件とは、業務を遂行するために必要な要件を指し、実際の業務環境・データでテストを実施することが大切です。
また、ネットワーク環境も実際の運用環境に合わせて確認しましょう。
UAT(受け入れテスト)の参加者

UAT(受け入れテスト)の主な参加者は、次の通りです。
- 現場の担当者
- 業務プロセスに精通した担当者
- 開発担当者
システムを使用する各部門・業務プロセスに精通した担当者や現場の担当者が、参加して、使用感や操作性・信頼性を確認します。
さらにシステムの開発担当者が参加することで、何かトラブルがあった際に迅速な対応ができます。
なおUATでは、ユーザー部門や情報システム部門・開発会社など各部門の担当者が連携して使用感・機能性をテストすることが重要です。
また、UATを実施するには、各ベンダーとの打ち合わせや成果物の確認など、業務担当者の負担が増えるため、UATの必要性を理解してもらうことが大切です。
プロジェクトオーナーなどを通して、参加者に「なぜ参加するのか」必要性を理解してもらうよう働きかけましょう。
UAT(受け入れテスト)の種類

UATは、検証する内容によっていくつかの種類に分けられます。
本章では、以下の種類のUATについて解説します。
- ユーザー受け入れテスト
- 工場受け入れテスト
- サイト受け入れテスト
- 運用受け入れテスト
- 契約・規制による受け入れテスト
- アルファテスト・ベータテスト
それぞれのテストの内容を適切に理解しましょう。
ユーザー受け入れテスト
ユーザー受け入れテストとは、システムの使用者であるユーザーの目線に立って実施するテストです。
「ユーザーニーズや要件を満たしているか」をチェックするために実施されます。
また、ユーザー受け入れテストでは、システムの使用感も重要な検証項目です。
「ユーザーがスムーズに操作できる仕様か」「エラーが発生した場合に適切な誘導ができるか」など、ユーザビリティに関わる部分も入念に検証する必要があります。
工場受け入れテスト
工場受け入れテスト(FAT)とは、供給者が工場で実施するテストであり、システムやコンポーネントが契約や要件を満たしているか確認するテストです。
これにはハードウェアやソフトウェアの動作確認も含まれます。
工場受け入れテストは、システムのソフトウェアだけでなく、ハードウェアの要件を確認するためにも実施されるテストです。
ハードウェアは複雑な機構が組み込まれているほど、エラーを誘発するリスクが高まります。
工場受け入れテストを入念に実施することで、リスクを効果的に軽減できます。
サイト受け入れテスト
サイト受け入れテストとは、開発したコンポーネントやシステムを顧客やユーザーが自身のサイトに受け入れる形で実施する受け入れテストです。
サイト受け入れテストも、ソフトウェアとハードウェアの両方をチェックする点が特徴です。
顧客やユーザーのニーズ・ビジネスプロセスと適合しているかを確認します。
運用受け入れテスト
運用受け入れテストは、ユーザーではなく、システムを運用する側の視点で行われるテストです。
開発したソフトウェアが円滑に運用できるかを確認するために実施されます。
また、「性能が実運用に耐えられるか」「エラーが発生しても適切に対応できるか」「仕様書・要件定義書通りに稼働するか」なども運用受け入れテストのチェック項目です。
運用面の検証は、運用者はもちろん、顧客やユーザーの満足度を向上させるうえで欠かせないプロセスです。
契約・規制による受け入れテスト
契約・規制による受け入れテストとは、顧客との契約や各種法規制に基づいてシステムに問題がないかを確認するためのテストです。
契約による受け入れテストでは、顧客と交わした契約内容とシステムに相違がないかを確認します。
一方、規制による受け入れテストは、各種法規制と照合し、安全面やコンプライアンス上の問題がないかをチェックします。
契約・規制による受け入れテストは、専門的な知識を持つ第三者によって実施されるケースが少なくありません。
アルファテスト・ベータテスト
アルファテスト・ベータテストは、実際にユーザーや運用者がシステムを利用し、フィードバックを得るために行われるテストです。
フィードバックを得ることで、リリースに向けてさらに改良を進められます。
アルファテストは、開発チーム内部や一部の限られたユーザーによって実施され、製品の初期バージョンを確認します。
一方、ベータテストは、実際のユーザーや運用者にシステムを使ってもらい、リリース前に広範なフィードバックを得るためのテストです。
アルファテストとベータテストは一見似たものに見えますが、実施者が異なる点に注意しましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
UAT(受け入れテスト)の進め方

UATの進め方は以下の通りです。
- テストの目的と範囲を明確にする
- テスト計画書を作成する
- テストのシナリオを作成する
- テストケースを作成する
- テストの環境を構築する
- テストを実施する
- テスト結果報告書を作成する
- 結果の最終承認を得る
- 再度テストを実施する
UATは進め方によって効率性や効果が大きく左右されます。
適切なプロセスを知り、スムーズに進められるようにしましょう。
テストの目的と範囲を明確にする
UATで最初に実施することは、テストの目的と範囲の明確化です。
このプロセスでは、以下の事項を決定します。
- テストする内容
- テストの方法
- テストする内容の優先順位
- テストのスケジュール
テスト範囲の計画は、今後のプロセスを左右する重要な取り組みです。
テスト範囲が不明確だと無駄なタスクが発生しやすくなり、UATをスムーズに進められません。
余計なコストが発生したり、過剰な労力・時間をかけてしまう結果になるので注意しましょう。
テスト計画書を作成する
テストの目的と範囲を明確にすれば、UAを実施するためのテスト計画書を作成することが大切です。
スケジュールや連絡ルート、重要な業務の優先順位をふまえたテスト計画書を開発側が作成し、発注者の承認を得ましょう。
発注者から許可が出れば、テストシナリオなどを定義したテスト仕様書を作成してください。
テスト計画書や仕様書を作成することで、スムーズにUTAを進行できます。
テストのシナリオを作成する
次にテストの対象・UATを実施する範囲・スケジュール・検証項目などを網羅したシナリオを作成します。
シナリオを作成する際は、テストの内容を明記したテストケースも作成しましょう。
テストシナリオはなるべく具体的に作成することが重要です。
プロセスを具体化することで、スムーズにテストを進められます。
以下にユーザーシナリオのサンプルを記載するので、テンプレートとして参考にしてください。
| 工程 | No. | 項目 | テストシナリオ | 結果 | 実施日 | 担当者 | 備考 |
| ユーザー登録 | 1 | ユーザー登録機能 | ユーザーを問題なく登録できるか | 〇 | 10/18 | 〇〇 | |
| ユーザー登録 | 2 | ユーザー削除機能 | ユーザーを問題なく削除できるか | × | 10/19 | △△ | |
| 業務フロー | 3 | 業務フロー(商品登録) | 商品情報を問題なく登録できるか | 〇 | 10/19 | 〇〇 | |
| 業務フロー | 4 | 業務フロー(仕入れ) | 仕入れ情報を問題なく登録できるか | 〇 | 10/19 | 〇〇 | |
| 業務フロー | 5 | 業務フロー(売上) | 売上情報を問題なく登録できるか | 〇 | 10/19 | 〇〇 |
シナリオの書式は企業によって異なるので、自社のテスト方式に合ったものを選びましょう。
テストケースを作成する
次にテストのシナリオに基づいて、テストケースを作成する段階です。
テストケースとは、システムの各機能をチェックするための手順や求める結果をまとめたものです。
テストケースは、システムが正確に動作するか確認するツールであり、どの機能がどのようなテストを実施したか、期待される結果は何かを明記します。
テストケースを作成すれば、テストを漏れなく実施でき、潜在的な問題を洗い出すことが可能です。
また、テストケースはテストの進行具合を追跡し、スケジュール管理にも活用できます。
テストケースを作成する際は、できるだけ小単位の確認項目を作成し、システムの品質・性能を細かくチェックできる状態にしましょう。
テストの環境を構築する
シナリオを作成したら、テスト内容に合わせて環境を構築しましょう。
検証方法や検証項目によって環境のディテールは変わりますが、基本的には実運用を想定した環境を構築する必要があります。
実運用に極力近い環境でなければ、リリース後に生じる可能性のあるリスクを把握できないためです。
なお、受け入れテストはシステムの構造や開発プロセスを理解している従業員が実施する必要があります。
システムに対する理解が浅いメンバーでは、適切な検証ができません。
テストを実施する
準備が完了したら、いよいよ受け入れテストを実施します。
事前に用意したテストシナリオに基づいてシステムを操作し、テストケースで想定した通りに動作するか確認しましょう。
テストを実施する際は、突発的なエラーやトラブルに対応できるよう、システムの品質や操作性をチェックすることが大切です。
テスト結果を記録し、問題が発生した際には開発部門と連携して、迅速に修正対応を行いましょう。
テスト結果報告書を作成する
シナリオに応じて検証を進め、結果を詳細に記録しましょう。
万が一リスクや問題を発見した場合は、具体的な内容と影響を記録します。
さらに成功・要改善を含めたテスト結果をそれぞれ記録し、テストケースと比較できるようにしましょう。
テストの実施状況や発見された不具合、必要な対策などを報告書にまとめ、各部門の担当者と連携してください。
テスト結果報告書を作成することで、テストプロセスを振り返り、今後のプロジェクトに反省点や改善点を反映できます。
結果の最終承認を得る
テスト結果報告書を各部門の担当者に提出して、依頼者からの最終承認を得ましょう。
テストの結果によっては、改善点を修正して再度テストする必要があります。
依頼者が満足できる結果になるまで、テストを繰り返して最終承認を得ましょう。
再度テストを実施する
リスクや問題の原因を把握できたら修正を行い、再度テストを実施します。特に、前回のテストで問題が生じた箇所は、重点的にテストしましょう。
また、修正箇所だけではなく、関連する機能全体が正常に動作することを検証することが大切です。以下の例を参考にしてください。
- 修正によって、システムの安定性や応答性などのパフォーマンスが劣化していないか
- 修正箇所のセキュリティに新たな脆弱性が生じていないか
- 修正によって、既存機能への影響や意図しない不具合が発生していないか
上記のテストをすべてクリアし、最終承認が得られた段階で、システムを本格導入します。
UAT(受け入れテスト)を自動化できるツール

UATを自動化できる代表的なツールは、次の通りです。
- Autify
- SHIFT
- STAR-RPA
- Remote TestKit
それぞれの特徴を解説するので、UATの業務効率を向上させたい方は、自社に合った受入テストツールを導入しましょう。
Autify
Autifyは、AIを活用したノーコードテスト用ツールです。
AIによるセルフヒーリングで、テストシナリオを作成する手間が大幅に軽減され、誰でも簡単にUATを実施できます。
複数部署や組織全体で情報を共有しながらテストできるので、スムーズにUATを進められます。
また生成AIによるテストケース・テストシナリオ作成機能が備わっており、担当者の負担を軽減可能です。
テスト戦略・計画の立案からテスト実行、レビューまでプロセスを自動化できるため、UATのフローを一元管理したい方におすすめです。
SHIFT
SHIFTは、開発プロジェクトの上流工程から下流工程まで一気通貫で品質保証します。
テスト・品質保証の戦略・計画策定といったコンサルティングから、各工程でのテスト設計・実行、テスト自動化やテスト管理ツールの提案まで依頼可能です。
合格率6%の超難関試験突破者がUATをコンサルティングし、PMや開発メンバーの業務を効率化するためのサポートを提供します。
またソフトウェアテストやテスト自動化だけでなく、AI特化型品質保証サービスや設計書なしのアドホックテストなど、多種多様なサービスによって企業のニーズに沿ったUATを実施できます。
STAR-RPA
STAR-RPAは、クラウド型とオンプレミス型どちらでも稼働できるテスト自動化ツールです。
自動テスト・テスト仕様書作成・テスト管理の各機能が連携したテストプラットフォームにより、UATの関連情報を一元管理できます。
また、画面・操作・データの部品を事前に作成し、テストシナリオ作成時にこれらをDrag&Dropして組み立てるプレキャスト方式を採用しており、仕様変更の際にも柔軟な対応が可能です。
なお、モバイルアプリ開発を支援するSTAR-RPA for Mobile APも提供しており、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスで稼働するiOS版とAndroid版のNativeアプリやWebViewアプリの動作をテストできます。
Remote TestKit
Remote TestKitは、場所を問わずにリモートでUATを実施できるテスト自動化ツールです。
クラウド上の端末をPCで操作し、実際の操作環境を用意して動作確認ができます。
700種以上の機種からテストしたい端末をレンタルし、iPhoneやAndroidなどデバイスごとの表示デザインや操作性をチェックできます。
顧客が利用する実践的な環境下での動作テストを実施したい方に、おすすめのクラウド型テストツールです。
UAT(受け入れテスト)を外注できる会社

UATを外注できる代表的な会社は、次の通りです。
- バルテス株式会社
- TaaS
UATの外注を検討している方は、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
バルテス株式会社
バルテス株式会社は、年間3,400件のプロジェクトを担当するテスト工程アウトソーシングサービスを提供しています。
テスト技術者資格JSQBT保有率92%の経験とスキルが豊富なテストエンジニアが在籍しており、テスト工程を最大20%効率化させます。
テスト・品質保証のプロセスをどこからでも委託できるため、自社ではUATを実施するリソースやノウハウが不足している企業でも安心です。
TaaS
Taas(Testing as a Service)は、ソフトウェアテストのアウトソーシングサービスです。
開発工程に必要な各種テスト業務を支援し、要件定義資料や設計書を提供すれば、プロジェクトを一気通貫してアウトソーシングできます。
要件定義書や設計書がない場合でも、ヒアリングをもとに企業が求める条件や仕様を洗い出し、プロジェクトを丸ごとアウトソーシングすることも可能です。
UATの他に、多端末テストやユーザビリティテスト、モンキーテストなど、求める項目や条件でのテストも依頼できます。
参照:Taas公式ホームページ
UAT(受け入れテスト)の課題と対策

UATを実施する際には、さまざまな課題が発生する場合があり、適切に解決できなければ、システムの品質や本番稼働後の運用に悪影響を及ぼします。
UATの主な課題は、次の通りです。
- テスト期間の不足
- テスト環境の不備
- ユーザー部門の協力不足
それぞれの課題別に対策を解説するので、UATをスムーズに進めるための参考にしてください。
テスト期間の不足
UATのスケジュールが十分に確保されず、テストの実施期間が短縮されるケースは珍しくありません。
プロジェクトの進行が遅れた場合、リリース日まで十分な時間が取れず、テスト期間が圧縮される可能性があります。
テスト期間が不足すると、十分な検証ができずに不具合が見落とされるリスクが高まるため要注意です。
解消するためには、UATの計画をプロジェクトの初期段階で策定し、開発フェーズのスケジュール遅延があってもテスト期間を確保できるよう対策することが大切です。
また、すべての機能を均等にテストするより、優先順位の高い機能や高リスクの領域を優先的にテストすれば、限られた期間でも効率的にテストを進められます。
テスト期間の不足が心配な場合は、システムテスト(ST)や統合テスト(IT)の段階からユーザー部門と連携しながらテストを進めて、UATの期間短縮を防ぎましょう。
テスト環境の不備
UATを実施するための環境が整っていないと、正確なテストができず、システムの品質が低下するリスクがあります。
例えば、本番環境と異なる設定やデータが使用されていたり、パフォーマンスが異なる環境でテストを行ったりすると、本リリース後に想定外の問題が発生する可能性があるのです。
本リリース後に想定外の不具合を出さないよう、UATでは本番環境に近いテスト環境を用意しましょう。
テスト環境を本番と同じ設定・データで構築し、できる限り実運用に近い形でテストを実施することが大切です。
また、テストデータの不備が原因で正確なテスト結果を得られないケースもあるため、事前に十分なデータを準備しておきましょう。
ユーザー部門の協力不足
UATは、システムの最終的な確認を行う重要な工程ですが、ユーザー部門が十分に協力しない場合は、想定していた業務シナリオをテストできない可能性があります。
テストが不十分なまま本リリースしてしまうと、稼働後に問題が発生しトラブルへ発展するリスクがあります。
ユーザー部門の協力が不足する原因としては、ユーザー部門のリソース不足やUATの重要性が十分に理解されていないことが多いです。
対策として、UATのスケジュールや実施内容を事前にユーザー部門と調整し、業務との兼ね合いを考慮した計画を立てる必要があります。
ユーザー部門の繁忙期と重ならないように、スケジュールを調整して協力し合う体制を構築しましょう。
また、ユーザー部門がUATの目的を理解していないと、十分にテストできない可能性があります。
UATがシステム品質に与える影響や、業務を円滑に進めるための重要なプロセスである旨をユーザー部門に説明して協力を促してください。
UAT(受け入れテスト)を成功させるポイント

UATを成功させるなら、以下のポイントを意識しましょう。
- 優先順位を決める
- シナリオに沿って進める
- 実際の環境・データを使う
- 合否基準を明確にする
- プロジェクトの遅延に注意する
- 連携するシステムも確認する
いずれも、UATの効率化やコスト削減につながるものです。
効果的にテストを行うためにも、抜け漏れなくチェックしましょう。
優先順位を決める
UATを実施する際は、検証項目の重要度に応じてテストの優先順位を決めましょう。
一般的にUATはプロジェクトの最終段階で実施するため、スケジュールに余裕がないケースは珍しくありません。
状況によっては、システムの全機能を検証する時間を確保できない場合もあります。
重要性が高い機能を確実にチェックすれば、システムの致命的なエラーを防ぎやすくなります。
優先順位を決めていない状態で受け入れテストを行うと、基幹機能の不具合を見落としかねません。
システムの品質を担保するためにも、重要度が高い項目は優先的に検証しましょう。
特にシステムの中核を担う機能や、仕様変更した機能は優先的に検証する必要があります。
シナリオに沿って進める
UATはシナリオに沿って進めることが重要です。
UATは限られたスケジュールで実施するため、効率的に進行しなければなりません。
突発的に検証項目を増やしたり、検証に過度な時間をかけたりすると、スケジュールが狂い、受け入れテストが不徹底になる恐れがあります。
また、UATの進行が遅れると、その分人件費などのコストが増加します。
シナリオに沿って進めることは、無駄なプロセスをなくし、コストを削減するうえで不可欠な取り組みです。
実際の環境・データを使う
システムを検証する際は、実運用を想定した環境・データを利用しましょう。
実運用を想定した環境・データでテストを行わないと、リリース後に潜在的なリスクが顕在化することがあります。たとえば、負荷テストやセキュリティテストにおいては、実際のデータ量や運用環境に近い条件でテストすることで、リリース後に予期しない問題が発生するのを防止できます。
擬似データの利用が前提となる開発環境で検証しても、正しい結果は得られません。
正確に検証するためにも、UATでは実際の環境・データを利用して検証を行いましょう。
合否基準を明確にする
UATの結果を評価する際は、明確な合否基準を設定しましょう。
合否基準が曖昧だと、テスト結果に一貫性がなくなってしまい正確な検証ができません。
合否基準は主観的な評価ではなく、要件定義書に基づいた客観的な評価ができるように設定しましょう。
開発の目標や数値化したデータなどを用意し、複数の基準を設定すれば、より有意義なUATが実践できます。
プロジェクトの遅延に注意する
UATは性質上、プロジェクトの最終フェーズで実施されるものです。
そのため、プロジェクトのスケジュールが遅延しているとその影響を受けるリスクが高まります。
スケジュールが遅延している状況でUATを実施すれば、十分な検証ができず、リスクを放置する結果になりかねません。
UATを実施する際は、優先順位を意識するだけでなく、効率的かつスピーディーに実施できる体制を構築しましょう。
必要に応じて、UATを専門家に外注する方法も効果的です。
経験豊富なプロフェッショナルに任せることで、スムーズかつ効果的なUATを実践できます。
連携するシステムも確認する
UATを実施する際は、連携するシステムも確認しましょう。
特にシステムの仕様変更を行う際は、開発者が仕様の変更作業に気を取られてしまい、連携するシステムへの配慮がおろそかになる場合があります。
万が一連携するシステムのリスクを見落とすと、リリース後に重大なエラーが発生する事態になりかねません。
仕様変更を行う際は、連携するシステムも確認し、想定通りの動作を行っているかチェックしましょう。
もちろん、通常の開発においても、連携するシステムの確認は不可欠です。
UAT(受け入れテスト)でプロジェクトの成功率を向上させよう

UATは稼働前・納品前にシステムの最終的な検証を実施するプロセスです。
システムに致命的なエラーがなく、求められている要件を満たしているかを確認するため、UATは適切に実施されなければなりません。
UATの正しい進め方や意識すべきポイントを理解することは、UATの効果や効率性の向上につながります。
また、有意義なUATを実施すれば、プロジェクトの成功率向上が期待できます。
自社の信頼を守るためにも、UATは適切な手順で取り組みましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、