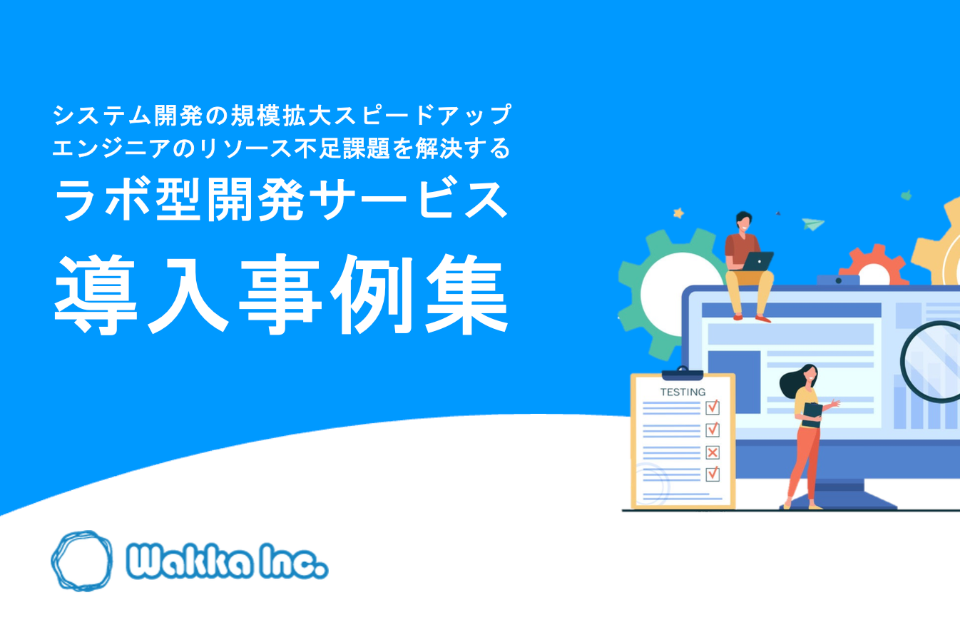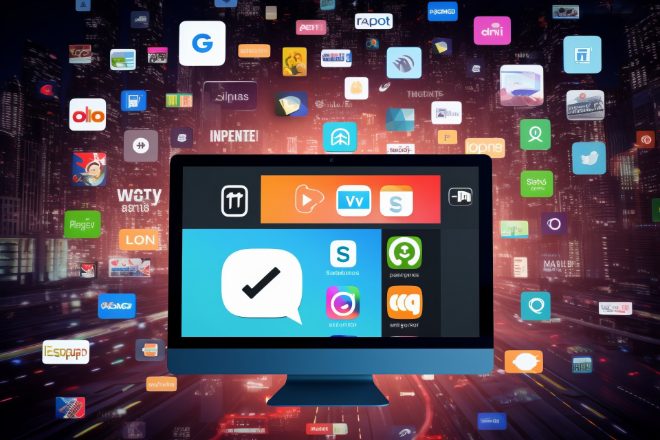マルチプラットフォームとは?意味・メリット・開発手法まで徹底解説


こんにちは。Wakka Inc.のWebディレクターの安藤です。
マルチプラットフォームを活用すれば、アプリ開発の効率化が進み、エンジニアにとっても大きなメリットが得られます。
実際、近年のアプリ開発ではマルチプラットフォーム開発の導入がますます進んでいます。
一方で、
「マルチプラットフォームという言葉を聞いたことはあるが、具体的な意味までは分からない」
「マルチプラットフォームを活用して効率よくアプリ開発をする方法を知りたい」
といった悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?
本記事では、マルチプラットフォームのシステムやメリットから具体的なツールまで詳しくご紹介します。
マルチプラットフォームで効率的なアプリ開発を実現し、コスト削減や新規ユーザー獲得に役立てたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
開発リソース不足にお悩みがある方はラボ型開発がおすすめ。
最適なプロジェクト体制で優秀な人材を低コストで確保できます。ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
マルチプラットフォームとは

マルチプラットフォーム(クロスプラットフォーム)とは、異なる機種やOSでも同じアプリを動作させられる仕組みや開発手法を指します。
現在はシステムやツールの動作環境が多様化し、単一のプログラムで対応できるマルチプラットフォームが求められています。
また、スマートフォンのアプリ開発に関しても、iOS・Android両方に対応させるケースが一般的になってきました。本章では、マルチプラットフォームについて、ほかの用語との違いや、代表的な利用シーンについて解説します。
クロスプラットフォームとの違い
マルチプラットフォームとクロスプラットフォームは、いずれもソフトウェア開発においてよく使われる用語ですが、意味合いが異なります。
先述したようにクロスプラットフォームは、同じソフトウェアやアプリを複数の異なるプラットフォーム上で動作させることです。
各プラットフォームごとに個別に開発や調整が必要となる場合が一般的です。
一方、マルチプラットフォームは、一つのコードベースで複数のプラットフォームに対応できる開発手法やフレームワークを指します。
これにより、開発コストや時間を削減し、メンテナンスも容易になります。
まとめると、クロスプラットフォームは「複数のプラットフォームに対応すること」、マルチプラットフォームは「1つのコードベースで複数のプラットフォームに対応できること」を意味する用語です。
代表的な利用シーン(アプリ開発/業務システム/ゲーム)
マルチプラットフォームの代表的な利用シーンは以下の通りです。
- アプリ開発
- 業務システム
- ゲーム
アプリ開発
マルチプラットフォームは、スマートフォンなどのアプリ開発で積極的に導入されています。
昨今、スマートフォンが普及したこともあり、多くのユーザーがさまざまなアプリを利用するようになりました。
一方、スマートフォンはiOSとAndroidの2種類のOSがあるため、企業はそれぞれのプラットフォームでアプリが安定的に稼働できるようにする必要があります。
マルチプラットフォームはそれぞれのOSに対応するうえで不可欠です。
ユーザーの利便性が上がるだけでなく、2種類のOSそれぞれに合わせて開発する手間を減らせます。
業務システム
業務システムにマルチプラットフォームを取り入れることも、多くの企業で実践されている取り組みです。
マルチプラットフォームを業務システムに導入すれば、異なるデバイス・OSからもアクセスできるため、業務を効率化できます。
また、柔軟なサービスの提供が実現できるため、顧客満足度を高める効果も期待できます。
加えて、あるプラットフォームに障害が発生しても、他のプラットフォームからアクセスできるため、業務の継続性を確保可能です。
業務が中断されるリスクを回避できるのも、マルチプラットフォームのメリットです。
ゲーム
ゲーム開発においても、マルチプラットフォームは不可欠です。
マルチプラットフォームで、あらかじめ複数のOSに対応したゲームアプリを開発すれば、必要な工数や予算の削減が可能です。
また、複数のOS・デバイスに対応したゲームアプリなら、より多くのユーザーがプレイできるため、収益の向上も期待できます。
近年は、異なるプラットフォーム間でオンライン対戦や協力プレイが可能なクロスプレイ対応ゲームの需要が高まっており、その基盤となるマルチプラットフォーム開発はもはや標準的な手法となりつつあります。
マルチプラットフォーム開発が求められる背景
昨今、マルチプラットフォーム開発が求められているのには、以下のような背景があります。
- デバイス・OSの多様化
- エンジニア不足と開発効率化ニーズ
- DX推進とユーザー体験の統一化
それぞれの背景について、順番に解説します。
デバイス・OSの多様化
近年はデバイスやOSが多様化し、ユーザーが自由に選択できる時代になりました。
そのため、同じシステムやアプリでもユーザーがアクセスする方法も多様化しています。
すべてのユーザーに安定したユーザー体験を提供するためには、アプリが多様なデバイス・OSに対応していなければなりません。
デバイスやOSによってサービスの提供に支障が出る事態になれば、ユーザーが離れるリスクが高まります。
マルチプラットフォームは、多様化するデバイス・OSに対応するうえで有効な手段です。
複数のプラットフォームに対応したシステム・アプリを提供することは、事業の成長を左右する要素になります。
エンジニア不足と開発効率化ニーズ
昨今、IT業界ではエンジニア不足に伴う開発効率化ニーズの高まりが顕著となりました。
特にエンジニア不足は深刻で、経済産業省の試算によれば、2030年には約80万人のIT人材が不足すると見込まれています。
また、複数のプラットフォームに対応するシステムやアプリを開発する際、各デバイス・OSに対応するものを個別に開発していては、無駄な工数が発生し、エンジニアの負担が増加する恐れがあります。
そのため、アプリやシステムの開発において、少人数でも工程を進められるように効率化することが重大な課題となりました。
マルチプラットフォームによる開発の効率化は、課題を解決するうえで有用な手段です。
DX推進とユーザー体験の統一化
マルチプラットフォームはDXの推進やユーザー体験の統一化にも役立つ取り組みです。
近年は多くの企業がDXに取り組んでいますが、その過程でマルチプラットフォームへの対応も課題となっています。
業務システムや基幹システムを複数のデバイスでアクセスできるようにすれば、情報共有がスムーズになるうえに、緊急時への対応もしやすくなるためです。
特に従業員の外出頻度が多かったり、テレワークの導入を検討していたりする企業であるなら、マルチプラットフォームは欠かせません。
また、ユーザー体験の統一化においても、マルチプラットフォームは重要です。
デバイスやOSの差異によってシステムやアプリの品質にばらつきが生じると、満足度の高いユーザー体験は実現できません。
ユーザー体験を統一化するには、マルチプラットフォーム開発によって、デバイスやOSに左右されないサービスの提供を実現する必要があります。
マルチプラットフォームの開発手法

マルチプラットフォームの開発手法には、下記の3種類があります。
- ソースコードを同じにする手法
- 仮想マシンを活用する手法
- クラウドサービスを利用したアプローチ
それぞれ詳しく解説します。
ソースコードを同じにする手法
マルチプラットフォームの開発手法のひとつは、ソースコードを同じにする方法です。ソースコードを同一にし、複数のプラットフォーム向けに動作可能なプログラムを作成します。
iOSとAndroid、MacOSとWindowsなど異なるプラットフォームそれぞれに対応したアプリを開発する際に、頻繁に活用される手法です。
また、商用のソフトウェア製品をマルチプラットフォーム化する場合も、ソースコードを同一にする手法が用いられています。
仮想マシンを活用する手法
マルチプラットフォームは、仮想マシンを使って開発されるケースもあります。
仮想マシンとは、物理的なコンピュータ上に別のOSや環境を仮想的に構築できる仕組みを指します。
例えば、macOSが搭載されたMacBook上でWindowsを起動させることも可能です。
1台のコンピュータ上で複数のOSを稼働させることで、さまざまなプログラミング言語やライブラリに対応した実行環境を柔軟に用意できます。
この手法は、Javaや各種スクリプト言語を用いたソフトウェア開発でよく利用されます。
クラウドサービスを利用したアプローチ
昨今は、クラウドサービスによってマルチプラットフォーム開発を実現する企業も増加しました。
FlutterやXamarinなどのマルチプラットフォーム開発ツールは、クラウド上のビルド・デプロイ環境を活用することで、複数のプラットフォームに対応したアプリやシステムを効率的に開発・管理できます。
さらに、マルチプラットフォーム開発に特化したクラウドサービスには、ビルドやデプロイを自動化・効率化する機能が多く備わっており、開発プロセス全体の最適化を実現できます。
マルチプラットフォームの種類
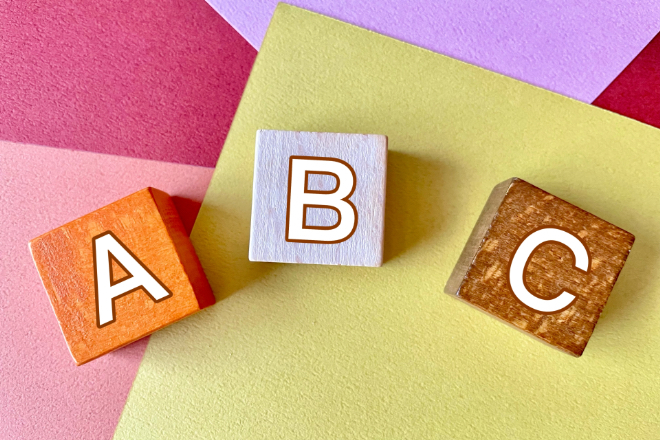
マルチプラットフォーム開発には大きく4つのパターンがあります。特徴を理解することで、開発の目的や状況に応じて最適な手法を選択できるようになります。
具体的なパターンは、以下の4種類です。
- ネイティブ型(Xamarin / React Nativeなど)
- ハイブリッド型(Cordova / Ionicなど)
- 独自レンダラ型(Flutter / Unityなど)
- 新興アプローチ(Kotlin Multiplatform / .NET MAUIなど)
順番に見ていきましょう。
ネイティブ型(Xamarin / React Nativeなど)
ネイティブ型の特徴は、各OSが持つ描画エンジンを直接利用して開発する点です。
そのため、操作性に優れたUIを実現でき、ユーザー体験もネイティブアプリに近い仕上がりになります。
その他にも、処理速度が高速な点や、オフライン環境でのアプリ開発も快適な点が特徴として挙げられます。
ネイティブ型の開発環境は、Microsoft社が提供するXamarinやMeta社(Facebook)が開発したReact Nativeなどが代表的です。
ハイブリッド型(Cordova / Ionicなど)
ハイブリッド型は、HTML・CSS・JavaScriptなどのプログラミング言語を用いて、Web機能を開発します。
スマートフォンに組み込まれているWebViewと呼ばれるソフトウェアを利用し、ChromeやSafariなどのブラウザと同じように、WebページをOS上に表示できるのが特徴です。
ただし、Webページを利用するため、アプリと比べると処理速度が遅めで、ネイティブ型ほど高度な機能は実装できません。
ハイブリッド型の開発環境は、Cordova・Ionic・Titanium Mobileなどが代表的です。
独自レンダラ型(Flutter / Unityなど)
独自レンダラ型は、独自のレンダリングエンジン*を利用してアプリを開発するパターンです。
ネイティブ型やハイブリッド型と違い、OSやWebの描画エンジンに依存せず、独自のレンダリングエンジンを利用してUIを描画するため、自由度の高いデザインや表現ができます。
独自レンダラ型は自由度が高く、アプリ開発やゲーム開発に向いているのが特徴です。
独自レンダラ型の開発環境は、UnityやFlutterなどが代表的です。
※レンダリングエンジン……プログラミング言語を解釈し、描画するシステム
新興アプローチ(Kotlin Multiplatform / .NET MAUI)
モダン言語やフレームワークを利用した、新興アプローチによるマルチプラットフォーム開発も、注目すべき手法です。
Kotlin MultiplatformはKotlinと呼ばれる開発言語を利用したツールであり、同一のコードで開発したシステム・アプリを複数のプラットフォームに合わせてカスタマイズするだけで運用できます。
KotlinはもともとAndroid向けの開発で広く利用されてきた、シンプルで扱いやすい言語のため、効率的な開発が可能です。
一方の.NET MAUIは.NET 6以降で登場したクロスプラットフォームフレームワークです。
Xamarinの後継であり、ネイティブアプリをC#で効率的に開発できます。
.NET MAUIは各プラットフォームのAPIを単一のAPIとして管理できるため、コードベースを1つだけにできます。
各プラットフォームへの対応は固有のコードやリソースを追加するだけで完了できるため、スピーディーな開発が可能です。
これらの新興アプローチは、既存言語の延長でマルチプラットフォーム開発ができる点で注目度が高まっています。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
マルチプラットフォーム開発のメリット

マルチプラットフォーム開発には、経営視点に留まらず、開発者の視点で見ても多くのメリットがあります。
マルチプラットフォーム開発の代表的なメリットは次の4つです。
- 開発コストを減らせる
- 開発人員を確保しやすい
- 多くのユーザー獲得が期待できる
- 保守やアップデートを効率化できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
開発コストを減らせる
マルチプラットフォーム開発により、開発にかかるコストを大幅に減らせる可能性があります。
開発時にマルチプラットフォームを活用すれば、ひとつの言語でコーディングをするため、ソースコードの削減が可能です。
OSごとの新たな言語学習コストがなくなり、開発期間の短縮にもつながります。
また、ソースコードが統一されることで、バグの修正や機能追加も容易になり、エンジニアの負担も軽減されます。
開発人員を確保しやすい
開発人員を確保しやすい点も、マルチプラットフォーム開発のメリットのひとつです。
従来は、デバイスのOSごとに異なるプログラミング言語での開発が必要でした。
対して、マルチプラットフォームを活用すれば単一言語で開発できるため、人的リソースを節約できます。
経済産業省の試算では、2030年に79万人のエンジニアが不足すると予測されています。
少ない人的リソースに対応できるマルチプラットフォーム開発は、エンジニア不足の解消にも有効な手段です。
多くのユーザー獲得が期待できる
マルチプラットフォーム開発を導入すれば、多くのユーザー獲得が見込めます。
マルチプラットフォーム開発で複数のOSやデバイスに対応できる状態にすれば、アプリを利用するユーザーの幅も広がります。
例えばスマートフォンアプリであれば、iOSとAndroidの両方に対応するアプリをリリースすることで、より多くのユーザーへのリーチが可能です。
さらにマルチプラットフォームならエンジニアの業務負担も減らせるため、アプリそのものの品質向上に集中できます。
その結果、よりユーザーのニーズに沿ったアプリ開発を実現できます。
保守やアップデートを効率化できる
保守やアップデートの効率化を図れる点も、マルチプラットフォーム開発の重要なメリットです。
マルチプラットフォーム開発は単一のコードベースを利用するため、万が一不具合が発生しても一括で修正できます。
もちろん、アップデートも大元となるコードベースを改修するだけで完了です。
従来の手法では各プラットフォームごとに保守やアップデートを行う必要がありましたが、マルチプラットフォーム開発ならソースコードの改修で機能の追加やバグの修正を実施できます。
リリースにかかる時間やコストを削減しつつ、改善サイクルを加速できるため、ユーザー体験を維持・向上させながらサービスを提供できます。
マルチプラットフォーム開発のデメリット
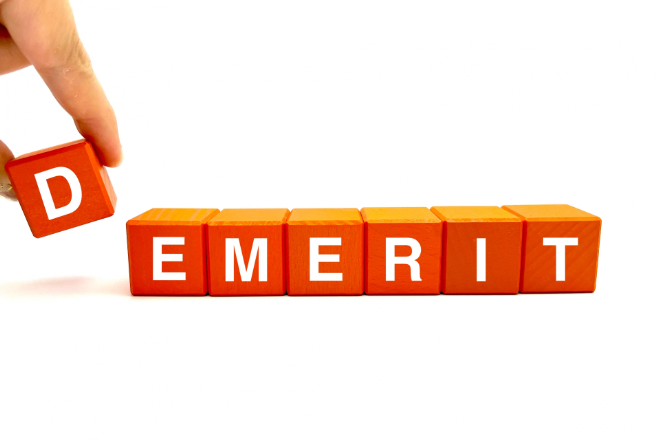
マルチプラットフォーム開発には、メリットだけでなくデメリットもあります。
導入後のトラブルを防ぐためにも、デメリットも把握したうえで自社への導入の可否を判断しましょう。
マルチプラットフォーム開発で想定される代表的なデメリットは下記の3点です。
- 開発事例が少ない
- 不具合への対応が複雑
- 新機能を取り入れにくい
デメリットの詳細を理解し、効果的な対策を講じましょう。
開発事例が少ない
開発事例が少ないことが、マルチプラットフォーム開発のデメリットのひとつです。
マルチプラットフォーム開発は比較的新しい技術のため、開発事例がまだそれほど多くありません。
日本国内の事例に限定するとさらに数は少なく、導入や運用には高度な知識と経験を持つエンジニアが欠かせません。
そのため、マルチプラットフォームを導入するなら、専門家のサポートが不可欠です。
不具合への対応が複雑
不具合への対応が複雑な点も、マルチプラットフォームのデメリットです。
マルチプラットフォームを活用すれば単一言語で開発できますが、不具合時には各OSに対応した言語での修正が必要となる場合があります。
例えばiOSとAndroidの両方に対応したアプリを開発した場合、片方だけで不具合が発生し、その修正に別の言語での対応が求められるケースもあります。
不具合に対応するためにも、スピーディーに修正対応ができる体制は整えておきましょう。
修正対応が遅れると、ユーザーに深刻な影響をおよぼすリスクが高まります。
新機能を取り入れにくい
マルチプラットフォーム開発には、新機能を取り入れにくいデメリットもあります。
マルチプラットフォームを活用すれば異なるOSでの開発が可能ですが、新機能が不具合なく利用できるかは実装してみないと分からないケースも少なくありません。
特にカメラやセンサーなどデバイス固有の機能は、マルチプラットフォームでの実装が難しく、想定以上に開発工数がかかる場合があります。
PoCなどを実践し、実現可能性を入念にチェックしましょう。
マルチプラットフォーム開発ツール7選

マルチプラットフォームに欠かせない開発ツールには、それぞれ強みや特徴があります。自社の開発目的と合致するツールを適切に選ぶためには、ツールへの知見も欠かせません。
今回ご紹介するマルチプラットフォーム開発ツールは、下記の通りです。
- Flutter
- React Native
- Unity
- Xamarin
- Cordova
- Swift / Kotlin Multiplatform
- .NET MAUI
Flutter
Flutter(フラッター)は、Google社が提供する独自レンダラ型のマルチプラットフォーム用フレームワークです。Google社が開発した言語であるDartを使用しており、アプリの処理速度が速いのが特徴です。
さらにプログラムの変更をリアルタイムで確認できるホットリロード機能も備えています。
UIの自由度が高く、ホットリロード機能により開発効率も高いため、初心者から経験者まで幅広く利用されているフレームワークです。
React Native
React Native(リアクト・ネイティブ)は、Meta社(Facebook)が開発したネイティブ型のマルチプラットフォームです。
iOSとAndroidを単一言語で開発でき、プログラムの変更をリアルタイムでUIに反映させられます。
JavaScriptを扱えるエンジニアであれば、ネイティブ環境のノウハウがなくても扱える点もメリットです。
そのため、マルチプラットフォーム開発の経験が少なくても導入しやすい点が魅力です。
Unity
Unity(ユニティ)は、Unity Technologies社が提供する独自レンダラ型のマルチプラットフォーム用フレームワークです。
プログラミング言語はC#を使っており、主にゲーム開発にて活用されています。
3D描画にも対応しているなど、汎用性が高い点がUnityの魅力です。
完成されたプログラム部品や素材を購入できたり、コミュニティが準備されていたりするため、初めて導入する企業でも手軽に扱えます。
Xamarin
Xamarin(ザマリン)は、Microsoft社が提供するマルチプラットフォームです。
歴史的に広く用いられてきましたが、現在は後継の .NET MAUI が主流です。
ネイティブアプリの開発言語をC#に置き換えることで、OSを問わず高性能なアプリを開発できます。
C#の豊富なライブラリや機能を活用でき、効率的かつ堅牢なアプリ開発が可能です。
Cordova
Cordova(コルドバ)は、Apache社のソフトウェア財団が提供するハイブリッド型のマルチプラットフォームです。
Web開発の基本的な技術であるHTML5・JavaScript・CSSが使われており、学習コストが低いため、Web技術を持つエンジニアであればスムーズに開発に着手できます。
また、プラグインが豊富な点もCordovaの特徴です。
Swift / Kotlin Multiplatform
SwiftはAppleが開発したオープンソース言語で、iOSやmacOS向けアプリに多用されます。
学習コストが低く、直感的に扱える点が特徴です。
Kotlin MultiplatformはGoogle推進のKotlinをベースに、Android・iOS・デスクトップ・Webといった複数の環境で共通コードを活用できる仕組みです。
いずれもモダン言語を活用した新しいアプローチとして注目されており、既存の開発リソースを活かしながら効率的なマルチプラットフォーム開発を実現できます。
.NET MAUI
.NET MAUIはXamarinの後継モデルとしてMicrosoft社が開発したプラットフォーム開発ツールです。
オープンソースであり、Xamarinの問題点や課題を修正する形でリリースされています。
開発言語はC#とXAMLを利用しており、単一のソースコードからさまざまなOSに合わせたアプリの開発が可能です。
スムーズかつ効率的な開発・管理を実現するうえで有用です。
よくある質問(FAQ)
本章では、マルチプラットフォーム開発に関する以下の質問について解説します。
- マルチプラットフォームとクロスプラットフォームの違いは?
- ネイティブ開発との違いは?
- どのフレームワークを選ぶべき?
- ゲーム開発でも使える?
- 導入コストの目安は?
マルチプラットフォームへの疑問を解消する際にお役立てください。
マルチプラットフォームとクロスプラットフォームの違いは?
マルチプラットフォームは一つのコードベースで複数のプラットフォームに対応できる手法やフレームワークを意味する用語です。
対して、クロスプラットフォームは同じソフトウェアやアプリを複数の異なるプラットフォーム上で動作させることを意味します。
マルチプラットフォームは、複数のデバイスやOSに対応するうえで必要なツールやフレームワークを指す用語と覚えておきましょう。
ネイティブ開発との違いは?
ネイティブ開発とは、特定のプラットフォームに特化したアプリやソフトウェアの開発手法を意味します。
iOSやAndroidなど、特定のプラットフォームに最適化することにより、デバイスの本来のスペックを最大限活用できるプロダクトを開発できます。
複数のデバイスやOSでの運用を想定しているプラットフォームと異なり、単一のプラットフォームに特化している点が大きな違いです。
どのフレームワークを選ぶべき?
マルチプラットフォームを導入する際は、まず開発言語に注目しましょう。
ツールの種類によって利用できる開発言語は異なっています。
開発プロセスの変更を最小限にしたいなら、自社が使う開発言語をそのまま流用できるツールを選びましょう。
もちろん、利用料金やユーザーインターフェースも注目すべきポイントです。
ゲーム開発でも使える?
マルチプラットフォームはゲーム開発においても多用されています。
近年のゲームはクロスプラットフォームで運用できるタイプが多く、ユーザーも複数のデバイスやOSへの対応を求めています。
また、マルチプラットフォームを導入すれば、一つのコードベースで複数の環境に展開できるため、開発コストの削減や作業効率の向上も可能です。
特にUnityやFlutterといったフレームワークは、ゲーム開発でも多くの実績があります
導入コストの目安は?
マルチプラットフォームはオープンソースによって無料で利用できるツールがあるため、比較的コストを抑えられます。
ただし、中規模~大規模なシステムやアプリの開発で利用するツールは有料であるケースがほとんどです。
月額数万円程度で利用するものもあれば、年間で数百万円以上かかるツールもあります。
マルチプラットフォームを導入して効率的に開発を進めよう

今回はマルチプラットフォームの開発手法やメリットについて詳しく解説しました。
効率的な開発が可能なマルチプラットフォームは、今後ますます需要が拡大していくと予測されます。
ただし、マルチプラットフォームはメリットが多い反面、実際に導入するにはさまざまな課題をクリアする必要があります。
また、開発プロジェクトによってはマルチプラットフォームが適さないケースも少なくありません。
マルチプラットフォームが自社に合っているかを判断するためにも、まずはシステム開発に精通したベンダーに相談してみてください。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、

学生時代にWebサイトを自作したことがきっかけでWebの世界に。制作会社でデザイン、WordPressテーマ開発の実務を経て、テクニカル・ディレクターとして大規模サイト構築のディレクションを経験。2021年からWakka Inc.の日本拠点でWebディレクターとして参画。最近はブロックエディタになったWordPressをもう一度、勉強しています。