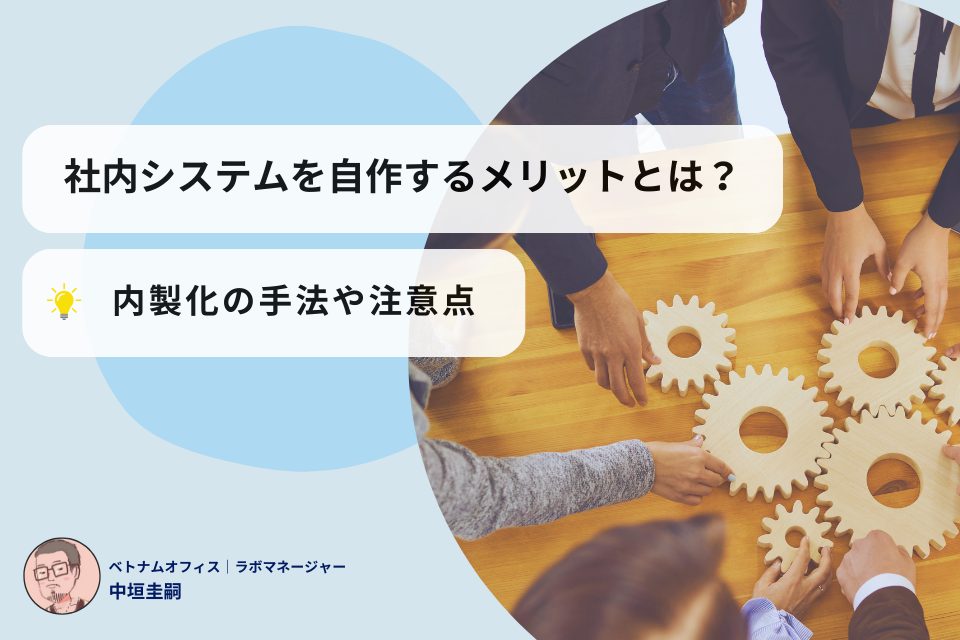エンジニアの採用単価はいくら?市場感と最適な採用法を解説


こんにちは。Wakka Inc.ベトナムラボマネージャーの中垣です。
「エンジニア採用には具体的にどれくらい費用がかかるのか?」あまり正確に分かっていない方も多いのではないでしょうか。
現在、エンジニアは世界的に不足しており、その採用単価も高い傾向にあります。
そこで、本記事ではエンジニアの採用単価に関する情報や、採用コストを抑えるための9つの方法を解説します。
エンジニアが不足している企業の採用担当の方は、ぜひ最後まで記事をお読みいただき、エンジニア採用の効率化やコスト削減にお役立てください。
開発リソース不足が課題の場合はラボ型開発がおすすめです。
最適なプロジェクト体制で優秀な人材を低コストで確保できます。ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
【10分でわかる】ラボ型開発ガイドブック
開発リソース不足に悩んでいる方や、エンジニアの採用に苦労している方にオススメ
エンジニアの採用単価と採用コストとは?

エンジニアの採用にかかる費用を知るうえで必ず押さえておきたいのが、採用単価と採用コストです。
採用単価とは、1人採用するのにかかった費用のことです。
採用したエンジニアの人数を、かかった費用で割ることで、エンジニアの採用単価を算出できます。
一方、採用コストとは、人材を採用するのにかかったすべての費用を合計したものです。
採用コストは、以下のように、大まかに外部コストと内部コストに分かれています。
| 外部コスト | 内部コスト |
| (例) ・求人広告費 ・人材エージェント利用料 ・採用ホームページの制作費 | (例) ・採用担当者の人件費 ・応募者の交通費 ・入社祝い金 |
内部コストに関しては、正確に把握することが難しい場合もあります。
外部と内部どちらのコストも含めた採用コストを算出し、エンジニアの採用単価を明確に把握できる状態を作りましょう。
エンジニアの採用方法

用コストが高騰している場合には、採用方法を変更するのも良いアイデアです。
エンジニアの採用方法としては、企業の採用戦略に応じて以下の方法が選択される傾向にあります。
- 求人サイト(求人広告)
- 人材紹介・人材エージェント
- リファラル採用
- ダイレクトリクルーティング
- 採用イベント
- 採用ブランディング
それぞれの方法について、順番に解説します。
求人サイト(求人広告)
求人広告の掲載メディアに自社の広告を出稿して応募者を募集するのが、求人サイトを利用する採用方法です。
近年は、エンジニア専門の採用サイトも増えているため、求人広告による採用単価は抑えやすくなっています。
とはいえ、求人サイトでの採用コストは、他の採用手法に比べると高くなるのが一般的です。
人材紹介・人材エージェント
人材紹介やエージェントの利用による求人も、エンジニアの採用方法として主な手段の1つです。
人材紹介会社に登録することで、エージェントが自社に適した人材を紹介してくれます。
一定の条件面を満たした候補のみが紹介されるので、選考のコストを抑えつつ、希望に適う人材を見つけやすいのがメリットです。
紹介料や採用によるインセンティブが高いので、人材エージェントの利用はエンジニア採用手法のなかでも特にコストが高い部類にあたります。
多少コストがかかっても、短期間で即戦力のエンジニアを獲得したい企業におすすめの手法です。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員から知り合いを紹介してもらい、採用する手法です。
エンジニアの知り合いを紹介してもらい、採用につながった際には社員にインセンティブを支給します。
リファラル採用ならインセンティブを支払うだけで優れたエンジニアを確保できる可能性があるため、うまくいけば低コストでの採用が可能です。
ただし、多くの応募者から選定する方法ではないため、まとまった人数を採用したい企業には不向きです。
ダイレクトリクルーティング
企業側から求職者にアプローチして採用する手法が、ダイレクトリクルーティングです。
自社に必要なエンジニアの要件を満たしている人材にのみアプローチできるので、採用につながりやすくコストを抑えやすいことが特徴です。
比較的低コストであり、エンジニア専門の転職サイトなども増えているため、ダイレクトリクルーティングによるエンジニアの採用人数は増加傾向にあります。
ただし、人材選定や候補者へのアプローチなどの内部コストが発生しやすいため、採用コストを明確に把握しにくい点には注意が必要です。
採用イベント
近年はエンジニア採用に特化した採用イベントも多く開催されています。
採用イベントは規模が大きいものだと1日で1,000人以上来場するケースもあるため、多数の応募者にアプローチしたいときに適切です。
開催頻度が多かったり、さまざまな採用チャネルと連動していたりするイベントなら、自社の情報をより広く発信するきっかけにもなります。
さらに応募者と直接交流できるため、人柄や適性を対面でチェックできる点もメリットです。
採用イベントにはさまざまな形式があり、ターゲット層を絞ったイベントもあります。
参加する際は、自社が理想とするターゲット層に合わせてイベントを選びましょう。
採用ブランディング
SNSや広告、自社製品やサービスの利用などにより、自社に対する良いイメージを印象付けることで採用につなげる手法を採用ブランディングと言います。
特に売り手が優位である現在の採用市場においては、自社のポジティブな認知度を上げておくことで、求職者からの応募が増えやすくなります。
ただし、採用ブランディングは実際の採用人数に対する直接的な効果が分かりにくいため、エンジニアの採用単価を計算することは困難です。
また、採用ブランディングは業務が広範囲に及び、人的リソースを必要とするため、少ない人数を低コストで採用したい場合におすすめの方法ではありません。
エンジニアの種類ごとに異なる採用単価と相場

ひとえに採用単価の相場といっても、エンジニアごとに金額は大きく異なってきます。
採用単価を決めるのは、主にエンジニアの種類とスキルレベルです。
一般的に、プロジェクトマネージャー(PM)などの上流過程を担当できるエンジニアほど採用単価が高く、システムエンジニア(SE)・プログラマー(PG)とスキルレベルが下がるにつれて単価は下がる傾向にあります。
また、同じ立場のエンジニアでも、経験や対応可能な言語などが豊富であれば、より採用単価が高くなる傾向にあります。
エンジニアと他職種との採用単価の比較

他職種とエンジニアの採用単価を比較した場合、エンジニアのほうが採用単価が高くなる傾向にあります。
中途採用状況調査2024年版に掲載されている、業種別中途採用の平均実績金額は下記の通りです。
| IT・通信・インターネット | 998.5万円 |
| メーカー | 827.9万円 |
| 商社 | 241.7万円 |
| サービス・レジャー | 438.3万円 |
| 医療・福祉・介護 | 262.8万円 |
| 流通・小売・フードサービス | 399.9万円 |
| 金融・保険・コンサルティング | 907.5万円 |
| 不動産・建設・設備・住宅関連 | 539.2万円 |
| 運輸・交通・物流・倉庫 | 525.3万円 |
エンジニアが特に多いIT・通信・インターネット業界の採用コストは、他業種と比較しても高い部類であることが分かります。
以下の通り、職種別の平均採用人数においても、他職種と比較して極端に人数が多いわけではないので、採用単価も高くなることが予想されます。
| 営業 | 5.5人 |
| 企画・経営 | 2.7人 |
| 管理・事務 | 2.7人 |
| 医療・福祉 | 2.9人 |
| 保育・教育・通訳 | 1.8人 |
| Web・インターネット・ゲーム | 2.1人 |
| ITエンジニア | 3.4人 |
| 建築・土木 | 4.1人 |
実際に、職種ごとの求人広告単価についても、エンジニアは高額であることが見て取れます。
| 営業 | 50万円 |
| 企画・経営 | 28.7万円 |
| 管理・事務 | 39.6万円 |
| 医療・福祉 | 13.6万円 |
| 保育・教育・通訳 | 7.4万円 |
| Web・インターネット・ゲーム | 8.9万円 |
| ITエンジニア | 22.4万円 |
| 建築・土木 | 8.7万円 |
データをもとに他職種と比較しても、エンジニアの採用単価は高額であることが証明される結果となりました。
エンジニアの採用単価が高い理由

では、エンジニアの採用単価はなぜ高くなる傾向にあるのでしょうか。主な理由としては、以下の3点が挙げられます。
- IT化やDXがビジネスのトレンド
- 世界的にエンジニアが人材不足
- エンジニアに必要なスキルの細分化
具体的な背景や要因が分かれば、エンジニアの採用単価を抑えるためのヒントが得られる可能性があります。
IT化やDXがビジネスのトレンド
まず1つ目に挙げられる採用単価が高い原因は、IT化やDXがトレンドになっていることです。
現在では、パソコンやスマートフォンが普及し、誰でもインターネットにアクセスできる時代になりました。
そのため、すべての製品やサービスを手軽に利用できるように、IT技術を取り入れたり、DX戦略を推進し始めたりしている企業は急激に増えています。
2020年以降、オンラインや非接触といったワードが話題となり、デジタル化のトレンドはより加速しているといっても過言ではありません。
その状況下で、加速するIT化やDXを担う人材こそが、エンジニアなのです。
ビジネスのトレンドを推し進めている職種がエンジニアなので、さまざまな方面からのニーズが生まれて不足するのは当然です。
世界的にエンジニアが人材不足
エンジニアのニーズが高まっているにもかかわらず、根本の問題としてエンジニアの数が少ないことも、採用単価が高くなる理由のひとつです。
経済産業省が2019年に発表したIT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果では、2030年までに78万人以上ものエンジニアが不足すると予測されています。
参考:経済産業省『IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果』
現在は、調査当時の2019年と比べてもエンジニアの需要が高まっているため、より多くのエンジニアが不足する可能性があります。
さらに、世界的に見ても、エンジニアは人材不足の状態です。
ヒューマンリソシアの統計によれば、2023年時点で日本には144万人以上のエンジニアがおり、世界で4位の数字であるとされています。
世界には2136万人以上のIT技術者がいる結果ですが、世界4位である日本がエンジニア不足となっている現状を踏まえれば、世界的にもエンジニアは不足していると捉えられます。
参照:ヒューマンリソシア『成長する世界のITエンジニア市場、2,994万人で前年比6.1%増、1位は急拡大するインド、2位に米国、3位は中国、「2025年の崖」が迫る日本は、4位を維持するも停滞の兆し』
エンジニア不足については以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
エンジニアに必要なスキルの細分化
エンジニアにとって必要なスキルが細分化されていることも、エンジニアの採用単価を高くしている要因の1つと考えられます。
その背景として、エンジニアには下記のように多くの種類があります。
- ユーザーの目に届く範囲を構築するフロントエンジニア
- 裏側のシステムやプログラムを構築するバックエンドエンジニア
- スマートフォンなどのアプリケーションを構築するアプリケーションエンジニア
そして、各エンジニアによって、身に付けるべきスキルや得意な言語などは異なります。
つまり、エンジニア自体は見つかるものの、自社の開発に必要なスキルセットを併せ持っているエンジニアに出会える確率は格段に下がってしまうため、採用コストが増えてしまう恐れがあります。
また、他職種とは異なり、未経験のエンジニアを採用することが現実的ではない点も、採用単価が高くなってしまう原因です。
エンジニアの採用コストを抑えるための9つの方法
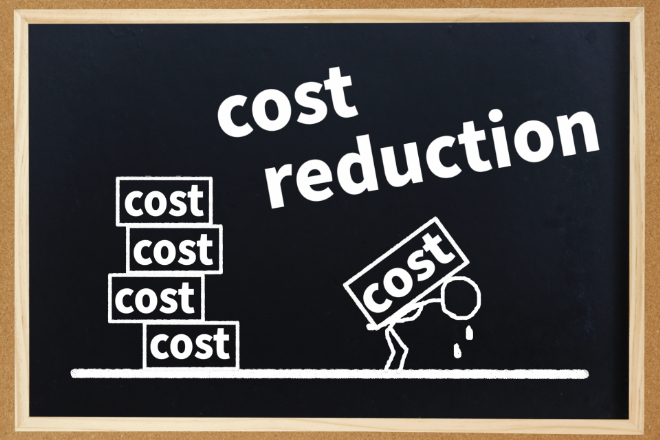
高騰しがちなエンジニアの採用単価を抑えるためには、下記の9つの方法で対策できます。
- 採用コストが高い原因を分析する
- 採用戦略を見直す
- 採用プロセスを改善する
- 採用基準を見直す
- 低コストな採用手法を導入する
- 派遣や業務委託のエンジニアを採用する
- 海外のエンジニアを登用する
- エンジニア人材の定着を図る
- 採用ツールを活用する
各方法について詳しくご紹介するので、採用単価を抑えてエンジニアを採用したい企業の方は必見です。
自社に合うのはどの方法なのか、じっくりと比較検討してください。
1.採用コストが高くなっている原因を分析する
採用単価を低くするためには、まず現状の採用コストを細かく把握することが重要です。
なぜ自社の採用コストが高いのかを理解していなければ、適切に対策できません。
そのため、採用コストを外部コストと内部コストに分解し、採用単価の内訳を確認してから、対策方法を考えていくべきです。
以下の例を見てみましょう。
(例)求人応募の母数が少ないために採用人数を確保できず、採用期間が長期化して採用単価が高くなっているにもかかわらず、コストカットのために求人広告を削るという誤った対策を取ってしまう。
上記のようなケースは、原因分析の不足により起こりがちな間違った対策方法です。
また、ほぼ利用していない求人サイトに対して利用料を支払い続けているなど、採用コストが高くなっている原因を分析するだけで、コスト削減につながる可能性もあります。
効率良く採用単価を抑えるためにも、まずは自社の採用コストが高い要因を分析することから始めましょう。
2.採用戦略を見直す
理想的なエンジニアを確保するなら、採用戦略の見直しも必要です。
ただ無作為に人材を集めても、理想的なエンジニアの確保は困難です。
求める人材像に合わせてターゲット層を明確化し、特定の傾向を持つ人材を集中的にピックアップしていけば、理想的な人材を確保しやすくなります。
ターゲットを絞り込む際は、採用チャネルの最適化や採用広報の強化も合わせて実践しましょう。
ターゲット層が注目する採用チャネルを優先的に活用し、採用広報に求められている情報を明記すれば、応募が増加する可能性が高まります。
また、無駄なコストを発生させている採用チャネルを整理する機会にもなります。
3.採用プロセスを改善する
より良いエンジニアを確保するなら、採用プロセスも積極的に改善しましょう。
例えば、選考フローを見直し、無駄なプロセスを削減すると、応募者が多い場合でもスムーズに選考を進められます。
加えて、プロセスを整理しておけば、採用コストの削減も可能です。
また、優れた人材の取りこぼしを防ぐためにも、各選考プロセスを改善することも欠かせません。
特に、面接は応募者から必要な情報を聞き出すだけでなく、適性を見抜く力が求められるプロセスです。
面接官のトレーニングを徹底し、効果的な面接を実現しましょう。
なお、採用プロセスを改善する際は、内定承諾率も意識する必要があります。
どれだけ採用プロセスを見直しても、肝心の内定承諾が得られなければ、優れたエンジニアの入社は実現できません。
内定承諾率が低い状況だと、自社の魅力が伝わっていなかったり、労働条件と応募者のニーズに齟齬が発生していたりする可能性があります。
4.採用基準を見直す
採用基準を見直すことでも、採用単価を抑えられます。
例えば、採用基準が高すぎると、条件を満たすエンジニアになかなか出会えない可能性があります。
その結果、求人サイトへの広告出稿料がかさんだり、面接回数が増えたりして、コストが高くなるでしょう。
一方で、採用基準が低すぎても、業務効率が落ちたり教育に時間がかかったりして、余計にコストがかかってしまう恐れがあります。
リモートワークを許可して採用可能な地理的範囲を広げたり、経験の少ない若手エンジニアも採用の対象に変更したりと、妥協点を決めて採用基準を見直すことをおすすめします。
5.採用ツールを活用する
採用ツールの導入も、エンジニアを確保するうえで役立ちます。
例えば、大勢の応募者を集める際は、採用管理システム(ATS)があると便利です。
採用管理システムがあれば、応募者が多数集まっても、個々の詳細な情報を把握しやすくなり、管理が効率化します。
選考フローをブラッシュアップするなら、適性検査ツールの導入も検討しましょう。
適切な適性検査ツールを導入すれば、応募者の適性や心理的な傾向などの把握が可能です。
また、スカウトツールを利用して優れたエンジニアを能動的に確保する方法も効果的です。
近年はエンジニアの確保に特化したスカウトツールが登場しており、うまく活用することでスピーディーな採用を実現しやすくなります。
6.派遣や業務委託のエンジニアを採用する
派遣や業務委託のエンジニアを採用することも、採用コストを抑えられる方法です。
派遣や業務委託のエンジニアの採用は、選考プロセスが短く済み、たとえミスマッチがあったとしても契約を終了しやすい点がメリットです。
特定の業務に対して派遣や業務委託のエンジニアをスポット的に活用すれば、正社員のエンジニアよりも安く採用できるケースもあります。
また、活躍の度合いやエンジニアのコミットメント次第では、正社員への切り替えを検討するなど、採用活動の一端としても期待できます。
ただし、労働条件とのすり合わせが必要なため、エンジニアの同意が得られるように交渉する必要がある点には注意しましょう。
派遣元や業務受託先の労働条件より悪いと判断されると、採用を拒否する可能性があります。
7.エンジニア人材の定着を図る
直接的ではないにせよ、エンジニア人材の定着を図ることも、採用コストを抑えたうえで優れた人材を確保する方法と捉えられます。
なぜなら、人材が流動的になると、常に採用活動を継続する必要があり、採用コストが発生し続けるからです。
エンジニア1人あたりの採用単価では大きな変化はありませんが、1年を通して採用する人数を少なくできれば、全体の採用コストとしては安く済みます。
エンジニアが社内に定着しやすくするためには、以下のような施策を実施する必要があります。
- 給与や福利厚生などの待遇を充実させる
- 入社後の研修やフォローを手厚くする
- ハラスメント対策など社内環境を整備する
- 事業のミッションやビジョンを明確化する
- 入社後のキャリアパスを拡大する
上記のような施策を取り入れることで、社内における人材の流動化を防ぎ、無駄な採用コストを発生させない体制の構築が可能です。
8.採用アウトソーシングを活用する
自社に採用のノウハウが不足していたり、対応できる人材が限られたりしている際は、採用アウトソーシングを活用する方法を検討しましょう。
採用業務を代行業者にアウトソーシングすれば、プロのノウハウを活用できるため、自社で実践するよりも高い効果が期待できます。
また、採用アウトソーシングはコア業務に集中しやすい環境を作ることにもつながります。
「採用に注力したいが自社業務への人的リソースを割きたくない」と考えている企業にとって、採用アウトソーシングは積極的に検討すべき選択肢です。
業者が提示する条件にもよりますが、自社で採用を実施するよりもコストが抑えられる可能性もあります。
9.海外エンジニアを登用する
エンジニアの採用単価を抑える方法としては、海外エンジニアの採用も有効な手段の一つです。
エンジニア不足の情勢の中で、グローバルに採用対象を広げれば、求めているエンジニアを早く採用できる可能性がより高まります。
採用までの期間が短くなるほど、採用コストの削減が可能です。
また、同じスキルレベルのエンジニアだとしても、アジア諸国などのエンジニアを採用する場合、日本人エンジニアの採用単価の3分の1程度に抑えられる場合もあります。
海外エンジニアを登用する場合には、受託型とラボ型があります。
長期的な目線で考えた場合には、自社専属のチームを海外で組織するラボ型開発がおすすめです。
WaGAZINE読者さま限定!
【10分でわかる】ラボ型開発ガイドブック
開発リソース不足に悩んでいる方や、エンジニアの採用に苦労している方にオススメ
エンジニア採用における費用対効果の考え方

エンジニア採用における費用対効果は、2段階に分けて考えるようにしましょう。
まずはエンジニアを採用する段階で発生する採用単価です。
求人広告・人材紹介・採用イベントなど、利用する採用チャネルによって採用単価は大きく変わります。
当然、採用チャネルを増やせば応募者が増える可能性は高まりますが、必ずしも理想的なエンジニアを採用できるとは限りません。
むしろ、求める人物像と合わない応募者ばかりが増加し、採用に無駄なコストや時間を費やす結果に終わる場合があります。
そのため、複数の採用チャネルを利用する際は、内定承諾率を算出し、定期的に見直しを実施しましょう。
もう1つは、採用後のパフォーマンスを考慮して費用対効果を算定する段階です。
採用時点では好印象だった人材でも、実際に現場に入ると想定以上にパフォーマンスを発揮していなかったり、すぐに離職したりする場合があります。
採用後のパフォーマンスや定着率の高さも、採用の費用対効果を判断するうえでの重要な指標です。
もし自社が求めるパフォーマンスを発揮しないうえに、すぐに離職する人材だった場合、せっかくの採用コストも無駄になってしまいます。
そのため、費用対効果の測定は採用後にも注目して実施することが重要です。
エンジニア採用の成功事例

本章では弊社Wakka Inc.で実施した採用アプローチについて紹介します。
Wakka Inc.では採用した人材の紹介記事をオウンドメディアに掲載し、求職中のエンジニア向けに社内の雰囲気や内定承諾の決め手を伝えています。
実際の従業員が社内の状況や働き方について直接伝えることにより、応募者がイメージしやすいようにしている点が特徴です。
実際、Wakka Inc.のホームページを見て内定を決めたケースがあるなど、オウンドメディアによる情報の開示は一定の効果をあげています。
参照:Wakkahub『入社4ヵ月、最年少 夏井さんにWakka Inc.について聞いてみた』
適切な採用手法でエンジニアの採用難を乗り切ろう

エンジニアは慢性的に不足しており、採用単価は今後も高くなっていくことが予想されます。
採用単価を抑える方法を駆使しつつ、求めているエンジニアを採用できるように活動しましょう。
なかでも、採用手法を変更する方法や、海外エンジニアの採用に乗り出す方法は、成功している企業の事例も多く特におすすめです。
ぜひこのタイミングで最適なエンジニアの採用方法に切り替えて、事業を成功させてください。
WaGAZINE読者さま限定!
【10分でわかる】ラボ型開発ガイドブック
開発リソース不足に悩んでいる方や、エンジニアの採用に苦労している方にオススメ
▼参考記事

WebメディアでPGから管理職まで幅広く経験し、Wakka Inc.に参画。Wakka Inc.のオフショア開発拠点でラボマネジャーを担当し、2013年よりベトナムホーチミンシティに駐在中。最近では自粛生活のなかでベトナム語の勉強にハマっています。