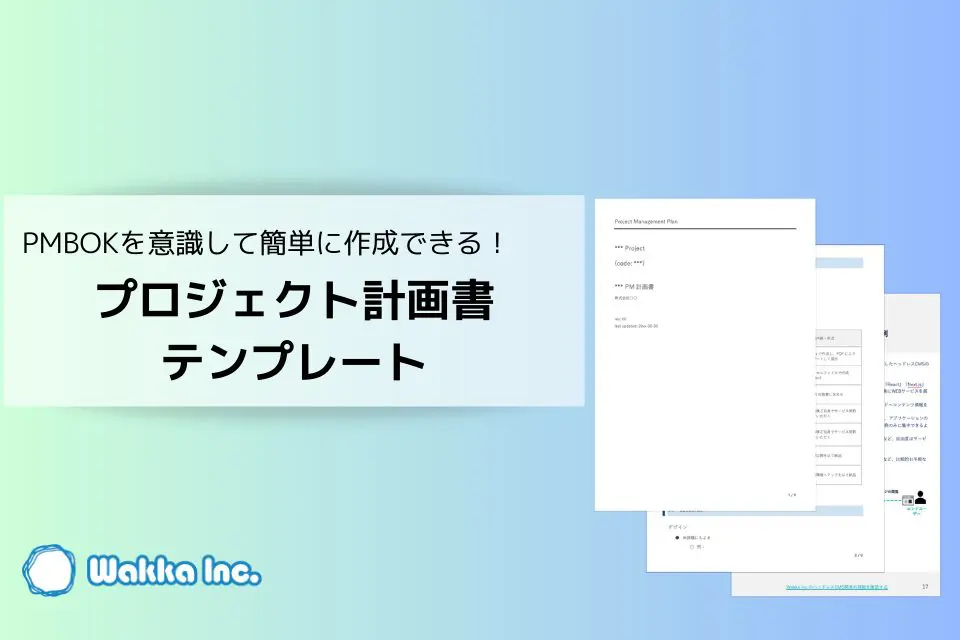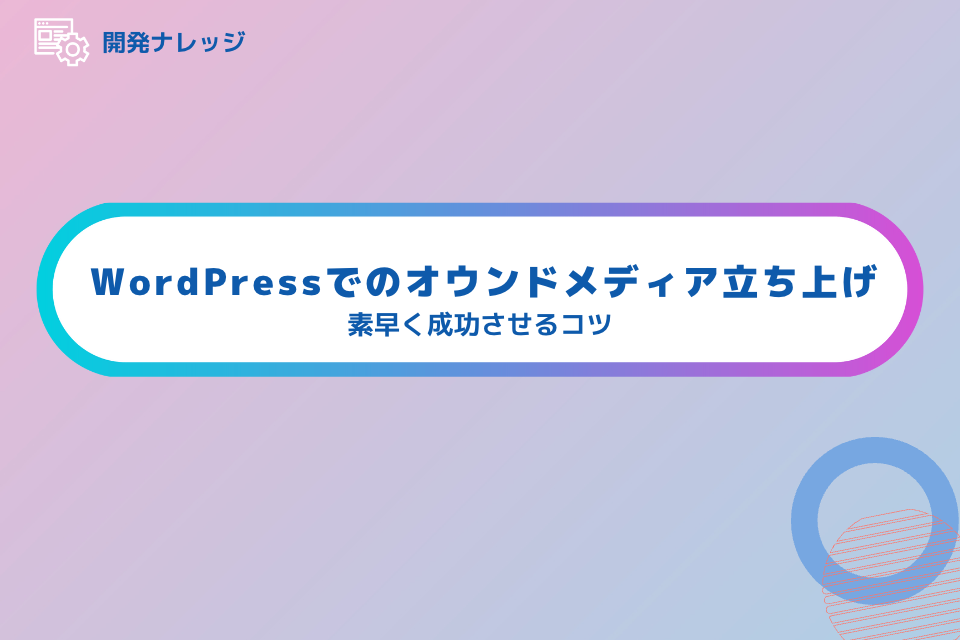ポジショニングマップとは?作り方・軸の決め方を解説|作成ツール&テンプレートも


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
ポジショニングマップは、多様化が進むニーズへの対応や、自社の進むべき方向の策定に役立つフレームワークです。
市場分析において自社と競合の立ち位置を客観的に把握し、視覚化できます。
本記事ではポジショニングマップとはどのような分析方法かを中心に、基礎知識・具体的な作成手順・活用時のポイントなどを解説します。
ポジショニングマップを作成できる無料ツールとテンプレートも、あわせてご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ
新規事業部門のマネージャーの方や、
ポジショニングマップとは

ポジショニングマップとは、市場における自社や競合の製品・サービスの立ち位置を、2つの軸で構成される座標上に視覚的に示した図のことです。
市場を広大な土地の地図に例えると、競合との位置関係や未開拓のエリアを一目で把握できます。
ポジショニングマップを作成することで、漠然としていた市場の構造が明確になり、データに基づいた客観的な戦略立案が可能です。
競合分析をもとにマーケティング戦略を考える際に、有用なフレームワークの一つと言えるでしょう。
STP分析の手法のひとつ
ポジショニングマップは、単独で使われるほか、マーケティング戦略の全体像を設計する「STP分析」というフレームワークの一部として活用するのが一般的です。
STP分析は、以下の3つのステップで構成されます。
| ステップ | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| S | セグメンテーション(Segmentation) | 市場を顧客のニーズや属性などの共通項で細分化する |
| T | ターゲティング(Targeting) | 細分化した市場の中から、自社が狙うべきターゲット市場を決定する |
| P | ポジショニング(Positioning) | ターゲット市場において、競合と差別化できる自社の立ち位置を明確にする |
ポジショニングマップは、STP分析の「P(ポジショニング)」の段階で、自社が目指すべき具体的な立ち位置を可視化し、検討・決定するために用いられます。
STP分析の流れを理解することで、ポジショニングマップの役割と重要性をより深く把握できるでしょう。
縦軸・横軸で構成される
ポジショニングマップの基本構造は非常にシンプルです。
縦と横にそれぞれ1本ずつ軸を引き、4つの象限(4つのエリア)を持つマトリクスを作成します。
このような手法は、多次元尺度構成法と呼ばれるものです。
縦軸と横軸には、顧客が製品やサービスを選ぶ際の重要な判断基準(価格・品質など)を設定します。
そして、その座標軸上に自社や競合の製品・サービスを配置していくことで、市場全体の俯瞰図が完成します。
マップ上に配置する要素は、因子分析やクラスター分析といった手法によって洗い出し、共通する影響を見出したり、類似点をグループ化したりして整理すると効率的です。
ポジショニングマップは、複雑な競合関係や市場構造をシンプルな図に落とし込み、より効果的なマーケティング戦略の立案に効果を発揮します。
主な目的
企業がポジショニングマップを作成する主な目的は、大きく分けて3つあります。
ポジショニングマップを作成する3つの目的は以下の通りです。
| 目的 | 詳細 |
|---|---|
| 競合との差別化ポイントの明確化 | マップ上で自社と競合の位置関係を把握することで、どの競合と似ているか・どの点で差別化できているかを明確化できます。 自社独自の強みを活かしたアピール方法を策定できます。 |
| 市場の空白地帯(ブルーオーシャン)の発見 | 競合が密集しているレッドオーシャンと、まだ競合が存在しない空白地帯(ブルーオーシャン)が可視化されます。 空白地帯は、新規事業や新商品開発における大きなビジネスチャンスとなり得ます。 |
| 社内での共通認識の醸成 | 戦略を一枚の図で示すことで、マーケティング・開発・営業など、部門を超えてチーム全体で共通認識を持つことができます。 また、戦略を図式化することで、全員が同じ目標に向かって一貫した行動をとることができます。 |
ビジネスにおける重要性
現代の市場のように、モノやサービスが多い環境下では、単に製品の品質が良いだけでは顧客に選ばれることが難しい場合があります。
顧客の頭の中に明確なイメージを植え付けることが、ビジネスの成功に不可欠です。
ポジショニングマップの重要性は、顧客の頭の中にあるイメージを戦略的に構築するための設計図となる点にあります。
感覚や思い込みに頼るのではなく、データに基づいて客観的に自社の立ち位置を分析し、競合との違いを明確にすることで、説得力のあるマーケティング戦略の策定が実現します。
知覚マップ(Perceptual Map)との違い
知覚マップとは、顧客がブランドや製品を、どのように認識しているかを把握するためのフレームワークです。
ポジショニングマップと同様に2軸で構成されますが、フレームワークで用いる視点や目的が異なります。
知覚マップとポジショニングマップの違いは下記の通りです。
| 主な違い | ポジショニングマップ | 知覚マップ |
|---|---|---|
| 視点 | 企業 | 顧客 |
| 可視化する内容 | 市場における自社と競合他社の位置関係 | 顧客がブランドや製品をどのように認識しているか |
| 目的 | 自社の強みと弱みを把握して競合他社との差別化戦略を策定する | 顧客の認識を把握してブランドイメージの改善や新たなマーケティング戦略を立案する |
ポジショニングマップと知覚マップは似ているようで異なるものだということを覚えておきましょう。
ポジショニングマップの種類と主な活用方法

ポジショニングマップは、設定する軸によってさまざまな種類に分けられます。
分析の目的に応じて、適切な種類のマップを使い分けることが重要です。
機能的ポジショニング
機能的ポジショニングは、製品が持つ具体的な機能・性能・品質・価格といった客観的な事実に基づいたマップです。
例えば「業界トップクラスの処理速度」や「もっともリーズナブルな価格設定」といった、測定可能で分かりやすい価値を訴求する際に用いられます。
顧客が製品のスペックを重視して合理的な判断を下す市場で特に有効です。
感情的ポジショニング
感情的ポジショニングは、製品やサービスが顧客の感情や自己表現の欲求にどう訴えかけるかに焦点を当てたものです。
「このブランドを持つことで、特別な自分になれる」「このサービスを利用すると、心が安らぐ」といった、情緒的な価値を提供します。
感情的ポジショニングは、ベネフィットベースや知覚マップといった手法を用いて分析されることがあります。
ファッションブランドや高級車、趣味性の高い製品など、機能だけでは差別化が難しい市場で重要です。
競合ベースのポジショニング
競合ベースのポジショニングは、特定の競合他社を基準点として、自社の立ち位置を定義するアプローチです。
「業界No.1のA社よりも、〇〇の点で優れている」といった形で、明確な比較対象を示すことで、顧客に自社の特徴を理解させやすくします。
特に市場に後から参入する場合や、強力なリーダー企業が存在する市場で有効な戦略です。
ただし、競合に追随するだけの戦略に陥らないよう、自社ならではの独自の価値を打ち出すことが重要です。
WaGAZINE読者さま限定!
【10分でわかる】ラボ型開発ガイドブック
開発リソース不足に悩んでいる方や、エンジニアの採用に苦労している方にオススメ
ポジショニングマップの作成手順
本章では、実際にポジショニングマップを作成する手順を5つのステップに分けて解説します。
この流れに沿って進めることで、論理的で説得力のあるマップを作成できます。
ターゲットとKBF(購買決定要因)を洗い出す
最初のステップは、自社の製品やサービスを誰に届けたいのかという観点から、ターゲットを明確にすることです。
次に、ターゲットが製品やサービスを購入する際の決め手は何なのか、つまりKBF(Key Buying Factor:購買決定要因)を徹底的に洗い出します。
KBFは、その後の軸設定の基盤となるため、非常に重要なプロセスです。
KBFを洗い出すには、以下のような方法があります。
| 調査方法 | 概要と特徴 |
|---|---|
| 定量調査 | アンケートなどを通じて、多くの人から数値データを収集する方法です。 価格・機能・デザインなどの選択肢を用意し、どの要素がどれくらい重視されているかを把握します。 |
| 定性調査 | 顧客へのインタビューやグループディスカッションを通じて、個々の顧客の深い意見や本音を探る方法です。 なぜその要素を重視するのか、といった背景にある価値観まで理解することができます。 |
ターゲットとKBFを洗い出す段階では、思い込みを捨て、顧客視点に立ってできるだけ多くのKBF候補をリストアップすることが成功の鍵です。
競合他社の位置づけを調査・比較する
次に、自社と同じ市場で戦う競合他社を選定して、それぞれの位置づけを調査します。
洗い出したターゲットとKBFのリストに基づき、各競合製品がそれぞれの項目でどの程度の評価を得ているかを客観的に分析します。
| 調査対象 | 主な調査方法 |
|---|---|
| 直接的な競合 | 自社とまったく同じような製品・サービスを提供している企業。 |
| 間接的な競合 | 提供するものは異なるが、同じニーズを満たす可能性のある企業。 |
| 調査方法の例 | ・競合の公式Webサイトやパンフレットの確認 ・IR情報(財務諸表・事業報告書)の分析 ・口コミサイトやSNSでの評判調査 ・実際に競合の製品・サービスを利用してみる |
比較分析を通じて、各競合の強みと弱み、そして市場における全体像を明らかにします。
マップの「軸」を決定する
軸の決定は、ポジショニングマップ作成の手順の中でも特に重要な点です。
洗い出した多くのKBFの中から、市場を効果的に切り分けることができる「2つの軸」を選び抜きます。
選んだ2つの軸によってマップから得られる示唆は大きく変わるため、慎重な検討が必要です。
例えば、スマートフォンの市場を分析する際に、価格とカメラ性能を軸にするのか、それともバッテリー容量と画面サイズを軸にするのかで、見えるものはまったく異なります。
マップに自社と競合を配置(プロット)する
軸が決まったら、いよいよマップを作成します。
具体的には、縦軸と横軸を引いて4象限のマトリクスを作る工程です。
縦軸と横軸を引いたら、競合比較の分析結果に基づいて、自社と各競合製品をマップ上の適切な位置に配置(プロット)していきます。
視覚的に分かりやすいポジショニングマップを作るために、各プロットが何を示しているのか一目で分かるように、企業ロゴや製品写真を活用するのがポイントです。
空白地帯(勝てるポジション)を分析・検討する
完成したマップを分析し、競合がまだ参入していない空白地帯を抽出します。
空白地帯は競争が少なく、自社が優位性を確保しやすい領域です。
ただし、空白地帯が必ずしもチャンスとは限らない点には注意が必要です。
顧客のニーズが存在しないために、誰も参入していない可能性もあります。
したがって、見つけた空白地帯に本当にビジネスチャンスがあるのか、追加の市場調査を行って慎重に検証することが重要です。
空白地帯の分析・検討を通じて、自社が次に目指すべき戦略的なポジションを定義します。
ポジショニングマップの軸の決め方と5要素

ポジショニングマップの軸を選ぶ際に、どのような切り口があるのか迷うこともあるでしょう。
本章では、軸のヒントとなる代表的な5つの要素を解説します。
商品の性質
商品の性質とは、価格・品質・性能・サイズ・デザイン・成分など、製品そのものが持つ物理的・機能的な特徴です。
商品の性質は、顧客にとって分かりやすく、比較しやすい要素として知られています。
商品の性質は、下記の3つに大別されます。
| 性質 | 詳細 |
|---|---|
| コア | 商品が持つ、顧客のニーズを満たすための根本的な機能です。 スマートフォンの場合は、通話やインターネット接続などの機能が該当します。 |
| 形態 | コアに付随した、製品の形・品質・デザイン・ブランド・パッケージなどの要素です。 スマートフォンの場合は、デザインやディスプレイの品質などが該当します。 |
| 付随機能 | コアや形態を補完する機能です。 スマートフォンの保証・アフターサービスなどが該当します。 |
顧客のメリット
顧客のメリットとは、商品を利用することで顧客が得られる価値や利益です。
顧客のニーズや期待を満たすことは顧客満足度の向上につながり、企業と顧客の良好な関係構築に貢献します。
顧客のメリットの具体的な内容は以下の通りです。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 問題解決 | 商品の利用が顧客の課題や悩みを解決するのに役立つ場合のメリットです。 時間の節約・コスト削減・作業効率化などが該当します。 |
| 価値の向上 | 商品の利用が顧客の生活やビジネスをより良くするために役立つ場合のメリットです。 生活の質の向上・ビジネスの成功・自己成長などが該当します。 |
| 感情的な満足 | 商品が顧客に喜び・感動・安心感を与えた場合のメリットです。 映画や音楽などのエンターテイメント・リラックス効果などが該当します。 |
| 特別な体験 | 商品が顧客に特別な体験や思い出を提供した場合のメリットです。 旅行・イベントなどが該当します。 |
商品価値・品質
商品価値とは、商品が持つ魅力や有用性、そして顧客が商品に対して感じる価値です。
商品の品質とは、商品が持つ特性・性能などが、顧客のニーズや期待とどれだけ合致しているかを示す概念です。
| 商品価値 | 商品の品質 | |
|---|---|---|
| 定義 | 商品が顧客にもたらす利便性や満足度、又はそれに対する顧客からの評価です。 | 商品が、顧客のニーズや期待をどれだけ満たしているかの度合いです。 |
| 要素 | 機能・性能・デザイン・ブランドイメージ・価格・希少性など | 耐久性・信頼性・安全性・機能性・デザイン・使用感など |
| 重要性 | 顧客の購買意欲の促進や競合との差別化を図る上で重要です。 | 顧客満足度やブランドイメージ、企業の評価などに直結します。 |
商品の品質は、商品価値を構成する重要な要素のひとつです。
企業が競争力を獲得するには、商品価値と品質の両要素をバランス良く高める必要があります。
商品の用途
商品の用途とは、商品の機能や特性に基づいて、顧客がどのように活用できるかを具体的に示したものです。
日常使い・特別な日用・ビジネス向け・レジャー向けなどの軸があり、下記のような項目を考慮して検討します。
| 用途 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 商品が解決できる顧客のニーズです。 |
| 機能 | 商品が持つ具体的な機能です。 |
| 使用方法 | 商品を安全・効果的に使用するための具体的な使用方法です。 |
| ターゲット | 対象となる商品は、どのような人に適しているかです。 |
| 使用場面 | 商品が使用される具体的な場面です。 |
| 効果・効能 | 商品の使用によって得られる具体的な効果や効能です。 |
競合商品
競合商品とは、同じ市場で同じ顧客層をターゲットとした、自社商品と類似した他社の商品です。
機能性の高さや価格などを軸とするケースが多く見られます。
また、競合商品は下記の3種に大別されます。
| 競合の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 直接競合 | 自社と同じ商品を提供する企業のことです。 |
| 二次競合 | 同じカテゴリーに属する商品を提供する企業のことです。 |
| 間接競合 | 提供する商品は異なるものの、類似したニーズを満たす商品を提供する企業のことです。 |
ポジショニングマップ作成に役立つ無料ツールとテンプレート

ポジショニングマップは、特別なツールがなくてもPowerPointやExcelを使って簡単に作成できます。
| ツール名 | 特徴とおすすめの用途 |
|---|---|
| Microsoft PowerPoint / Excel | 多くのビジネスパーソンが使い慣れているツール。 図形やグラフ機能を使えば、見栄えの良いマップを簡単に作成できます。 |
| Miro / Mural | オンラインホワイトボードツール。 複数人でリアルタイムに共同編集できるため、チームでのブレインストーミングやアイデア出しに最適です。 |
| Tableau | データ可視化に特化したBIツール。 大量の顧客データや市場データを分析し、インタラクティブで詳細なポジショニングマップを作成したい場合に強力です。 |
テンプレートに関しては、無料で利用できるものをWeb上で入手できる場合もあります。
活用を検討する際は、Webでリサーチをするのもおすすめです。
ポジショニングマップ活用時の7つのポイント

効果的なポジショニングマップを作成し、戦略に活かすためには、いくつかの重要なポイントがあります。
本章では、ポジショニングマップを活用するときの7つのポイントを解説します。
重要なKBF(購買決定要因)を軸にする
マップの軸には、KBFの中でも顧客が購入を決定する上で特に重要視している要素を選びましょう。
どれだけユニークな軸を設定しても、それが顧客にとって重要度の低いことであれば、マップから得られる戦略的な示唆はほとんどありません。
あくまで「顧客の視点」でもっとも重要な判断基準は何かを追求することが大切です。
縦軸と横軸の相関性を低くする
縦軸と横軸には、互いに直接的な関係性がない(相関性が低い)、独立した要素を選ぶことが鉄則です。
価格と品質を軸に選んだ場合、価格が高いものは品質も良い、という相関関係になることが一般的です。
そのため、ほとんどの製品が右肩上がりの直線上にプロットされてしまい、各社の違いを把握しにくくなります。
価格とデザイン性のように、一方が高くてももう一方は高いとも低いとも言えない、独立した軸を選ぶことで分析の精度が高まります。
ターゲットのニーズを理解する
ポジショニングマップを作成する大前提として、ターゲットのニーズを明確に設定することが重要です。
例えば、ビジネスパーソン向けのPCと、学生向けのPCとでは、重視されるKBF(価格・性能・携帯性など)は大きく異なります。
ターゲット顧客の具体像を明確にし、ニーズに沿った軸を設定することが重要です。
マップの客観性を重視する
ポジショニングマップに自社や競合をプロットする際には、客観的なデータに基づかなければなりません。
アンケート調査の結果、公表されているスペック・第三者機関による評価・顧客レビューなど、信頼できる情報源を活用しましょう。
「自社の製品は高品質なはずだ」といった主観でプロットしてしまうと、市場の実態とかけ離れたマップになる可能性があります。
実現可能性や自社の強みを考慮する
マップ上で魅力的な空白地帯が見つかったとしても、参入することが自社にとって現実的でなければ意味がありません。
そのポジションを獲得するために必要な技術・資金・ブランドイメージなどが自社にあるのかを冷静に評価する必要があります。
また、自社が持つ独自の強み(技術力・開発体制・ブランド力など)を活かせるポジションを選ぶことで、持続的な競争優位性を築きやすくなります。
ポジショニングマップの作成目的を明確にする
ポジショニングマップの作成に取り掛かる前に、「何のために作るのか」という目的を明確にしておきましょう。
新規事業のアイデアを探すため・既存商品のリブランディングのため・競合への対抗策を練るためなど、目的によって最適な軸の選び方や分析の視点が変わってきます。
目的が明確であれば、チーム内での議論もスムーズに進み、より本質的な分析に集中できます。
ポジショニングマップは定期的に見直す
市場環境や顧客のニーズ、競合の動向は絶えず変化するため、一度作成したポジショニングマップが永遠に有効なわけではありません。
最低でも年に1回は定期的にマップを見直し、現状に合わせて更新することが重要です。
古い地図を頼りに航海するのが危険なように、古いポジショニングマップに基づいた戦略は、ビジネスを誤った方向へ導くリスクがあります。
ポジショニングマップの注意点・失敗例

ポジショニングマップの作成・活用で失敗しないためには、注意点を把握する必要があります。
本章では、ポジショニングマップの注意点・失敗例を解説します。
ポジショニングマップ作成自体を目的としない
ポジショニングマップは、あくまで戦略立案のための手段です。
しかし、作成自体を目的と勘違いしてしまったケースもあります。
ポジショニングマップは、目的を明確化するほかに、携わるメンバーが目的を常に確認できるように工夫して履き違えないよう注意しましょう。
アナログな方法ですが、オフィスの壁に目的を書いて貼り出すだけでも効果が期待できます。
顧客の属性を見極める
BtoB(企業間取引)とBtoC(企業対消費者間取引)ではKBFが異なるため、ポジショニングマップの軸の考え方も変えなければなりません。
BtoBとBtoCの違いは下記の通りです。
| 顧客属性 | 特徴 |
|---|---|
| BtoB | 購買意思の決定は企業としての合理性や自社事業との相性などが重視されます。 コストパフォーマンスやセキュリティ性などが軸になりやすく、事業規模や売上規模などが切り口となります。 |
| BtoC | 主観的な要素が重視されやすく、デザインやブランドイメージなどが軸になりやすい。 年齢・性別・職業・収入などが切り口となります。 |
ポジショニングマップで自社の勝てる戦略を描こう

本記事では、ポジショニングマップの基礎知識や作成手順などを解説しました。
ポジショニングマップを活用することで、ビジネスの持続的な成長を実現できます。
この機会にポジショニングマップを作成し、より効果的なマーケティング戦略の立案にご活用ください。
WaGAZINE読者さま限定!
プロジェクト計画書テンプレート
プロジェクト管理業務を担う方や、