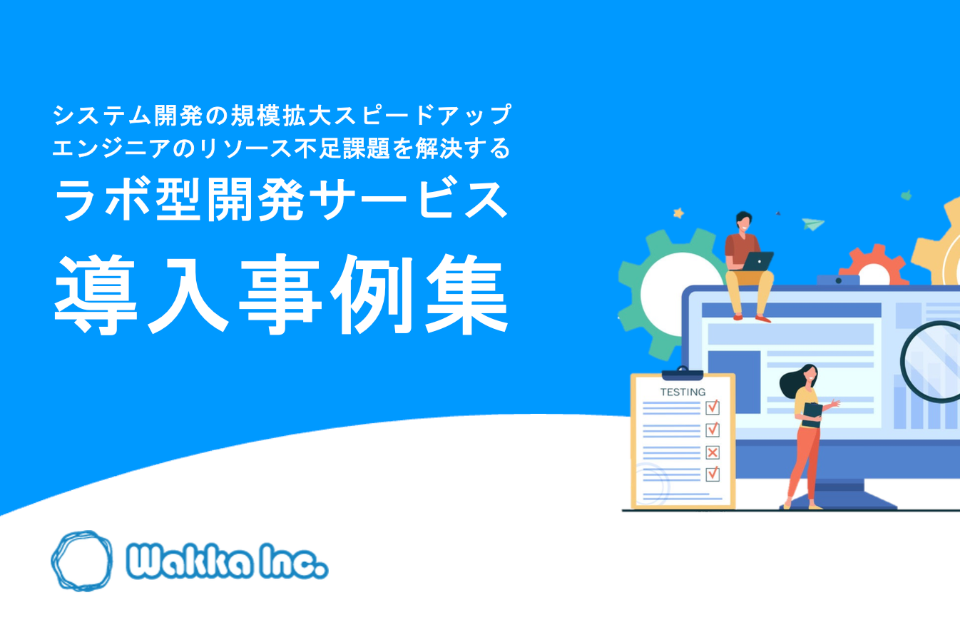生産管理システムの主な機能や種類|MESとの違いやおすすめツール5選を紹介


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
製造業における生産工程を適切に管理する方法として、生産管理システムの導入がおすすめです。
生産管理システムは、販売管理や購買管理・在庫管理などさまざまな機能が備わっており、生産に関わる業務を一元管理できます。
しかし生産管理システムによって搭載されている機能や利用料金・アフターサポートの充実度が異なるため、自社に合うシステムを選ぶことが大切です。
そこで本記事では、おすすめの生産管理システム5選と自社に合う選び方を詳しく解説します。
生産管理システムを導入するメリットとデメリットもあわせて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
生産管理システムとは
生産管理システムとは、生産工程の情報を集約・分析し、一元管理するシステムです。
製造業における製品の流れと進捗状況や出荷状況などの情報をシステムで管理し、生産管理にかかる負担を軽減します。
製造業におけるDXが浸透している現代では、紙媒体やExcelでの管理から生産管理システムへ移行した企業が増えました。
生産管理システムの導入を検討している企業は、生産管理の概要とシステムの必要性を確認しておきましょう。
生産管理とは
そもそも生産管理とは、製造業の生産工程におけるQCDを向上させる管理業務です。
QCDとは、下記の頭文字を取った生産業務の評価指標です。
- Quality(品質)
- Cost(コスト)
- Delivery(納期)
製造業では、どのような原材料をいくらで仕入れ、いつまでに納品するかで生産計画が変わります。
在庫不足や過剰在庫を防止し、納期・予算内に生産活動を進めるために、生産管理が必要です。
生産管理は、製造業のQCDを最適化し、顧客満足度の向上や業績アップにつなげる重要な業務です。
生産管理システムの必要性
生産管理システムの導入が推奨される理由は、QCDを高めるために下記の課題を解消する必要があるからです。
| 納期管理の課題 | ・受発注残を把握したい ・納期を短縮したい ・納期遅延を防ぎたい ・発注した部品や材料がスケジュール通りに納品されるか確認したい |
| 在庫管理の課題 | ・在庫管理を徹底したい ・不要な材料や製品の在庫を減らしたい ・材料や製品の欠品を減らしたい |
| 工程管理の課題 | ・スケジュール通りに製品を納品できるか進捗状況を知りたい ・工程の負荷状況を把握したい ・工程ごとのリソースを把握したい |
| 原価管理の課題 | ・製品の原価を案件、品質別に管理したい ・製品の原価を安く抑えたい ・標準原価と実際原価を的確に把握したい |
Excelで生産管理している場合は、上記の課題に直面するケースが多く、生産管理システムの導入が求められます。
生産管理システムの主な機能
生産管理システムの主な機能は、次の通りです。
- 販売管理機能
- 生産計画機能
- 所要量計算機能
- 購買管理機能
- 在庫管理機能
- 製造管理機能
- 出荷管理機能
- 原価管理機能
- 予算管理機能
システムによって搭載されている機能は異なりますが、上記は生産管理システムの代表的な機能例です。
それぞれの機能を確認して、自社に必要な機能が備わった生産管理システムを導入しましょう。
販売管理機能
販売管理機能は、顧客から注文の受付から見積作成・出荷・請求・売上まで一連のフローを管理する機能です。
システム上で受注から売上までの流れを適切に管理し、受注漏れや請求漏れなどのヒューマンエラーを防止します。
販売管理機能を活用すれば、受注データを基にした出荷計画や納品スケジュールの策定が可能です。
過去の受注・売上データを分析すれば、需要予測によって在庫切れや過剰在庫を防止できます。
また販売に関する業務を一元管理できるため、人件費の削減や業務効率化につながります。
生産計画機能
生産計画機能は、生産管理において重要な機能であり、需要を予測し人員配置や原材料調達など生産計画の立案に役立ちます。
顧客からの受注情報や市場の需要を分析し、生産ラインの稼働計画を立案することが可能です。
製造に必要なリソースを配分し、無駄のない生産体制を構築することで業務効率化につなげられます。
生産計画は、工程ごとの進捗状況や作業負荷を可視化し、リソースの分配やスケジュールの変更・調整につながる重要な役割です。
計画が不適切な場合、需要やスケジュールを読み間違えて在庫切れや過剰在庫、納期遅延を引き起こします。
所要量計算機能
所要量計算機能は、生産計画に基づいて原材料や資材が「どのくらい」「いつまでに」必要か、数量とスケジュールを算出する機能です。
生産計画に必要な原材料や資材の量を把握し、過剰在庫・在庫不足による生産停止を防止します。
また、システム上で発注量や納期を自動的に算出すれば、購買業務の効率化にもつながります。
さらに、材料費や在庫コストを削減し、QCD最適化につなげられます。
購買管理機能
購買管理機能とは、資材や原材料の発注・仕入れなど、購買に関わる業務を効率化する機能です。
購買管理機能は、生産計画や所要量計算に基づいて、必要な材料や部品の発注を管理できます。
仕入先の選定や価格交渉・発注処理から納品確認まで、一連の購買プロセスを効率化します。
また、発注履歴や仕入先ごとの実績データを記録・分析すれば、コスト削減や信頼性の高い取引先を確保することが可能です。
購買管理機能は生産計画機能と密接な関係にあり、各データを連携しシームレスな共有を実現できます。
在庫管理機能
在庫管理機能は、市場のニーズに応えられるよう原材料や製品の在庫を管理する機能です。
原材料や部品・製品の在庫状況をリアルタイムで把握すれば、適切な在庫量を維持できます。
システム上で現在の在庫数や過去の取引データから分析した市場ニーズの推移を基に、維持するべき在庫数を算出可能です。
在庫管理機能を活用すれば、過剰在庫によるコストの増加や在庫切れによる機会損失を未然に防げるため、コストカットと業績アップを目指せます。
また、在庫の入出荷を管理することで、棚卸し作業やピッキング作業を効率化し、生産効率を向上させられます。
製造管理機能
製造管理機能は、実際に製品を製造する作業工程を管理する機能です。
作業指示と実績・作業進捗・作業日報などを管理する機能が備わっており、進捗と実績をリアルタイムで可視化します。
製造管理機能を活用すれば、製造現場の業務効率化と人的リソースの最適化が期待でき、リアルタイムでの進捗管理によって急なトラブルやヒューマンエラーに迅速な対処が可能です。
また、作業指示や工程進捗の確認、不良品の発生率や原因分析によって、QCDを向上させられます。
製造現場のデータを集約し、改善点を明確化すれば、より効率的な生産体制を構築できます。
出荷管理機能
出荷管理機能は、工場から製品が出荷されるまでのスケジュールや出荷台数などを管理する機能です。
顧客からの依頼に対して、適切に出荷・納品できているかをチェックするため、企業の信頼性を左右する重要な機能です。
具体的には、出荷指示の作成や配送スケジュールの調整、出荷実績の記録などを一元管理します。
また、配送業者との連携や納品先ごとの出荷状況を追跡できる利点は、顧客からの信頼を確保し、リピート受注の促進にもつながります。
原価管理機能
製造業の原価管理は手作業では計算ミスや管理不足に陥りやすいため、原価管理機能の活用がおすすめです。
損益分岐点や製品の採算性を分析し、製品・ロットごとの原価計算を行えます。
また、実績原価と標準原価をリアルタイムで比較し、予算の達成状況をモニタリングできます。
原価管理機能はQCDに直結する重要な役割であり、収益性の向上に必要です。
予算管理機能
予算管理機能は、組織単位や工場単位での予算を迅速に算出する機能です。
Excelでの予算管理は担当者に負担がかかり、ヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
しかし生産管理システムであれば、各機能と連携してデータの転記・計算を自動化できます。
また、予算不足や超過した場合も早急に事態を把握し、スピーディーに対処法を講じることが可能です。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、
生産管理システムを導入するメリット
生産管理システムを導入するメリットは、次の通りです。
- 生産状況を可視化できる
- 業務を効率化できる
- コストカットできる
- リードタイムを短縮できる
- 情報共有を円滑化できる
- 属人化を解消できる
それぞれのメリットを確認して、生産管理システムの導入を検討しましょう。
生産状況を可視化できる
生産管理システムの工程管理機能を活用すれば、生産状況をリアルタイムで可視化できます。
無駄な作業を見直し生産プロセスの最適化を図るため、納期遅延や業務負荷の偏りを防止しましょう。
生産工程では、他にも機械トラブルやヒューマンエラー、イレギュラー対応が起きた場合、作業が遅延してしまいます。
生産管理システムで生産状況を可視化して、遅延している工程をサポートすれば、納期遅延を防止して、スケジュール通りに製品を納品できます。
業務を効率化できる
生産管理を紙媒体に手書きやExcelで手打ちしている場合、管理にかかる工数が多いです。
対して生産管理システムを導入して、ハンディやタブレットで管理状況を記録すれば、作業にかかる工数を削減できます。
また、生産管理システムは、需要予測や人員計画・資材調達計画・仕入先への発注など、生産に関わるさまざまな工程を一元管理できます。
管理システムによって判明した部品や材料不足、人材不足を改善し、作業効率化に向けた施策を実行しましょう。
コストカットできる
生産管理システムで、生産計画の最適化や在庫管理の効率化を実現すれば、生産にかかるコストをカットできます。
生産計画に不要な作業や人員がある場合、余分な作業コストと人件費・設備費がかかり、生産コストが増加します。
在庫管理にも管理コストがかかるため、作業やフローを見直して業務効率化することが大切です。
生産管理システムを導入すれば、リアルタイムで生産状況を可視化でき、不良やトラブルによる修正コストも削減できます。
リードタイムを短縮できる
生産管理システムを導入して作業効率化すれば、各工程の作業時間を短縮できます。
作業時間が短縮されると、受注から納品までのリードタイムを短縮し、迅速な納品を実現可能です。
生産工程を可視化して業務フローを改善すれば、より効率的な作業手順・方法を策定し、QCDの向上につなげられます。
情報共有を円滑化できる
生産工程システムで各工程の情報を一元管理すると、部門間の情報共有を円滑化できます。
部門間の情報共有が疎かになると、品質の低下やトラブルにつながる可能性があるため、システムで情報を一元管理することが大切です。
また、情報共有にかかる手間と時間を削減でき、業務効率化につながります。
属人化を解消できる
従来の紙媒体やExcelでの生産管理では、担当者のスキルや経験に依存してしまい、業務が属人化します。
業務が属人化すると、担当者が休業・離職・異動した際に、生産管理のノウハウが組織内に蓄積されません。
生産管理システムを導入すれば、管理業務のフローやノウハウが標準化されるため、業務の属人化を防止できます。
生産管理システムを導入するデメリット
生産管理システムを導入するデメリットは、次の通りです。
- 導入コストがかかる
- 運用に一定のスキルと経験が必要
- 操作に慣れるまで時間がかかる
メリットとデメリットの双方を確認した上で、生産管理システムを導入するべきか検討しましょう。
導入コストがかかる
生産管理システムの多くは有料であり、導入には一定のコストがかかります。
生産管理システムの導入形態は、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。
クラウド型はベンダーのサーバーに構築されたシステムを利用するため、月額利用料が発生します。
オンプレミス型は、自社のサーバーにシステムを構築する必要があり、数百万円から数億円単位の高額な初期費用が必要です。
また導入当初の機能や仕様だけで満足できない場合は、機能を追加する際にオプション料金がかかり、メンテナンスや人材育成にかかるコストも想定しなければなりません。
運用に一定のスキルと経験が必要
生産管理システムを有効活用するには、一定のスキルと経験が必要になるため、導入前に操作方法を研修する必要があります。
システムの操作方法や運用マニュアルだけでなく、メンテナンスやアップデートを実施する専門的なスキルが必要です。
組織内にシステムを運用するスキルと経験が不足している場合は、ベンダー側が自動更新してくれるクラウド型を採用しましょう。
また外部の組織にアウトソーシングしたりコンサルティングを依頼したりと、組織外から専門性の高い人員を呼ぶ方法も効果的です。
操作に慣れるまで時間がかかる
新しい施策やシステムを導入する場合は、操作性に慣れるまで時間がかかってしまいます。
従来の紙媒体やExcelでの生産管理に慣れている従業員の中には、「前の管理体制が良かった」と新しいシステムの操作に不満を感じる方もいるのではないでしょうか。
作業効率化のために導入した生産管理システムですが、操作に慣れない間は余計に時間がかかってしまう可能性があります。
システム導入後に作業が遅延しないよう、事前に操作方法や運用マニュアルを研修しておきましょう。
生産管理システムの選び方
生産管理システムの選び方は、次の通りです。
- 機能の充実度
- 生産形態と管理方式の適合性
- 予算やニーズに合った導入形態
- 業務範囲のカバー力
- セキュリティの信頼性
- アフターサポートの充実度
- 既存システムとの連携性
自社に適した生産管理システムを選ぶために、上記のポイントを参考に複数のシステムを比較検討しましょう。
機能の充実度
生産管理システムには、下記のように豊富な機能が備わっており、自社が求める機能によって導入するべきシステムが変わります。
- 販売管理機能
- 生産計画機能
- 所要量計算機能
- 購買管理機能
- 在庫管理機能
- 製造管理機能
- 出荷管理機能
- 原価管理機能
- 予算管理機能
自社の要望とマッチしていない機能が備わったシステムを選ぶと、利用しない機能を持てあますことになり、余分なコストがかかります。
生産管理システムを導入して「何をしたいのか」目的と現在の課題を明確化してから、自社に合う機能を備えたシステムを探してください。
生産形態と管理方式の適合性
生産手法には、さまざまな生産形態があるため、システムの管理方式との適合性を確認しておくことが大切です。
製造業における主な生産形態は、次の通りです。
| 連続生産 | 同一製品を長期間にわたり連続して生産する方式 |
| ロット生産 | 製品を一定の単位(ロット)ごとにまとめて生産する方式 |
| 個別受注生産 | 顧客からの注文に基づいて一つひとつの製品を設計・製造する方式 |
| 見込み生産 | 将来の需要を予測し、製品をあらかじめ生産する方式 |
| 受注生産 | 顧客から注文を受けてから製造を開始する方式 |
生産形態と管理方式が適合していない場合、業務を効率化できません。
自社の生産形態や手法にマッチした管理方式のシステムを選ぶことで、生産管理にかかる時間や工数を削減できます。
予算やニーズに合った導入形態
生産管理システムは、導入形態によって必要な費用が大きく変わります。
生産管理システムを選ぶ際には、予算やニーズに合った導入形態のシステムを選びましょう。
クラウド型は月額数千円から1万円程度、オンプレミス型は初期費用に数百万円から数億円単位の費用が必要です。
またクラウド型は、ベンダー企業がメンテナンスやセキュリティ対策を実施してくれ、インターネット環境があれば場所を選ばずにアクセスできます。
対してオンプレミス型は、自社好みの機能や仕様にシステムをカスタマイズしやすく、課題や目的に応じてパーソナライズした生産管理システムを構築できます。
導入形態ごとの違いを押さえて、予算やニーズに合った生産管理システムを選ぶことが大切です。
業務範囲のカバー力
生産管理システムを比較する前に、自社で効率化したい業務範囲をカバーできるものを選びましょう。
例えば、生産管理だけでなく販売管理も効率化したい場合は、販売管理機能が充実したシステムを選ぶべきです。
中には販売管理機能が備わっていても、見積作成はオプション費用がかかったり債務管理にはシステム連携が必要だったりと、自社が求める業務範囲をカバーできない可能性があります。
改善したい自社の業務プロセスを洗い出し、求めている業務範囲に対応できるシステムを選びましょう。
セキュリティの信頼性
生産管理システムを導入する際は、セキュリティの信頼性を確認してください。
自社の生産状況や顧客との取引情報など、基幹システムである生産管理システムには、多くの機密情報が集約されます。
外部からのサイバー攻撃や内部関係者の不正アクセスによって、情報を改ざん・漏えいされないよう、セキュリティ性が高いシステムを選びましょう。
アフターサポートの充実度
生産管理システムは、導入後に操作方法やメンテナンス方法で疑問が生じるケースもあるため、アフターサポートが充実しているものを選びましょう。
トラブル発生時に疑問を解消できるカスタマーサポートや、メンテナンス対応が備わっている生産管理システムを導入すれば、安心してシステムを運用できます。
サポート対応時間や内容・保証期間など企業やプランによって異なるので、事前にアフターサポートの充実度を確認してから、導入するべきシステムを選定しましょう。
既存システムとの連携性
生産管理システムは、販売管理システムや会計システムと連携してERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)として運用できます。
しかしERPとして生産管理システムを活用するには、既存システムと連携できるシステムを導入しなければなりません。
既存システムと連携できない場合は、データを複数のシステムで管理する必要があり、一元化による業務効率化を実現できません。
製造業における生産方式の種類
製造業における生産方式は、次のような種類があります。
| 主な生産方式 | 特徴 |
| ライン生産 | 同一製品を流れ作業で大量生産。専用設備や自動化された生産ラインを使用して製造する |
| ロット生産 | 一定単位(ロット)ごとに製品をまとめて生産する。多品種少量生産に対応できるが、段取り替えに手間がかかる |
| 個別生産 | 顧客の要望に応じて1つずつ特注品を設計・製造する。柔軟な生産対応が必要 |
| 見込み生産 | 需要予測に基づいてあらかじめ製品を生産する。短納期対応が可能だが、過剰在庫や欠品リスクがある |
| 受注生産 | 顧客の注文を受けてから生産開始する。在庫を抱えるコスト・リスクが低い |
| 少品種大量生産 | 限られた品種を大量に生産する。生産効率が高く、コストを抑えられる |
| 多品種少量生産 | 多様な製品を少量ずつ生産する。段取り替えや柔軟な設備対応が必要 |
| 変動変量生産 | 製品の種類や生産量が頻繁に変化する環境に対応する。柔軟な生産計画と設備運用が重要 |
生産方式によって、導入するべき生産管理システムが異なるため、自社の方式に適したものを選びましょう。
MES(製造実行システム)と生産管理システムとの違い
生産管理システムとMES(製造実行システム)は、どちらも製造工程を効率化する目的で利用される点から混同されやすいです。
生産管理システムが、受注から出荷まで生産に関わるすべての工程を管理するのに対して、MESは製造工程のみを管理します。
MESは、生産管理システムの一部であり、製造工程の管理に特化したシステムです。
また、MESとERPも混同されやすいですが、それぞれ管理する範囲や目的が異なります。
| システムの種類 | MES | ERP |
| 役割 | 製造工程を効率化する生産工程管理システム | 経営効率化に向けた基幹システム |
| サポート対象範囲 | 生産工程 | 計画工程 |
| 主な利用者 | 生産管理業務の担当者 | 経営者、各基幹業務の担当者 |
MESは製造業における生産管理を効率化するためのシステムです。
生産管理システムとMESの違いを把握するには、次のポイントを押さえておきましょう。
- MESの業務範囲
- MESの主な機能
MESの業務範囲
MESの業務範囲は、製造工程に限定されています。
主に、製造工程の進捗管理や品質管理・設備管理など、作業担当者に業務フローの改善や在庫管理を促し、生産活動をサポートする役割です。
リアルタイムでデータを把握することで、製造工程を可視化し業務効率化に向けた取り組みを立案できます。
MESの主な機能
MESに標準搭載されている機能は、システムによってさまざまです。
参考として、米国のMES推進団体であるMESA(Manufacturing Enterprise Solutions Association)が定義する「MESの11機能」は、次の通りです。
| MESの主な機能 | 概要 |
| 生産資源の配分と監視(Resource Allocation & Status) | ヒト・モノ・カネとして人的リソース、設備リソースなどを配分する |
| 作業のスケジューリング(Operations/Detailed Scheduling) | 生産計画に基づき、具体的な生産スケジュールを計画する。勤務シフトにも対応 |
| 仕様・文書管理(Document Control) | 製造に関する仕様書や作業手順書などを作成・管理する |
| 差立・製造指示(Dispatching Production Units) | 作業計画に基づき、作業の手配を実施する |
| 作業者管理(Labor Management) | 作業員の配置・シフトなどを管理し、最適な割り当てを実現する |
| 工程管理(Process Management) | プロセスの制御や工程間の制御などを実施する |
| データ収集(Data Collection & Acquisition) | 各工程内の進捗状況や点検結果をリアルタイムに収集する |
| 製品の追跡と体系管理(Product Tracking & Genealogy) | 仕掛品や製品の追跡を実施し、トレーサビリティを高める |
| 実績分析(Performance Analysis) | 過去の実績や計画と比較して、現在の生産状況を分析する |
| 品質管理(Quality Management) | サンプル調査による統計的品質管理など、適正な品質管理を実施する |
| 保守・保全管理(Maintenance Management) | 設備の点検・修繕など、定期保全・予防保全を計画する |
参照元:History of the MESA Models – Manufacturing Enterprise Solutions Association | MESA International
おすすめの生産管理システム5選
おすすめの生産管理システムは、次の5種類です。
| システム名 | 導入形態 | 対応規模 | 無料トライアルの有無 |
| TECHS-BK | クラウド型オンプレミス型 | 中小企業向け | 60日間あり |
| スマートF | クラウド型 | すべての規模に対応 | 14日間あり |
| i-PROERP3 | クラウド型オンプレミス型 | 中小企業向け | なし |
| FutureStage | クラウド型オンプレミス型 | 中小企業向け | なし |
| Smart生産管理システム | クラウド型オンプレミス型 | 中小企業向け | 30日間あり |
それぞれの特徴を比較して、自社に合う生産管理システムを選ぶ参考にしてください。
TECHS-BK
TECHS-BKは、品種少量型の部品加工業向けに開発された生産管理システムです。
クラウド対応のオプションも備わっており、受注から生産、売上まで一元的に管理が可能です。
バーコードハンディターミナルにより、リアルタイムに進捗状況を把握でき、得意先からの受注データもシステムに取り込めます。
また、必要な機能や業務範囲によって「Standard」「Basic」「Mini」の3つのエディションが用意されており、予算と要望に合ったプランを選択可能です。
「Basic」「Mini」は、クラウド専用エディションであり、「Standard」は社員数20名以下の小規模事業者を対象にマスタ登録支援サービスも提供しています。
スマートF
スマートFは、スモールスタートで始めたい企業向けのクラウド型生産管理システムです。
専任担当による充実のサポートが付いており、初めて生産管理システムを導入する方でも安心して利用できます。
130以上の機能と幅広い連携に対応し、生産管理・MES・基幹システムなど、幅広く活用可能です。
在庫管理や工程管理・生産計画・受発注管理・品質管理・原価管理など基本的な機能だけでなく、計量器連携・PLC連携・AIOCR受注登録自動化など、オプション機能が充実しています。
無料トライアル期間も設けられているため、まずはお試しで利用しましょう。
i-PROERP3
i-PROERP3は、個別受注や多品種少量生産を行っている中小部品加工業向けの生産管理システムです。
部品加工業に特化しており、低コスト・短納期で導入できます。
見積り作成から受注・出荷・工程進捗管理・在庫管理・売上・請求、仕入・買掛管理、トレーサビリティまで、生産管理に関するさまざまな業務をカバーできます。
基本的にパッケージ型のシステムですが、受注から出荷・製造計画・売上・仕入計上など、現場を支えるバックヤードの業務はVPN回線などを使用してテレワークでも利用可能です。
製品・素材の在庫もリアルタイムに把握できるため、無駄な製品や素材を削減しコストカットできます。
FutureStage
FutureStageは、日立システムズが提供する中堅・中小規模の製造業・卸売業・小売業に特化した基幹業務パッケージです。
経営層・現場・IT部門の悩みを一括で解消するために、基幹業務情報を一元管理し、柔軟性の高いカスタマイズで企業のニーズに沿ったシステムを構築します。
属人化した業務の標準化により収益性を向上させ、タイムリーな情報把握で経営判断の迅速化を実現します。
個別受注生産型(多品種少量生産型)や繰返し生産型・ハイブリッド型に対応しており、導入から運用までワンストップでサポートしてくれるので安心です。
Smart生産管理システム
Smart生産管理システムは、生産管理と販売管理の機能を備えた業務管理システムです。
大掛かりなERPシステムや、多機能すぎるパッケージ製品ではなく、必要な機能だけを搭載しているので、リーズナブルな価格で提供できます。
企業のニーズに応えるよう柔軟なカスタマイズ性を備えており、多言語・多通貨対応と複数社によるシステム共有が強みです。
また、ネットワーク環境とWebブラウザがあれば場所を問わずに利用でき、クラウド型とオンプレミス型どちらでも導入可能です。
1カ月間の無料トライアル期間が設けられているため、まずはお試しでご利用ください。
生産管理システムを導入してQCDを向上させよう
生産管理システムは、在庫管理・購買管理・予算管理とモノづくりに関するさまざまな業務を一元管理できるため、組織全体の生産性を高めることが可能です。
本記事で紹介したおすすめシステムと選び方を参考に、自社に適した生産管理システムを導入しましょう。
生産管理システムを導入して業務改善すれば、QCDを向上できます。
不要なコストや工程を削減し、ヒューマンエラーを防止すれば、QCDが向上し顧客満足度の向上につながります。
下記では、製造業におけるDXの課題・メリット・手順などをまとめています。
製造業におけるDXや業務のさらなるシステム化を検討している方は、下記のガイドブックをダウンロードしましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
ラボ型開発サービス導入事例集
エンジニアや開発リソースを確保したい方、