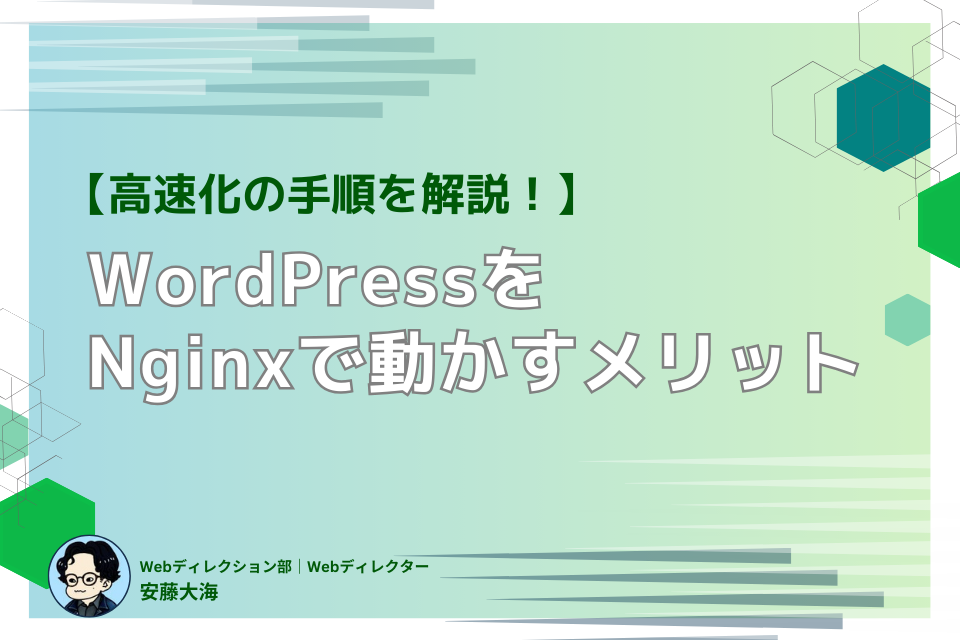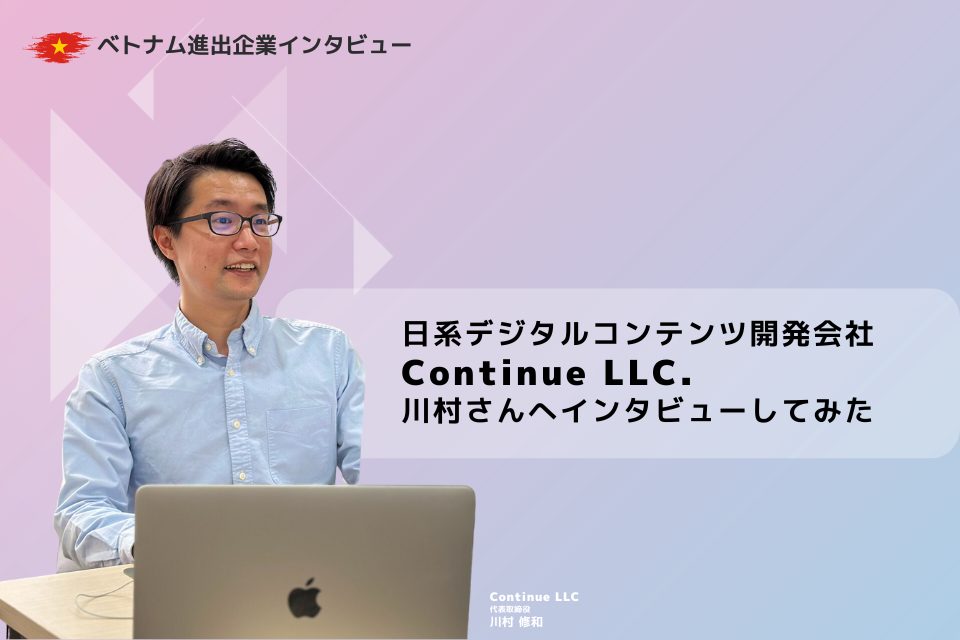リーンスタートアップとは?フレームワークや開発手法、事例などを解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
新規事業は、大きなビジネスチャンスをつかめる機会です。
競合がまだ実現していないプロダクトを実現できれば、マーケットでのシェアの多くを獲得できるでしょう。
新規事業に取り組むうえで、リーンスタートアップは役立つフレームワークです。
リーンスタートアップを理解し、開発やリリースのプロセスに取り入れられれば、新規事業が成功する可能性を高められます。
本記事ではリーンスタートアップについて解説します。
フレームワークや、実際に行った事例などについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ
新規事業部門のマネージャーの方や、
リーンスタートアップとは

リーンスタートアップとは、プロダクトを必要最低限の機能と品質に絞ることで、開発コストを抑えつつ、短期間でリリースを目指す製品開発のマネジメント手法です。
リリース後は、ユーザーからのフィードバックをもとに改善を重ね、プロダクトの品質を高めていきます。
その性質上、リーンスタートアップはトレンドが変わりやすいマーケットや、改善を求められる機会が多いマーケットに適しています。
リーンスタートアップを実施する目的
リーンスタートアップを実施する目的は、リスクを抑えたうえで、画期的な新しい製品・サービスを提供することです。
そもそも、新規事業開発においてリスクはつきものです。
どれだけ斬新なアイデアがあったとしても、マーケットやユーザーが想定通りに受け入れてくれるとは限りません。
見通しが簡単に立てられない以上、新規事業開発に多大なコストや労力をかけると、万が一失敗した際に膨大な損失を被る恐れがあります。
適切にリーンスタートアップを実践できれば、新規開発に伴うリスクを軽減し、成功する可能性を引き上げられます。
リソースが限られている場合はリーンスタートアップが有効
リーンスタートアップを「時代遅れ」と批判する声も少なくありません。
昨今はSNSの普及により、企業や製品・サービスの悪評が拡散されやすい時代となりました。
リーンスタートアップのようにユーザーからのフィードバックを前提とした開発手法の場合、悪評が広まるとイメージの改善が難しいことがあります。
また、リーンスタートアップはプロダクトによっては相性が悪い手法です。
特に複雑な機能を搭載していたり、最先端の技術を投入していたりするプロダクトは、開発に時間がかかるため、リーンスタートアップを実施しても効果を得られません。
ただし、リーンスタートアップは必ずしも時代遅れではありません。
リーンスタートアップはコストを抑えながらスピーディーに開発を進めるため、リソースが限られている企業にとっては有効的な手法です。
さらにユーザーのフィードバックを得ることで失敗するリスクを抑えられるため、新しいアイデアを試すうえでもリーンスタートアップは有用です。
実際、現在進行形でリーンスタートアップを実践している企業は多くあります。
リーンスタートアップと開発手法の関係

リーンスタートアップは、さまざまな開発手法と組み合わせるケースが多くあります。
本章では、リーンスタートアップと組み合わせることが多い、MVP開発とアジャイル開発について解説します。
MVP開発との関係
MVP開発は必要最小限の機能を備えたプロダクトを開発し、リリース後にユーザーのフィードバックを得ながら開発を進める開発手法です。
MVP開発はリーンスタートアップと非常に相性が良い開発手法であり、さまざまな企業が実践しています。
コストを抑えつつ、スピーディーな開発を実現できるため、新規事業やスタートアップ企業でも手軽に実践できます。
MVP開発の手法はただプロダクトを開発するだけではありません。
プロダクトのランディングページや動画などを作成し、ユーザーのリアクションを見て開発を進めるなど、さまざまな方法があります。
アジャイル開発との違い
アジャイル開発もリーンスタートアップで多用される開発手法です。
アジャイル開発は開発工程を機能単位に分け、計画・設計・開発・検証を繰り返すことでプロダクトをスピーディーにリリースする手法です。
MVP開発と同様に低コストかつスピーディーな開発を実現できます。
なお、同じようにリーンスタートアップで多用されることもあり、アジャイル開発とMVP開発は混同されやすい傾向にあります。
しかし、両者は実践する場面が異なります。
MVP開発はマーケットのリアクションを見ながら、確実にニーズを取り入れて開発を進める手法です。
対して、アジャイル開発は短期間でのプロダクト開発を重視しています。
リーンスタートアップのフレームワーク

本章では、リーンスタートアップのフレームワークについて解説します。
リーンスタートアップの手順は以下の通りです。
- 仮説の構築
- 計測と実験
- 結果を基にした学習
- 再構築
それぞれの手順について、順番に解説します。
1. フレームワークを用いた仮説の構築
リーンスタートアップでは以下2つのフレームワークを用いて仮説を構築します。
- リーンキャンバス
- MVPキャンバス
リーンキャンバス
リーンキャンバスとは、新しいアイデアや価値をユーザーに提供するうえで、必要な情報を集めて構築する仮説です。
新規開発に必要な情報をまとめることで、ビジネスモデルを可視化できます。
リーンキャンバスに記載する項目は以下の通りです。
- 顧客セグメント
- 顧客課題
- 提供価値
- 課題解決(ソリューション)
- チャネル
- 収益の流れ
- コスト構造
- 主要指標
- 圧倒的優位性
詳しくは以下の記事もご参照ください。
MVPキャンバス
MVPキャンバスとは、実際に開発するプロダクトに搭載する機能を決定するためのフレームワークです。
リーンキャンバスで決定した内容を基に、MVPの内容を具体化します。
MVPキャンバスで記載する項目は以下の通りです。
※表は、横にスクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 仮説 | 製品・サービスにおける検証したい前提条件・予測を記述します。 |
| 目的 | MVP開発で達成したい具体的な目標を明確化します。 |
| 検証方法 | 仮説を検証するための具体的なアプローチ・手順を策定します。 |
| 必要なデータ・条件 | 仮説の正当性を評価するために、具体的な指標・条件を設定します。 |
| プロダクト | 仮説を検証するために必要な機能を持つプロダクトを具体化します。 |
| 開発コスト | プロダクトの開発・運用・評価に要するリソースをリストアップします。 |
| 検証コスト・期間 | 仮説の検証にかかる期間や、それまでのスケジュールを策定します。 |
| 想定されるリスク | プロジェクトで発生する可能性のあるリスクを洗い出して対策を検討します。 |
| 結果 | MVPの検証結果を記録して、設定した条件と比較して評価します。 |
| フィードバック | 検証結果を分析し、次のアクションはどうすべきかを具体化します。 |
MVPキャンバスを実施する際は、上記の項目を埋めていくことで効率的な仮説の検証が可能です。
また、項目を埋めるだけでなく、効率も考慮して行動することも大切です。
MVPキャンバスを決定したら、いよいよMVPの開発に入ります。詳しくは以下の記事もご参照ください。
リーンスタートアップは初めから完全なプロダクトを作成すると成功しません。
プロダクトには、ニーズを満たせるだけの必要最小限の機能を搭載することを意識しましょう。
2. 計測と実験
MVPを開発したら、実際にプロダクトをリリースし、マーケットやユーザーの反応を確かめながら、計測・実験を行います。
計測・実験では、実際にプロダクトを手に取ってもらうユーザーの選択が重要です。
ユーザーは必ずしも大人数である必要がありませんが、アーリーアダプターからリアクションをもらうようにすると有用なフィードバックが期待できます。
アーリーアダプターとは「初期採用者」を意味する言葉であり、トレンドに敏感なうえに自ら積極的に情報収集するユーザーを指します。
早い段階でプロダクトに合ったアーリーアダプターを絞り込めば、より良いフィードバックの獲得が可能です。
リーンスタートアップはフィードバックを得ることによる改善を前提にした手法です。
意見を提供してもらうユーザーを確保する方法や、フィードバックを得る際に利用するメディアを工夫すれば、より効果的な計測と実験ができます。
上記は、アメリカの社会学者エベレット・M・ロジャースが提唱したイノベーター理論に基づく内容です。
詳細は、国立大学法人 東京大学が100%資本を持つ投資会社 東京IPCの「イノベーター理論をわかりやすく解説!【事例あり】」をご覧ください。
3. 結果を基にした学習
ユーザーからフィードバックを得たら、結果を基にした学習を実施しましょう。
このフェーズではフィードバックを踏まえ、プロダクトを改良することでビジネスモデルをブラッシュアップします。
リリースを通じて課題が見つかった際は、原因を突き止め、適切な対策を講じなければなりません。
また、ユーザーから新たな機能の要望があった際は、実装を検討しましょう。
4. 再構築
致命的な課題やコンセプトの修正が必要になった際は、再構築を実施しなければなりません。
再構築の段階では、プロダクトの全般的な見直しも含めて、大幅な修正を行います。
リーンスタートアップは失敗した場合を踏まえ、あらかじめ再構築をプロセスに加えています。
低コストで開発・リリースを行うからこそ、再構築になったとしても損失が少なくて済むためです。
むしろ、再構築する可能性も踏まえ、試行錯誤を繰り返してより良いプロダクトを開発できることが、リーンスタートアップの大きなメリットと言えます。
もちろん、プロダクトの評価が高く、微細な修正で完了する場合なら再構築は不要です。
WaGAZINE読者さま限定!
企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ
新規事業部門のマネージャーの方や、
リーンスタートアップの特徴と効果

リーンスタートアップを実施すると、以下のようなメリットが期待できます。
- 開発のコストや時間を減らせる
- 早期のリリースを実現できる
- ユーザーのニーズを取り入れやすい
リーンスタートアップを実施する意義を理解するためにも、それぞれのメリットを把握しましょう。
開発のコストや時間を減らせる
リーンスタートアップは開発のコストや時間を減らせる点がメリットです。
通常、新規開発は不確実性が高く、見通しがつかないものです。
コストや時間をかけて優れたプロダクトを開発しても、失敗すれば多大な損失を被るリスクがあります。
対して、リーンスタートアップは低コストでプロダクトを開発・リリースする手法であるため、失敗した際の損失を抑えられます。
加えて、ユーザーのフィードバックを得ながら改良を繰り返すため、軌道修正も容易です。
ウォーターフォール型のような開発手法だと、軌道修正は多大な損失を招くリスクがあります。
しかし、リーンスタートアップのように改善を前提にした手法なら、損失を抑制できるため、必要に応じて積極的に実践できます。
早期のリリースを実現できる
リーンスタートアップは早期のリリースを実現するうえでも、有効的な手法です。
必要最小限の機能を搭載した状態でプロダクトをリリースするため、通常の手法より開発にかかる時間を大幅に削減できます。
早期のリリースは、競合他社に先んじて新たなアイデアをマーケットに提供できる可能性を高めます。
そのため、先行者利益を得やすく、マーケットでシェアを獲得するうえで有利に働きます。
ユーザーのニーズを取り入れやすい
リーンスタートアップの大きな利点は、ユーザーからのフィードバックを積極的に求め、そのニーズを迅速に取り入れられることです。
このようなアプローチにより、製品・サービスとユーザー・マーケットのニーズとのギャップを効果的に埋めることができます。
ユーザーの要望にスピーディーに応えられるようになれば、顧客満足度の向上やリピーターの増加も実現できます。
リーンスタートアップのデメリット・注意点

リーンスタートアップは優れた開発手法ですが、デメリットがある点も考慮しなければなりません。
リーンスタートアップには以下のようなデメリットがあります。
- プロダクトによっては相性が悪い
- コンセプトが失われるリスクがある
- 組織内の調整が難しい
デメリットを把握し、適切な対応が取れるようにしましょう。
プロダクトによっては相性が悪い
リーンスタートアップはプロダクトによっては相性が悪い手法です。
特に複雑な機能や最先端の技術を搭載することで、開発コストが高くなるプロダクトはリーンスタートアップには向いていません。
相性が悪いプロダクトの開発にリーンスタートアップを実施しても本来の効果は得られません。
企業の基幹システムや自動車のように、完成が前提となっているプロダクトを開発するなら、別の開発手法を検討しましょう。
コンセプトが失われるリスクがある
リーンスタートアップはコンセプトが失われるリスクにも留意しなければなりません。
ユーザーのフィードバックを得たうえでの改善は、ニーズを取り入れるのに役立つ一方、コンセプトのブレを生じさせる恐れがあります。
また、ユーザーの意見を取り入れるあまり、無駄な機能を搭載することになれば、開発コストの高騰を招きます。
フィードバックを得る際は、意見を取捨選択しましょう。
意見を提供するユーザーを絞るなどして、有用な意見のみを取り込める体制作りも不可欠です。
組織内の調整が難しい
リーンスタートアップはその性質上、プロダクトの改善や変更が頻繁に発生するため、組織内でのプロセスの調整が難しい一面があります。
改善作業が連続で発生すれば、他の業務に支障をきたす可能性があります。
したがって、リーンスタートアップを実施する際は、作業の変更に柔軟に対応できる開発体制を構築することが重要です。
リーンスタートアップが有効な市場

リーンスタートアップにはデメリットや注意点もありますが、そのメリットを活かせる市場も数多く存在します。
本章では、リーンスタートアップが有効な8つの市場を解説します。
セミオーダーメイド市場
セミオーダーメイド市場は、顧客ニーズの多様化が進んでいるため、リーンスタートアップの強みを活用できます。
MVPを提供しながら改善できるため、顧客の好みや特性に応じた商品を少ロットで実現することも可能でしょう。
セミオーダーメイド市場のように、個別対応を要する市場においては、リーンスタートアップが有効です。
業務効率化ソリューション市場
定型業務を自動実行するソリューションのRPAやAIを活用した業務効率化ソリューション分野では、多くの場合リーンスタートアップが用いられます。
これは、業務効率化ソリューション市場では段階的な導入と検証が不可欠だからです。
まずはMVPを小規模に展開して効果測定を実施し、機能やサポートを調整する方法が顧客満足度を高めるための方法として一般的です。
そのため、業務効率化ソリューション市場においてはリーンスタートアップが有効と言えます。
高い専門性を求められる市場
税務・労務・金融などの専門性の高い市場もリーンスタートアップが有効です。
その理由は、顧客に応じた柔軟性の高い対応が求められるためです。
高い専門性を求める顧客に対しては、期待値や不満点を把握・分析しながら満足度を高める工夫が必要です。フィードバックを基にしてブラッシュアップするリーンスタートアップを実施することで、顧客の満足度の向上が見込めます。
新興市場
新技術や嗜好に基づく商品・サービスは、ニーズを事前に把握するのが難しく、フィードバックと改善を要する市場です。
新興市場では、MVPの提供・検証・フィードバックを繰り返すリーンスタートアップの理解を深めることが大切です。
リーンスタートアップへの理解を深めることで、新商品・サービスの満足度をより効率的に高めることができます。
ニッチ市場
ニッチ市場は、利益率を維持しやすい・参入障壁が低いなどのメリットがあります。
しかし、マーケティングが難しく、不確実性が高い市場です。
そのため、リーンスタートアップによってMVPの提供と検証を繰り返す手法が有効です。
初期のMVPはクローズド環境で提供して改良することで、少数の顧客と向き合うことができ、不確実性を薄める効果に期待できます。
産業用IT・システム市場
農業・建設などの産業分野におけるシステム化の推進においてもリーンスタートアップは有効です。
例えば、既存のインフラを活用しながらシステム化を進めたい農場の場合は、MVPの提供と検証を繰り返してブラッシュアップを図る方法が有効です。
システム化を少しずつ進めることで、未知の業界にフィットしたものを提供できます。
ファッション・インテリア市場
ファッションやインテリアなど、情緒的なニーズが高い市場では、リーンスタートアップが有効です。
なぜなら、ユーザーの感性の影響を受けやすく、事前にニーズを予測するのが困難なためです。
特に、生産量が少なく、短期間での納品が求められる市場では、リーンスタートアップとの相性が良いと言えるでしょう。
ユーザーの声を反映しつつ商品を改良することで、顧客満足度を高めることが可能です。
Webサービス・通販市場
Webサービス・通販市場では、リアルタイムでユーザーの反応を把握できるため、リーンスタートアップによる高い効果を見込めます。
CRM施策で細かくPDCAサイクルを回す取り組みにおいては、リーンスタートアップが特に有効です。
CRM施策とは、顧客データを活用して顧客ごとに応じた最適なアプローチを実施し、顧客との良好な関係を構築・維持・強化する取り組みのこと。
MVPの提供と評価を繰り返すリーンスタートアップがフィットしやすく、売上向上・顧客定着などに期待できます。
リーンスタートアップの5つの事例

本章では、実際にリーンスタートアップを実践した以下の企業の事例を解説します。
- 株式会社テックピット
- Dropbox
- 食べログ
- Airbnb
世界的に有名な企業の事例もあるので、ぜひ参考にしてください。
Instagramは写真・動画の投稿・共有ができるSNSです。
Instagramは2010年にリリースされましたが、当時は「Burbn」という名前の位置情報アプリでした。
しかし、Burbnはヒットせず、ユーザーの定着が進まない状況だったため、検証の結果、写真の加工・投稿・共有に機能を絞ったアプリにリニューアルしています。
Instagramに名前を変更してからは、今では当たり前にあるハッシュタグを初めて導入するなど、ユーザーのニーズに合わせた機能の導入を積極的に行いました。
その結果、Instagramはユーザーが8,000万人を超えるほどのSNSに成長しています。
参照:Instagramとは何者だ? リリースから2021年10月までの歴史を探る|Grab
参照:失敗から生まれた画像SNS『Instagram』 ~ケビン・シストロム~|KDDI
株式会社テックピット
株式会社テックピットは、専門的な知識を持つエンジニアが学習コンテンツを提供するアプリ「Techpit」やリスキリング支援SaaS「Techpit for Enterprise」を提供しています。
テックピットは事業を拡大する際に、X(旧Twitter)を活用したことで話題になりました。
Xでユーザーから直接ニーズを取り入れることで、テックピットは事業の拡大に成功しています。
テックピットはリーンスタートアップにおいてSNSを活用した好例と評価されています。
Dropbox
オンラインストレージサービスとして、5億人以上のユーザーを抱えるDropboxもリーンスタートアップを活用した企業です。
Dropboxはサービスをリリースするにあたって、ユーザーのニーズを検証するためにデモ動画を作成しています。
デモ動画を公開する際、Dropboxは訴求力を高めるためにも、テクノロジーに詳しいユーザーのアーリーアダプターに設定しています。
その結果、Dropboxはリリース時点で10万人を超えるユーザーの獲得に成功しています。
リリース後、Dropboxはモバイルアプリ・API・法人向けの有料プランなどの提供を段階的に行い、事業を拡大しました。
Dropboxはリーンスタートアップに成功した典型例であり、ニーズを巧みに取り入れながらサービスの改善を繰り返しています。
参照:Dropbox公式サイト
食べログ
食べログは、飲食店のユーザーによる5段階評価が掲載される口コミサイトです。
手作業で構築したデータベースを基に、ユーザーからの改善要望に対応することで、継続的に成長を遂げています。
サービスの開始は2005年の3月、当初のユーザー数は数十人程度でした。
しかし、リーンスタートアップの実践により、月間総PV は20億、月間利用者数は約9,500万人に達しています(2023年3月実績)。
参照:食べログ、サステナビリティに関する情報の掲載を開始 | 株式会社カカクコム
Airbnb
Airbnbは、旅行者(ゲスト)と宿泊先の提供者(ホスト)をつなぐ民泊マッチングサービスです。
個人の自宅や別荘に宿泊することで、現地の生活文化を身近に感じられる点が人気の理由となっています。
Airbnbは当初、最低限の機能を持つWebサイト(MVP)を構築し、ユーザーからのフィードバックを基にしてサービスの改善を繰り返して成長を遂げています。
MVPの提供、仮説検証、改善のサイクルを高速で回すことで市場のニーズに応え、世界最大級のプラットフォームへと成長を遂げました。
リーンスタートアップを成功させる6つのポイント

リーンスタートアップを成功させるなら、以下のポイントを意識しましょう。
- 目的を明確に設定する
- コストをかけ過ぎない
- ネガティブな反応も活用する
- 情報収集を徹底する
- 手段と目的を逆転しない
- マーケットの動向を見極める
いずれのポイントも、リーンスタートアップを成功させるうえで不可欠です。
目的を明確に設定する
リーンスタートアップを実施する際は、開発の目的を明確に設定しましょう。
リーンスタートアップはユーザーに提供したい価値や、プロダクトのコンセプトが明確であるからこそ、スピーディーな開発を実現できる手法です。
目的が曖昧な状態だと、無駄な機能を搭載したり、ユーザーの表面上のニーズに振り回されたりするため、開発やリリースが遅滞する恐れがあります。
目的が明確だからこそ、無駄を省いたスピーディーな開発を実践できます。
リーンスタートアップを実践する際は、従業員やエンジニア同士で目的を共有し、軸がブレないようにしましょう。
コストをかけ過ぎない
リーンスタートアップでは、コストをかけ過ぎないように注意しなければなりません。
最初からコストや労力をかけてプロダクトを開発すると、リーンスタートアップの効果は得られません。
むしろ、柔軟な改善や軌道修正ができなくなり、開発コストの高騰を招きます。
また、リーンスタートアップで製作するプロダクトは、あくまで仮説を検証する道具に過ぎません。
先述したように、場合によっては再構築を行うため、過剰にコストや労力をかけると失敗した際の損失が増加します。
ネガティブな反応も活用する
リーンスタートアップを実施する過程で、ユーザーからネガティブな反応があったとしても積極的に活用しましょう。
ネガティブな反応があったとしても、必ずしもプロダクトの失敗を意味するわけではありません。
ネガティブな反応のなかには、プロダクトの課題を如実に示すものがあります。
むしろ、ネガティブな反応を精査し、課題を解決していけば、より良いプロダクトの実現につながります。
しかし、ネガティブな反応が過剰に発生したり、コンセプトを根底から否定する反応があったりした際は注意が必要です。
先述したように、昨今は企業の悪評が拡散しやすい時代です。
プロダクトの開発継続がかえって企業のイメージを悪化させる状況になった際は、プロジェクトの中断を検討しましょう。
情報収集を徹底する
リーンスタートアップにおいては、ユーザーやマーケットに関する情報収集の徹底も重要です。
ユーザーやマーケットのニーズを的確に把握すれば、仮説の裏付けができ、開発をスムーズに進められます。
また、情報収集を行う際は、開発に関わる従業員への共有も行いましょう。
従業員が必要な情報を理解していれば、それだけ開発や改善が円滑化されます。
手段と目的を混同しない
リーンスタートアップを実施するうえで、手段と目的の混同は禁物です。
リーンスタートアップはあくまで製品開発のマネジメント手法に過ぎず、新しいアイデアを生み出すものではありません。
また、「考える前に動くこと」を推奨する手法でもありません。
そのため、リーンスタートアップの実施自体を目的化すると、ひたすらMVPをリリースする状態に陥る恐れがあります。
リーンスタートアップを成功させるなら、別途でより良いアイデアを生み出すフレームワークを実践しましょう。
より良いアイデアがあってこそ、リーンスタートアップは適切に機能します。
マーケットの動向を見極める
リーンスタートアップを行う際は、マーケットの動向を適切に見極める必要があります。
先述したように、リーンスタートアップはプロダクトによっては効果を発揮しません。
不適切なプロダクトのマーケットで実践する際は、別の開発手法を検討しましょう。
また、マーケットによってはユーザーの評価が拡散されやすい場合があります。
そのようなマーケットだと、リーンスタートアップに失敗すると企業のイメージが急速に悪化するリスクが高まるため、慎重な対応が不可欠です。
リーンスタートアップについてのよくある質問

リーンスタートアップに取り組むべきかを検討する際に、ふとした質問が頭をよぎることもあるでしょう。
本章では、リーンスタートアップについてのよくある4つの質問に回答します。
リーンスタートアップとはどういう意味ですか?
リーンスタートアップとは、必要最低限の機能と品質を備えたプロダクトを開発し、リリース後にユーザーからのフィードバックを得て、改善を繰り返す製品開発マネジメント手法です。
プロダクト開発にかかるコストを抑え、短期間でリリースできるのが特徴です。
特に、トレンドが変わりやすい市場や改善の機会が多い市場に適しています。
リーンスタートアップとアジャイルの違いは何ですか?
リーンスタートアップとアジャイル開発の違いは「何に焦点を当てるか」です。
リーンスタートアップは、顧客からのフィードバックを得てプロダクトを成長させることに重点を置くのに対し、アジャイル開発は、短期間での開発と継続的な機能追加・改善に重点を置いています。
両者は、不確実性の高い状況下で短いサイクルを繰り返しながら、リスクやムダを排除していく点で共通しているため混同されがちです。
なお、アジャイル開発については下記の記事で詳しく解説しています。
リーンスタートアップとはどういう内容ですか?
リーンスタートアップの主なプロセスは、以下の4ステップにまとめられます。
・仮説の構築:リーンキャンバスやMVPキャンバスなどのフレームワークを用いて、ビジネスモデルを可視化し、プロダクトに必要な機能を定義します。
・計測と実験:プロダクトをリリースし、ユーザーの反応を計測・分析することで、仮説を検証します。
・学習と改善:ユーザーからのフィードバックを基に、プロダクトの機能や方向性を見直し、改善を行います。
・再構築(ピボット):致命的な課題やコンセプトの抜本的な見直しが必要な場合は、方向性を変更(ピボット)します。
リーンスタートアップとMVPはどう違うのですか?
リーンスタートアップは、製品開発におけるマネジメント手法であるのに対し、MVP(Minimum Viable Product)は、顧客に価値を提供できる最小限の機能を備えた試作品(プロダクト)を指します。
MVPは、リーンスタートアップを実践する際に用いられ、ユーザーのフィードバックを基に改善を重ねることで、プロダクトの価値を高めていきます。
MVPの詳細は下記の記事をご覧ください。
ポイントを押さえてリーンスタートアップを成功させよう

リーンスタートアップはプロダクトの無駄な機能を省き、仮説を立証するうえで必要なものだけにしたうえで開発・リリースする手法です。
プロダクトの機能に必要なものだけに限定することで、低コストかつスピーディーに開発できる点がリーンスタートアップのメリットです。
また、ユーザーのニーズを積極的に取り入れることで、柔軟な改善や軌道修正を可能とします。
リーンスタートアップは世界的な企業も利用する手法であり、InstagramやDropboxの開発にも利用されました。
一方で、リーンスタートアップはプロダクトによって相性がはっきりしているうえに、フィードバックに振り回され過ぎるとコンセプトが失われるリスクがあります。
リーンスタートアップを実践する際は、目的を明確にし、プロダクトの適正を確認することを心がけましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ
新規事業部門のマネージャーの方や、