3Dセキュア2.0(本人認証サービス)とは?設定方法からエラー対処法まで徹底解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
ECサイトを運営する中で、顧客が決済時に離脱してしまう原因の一つに、本人認証の複雑さがあります。
特に、3Dセキュアと聞いて、その導入や運用に戸惑いを覚える運営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では「3Dセキュア2.0」の基本的な仕組みから、サイトへの導入方法、そして発生しうるエラーへの対処法までを徹底的に解説します。
さらに、3Dセキュア2.0がもたらすメリットとデメリットも詳細にご紹介し、安全かつスムーズなオンライン決済環境の構築にお役立ていただける情報を提供いたします。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブック
ECサイトでの売上増を目指している方、
そもそも3Dセキュア2.0とは

3Dセキュア2.0とは、インターネット上でクレジットカード決済をより安全に行うための本人認証サービスです。
カード番号や有効期限、セキュリティコードだけでなく、本人しか知り得ないパスワードを使用します。
さらに、スマートフォンに届くワンタイムパスワードなどを用いて、追加の認証を行います。
結果として、第三者にカード情報が盗まれた場合でも、不正利用を未然に防げるものです。
近年、クレジットカードの不正利用被害が急増していることを背景に、オンラインショッピングにおける本人認証の強化が不可欠となりました。
そこで、経済産業省の指針に基づき、2025年3月までにすべてのEC事業者に対して導入が義務化されたのが「3Dセキュア2.0(EMV 3-Dセキュア)」です。
参照:経済産業省「「クレジットカード・セキュリティガイドライン」が改訂されました」
これは、従来のカード情報(鍵)に加え、ワンタイムパスワードや生体認証など、本人しか操作できない「もう一つの鍵」を追加するような仕組みです。
さらに、すべての決済で追加認証を求めるのではなく、取引のリスクを判定し、不正利用の疑いが低い場合は認証を省略できる「リスクベース認証」という技術が採用されています。
これにより、旧バージョンで課題とされた手間を省き、利用者の利便性を損なうことなく、より高い安全性を確保できるようになりました。
3Dセキュア2.0と3Dセキュア1.0の違い
3Dセキュア1.0と3Dセキュア2.0の大きな違いは、リスクベース認証の有無にあります。
3Dセキュア1.0では、すべてのオンライン決済時にパスワードの入力が必要で、利用者にとって大きな負担となっていました。
一方、3Dセキュア2.0ではリスクベース認証が導入され、安全性と利便性の両立が実現されています。
リスクベース認証とは、利用者のデバイス情報や購買履歴、アクセス環境などをもとに不正利用のリスクを自動で判定する仕組みです。
リスクが低いと判断された取引では、追加認証なしで決済が完了します。
こうした仕組みにより、利用者の負担が大幅に減り、スムーズなオンライン決済ができるようになりました。
| 項目 | 3Dセキュア2.0 | 3Dセキュア1.0 |
|---|---|---|
| 認証方式 | リスクベース認証(取引内容に応じて認証方法が変化) | パスワード認証(原則毎回入力が必要) |
| 追加認証 | ワンタイムパスワード、生体認証など多様 | 事前に設定した固定パスワード |
| 利便性 | 高リスク時のみ認証が求められ、スムーズ | 毎回認証が必要で、手間がかかる |
| 対応デバイス | PC、スマートフォン、アプリ決済に対応 | 主にPCブラウザ向け |
| カゴ落ちリスク | 低い(認証の手間が少ないため) | 高い(パスワード忘れなどで離脱しやすい) |
以上のように、3Dセキュア2.0は安全性を高めながらも、利用者のストレスを軽減する進化を遂げています。
3Dセキュア2.0とセキュリティコードの違い
セキュリティコードは、クレジットカードの裏面などに記載された3桁又は4桁の数字で、カードが手元にあることを示す手段としてオンライン決済時に入力が求められます。
ただし、カード本体が盗難に遭った場合は、セキュリティコードも同時に悪用される可能性があります。
したがって、セキュリティコードだけでは不正利用を完全に防げません。
一方、3Dセキュア2.0は、インターネット上での決済をより安全に行うために導入された本人認証システムです。
カード情報だけに依存せず、ワンタイムパスワードや指紋・顔などの生体認証、又はカード会社によるリスク分析に基づいた追加認証を求める仕組みです。
たとえカード情報やセキュリティコードが流出した場合でも、本人しか通過できない認証ステップがあるため、なりすましによる不正利用を大幅に防げるようになります。
セキュリティコードがカードの所持を前提とした仕組みであるのに対し、3Dセキュア2.0は多要素認証によって、より強固なセキュリティを提供します。
| 項目 | 3Dセキュア2.0 | セキュリティコード |
|---|---|---|
| 目的 | 決済時の(本人)認証 | カードが(手元にある)ことの確認 |
| 認証情報 | ワンタイムパスワード、生体情報、専用パスワードなど | カード裏面の3桁又は4桁の数字 |
| セキュリティレベル | 高い(カード情報とは別の認証要素) | 限定的(カードと一緒に漏洩するリスク) |
| 利用場面 | 対応しているオンライン加盟店での決済時 | 主にオンライン決済全般 |
クレジットカードの3Dセキュア2.0対応

現在、国内で発行されている多くのクレジットカードが3Dセキュア2.0に対応しています。
カードが対応しているかどうか、また、どのように登録・設定すれば良いかはカードの発行会社や国際ブランドによって異なります。
以下に、主要カードブランドの対応状況と、登録状況の確認方法をまとめました。
主要な国際ブランドは、それぞれ独自の名称で3Dセキュア2.0サービスを提供しています。
| 国際ブランド | 3Dセキュア2.0のサービス名称 |
|---|---|
| Visa | Visa Secure(ビザセキュア) |
| Mastercard | Mastercard ID Check |
| JCB | J/Secure™ (ジェイセキュア) |
| American Express | American Express SafeKey® |
| Diners Club | ProtectBuy®(プロテクトバイ) |
上記のブランドが付いているカードであれば、基本的に3Dセキュア2.0に対応しています。
ただし、具体的な登録方法や認証方式(ワンタイムパスワード・専用アプリなど)は、カード発行会社の方針によって異なります。
<参考一覧>
Visa(世界中、使える安心。選ばれているクレジットカード)
Mastercard(お金で買えない価値がある。買えるものはMastercardで)
JCB(安心と信頼のジャパン・クオリティ。暮らしに寄り添うJCBカード)
American Express(困ったとき、頼れる一枚。万全のサポートで選ばれるアメックス)
Diners Club(日常を、特別に変えるカード)
3Dセキュア2.0とシステム連携のポイントとは

3Dセキュア2.0では、ECサイトのセキュリティ強化と顧客体験向上の両面が重要です。
しかし、そのような背景には複雑なシステム連携が不可欠です。
安全でスムーズなオンライン決済を実現するには、ECサイトや決済代行会社、そしてカード発行会社の三者間での密な連携が欠かせません。
以下では、3Dセキュア2.0のシステム連携において重要なポイントについて解説します。
3Dセキュア2.0の認証フローと連携の仕組み
3Dセキュア2.0で行われる認証フローは、従来のバージョンと比べて高度化されており、より多くの情報とシステム連携が必要です。
認証は主に以下のステップで進行し、複数のシステムが連携して処理を行います。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 取引情報の共有 | 顧客がECサイトで決済を試みると、ECサイトは顧客のデバイス情報や購入履歴、IPアドレスなどの取引情報を決済代行会社経由でカード発行会社へ送信します。 |
| リスクベース認証 | カード発行会社は、受け取った取引情報に基づいて不正リスクをリアルタイムで分析します。 リスクが低いと判断された場合、追加認証なしで取引が承認される(フリクションレスフロー)となります。 |
| チャレンジ認証 | リスクが高いと判断された場合、カード発行会社は顧客に対して追加認証(チャレンジフロー)を要求します。 追加認証は、ワンタイムパスワードの入力や指紋認証、顔認証など顧客が事前に登録した情報に基づいて行われます。 |
| 認証結果の伝達 | 問題なく認証されると、認証結果がカード発行会社から決済代行会社、そしてECサイトへと伝達され決済が完了します。 認証できなかった場合は、決済が拒否されます。 |
上記の認証フローをスムーズに実行するには、ECサイトにおける決済システムや決済代行会社が提供するゲートウェイ、そしてカード発行会社が運用する認証システムの密接な連携が必要です。
また、データフォーマットを統一することも重要です。
決済代行会社とのシステム連携の進め方
3Dセキュア2.0を導入する際は、まず現在利用中の決済代行会社が認証方式に対応しているかどうかを確認することが重要です。
対応している場合、多くの決済代行会社では開発者向けにAPI仕様書や技術ガイドライン、実装サンプルなどの技術資料を提供しています。
公開されている技術資料を参照しながら、システムとの連携作業を進めていく必要があります。
具体的な実装にあたっては、下のステップを順に踏むことが一般的です。
- 決済代行会社から提供されるAPI仕様書や技術書類を入手し、認証フローやパラメータの構成を正確に把握する
- テスト環境で使用するアカウント情報や認証キー、テスト用カード番号などを取得し、開発環境に組み込む
- 認証リクエストの送信処理(Challenge Request)及び、カード発行会社から返されるレスポンスの受信・解析処理を実装する
- 認証されない場合やタイムアウト、通信エラーなどの異常系に備えたエラーハンドリングやリトライ処理を設計する
各決済代行会社によって仕様や実装方法が異なる場合があるため、事前に詳細な仕様確認を行い、実装ミスを防ぐことが大切です。
テスト環境での検証と本番移行時の注意点
3Dセキュア2.0の導入において、テスト環境での入念な検証は不可欠です。
まず、以下の表で検証内容をご確認ください。
| 検証内容 | 内容 |
|---|---|
| 多様なテストシナリオ | フリクションレスフロー、さまざまなチャレンジ認証方法(SMS認証・アプリ認証など)認証されない場合やタイムアウト、ネットワークエラーといった多様なシナリオでテストを実施しましょう。 異なるデバイス(PC・スマートフォン・タブレット)やブラウザでの動作確認も重要です。 |
| エラーハンドリングの確認 | 認証エラーが発生した場合に、ECサイト側で適切にエラーメッセージを表示し、顧客に再試行を促したり別の決済手段を案内したりできるかを確認します。 |
| ログとモニタリング | テスト中に発生した問題の特定と解決に向けた、詳細なログが取得できているか、また本番稼働後のモニタリング体制を事前に確認しておきましょう。 |
テストが完了し、システムが安定していることを確認できたら、いよいよ本番環境への移行です。
本番移行時には、以下の点に注意が必要です。
| 注意すべき点 | 内容 |
|---|---|
| 段階的なリリース | 可能であれば、まず一部顧客や特定取引に対して3Dセキュア2.0を適用し、問題がないかを確認しつつ、段階的に対象範囲を拡大しましょう。 |
| 顧客への周知 | 3Dセキュア2.0が導入されることで決済フローに変化が生じる可能性があるため、顧客に対して事前に告知を行い、混乱を避けるように努めましょう。 よくある質問(FAQ)の準備も有効です。 |
| パフォーマンス監視 | 移行後は、決済処理のパフォーマンスや認証達成率を継続的に監視し、予期せぬ問題が発生していないか常にチェックすることが重要です。 |
以上のポイントを押さえることで、ECサイトは3Dセキュア2.0を効果的に導入し、安全でスムーズなオンライン決済環境が得られます。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブック
ECサイトでの売上増を目指している方、
3Dセキュア2.0を導入するメリット

3Dセキュア2.0は、セキュリティを強化するだけでなく、快適な利用環境の実現にも役立つ多くの利点があります。
ネットショッピングを安全かつスムーズに提供するために、導入による具体的なメリットを把握しておくことをおすすめします。
不正利用のリスクを大幅に軽減できる
3Dセキュア2.0のメリットは、クレジットカードの不正利用を強力に防止できる点です。
たとえカード情報が漏洩した場合でも、本人認証のプロセスが追加されていることで、第三者による不正な決済が防げます。
また、高額商品を購入する際や海外のECサイトでの決済においても、安全性が高く利用者は安心して取引を行えるようになります。
チャージバック(不正利用による返金請求)の削減
利用者が安心して買い物できる環境の維持には、3Dセキュア2.0の導入が有効です。
なぜなら、不正利用の防止によりECサイトのチャージバックリスクが大幅に軽減されるためです。
例えば、本人認証によって不正な決済が防がれれば、取引の安全性が高まり、販売事業者の信頼性も向上します。
結果として、セキュリティ強化が利用者の安心感と利便性の向上にもつながります。
スマートフォン対応でユーザー体験を損ねにくい
3Dセキュア2.0は、スマートフォンアプリ内での決済に最適です。
理由は、リスクベース認証によってパスワード入力の手間が省かれ、操作がスムーズになるためです。
小さな画面でも支払いが滞らず、パスワードを思い出せずに購入を断念する事態を防げます。
これらの仕組みにより、カゴ落ちのリスクが低減される可能性があります。
多様な認証方法に対応
3Dセキュア2.0は、多様な認証方法に対応している点も大きなメリットです。
従来のパスワード認証だけでなく、SMSやメールで届くワンタイムパスワードや専用の認証アプリ、さらには指紋や顔といった生体認証も利用可能です。
こうした多様な選択肢が提供されることで、ユーザーは自身がもっとも使いやすい認証方法を選べます。
結果として、よりスムーズに認証プロセスを完了でき、ストレスなくオンライン取引を進められます。
ユーザーの安心感が向上する
3Dセキュア2.0は、オンライン決済におけるユーザーの安心感を大幅に高めます。
なぜなら、多様な認証方法が利用可能になったことで、セキュリティが強化され不正利用のリスクが低減するからです。
安全な環境により、ユーザーはより安心してオンラインショッピングを利用できます。
さらには、カゴ落ちの減少やコンバージョン率の向上といった効果も期待できます。
3Dセキュア2.0を導入するデメリット
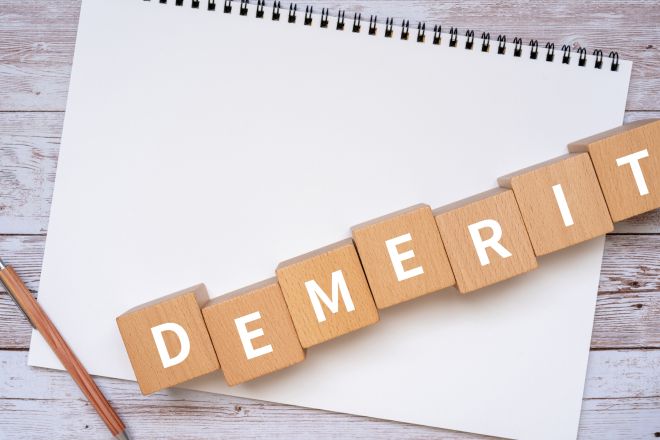
3Dセキュア2.0は、多くのメリットがある一方で、利用者視点でのデメリットも存在します。
これらの点を理解しておくことで、万が一の場合にも冷静に対処することが可能です。
システム連携や実装に手間がかかる
3Dセキュア2.0では、既存の決済システムとの連携や技術的な調整が必要です。
特にECサイトやアプリに組み込む場合、開発工数が増える可能性があります。
テストや検証にも時間がかかり、スムーズな運用開始には準備が欠かせません。
こうした準備にかかる時間は、技術リソースが限られている事業者にとって大きな負担です。
一部ユーザーが離脱する懸念
3Dセキュア2.0は、認証操作に不慣れなユーザーや高齢者の離脱するリスクを高めます。
認証プロセスの追加によって、購入完了までのステップを増やし、手続きが複雑になるからです。
スマートフォンを利用しているユーザーは、画面遷移や入力の煩雑さが障壁となり、スムーズな購入が難しくなることがあります。
したがって、認証プロセスの設計にあたっては、ユーザーの利便性を十分に考慮することが重要です。
決済サービスやカードによっては非対応
すべてのカード会社や決済サービスが3Dセキュア2.0に対応しているわけではありません。
非対応のカードを利用するユーザーは認証が行えず、人によっては決済を進められない場合もあります。
こうした状況は、購入機会の損失やカスタマーサポートへの問い合わせを増加させることにもつながります。
対応状況を事前に確認し、代替手段を用意することが重要です。
導入コストがかかる
3Dセキュア2.0を導入する際には、中小規模の事業者にとって大きな初期投資が必要です。
システム開発費や運用コストが発生し、さらに継続的なメンテナンスやアップデートにも費用がかかります。
中小規模の事業者がコストを考慮せずに導入を決定すると、経済的なリスクを抱える可能性があります。
3Dセキュア2.0は、費用対効果を慎重に見極めたうえで導入を検討しましょう。
誤検知による正常な取引のブロック
誤検知によって、正当な取引が不審と判断される場合があることも、3Dセキュア2.0のデメリットです。
こうした状況は、ユーザーが決済を完了できないため、機会損失のリスクを引き起こします。
特に高額商品や海外からのアクセスでは、誤検知のリスクが高まります。
ユーザー体験を損なわないためには、検知ロジックの調整が重要です。
3Dセキュア2.0の利用登録・設定変更が必要なケースと手順

3Dセキュア2.0を利用するためには、多くの場合、事前の利用登録や設定が必要です。
特に、ワンタイムパスワードの通知先が最新の情報になっているかどうかは、入念に確認しましょう。
ワンタイムパスワードの通知先や確認すべき点
3Dセキュア2.0では、決済時にワンタイムパスワードなどの追加認証が求められることがあります。
こちらのパスワードは、事前にお客様がカード会社に登録した電話番号(SMS)やメールアドレスに送信されることが一般的です。
設定変更や確認を行う際は、以下のポイントに注意してください。
| 確認すべき点 | 詳細 |
|---|---|
| 登録情報の最新性 | 登録している電話番号やメールアドレスが、現在使用しているものと一致しているかをしっかりと確認しましょう。 古い情報が登録されていると、ワンタイムパスワードを受信できず、決済が完了しません。 |
| カード会社のWebサイトでの確認 | 各カード会社の会員専用Webサイトにログインし、3Dセキュア2.0に関する設定項目を確認してください。 通常、(本人認証サービス)や(3Dセキュア)といった名称で案内されています。 |
| ID・パスワードの管理 | 3Dセキュア2.0の利用には、カード会社ごとに設定されたIDとパスワードが必要となる場合があります。 IDやパスワードは厳重に管理し、使い回しは避けましょう。 |
| 通知設定の確認 | ワンタイムパスワードの通知方法(SMS・メール・アプリなど)や通知先について、希望する設定になっているか確認しましょう。 |
主要カード会社別・設定ページへのリンク集
3Dセキュア2.0の登録や設定変更は、各カード会社の会員サイトから行えます。
本記事では、カードの設定ページを探す手間を減らすため、主要なカード会社の設定や案内ページをまとめました。
以下のリンクからご利用のカード会社サイトにアクセスし、設定状況をご確認ください。
| カード発行会社 | 設定・案内ページ |
|---|---|
| 楽天カード | https://www.rakuten-card.co.jp |
| 三井住友カード | https://www.smbc-card.com |
| JCBカード | https://www.jcb.co.jp |
| イオンカード | https://www.aeon.co.jp |
| dカード | https://dcard.docomo.ne.jp |
| PayPayカード | https://www.paypay-card.co.jp |
| セゾンカード | https://www.saisoncard.co.jp |
| 三菱UFJニコスカード | https://www.cr.mufg.jp |
3Dセキュア2.0の認証エラー原因と解決策

3Dセキュア2.0はオンライン決済の安全性を高める仕組みですが、時には認証エラーが発生し、決済が完了できないことがあります。
本章では、よくある認証エラーの原因と、それぞれの解決策について分かりやすく解説します。
認証されない5つのよくある原因
認証エラーが発生する際には、主に以下の原因が挙げられます。
状況がどれに当てはまるか、それぞれの項目を確認しましょう。
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| パスワードや認証コードの入力ミス | もっとも多い原因です。 ワンタイムパスワードや事前に設定したパスワードの入力間違い、大文字・小文字の間違いなどがないか確認しましょう。 |
| ワンタイムパスワードの有効期限切れ | ワンタイムパスワードには、短い有効期限が設定されています。 時間を過ぎてから入力するとエラーが発生します。 |
| そもそも本人認証サービスに未登録 | 3Dセキュア2.0を利用するには、事前の登録が必要です。 未登録の場合は認証自体が行えません。 |
| 登録情報が古い | SMSの送信先電話番号やメールアドレスが古いままになっていると、ワンタイムパスワードを受け取れません。 |
| ブラウザやアプリの環境の問題 | 推奨されていない古いバージョンのブラウザを利用していたり、広告ブロック機能が干渉したりして、認証画面が正しく表示されないことがあります。 |
原因別の対処法をステップ解説
認証されない原因が特定できた場合は、以下に記載した5つの対処法をお試しください。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| 入力ミス | 再度、新しいワンタイムパスワードを発行して、落ち着いて正確に入力する。 パスワードをコピー&ペーストする場合は、前後に不要な空白が入っていないか確認する。 |
| 有効期限切れ | 認証画面で(ワンタイムパスワードを再送)ボタンを押し、新しいパスワードで試す。 |
| 未登録 | ご利用のカード会社の会員サイトにログインし(本人認証サービス)メニューから新規登録を行う。(設定ページへのリンク集を参照) |
| 登録情報が古い | カード会社の会員サイトで、登録されている電話番号やメールアドレスを最新のものに更新する。 |
| ブラウザなどの環境 | ブラウザやアプリを最新バージョンにアップデートする。 一時的に広告ブロック機能をオフにして試す。 各対処法を実行しても解決しない場合は、別のブラウザやデバイスで試してみる。 |
上記の対処法を試しても解決しない場合は、カード会社のサポートセンターへお問い合わせください。
まとめ:3Dセキュア2.0で、安全・快適なネットショッピングを提供しよう

本記事では、3Dセキュア2.0の仕組みからメリット、具体的な設定方法や認証エラー時の対処法までを解説しました。
3Dセキュア2.0は、オンライン決済を不正利用の脅威から守るための重要な仕組みです。
また、リスクベース認証の導入により、安全性と利便性の両方が大きく向上している点も注目すべき特徴です。
正しい知識を身につけ、設定を万全にしておくことで、将来の決済トラブルも未然に防げます。
3Dセキュア2.0を正しく理解し、より安全で快適なネットショッピングを提供しましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
システム開発ハンドブック
ECサイトでの売上増を目指している方、















