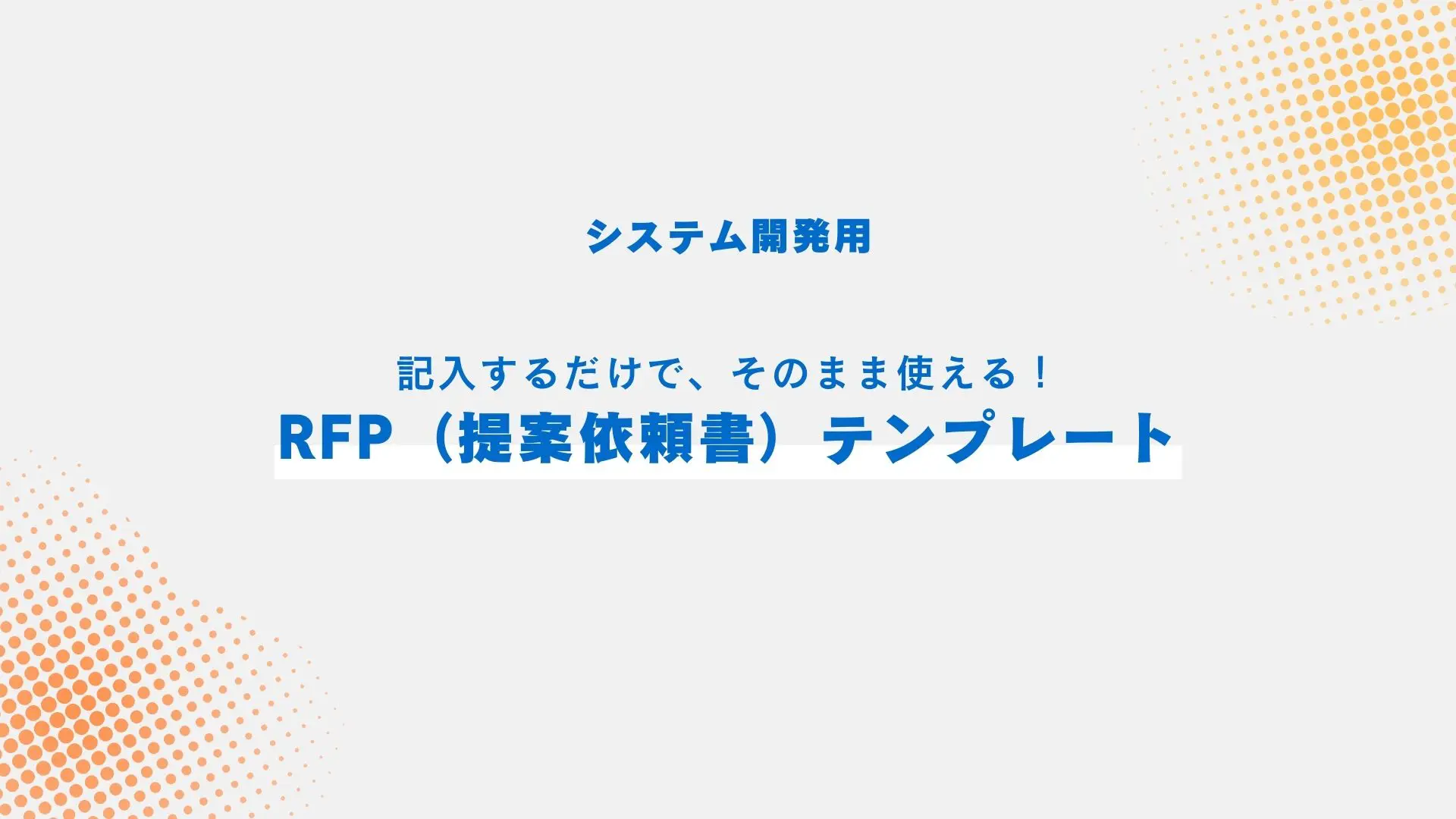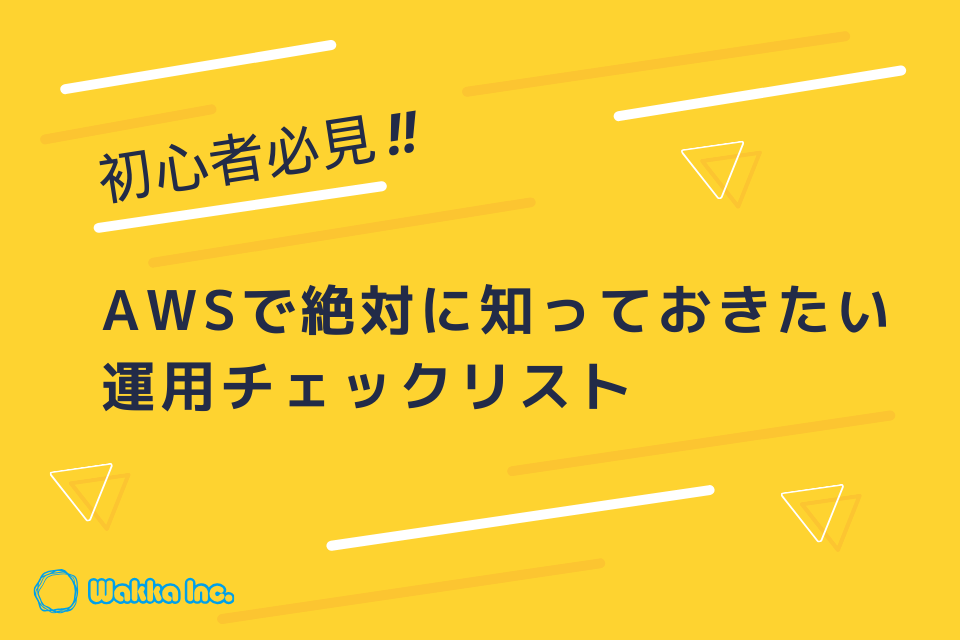要求仕様書の書き方|作成の目的や手順などを解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
システム開発プロジェクトを成功させるには、関係者間の認識を揃えることが不可欠です。
認識をすり合わせるうえで重要なのが要求仕様書ですが、いざ作成する段階になると、何を記載すべきか迷われる方も多いのではないでしょうか。
実際、分かりやすい要求仕様書を作成するには、記載すべき項目や押さえておくべきポイントがあります。
本記事では、要求仕様書の基本的な知識・具体的な書き方・伝わる文書を作成するためのコツまでを分かりやすく解説します。
プロジェクトを円滑に進めるための、的確な要求仕様書を作成する際の参考にしてください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
要求仕様書の概要

要求仕様書とは、開発するシステムに対して、発注者や利用者が何を求めているのかを具体的にまとめた文書のことです。
本章では要求仕様書の作成目的・役割に加え、ほかの書類との違いについて解説します。
要求仕様書の作成目的と役割
要求仕様書の最大の目的は、作るべきシステムの姿について発注者と開発者の間で共通認識を形成することです。
この目的を達成するために、要求仕様書は以下のような具体的な役割を果たします。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 要件の明確化 | 発注者がシステムに求める機能や性能を、誰が読んでも理解できるように具体的に言語化・可視化します。 |
| 開発範囲の定義 | 「何を作り、何を作らないのか」という開発のスコープを明確にし、プロジェクトの肥大化(スコープクリープ)を防ぎます。 |
| 開発・テストの指針 | 開発者にとっては設計・実装のインプットとなり、テスト担当者にとってはシステムの正しさを検証するための基準となります。 |
| 品質保証の基準 | 完成したシステムが、発注者の要求を満たしているかどうかを判断するための客観的な基準として機能します。 |
| 合意形成の証拠 | プロジェクトの途中で仕様変更に関するトラブルが発生した際に、契約内容や合意事項を確認するための拠り所となります。 |
上記の役割を通じて、要求仕様書はプロジェクト全体の品質と方向性を担保します。
要求仕様書の必要性
適切に作成された要求仕様書は発注者からのニーズを明確にし、開発の方針を定めることにより、プロジェクトを円滑に進める効果が期待できます。
開発プロジェクトでは、開発者が発注者の要望を正確に把握するため、丁寧にコミュニケーションを取る必要があります。
クライアントと齟齬がないようにコミュニケーションを取らなければ、開発に遅延が生じたり、適切なプロダクトを開発できなくなったりするリスクが生じます。
プロジェクトの方針や内容を正確に記載した要求仕様書は、発注者と開発者の間で認識のズレを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための不可欠なコミュニケーションツールです。
また、要求仕様書があることで、プロジェクトに関わる全員が「どのようなシステムを作るのか」という共通のゴールを正確に理解できます。
要件定義書との違い
要件定義書と要求仕様書はよく似ていますが、実際は異なる内容を記載した書類です。
先述したように、要求仕様書は開発予定のシステムの要件や開発範囲など、プロダクトの概要を発注者と開発者が主体となって作成するものです。
対して、要件定義書は発注者のニーズを踏まえ、開発者側がシステムに必要な機能や開発方法などを記載します。
つまり、要求仕様書と要件定義書は記載する主体が異なっています。
要求定義書との違い
要求仕様書ともっとも混同されやすいのが要求定義書です。
両者は密接に関連していますが、作成する主体と目的が異なります。
| ドキュメント種別 | 主な作成者 | 目的 | 内容の粒度 |
|---|---|---|---|
| 要求定義書 | 発注者(ユーザー側) | システムで解決したい課題や目的を定義する | 大局的・ビジネス視点 |
| 要求仕様書 | 発注者・開発者 | 要求定義書の内容を、より具体的にシステムで実現する機能に落とし込む | 具体的・システム視点 |
簡単に表現すれば、要求定義書が「なぜそのシステムが必要か」を示すのに対し、要求仕様書は「そのシステムで何ができるようにするべきか」を詳細に記述するものです。
RFPとの違い
RFP(Request for Proposal:提案依頼書)も要求仕様書と関連が深いため、混同されやすい傾向にあります。
RFPは開発を委託するベンダーを選定する際に、発注者が複数の候補企業に提示するために作成されます。
RFPの概要は以下の通りです。
| RFPが要求仕様書と異なる点 | 内容 |
|---|---|
| 作成する目的 | 複数のベンダーから最適な提案と見積もりを引き出すため。 |
| 記載する内容 | プロジェクトの背景・目的・予算・納期・要求の概要など。 |
| 書類の役割 | ベンダー選定のたたき台。 |
RFPに含まれる要求は概要レベルです。
正式に開発が決定した後に、RFPの内容をより詳細化・具体化したものが要求仕様書となります。
アジャイル開発と要求仕様書

アジャイル開発では機能ごとに小さな単位で開発を進めるため、各機能ごとに要求仕様書を作成するケースが多くなります。
機能別に発注者のニーズを確認するために、個別で要求仕様書を作成するケースが一般的です。
なお、その他の開発手法を用いる場合でも、RFPの後に要件定義書や要求仕様書を作成する場合があります。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
要求仕様書に記載する項目

本章では、要求仕様書に記載すべき主要な項目を解説します。
要求仕様書に記載する項目は以下の通りです。
- プロジェクトの概要
- 現状の課題
- 機能
- 開発体制や人員
- スケジュール
上記の項目をチェックリストとして活用することで、抜け漏れのない高品質なドキュメントの作成が可能です。
プロジェクトの概要
まず、プロジェクトが何を目指しているのか、全体像を関係者全員が共有できるように記述します。
プロジェクトの概要を記載する際は、以下の内容を網羅しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 背景と目的 | なぜこのシステム開発が必要なのか、その背景を説明します。 加えて、プロジェクトを通じて達成したい具体的な目標(売上向上・コスト削減など)を明記します。 |
| プロジェクトの範囲(スコープ) | 今回の開発で対象とする業務範囲や機能を明確にします。 逆に「何をしないか(対象外)」も記述することで、関係者の期待値のズレを防ぎます。 |
| 全体像 | システム構成図や業務フロー図を用いて、開発するシステムの全体像を視覚的に示します。 |
プロジェクトの概要を具体的に記載すれば、達成すべきビジョンが明確になります。
現状の課題
続いては現状の課題の整理です。
新しいシステムで解決したい、現在の業務における問題点や課題を具体的にリストアップします。
この項目を明確にすることで、開発するシステムの価値がより鮮明になります。
以下に要求仕様書に記載する課題の事例をまとめましたので、ご参考ください。
| 課題のカテゴリ | 具体的な課題の例 |
|---|---|
| 業務効率 | ・手作業でのデータ入力に毎月20時間かかっている。 ・複数のExcelファイルで顧客情報を管理しており、情報が分散している。 |
| コスト | ・既存システムの保守費用が年間500万円に上る。 ・紙の帳票の印刷・保管コストが高い。 |
| セキュリティ | ・個人情報の管理方法に脆弱性があり、情報漏洩のリスクがある。 |
現状の課題を整理すれば必要な機能が明確になり、開発工程や予算を決定しやすくなります。
機能
ユーザーがシステムで実現したい操作や処理内容を、機能要件として具体的に記述します。
この項目が要求仕様書の中核となる部分です。
機能について記載する場合は、以下の内容をチェックしましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能一覧 | システムに実装すべき機能を網羅的にリストアップします。 |
| 画面・帳票一覧 | ユーザーが操作する画面や、システムから出力される帳票の種類を洗い出します。 |
| データ要件 | システムで扱うデータの種類・項目・データ量などを定義します。 |
| 外部システム連携 | 他のシステムとデータをやり取りする必要がある場合、その連携方法やデータ形式を記述します。 |
開発体制や人員
プロジェクトを推進するための体制について記述します。
誰が、どのような役割で、いつまでに何を行うのかを明確にすることが目的です。
各人員の役割に加え、以下のようにコミュニケーション計画や意思決定のプロセスも明記しておくと、組織体制を明確にできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割分担 | プロジェクトマネージャー・開発リーダー・担当者など、関係者の役割と責任範囲を定義します。 |
| コミュニケーション計画 | 定例会議の頻度や報告方法、使用するツール(SlackやTeamsなど)を定めます。 |
| 意思決定プロセス | 仕様変更や問題発生時に、誰が最終的な判断を下すのかを明確にしておきます。 |
スケジュール
スケジュールを記載し、プロジェクト全体の工程と期間を明確にします。
マイルストーンを設定し、進捗を管理しやすくすることが重要です。
スケジュールは以下のように記載しましょう。
| フェーズ | 主なタスク | 期間(目安) |
|---|---|---|
| 要件定義 | 要求仕様書の作成・合意形成 | 1カ月 |
| 設計 | 基本設計・詳細設計 | 2カ月 |
| 開発・実装 | プログラミング・単体テスト | 4カ月 |
| テスト | 結合テスト・総合テスト・受け入れテスト | 2カ月 |
| リリース | 本番環境への移行、運用開始 | 1カ月 |
具体的なスケジュールを記載すれば、工数の正確な把握が可能です。
プロセスのブラッシュアップをしやすくなるため、無駄な工程を省いたり、コストを減らしたりできる可能性が高まります。
要求仕様書の作成手順
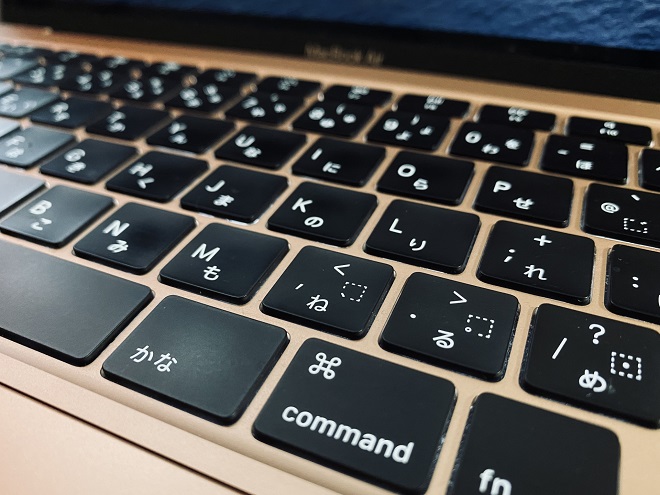
本章では、要求仕様書を完成させるまでの手順について解説します。
要求仕様書は以下のような4つのステップで作成するものです。
- 要求収集
- 要求分析
- 要求定義
- 要求仕様記述
質の高い要求仕様書は、場当たり的に作成できるものではありません。
体系立てられたプロセスに沿って進めることで、抜け漏れや矛盾を防止できます。
1. 要求収集
最初のステップは、関係者からシステムに対する要求を幅広く集める要求収集です。
この段階では、できるだけ多くの意見を収集することが重要です。
要求収集では、以下のような作業が実施されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヒアリング | 実際にシステムを利用するユーザーや、関連部署の担当者にインタビューを行います。 「何に困っているか」「どうなれば便利か」といった、現場の生の声を集めましょう。 |
| アンケート調査 | 関係者が多い場合はアンケートを実施して効率的に意見を収集しましょう。 |
| 現状業務の分析 | 既存の業務フロー・マニュアル・帳票類を分析し、課題や改善点を見つけ出します。 |
2. 要求分析
要求分析は収集した多種多様な要求を、整理・分析していくステップです。
すべての要求を鵜呑みにするのではなく、その背景や真の目的を見極めることが求められます。
収集した要求を分析する際は、以下の方法を実践しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要求の分類 | 機能に関する要求(機能要件)と、性能やセキュリティなど品質に関する要求(非機能要件)に分類します。 |
| 優先順位付け | 実現の難易度や、ビジネスへのインパクトを考慮し、各要求に優先順位を付けます。 |
| 要求の矛盾や重複の解消 | 異なる関係者から出た要求が矛盾していないか、同じ内容の要求が重複していないかを確認し、整理します。 |
3. 要求定義
要求定義とは、分析した要求をもとにシステムが実現すべきことを明確に定義する作業です。
このステップでは、曖昧だった要求を誰もが同じように解釈できる具体的な言葉に落とし込む作業が中心となります。
要求分析で整理した内容を、要求仕様書としてまとめる工程です。
4. 要求仕様記述
最後に、定義された要求を要求仕様書のフォーマットに沿って記述する要求仕様記述を行います。
これまでのステップで整理・定義された内容を、第三者が見ても正確に理解できるように、分かりやすく体系的にまとめることが重要です。
前述の「要求仕様書に記載する項目」を参考に、各項目を埋めていきましょう。
分かりやすい要求仕様書を書くポイント

本章では、要求仕様書の項目と作成手順を理解したうえで、さらにドキュメントの品質を向上させるための以下のポイントを紹介します。
- 曖昧な表現を避ける
- 関係者とのコミュニケーションを密にする
- 変更履歴を記録する
- レビュー体制を整える
- 最新の状態を維持する
- テンプレートやフォーマットを用意する
上記のポイントを意識することで、開発者との認識の齟齬を最小限に抑え、プロジェクトの成功確率を大幅に高めることができます。
曖昧な表現を避ける
要求仕様書を作成する際は、曖昧な表現を避けましょう。
開発者が迷わず実装できるよう、具体的ですぐに解釈できる言葉で記述することが極めて重要です。
誰が読んでも同じ意味に捉えられる表現を心がけましょう。
例えば、以下のような表現で記載しましょう。
| 悪い例(曖昧な表現) | 良い例(具体的な表現) |
|---|---|
| 素早く表示すること。 | 検索ボタンクリック後、3秒以内に検索結果を表示すること。 |
| 使いやすいデザインにすること。 | 主要な機能へは、トップページから2クリック以内でアクセスできること。 |
| 大量のデータにも対応できるように。 | 100万件の顧客データを保持し、通常利用に耐えうること。 |
関係者とのコミュニケーションを密にする
要求仕様書の作成において、関係者とのコミュニケーションを密にすることは重要です。
要求仕様書は一人で完成させるものではありません。
作成の各段階で、ユーザーや開発者などの関係者と密にコミュニケーションを取り、内容をレビューしてもらうことが不可欠です。
以下のような取り組みを実施しましょう。
- 定期的なレビュー会を開催する
- 認識のズレがないか、こまめに確認する
- 議事録を作成し、合意事項を記録に残す
関係者と綿密なコミュニケーションをするほど、より確度の高い内容を実現できます。
変更履歴を記録する
要求仕様書を作成する際は、変更履歴を逐一記録するように心がけましょう。
プロジェクトの進行に伴い、要求仕様が変更されることは珍しくありません。
いつ・誰が・なぜ・何を・どのように変更したのかを正確に記録することが、後の混乱を防ぎます。
変更履歴を残す際は、以下のような取り組みを実施しましょう。
- バージョン管理システム(Gitなど)を利用する
- 変更履歴の管理表をドキュメント内に設ける
正確な変更履歴を残すことにより、プロジェクトが軌道修正した際の影響を最小限に抑えられます。
レビュー体制を整える
要求仕様書をブラッシュアップするためにも、レビュー体制を整えましょう。
作成した要求仕様書に抜け漏れや矛盾がないか、複数人の目でチェックする体制を構築することは、より良い要求仕様書を実現するうえで欠かせません。
レビュー体制を整えておけば、作成者だけでは気づけない問題点を発見できます。
なお、レビューには以下のような段階があります。
| レビューの種類 | 内容 |
|---|---|
| ピアレビュー | 作成者以外の同僚にレビューを依頼する。 |
| 専門家レビュー | 技術的な実現可能性について、開発チームにレビューを依頼する。 |
| 最終承認 | プロジェクトの責任者やキーパーソンから最終的な承認を得る。 |
最新の状態を維持する
要求仕様書は常に最新の状態を維持しなければなりません。
要求仕様書は、一度作ったら終わりではありません。
プロジェクトの「生きたドキュメント」として、仕様変更があった場合は更新し、常に最新の状態を保つことが重要です。
常に最新の状態を維持しておけば、古い情報が参照されることによる手戻りを防止できます。
なお、内容を更新する際は先述したように変更履歴を残しておきましょう。
テンプレートやフォーマットを用意する
要求仕様書を作成するなら、テンプレートやフォーマットを用意しておくと便利です。
ゼロから作成するのではなく、標準的なテンプレートを活用することで、効率的に質の高いドキュメントを作成できます。
テンプレートやフォーマットを用意しておけば、記載すべき項目が明確になるため、初めて作成する担当者でもスムーズに要求仕様書を作成できます。
また、フォーマットを統一することにより、可読性の向上も期待できます。
特にIPA(情報処理推進機構)などが公開しているテンプレートは、網羅性が高く参考になるので、ぜひチェックしてみてください。
まとめ:要求仕様書の書き方を身に付けてプロジェクトを円滑に進めよう

本記事では、要求仕様書の基本的な概要から、具体的な記載項目・作成手順・品質を高めるためのポイントまでを解説しました。
要求仕様書は、システム開発を円滑に進めるうえで欠かせないものです。
正確で分かりやすい要求仕様書があれば、プロジェクトをスムーズに進行できます。
なお、要求仕様書の作成で困った場合は、専門家の知見を活用することも有効な選択肢です。
私たちWakka Inc.は、ITコンサルティングとオフショア開発を強みとし、お客様のビジネス課題を深く理解したうえで、最適なシステム開発を手厚くサポートします。
ご興味をお持ちいただけましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、