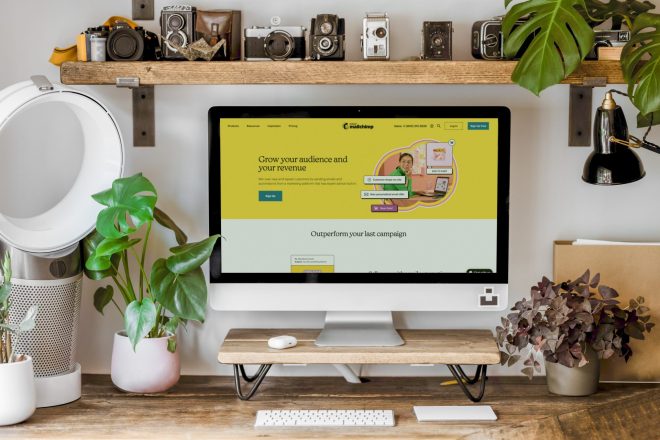ECと実店舗の連携を成功事例とともに解説。気になる割合や連携の秘訣とは?


こんにちは。
Wakka Inc.メディア編集部です。
近年はインターネットで買い物をする人向けに、ECサイトとリアル店舗を連携させてより顧客満足度や売上の向上を図る企業が増えています。
本記事では、リアル店舗とECの掛け合わせで事業をより促進させるコツをご紹介します。
リアル店舗とECの良いところをそれぞれ取り入れて、事業のスケールアップにお役立てください。
WaGAZINE読者さま限定!
料金目安もわかる
新規ECサイト構築や
リアル店舗とECサイトを連携させる取り組みとは

近年、オンラインとリアル店舗のどちらでも買い物をする消費者が増えています。
株式会社博報堂の調査では、ECとリアル店舗の両方で月1回以上買い物をし、さらに1年以内に同じカテゴリの商品を両方で購入した人を「ハイブリッド消費者」と定義しており、20~69歳のうち52.3%にのぼります。
さらに、ハイブリッド消費者による購入金額は、全体のECでの日用品購入金額のうちの81.8%を占めており、EC市場の中核的な存在となっています。
一方で、ハイブリッド消費者の半数は、ECとリアル店舗をまたぐ購入時に不満を感じていることも明らかになりました。
- 欠品時の入荷情報が分からない
- 店舗とECでポイントが連携されていない
- ECと店舗で価格に違いがある
以上のような不満は40代や60代の女性に多く見られ、ECとリアル店舗の連携不足が依然として課題であることが浮き彫りになりました。
調査では、多くの生活者がすでにECと実店舗の垣根を意識せずに買い物をしているにもかかわらず、企業側の提供価値が追いついていない現状が明らかになっています。
リアル店舗とECサイトを連携させるためには、主に以下の4つの取り組みを行うと効果的です。
- 会員情報を連携する
- 在庫管理を一元化する
- オフラインとオンラインのサービスを連携させる
- 顧客の購買データを活用する
リアル店舗とECの顧客データを連携し、取り置きや店舗受け取りなどを可能にすると顧客満足度が高くなります。
また、買いたいときにいつでも購入できるECを取り入れると、機会損失も防げます。
※出典:博報堂 HAKUHODO Inc.(https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/119136/)
リアル店舗とECサイトの連携が有効とされる理由

なぜ実店舗とECサイトの連携が有効かは、お互いのメリットを活かすことで購買行動が効率化され、販売促進が可能になるからです。
例えば、顧客はECサイトで欲しい商品を探し、在庫がある店舗へ行き、実物を見てすぐに購入の判断ができます。顧客の買い物体験は、高い満足度につながります。
また、実店舗で買い物をしていた人のEC利用率が上がると、蓄積できる顧客データの数が増え、より詳細な顧客データ分析が可能です。
顧客は利便性が上がり、店舗側はマーケティングや経営施策の幅が広がるため、リアル店舗とECの連携は有効と言えます。
リアル店舗とECサイトを連携させることで可能なサービス

リアル店舗とECサイトを連携させると、顧客は以下のサービスを利用できます。
- 会員情報の管理
- 実店舗とECのポイントの連携
- EC購入品の実店舗受け取り
- ECでの実店舗在庫把握
- 実店舗在庫の取り置きや取り寄せ
- 実店舗にない商品の購入
- ECサイト購入品の実店舗返品
顧客は、自らの登録情報や保有ポイントをECサイトから簡単に確認でき、変更も容易です。
加えて、欲しい商品の情報をすぐに調べられます。
また、購入や受け取り、返品などの方法を自分で選ぶ自由を得られるでしょう。
上記のようなサービスを展開すれば、企業側はリアル店舗とECサイト間の顧客情報を統一できます。
また、シンプルに顧客との接点が増加する面でも有益です。
顧客の機会損失を防ぎ、満足度を高めるためにも、リアル店舗とECサイトを連携させる取り組みは欠かせません。
リアル店舗とECの連携を成功させるポイント9点

リアル店舗とECの連携を成功させるポイントは以下の通りです。
【運営施策】
- 実店舗とECのシナジーを重視する
- 実店舗では取り扱わない商品をECサイトで限定販売する
- リアル店舗のお客様をECサイトのサブスクリプションへ誘導する
- お問い合わせや返品対応をスムーズにする
- SNSアカウントを運用する
- ライブコマースを活用する
【システム施策】
- 顧客情報とポイント連携を最初に行う
- ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取れるようにする
- キャンペーンやクーポンを発行しリアル店舗へ誘導する
上記のように、運営施策とシステム施策に分けてご紹介します。
具体的なポイントを紹介しますので、ひとつひとつ取り組んでいきましょう。
まずは、運営施策について解説します。
実店舗とECのシナジーを重視する
リアル店舗とECサイトのシナジー、すなわち相乗効果を重視する視点を持ちましょう。
ECサイトは単なる販売ツールではなく、商品及び実店舗を知ってもらうきっかけでもあります。
相乗効果によって何を生み出し、どのような効果を期待するのか、両者のブランディング及び戦略に一貫性を持たせて効率良く運用しましょう。
実店舗では取り扱わない商品をECサイトで限定販売する
ECサイトで限定販売を行うと、実店舗の顧客がオンライン販売を利用するきっかけになり得ます。
店舗利用が多い顧客をECサイトに誘導するのがむずかしい、と感じるケースは少なくありません。
限定販売のような特別な企画をして、まずは関心を持ってもらうことが大切です。
ECサイトを実際に使ってもらうためには、店舗でのセールストークで誘導しましょう。
スタッフとの接点にもなり、より顧客にとって満足度の高い店へと発展します。
リアル店舗のお客様をECサイトのサブスクリプションへ誘導する
顧客が定期的に購入する必要がある商品を取り扱っている場合、ECにてサブスクリプション契約(サブスク)を促しましょう。
特に、下記のように定期的に摂取や使用をする商品は、サブスクとの相性が良く効果的です。
- サプリメント
- プロテイン
- シャンプー
定期的に実店舗で購入していた顧客がECでサブスク契約すると、わざわざ店に行かなくても商品が家に届くため顧客の利便性が向上します。
また、企業にとってサブスク契約数を増やすことは、ストック収益を確保する面でも有用です。
お問い合わせや返品対応をスムーズにする
ECで買った商品の返品や交換対応の方法について、顧客にとって分かりやすい情報を発信しましょう。
例えば、返品方法を記載した紙を同封するなどの工夫があります。
さらに顧客満足度を上げるためには、代わりに購入する商品を選びやすいサイズ表なども一緒に送付すると効果的です。
また、返品をリアル店舗で受けられるようにすると、送料や手間を削減できるので顧客に対して親切です。
SNSアカウントを運用する
実店舗でのSNSアカウントを運用し、ECサイトがより軌道に乗るようにマーケティング施策を行いましょう。
例えば、商品の写真や使い心地などをSNSで発信すると、顧客の購買意欲を効果的に高められます。
ライブ機能を使用できるSNSであれば、生配信の形で商品紹介をするとリアリティや親しみやすさを演出できます。リアクションやコメント機能を使えば、顧客とのコミュニケーションも図ることも可能です。
ライブの詳細は“ライブコマースを活用する”の部分にて解説します。
ECサイトを使うのであれば、SNSは必須といっても過言ではありません。
ライブコマースを活用する
ライブコマースとは、ライブ配信にてユーザーの購買を促す新しいオンラインショッピングの形です。
スタッフがライブ配信をすると、リスナーは実際に実店舗でスタッフの説明を聞いているような気持ちになり、購買意欲が上がります。
また、自宅にいながら、来店しているようなイメージで配信を見られます。
商品に対する不明点はコメントで解消できるため、ECサイトで買うのを躊躇っていた商品も納得した後に購入が可能です。
ECサイトと並行してライブコマースを活用し、スタッフの技術向上と顧客体験の満足度向上を目指しましょう。
続いて、システム施策の具体例を解説します。
顧客情報とポイント連携を最初に行う
リアル店舗に来る顧客がECサイトを活用しやすいように、ポイント連携を行いましょう。
例えば、お買い物をした記録やポイント特典があると、顧客はより満足できる買い物体験が可能です。
ECサイトと実店舗の相乗効果を狙って、よりリピートしやすい工夫をしましょう。
ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取れるようにする
顧客が自分の好きなときにECサイトで買い物をして、実店舗で受け取れるようにすると顧客満足度が高まります。
特に、送料や配送時間を気にする顧客に対して効果的です。
実店舗側のメリットは、受け取る際に店舗への来客を促し、アップセルやクロスセルによる客単価アップが可能な点です。
ECサイトからの顧客とリアル店舗でも接点を持てるように、実店舗受け取りの仕組みを作りましょう。
実店舗に来るメリットを掛け合わせることでECとリアル店舗の良いとこどりが可能です。
キャンペーンやクーポンを発行しリアル店舗へ誘導する
ECサイトで実店舗向けのキャンペーンやクーポンを打ち出すと、リアル店舗へ足を運ぶきっかけを作れます。
例えば、実店舗限定で開催するキャンペーンや、店頭レジで使えるクーポンなどが一例です。
お得感のある特典を使ってECサイトからリアル店舗に送客すれば、単純な来店数が増加し、アップセルが期待できます。
期間限定キャンペーンなどを定期的に行い、来店を促しましょう。
WaGAZINE読者さま限定!
料金目安もわかる
新規ECサイト構築や
リアル店舗とECサイトそれぞれのメリット

リアル店舗とECサイトのそれぞれのメリットを解説します。
本章で挙げるメリットはリアル店舗とECサイトの連携によって、より高い効果を発揮します。
リアル店舗のメリット
リアル店舗の顧客メリットは以下の2点です。
- 欲しい商品をその場で購入できる
- 商品を実際に見たり触ったりできる
その場で実物を見て、すぐに持ち帰れるのが大きなメリットです。
一方、実店舗側のメリットは以下の通りです。
- 顧客と直接コミュニケーションが取れる
- 顧客体験を通じてブランドイメージを作りやすい
リアルなコミュニケーションによる販売や、ブランドイメージの構築ができる点が実店舗にとっては重要です。
ECのメリット
顧客から見たECのメリットは以下の2点です。
- いつでもどこでも購入可能
- 店舗に在庫がなくても購入や取り寄せがすぐにできる
特に、実店舗に行きたいけれど忙しくていけない顧客や、実店舗へのアクセスが悪い顧客は便利だと感じます。
企業側のメリットは下記の通りです。
- 解析ツールなどWebならではの機能が使える
- 少ない初期投資で始められる
顧客のプロフィール入力や購入履歴により、企業はマーケティングデータの収集が可能です。
また、販路拡大のために実店舗やスタッフを増やすと多額の費用が必要になるのに対し、ECサイトであれば初期費用を抑えられます。
リアル店舗とECサイトの連携における注意点

リアル店舗とECサイトの連携を行う際に、気をつけなければならないポイントを解説します。
- スモールスタートで慎重に進める
- リアル店舗スタッフのモチベーション低下に気をつける
- ECサイトの普及に尽力する
以下で詳しく解説していきます。
スモールスタートで慎重に始める
リアル店舗とECサイトの連携を始める際は、スモールスタートを心がけましょう。
連携に伴うシステム開発は、仕組みが増えるにつれて費用が大きく膨らみます。
まずはスモールスタートで様子を見てから、以降の投資を検討していく方法がおすすめです。
リアル店舗スタッフのモチベーション低下に気をつける
ECサイトとの連携がうまくいくと、顧客がリアル店舗からECに流れたと感じてモチベーションの下がるスタッフが現れる可能性があります。
また、実店舗で顧客に商品説明をしても、後日ECで購入した場合、自分の功績なのかが分かりません。
個人の売上や評価が不明瞭だと、モチベーションが下がる原因になりかねません。
実店舗スタッフのやりがいや意欲を維持できるような、現場の施策や評価制度を整える必要があります。
ECサイトの普及に尽力する
ECサイトとリアル店舗を連携させたら、普及活動が必要です。
実店舗に来る顧客にECサイトを紹介したり、口コミキャンペーンを実施したりして、まずはサイトの認知度を高めましょう。
割引クーポンやポイント付与があるなど、顧客のメリットが明確だとECサイトの利用を訴求しやすくなります。
リアル店舗とECを連携させた事例5選

以下では、リアル店舗とECサイトを連携させた企業の実例を紹介します。
- ユニクロ
- 無印良品
- ビックカメラ
- スターバックスコーヒー
- ツルハホールディングス
本章では、オムニチャネル化やO2O戦略など、リアル店舗とECの連携を活性化させるための戦略について解説します。
ユニクロ|ECを通じて顧客と直接つながる施策
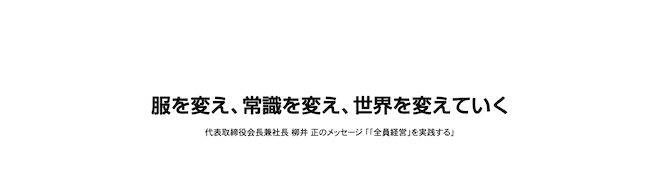
出典:ユニクロ
アパレル企業の株式会社ユニクロは、Eコマース(ECサイト)と店舗の連携により売上を向上させました。
2025年4月の発表では、Eコマースでの売上が前年比10.9%増となっており、ネットで購入し店舗で受け取れる点が好評です。
具体的には、以下のような連携施策を行っています。
- アプリの会員証をお会計時にレジで提示すると次回実店舗の買い物で使えるクーポンが発行される
- 店頭商品のバーコードスキャンをすればECと実店舗双方の在庫確認やレビューチェックが可能
- EC購入時に送料無料ラインに届かなくても、「ユニクロ店舗受取り」で送料不要にできる
- ECから実店舗への送客により「ついで買い」が期待できる
以上のようにユニクロのオムニチャネル戦略は、ECと実店舗を併用できるようにアプリ開発を進めています。
参照:2025年8月期 上期業績および通期 業績予想│株式会社ファーストリテイリング
無印良品|会員向けサービスを刷新しEC連携を強化
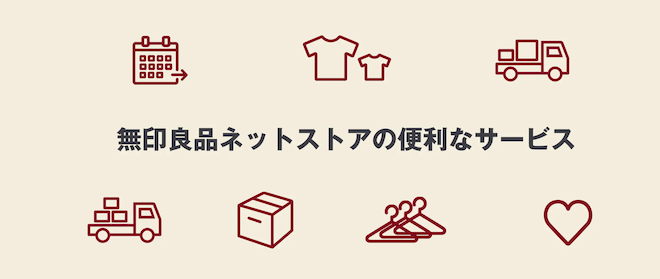
出典:無印良品
無印良品を展開する株式会社良品計画は、2025年9月より会員プログラムを従来の「MUJI passport」から「MUJI GOOD PROGRAM」へアップデートしました。
よりEC連携を強化するために、以下のような制度に変更しました。
| 項目 | 従来のMUJI passport | 今後のMUJI GOOD PROGRAM |
|---|---|---|
| ポイントの貯め方・使い方 | ・買い物をすると1円ごとに1つMUJIマイルが貯まる ・既定の数値を達成すれば会員ライクが上がりお買物券が発行される | ・買い物100円につき1ポイントが貯まる ・翌日から1ポイント1円として使える |
| ポイント期限 | 毎年2月にマイルリセット | ポイント有効期限は5カ月間 |
| 買い物以外のポイント付与 | 毎年1回誕生日特典(500P付与) | ・商品のお気に入り登録:1ポイント / 月5回まで ・配送リストの利用:10ポイント / 1日1回まで ・商品のレビュー:5ポイント / レビュー掲載商品1点につき、一会計1回まで ・IDEA PARKへの投稿:5ポイント / リクエスト投稿の公開1回につき ・お店のチェックイン:1ポイント / 1日1回まで、月10回まで ・アプリで記事を読む:1ポイント / 1日1ポイント、月5日まで ・MUJI Cardの入会:1000ポイント / 以降毎年5月・12月に各500ポイント ・MUJI HOTEL GINZAの利用:宿泊利用費100円 ごとに1ポイント ・ReMUJI 製品回収への参加:10ポイント / 1日1回まで ・お店へのマイバッグ持参/レジ袋辞退:1ポイント |
以上のように、買い物以外でもポイントが付与される条件が大幅に増えました。
また、レビュー投稿やお気に入り登録でもポイントが付与されたり、お店へのチェックインでもポイントが付与されるなど、EC連携を強化していることが分かります。
ビックカメラ|顧客メリットに注目したEC連携

引用:ビックカメラ
品揃えにこだわったECサイト運営をしているのが、株式会社ビックカメラです。
2023年中に1万SKU(最小単位)を目指しており、今後さらに拡充していく見込みです。
たとえ1点しか在庫がない商品でも取り扱うことをモットーにし、実店舗ではECサイトを使い慣れていない方向けに、コンシェルジュがサポートするサービスも提供しています。
ネットに慣れている方はECサイト、ネット上でのやりとりが不安な方はリアル店舗で充実したサポートと、2軸の経営戦略を展開中です。
また、ビックカメラは同業他社と比べて以下の点で違いを出しています。
| 項目 | 同業他社 | ビックカメラ |
|---|---|---|
| ポイントの有効期限 | 購入日から1年間の有効期限 | 最終利用日から2年間の有効期限 |
| ポイントの利用方法 | ECや実店舗、または運営しているショップで利用可能 | 実店舗とECだけでなく、同グループのコジマやソフマップでもポイント交換レートの変動なしでポイントを利用可能 |
さらに、オムニチャネル化のために以下のような施策も行っています。
- 電子棚札:商品のプライスカードと直接本部の基幹システムをネットワークでつなげ、変更時に即座にプライスカードの内容に反映される仕組み
- ネット取り置きサービス:ECで探した商品を、実店舗で取り置き・購入できるサービス(ついで買いを見込める)
以上のようにビックカメラでは、ユーザーのメリットも考慮しながらEC連携を進めています。
スターバックスコーヒー|モバイルオーダー & ロイヤルティプログラムによるO2O戦略

スターバックスは、デジタルとリアル店舗を連携させたO2O(Online to Offline:オンラインから実店舗への来店や購買を促すマーケティング施策)戦略の事例として国内外で評価されています。
中心となるのは「Mobile Order & Pay」による事前注文・決済サービスです。
顧客はアプリで商品を選び、カスタマイズしたうえで支払いまで完了できるため、店舗ではレジに並ぶことなく商品を受け取れます。
日本では2019年に東京の一部店舗から導入され、全国に展開されました。
結果として混雑によるストレスが解消されたほか、店舗側もレジ業務の負荷が減り、体験価値と運営効率の両立を実現しています。
さらに、注文・決済データはそのままロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards」と連動しています。
利用者はスターバックスカードをアプリに登録しておくことで、来店購入のたびにポイント(Stars)が貯まり、一定のランクに達すると無料ドリンクや限定特典が受けられる仕組みです。
「Starbucks Rewards」により、単なる便利な注文アプリではなく、使えば使うほどお得になる来店エコシステムとして機能している点が特徴的です。
結果として、アプリ・店舗をまたぐ一貫した顧客接点を構築し、オンラインの利便性からオフラインの来店購買へと自然につなげるO2Oモデルを確立しています。
ツルハホールディングス|来店促進と業務効率化を両立させたO2O戦略

引用:ツルハグループアプリ
ツルハホールディングスは、全国で店舗を展開するドラッグストアの中でも早くからデジタル活用を進め、O2O戦略によって来店促進と業務効率化の両立を図ってきました。
従来は紙のポイントカード中心の運用でしたが、顧客接点が分散し購買傾向を正確に把握できない課題がありました。
そこで自社アプリとマーケティングオートメーションを連携させ、すべての購買情報をID-POSとして統合する仕組みを構築します。
結果として、顧客一人ひとりの購買履歴や来店頻度に応じて、アプリ上でクーポンやキャンペーン情報を最適なタイミングで配信できるようになり、紙チラシや店頭貼り出しでは届かなかった層にもアプローチできるようになりました。
アプリのダウンロード数は1,000万件を超え、アプリ経由の購買比率も全体売上の3割以上に達するなど、オンライン接点の拡大がそのまま実店舗の売上向上に結びつく構造が確立されました。
ツルハのO2O戦略の特徴は、単にアプリでクーポンを配るのではなく、購買データを基盤にした個人向けのアプローチと、店舗オペレーションの効率化が一体になっている点にあります。
ECと実店舗連携に関するよくある質問

本章では、ECと実店舗連携に関するよくある質問をまとめました。
ECサイトとリアル店舗の違いは何ですか?
ECとリアル店舗の違いは、主に以下の点です。
【ECサイト】
接客:非対面(チャットボットやお問い合わせ)
利便性:インターネット環境があればいつでもどこでも購入可能
マーケティング:登録データによる多角的なアプローチが可能
コスト:規模によるものの比較的コストが低い
【リアル店舗】
接客:対面
利便性:商品をすぐに入手できる
マーケティング:会員募集に手間がかかる
コスト:家賃や人件費などコストがかかる
ネットショップと実店舗のどちらが良いですか?
「どちらか一方」ではなく、目的で選ぶことをおすすめします。
例えば、低コストで売上を拡大したい場合にはネットショップが有利と言えます。
接客・体験価値・ブランド力を重視するならば、実店舗の方がおすすめです。
両方のメリットを活かしたいならECと実店舗の連携による展開を行うと良いです。
近年は、以下のような施策を行う企業が増えています。
・店舗受け取り
・EC限定商品
・店舗とWebのポイント共通
・SNS連動販売
ECと実店舗を併用している企業は?
有名企業だと、以下の企業でECと実店舗の連携を積極的に行っています。
【アパレル】ユニクロ、ABCマート
【家電量販店】ヨドバシカメラ、ビックカメラ
【生活雑貨】ニトリ、無印良品
【食品】イトーヨーカドー、成城石井
【ドラッグストア】マツモトキヨシ、ウェルシア
今後も多くの企業でECと実店舗を連携させた企業が増えると見られます。
ECとリアル店舗の連携を成功させよう

ECサイトとリアル店舗の連携は、お互いの送客や顧客満足度の向上に効果的です。
特に若者世代は、ネットで商品購入に慣れています。
ECならではのいつでもどこでも購入できる点と、リアル店舗で実際の商品を手に取ってもらう特徴を掛け合わせましょう。
リアル店舗とECサイトの連携について、より詳しい情報を知りたい方はWakka Inc.へご依頼ください。
WaGAZINE読者さま限定!
料金目安もわかる
新規ECサイト構築や