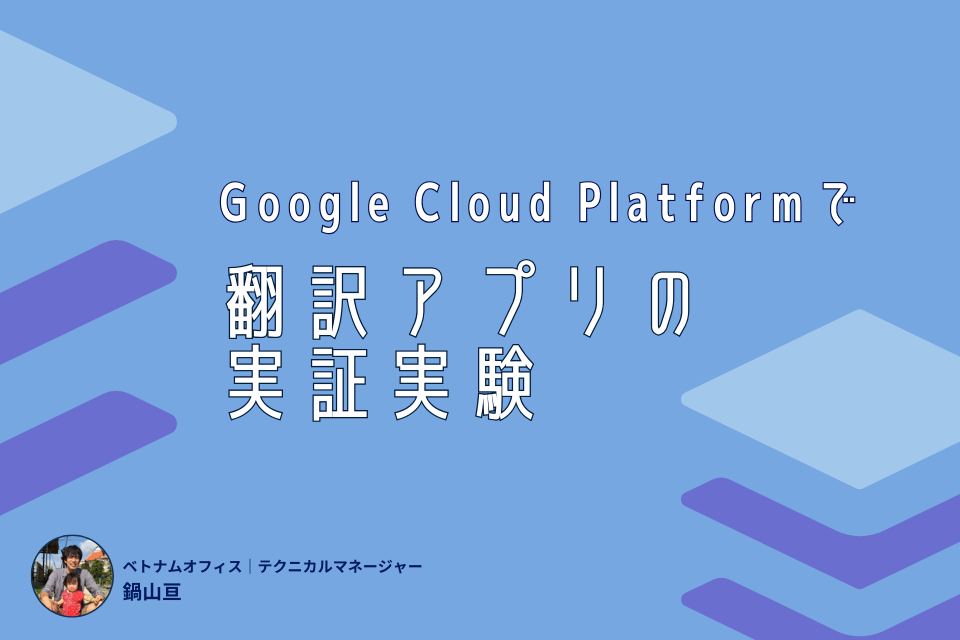販売管理と生産管理の違いとは?基礎やシステム導入のメリットを解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
企業の成長に不可欠な販売管理と生産管理。
販売管理と生産管理は密接に関連していますが、それぞれの役割や目的は異なります。
本記事では、販売管理と生産管理の基本的な違い・製造業における重要性・業務を効率化するシステム導入のメリットなどを解説します。
販売管理システム導入の成功事例やよくある質問も、あわせてご覧ください。
WaGAZINE読者さま限定!
DX進め方ガイドブック
社内での
販売管理と生産管理の違いとは

販売管理と生産管理は、どちらも企業の根幹を支える重要な業務ですが、管理対象と目的に違いがあります。
販売管理が「もの(商品)とお金」の流れを扱うのに対し、生産管理は「もの(製品)が作られる過程」を扱います。
まずは、それぞれの基本的な定義と業務内容を理解しましょう。
販売管理の業務内容と目的
販売管理とは、商品やサービスの受注から納品、そして代金回収までの一連の流れを管理する活動です。
販売管理のおもな目的は、管理業務の効率化・利益向上・顧客満足度向上などです。
販売管理で扱うものには、衣類・食品などの有形商材のほか、人材派遣サービス・コンサルティングなどの無形商材も含まれます。
しかし、有形商材・無形商材のどちらでも、基本的な販売管理の業務フローに大きな差はありません。
販売管理の業務は、一般的に以下のプロセスで進められます。
さまざまな情報が一元的に管理されることで、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
| プロセス | おもな業務内容 |
|---|---|
| 見積管理 | 顧客からの引き合いに対し、見積書を作成・発行・提出・保管・管理し、場合によっては、分析も含まれます。 また、定期継続案件などで条件が変わらない場合は、2回目以降の見積書作成は省略されるケースもあります。 |
| 受注管理 | 顧客からの注文を受け、受注伝票を作成し、サービスの提供内容を正確に記録します。 請求・入金までの業務を含む場合があります。 契約時に取り決めた内容に問題がないかを確認することが大切です。 |
| 出荷管理 | 受注内容に基づき、倉庫から商品を梱包・出荷し、納品書を作成します。 顧客に納品物を適切に渡すための正確性や効率性などが求められます。 |
| 請求管理 | 商品の納品後、顧客に対して請求書を発行し、送付します。 取引が発生してから代金を回収するまでを正確に管理し、誤請求や請求漏れを防止します。 取引内容や取引条件などは顧客ごとに異なるため、請求書の発行方法を事前に確認しておくことが大切です。 |
| 入金管理 | 顧客からの入金がどの取引に対する入金なのかを確認する消込作業を行います。 担当者は、入金額と売上高が一致しているかを確認し、整合していれば入金伝票を作成して仕訳を実施します。 入金の管理・記録・追跡・報告などが含まれ、売掛金の管理や資金繰りの安定に欠かせない業務です。 |
販売管理の手法は、おもにExcelで管理する方法と販売管理システムで管理する方法の2つです。
しかし、近年では販売管理システムを活用するケースが増えています。
なぜなら、販売管理システムは属人化のリスクが低く、効率的な管理を実現しているためです。
生産管理の業務内容と目的
生産管理とは、製品を「いつまでに」「どれだけ」「どのように」作るかを計画し、実行する活動です。
生産管理の目的は、QCDと呼ばれる3つの要素(品質・コスト・納期)を最適化することです。
QCDのうち、十分な価値のある商品を製造するために、Quality(品質)を優先するのが一般的です。
Cost(コスト)やDelivery(納期)は、品質を確保した上で、顧客の要望や状況を考慮して検討します。
適切な生産管理は、企業の競争力を直接的に左右する重要な要素です。
そのため、顧客満足度や利益追求のほか、自社の製造現場にかかる負荷や現場環境なども考慮して業務に取り組む必要があります。
生産管理は、販売計画や需要予測をもとに行われ、下記のように多岐にわたる業務を含みます。
| プロセス | おもな業務内容 |
|---|---|
| 生産計画 | 需要予測や受注情報に基づき、何を・いつまでに・どれほど生産するかを計画します。 原材料・生産能力・在庫・生産工程なども考慮して計画を策定します。 特に、お盆や年末年始などの休暇が集中する期間は生産能力が低下する可能性があるため、季節的な要素も踏まえて計画するのが大切です。 |
| 購買・調達 | 生産計画に必要な原材料や部品を発注し、仕入れます。 購買では原材料・部品・サービスなどを外部から調達し、購買では物資を外部から購入します。 |
| 工程管理 | 生産ラインの各工程の進捗状況を把握し、計画通りに進むよう管理します。 進捗状況に遅れが生じた際に、遅延の原因を特定して対策を講じる業務も含まれます。 同時に、遅れが生じたことを関係者間で共有したり、再調整のための再計画とリカバリー策の実施したりといった業務も必要です。 |
| 品質管理 | 製品が定められた品質基準を満たしているか検査し、品質を維持・向上させます。 具体的には、製造工程の管理・不良品の防止・品質改善などを実施する業務で、製品の設計から出荷までの各工程に関わる取り組みを実施します。 |
| 原価管理 | 製品にかかるコストを計算し、利益を確保できるよう管理・改善します。 具体的には、材料費や人件費などの計算や標準原価との差異分析などです。 コストが増大した際は、コスト削減のための改善策を講じる場合もあります。 |
生産管理プロセスにおいて、他部門との密に連携できる体制構築が重要です。
なぜなら、購買・調達や生産などは実際に対応する部門が存在するのが一般的だからです。
生産効率や顧客満足度を向上させるためにも、部門間の連携強化が求められます。
製造業における販売管理の重要性

製造業において、優れた製品を作る技術力はもちろん重要です。
しかし、作った製品を適切に販売し、利益を確保するための販売管理も大切です。
本章では、販売管理が製造業にもたらす3つの重要な価値について解説します。
顧客満足度向上
適切な販売管理は、顧客からの信頼獲得に直結します。
正確な納期の回答や、問い合わせに対する迅速な対応は、顧客満足度の大きな向上につながるためです。
10日後に納品する、と伝えた相手に、納期を何日もずらしては信頼獲得は難しいでしょう。
さらに、上記のような状態を繰り返していれば、信頼関係は崩れるばかりです。
顧客満足度は、リピート購入や良好な取引関係による、安定した経営基盤を築く上で欠かせません。
したがって顧客満足度の向上には、適切な販売管理が不可欠です。
売上最大化
顧客のニーズが激しく変化する環境下において、販売管理によって蓄積されたデータは、経営の羅針盤です。
しかし、経営の羅針盤となるべきデータが活用されていなければ、売上の向上や最大化は容易くないでしょう。
売上の向上に貢献する要因のひとつが需要予測です。
需要予測は、季節・顧客の属性・過去の購入歴などをもとに予測します。
しかし、上記のような情報も、「何が・いつ・どこで・誰に売れたか」が明確でなければ、予測の精度を高めることは困難です。
そのため、販売管理を通じて得た情報を活用します。
どの製品が・どの時期に・どの顧客に売れているかを分析することで、精度の高い需要予測を実現できるはずです。
高精度の需要予測により、欠品による販売機会の損失や過剰在庫のリスクを低減し、売上の最大化を図ることができます。
経営判断の迅速化
販売管理により蓄積されたデータは、経営判断の迅速化にもつながります。
なぜなら、収集されたデータ分析の結果から、リアルタイムで正確な販売状況や利益状況を把握できるからです。
リアルタイムで正確な販売状況や利益状況を把握できることは、経営における大きな強みです。
また、市場の急激な変化や突発的に発生したトラブルに対して、データに基づいた迅速な意思決定を下せます。
正確なデータの活用は、感覚的な経営からの脱却や、戦略的な事業展開を実現するための土台となり得ます。
製造業における販売管理の課題とは

多くの製造業では、販売管理において共通の課題を抱えています。
販売管理における課題を放置すると、業務効率の低下や機会損失につながる可能性があります。
自社の状況と照らし合わせながら、課題を認識することが改善の第一歩です。
属人化による業務効率の低下
「この業務はAさんしか分からない」という状況は、多くの企業で見られる課題です。
担当者が不在の際に業務が止まってしまったり、異動や退職によってノウハウが失われたりするリスクがあります。
近年では、独自に構築したシステムのブラックボックス化も課題です。
システムの構築者が高齢化し、定年退職することでシステムの更新が止まり、効率的な運営ができなくなるケースもあります。
業務プロセスやシステムの属人化は、大きな課題となります。
データ分散による情報共有の遅延
受注・在庫・出荷・請求といった情報が、部署や担当者ごとに異なるファイルで管理されているケースは少なくありません。
データが分散している状態では、最新の情報を全社で共有することが困難です。
他部署への問い合わせや確認作業に時間がかかり、対応の遅れや、聞き取りミス・記載ミスなどの原因になることも。
データ分散は、ヒューマンエラーの原因にもなるため、早期の解決を目指すべき課題です。
需要予測の精度不足による機会損失
過去の販売実績データを整理せず、担当者の勘や経験に頼っている場合、需要予測の精度低下はまぬがれません。
予測が外れると、売れ筋商品の欠品を招いて顧客を逃したり、逆に過剰な在庫を抱えてキャッシュフローを圧迫したりする事態につながります。
需要予測の精度向上には、過去のデータ収集・整理・分析が欠かせません。
重大な機会損失を避けるために、データの収集・整理から始めましょう。
販売管理システム導入の3つのメリット

販売管理システムの導入は、業務効率化・機会損失防止など、さまざまな課題解決に期待できます。
本章では、販売管理システムを導入する3つのメリットを解説します。
販売管理システム導入を検討する際にお役立てください。
手作業の削減と自動化
販売管理システムは、これまで手作業で行っていた見積書や請求書の作成、伝票の入力といった業務を自動化できます。
手作業の削減と自動化により、担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。
また、手作業による入力ミスや計算ミスといったヒューマンエラーの削減にもつながり、大幅な業務効率化を実現可能です。
リアルタイムな情報把握
販売管理システムには、受注・出荷・在庫などの情報を一元的に管理するデータベースとしての機能もあります。
関係者は、場所や時間を問わず、最新のデータにアクセスできるようになります。
リアルタイムな情報把握により、部署間のスムーズな情報連携が実現し、業務のスピードが格段に向上します。
迅速な対応と正確な情報提供
顧客から在庫の問い合わせがあった際、販売管理システムのデータを確認することで即座に正確な数量を回答できます。
迅速かつ正確な対応は、顧客満足度の向上に大きく貢献します。
また、過去の取引履歴もすぐに参照できるため、顧客一人ひとりに合わせた丁寧な対応が可能です。
属性・季節など、パーソナライズされた対応に努めることで、先回りした対応の実現にもつながります。
WaGAZINE読者さま限定!
DX進め方ガイドブック
社内での
販売管理システムのおもな機能

販売管理システムには、煩雑な業務を効率化する多彩な機能が搭載されています。
自社の課題を解決するために、どのような機能が必要かを検討する際の参考にしましょう。
見積管理
見積管理は、テンプレートを使って見積もりの入力作成を実施することで、自動化が進んで業務を効率化できる機能です。
導入する販売管理システムによっては、作成した見積書をPDFのような任意の形式で出力できます。
自社のデータベースに、作成した見積書を保存できて検索できるシステムもあり、さまざまな方面から業務効率化を促進できます。
受注管理
受注管理は、受注したデータを記録・管理するための機能です。
見積もりのデータから注文情報を自動入力する・発注とともにデータを登録・管理する、などの機能も備えています。
作成した受注データは必要に応じて検索でき、顧客管理や効果的なマーケティング施策の実施にも活用できます。
売上管理
売上管理は、売上・売掛情報の記録と保管を担う機能です。
登録している受注データからの自動作成・管理も可能で、作成した売上データはさまざまな形式での出力が可能。
作成した売上データは、分析や資料としても活用できます。
請求管理
請求管理は、請求書発行・債権検索などを実行できる機能です。
請求状況は取引先ごとに管理でき、代金未回収リスクの軽減に役立ちます。
入金終了後は、自動的に処理されるため、請求業務の業務効率化に貢献できます。
発注管理
発注管理は、発注情報の内容確認・発注データ記録などが可能な機能です。
注文書の発行も含まれるのが一般的です。
発注情報のデータは、需要予測に活用できます。
仕入管理
仕入管理は、見積作成・契約締結が済み、確定した注文情報に基づいた仕入を実行する機能です。
仕入情報は在庫として計上され、スケジュールや数量などの情報とも連携しています。
仕入管理を活用することで、顧客に正確な納期を伝えることができます。
入荷管理
入荷管理は、仕入データや入荷数の可視化を担う機能です。
入荷数が確定したものは在庫として計上されます。
仕入データや入荷数が可視化できるため、在庫管理の適正化を実現でき、過剰在庫の防止に役立ちます。
出荷管理
出荷管理は、出荷指示の入力と確定を実行する機能です。
在庫データとの整合性もチェックでき、在庫不足による機会損失を予防できます。
出荷管理は、過剰在庫の防止にもつながります。
予定より少なく出荷されたものを、いち早く察知でき、対処に取り掛かれるからです。
過剰在庫は、保管コスト増大・商品価値の低下・キャッシュフローの悪化などの原因になる要素のため、出荷管理でも適正に管理することで状態の悪化を防止できます。
棚卸管理
棚卸管理は、棚卸の管理・登録を実行する機能です。
実際の在庫とデータ上の在庫の整合性を確認し、棚卸状況のリアルタイムな可視化を実現します。
従来では、紙を主体として管理していた企業も多かったことでしょう。
しかし、販売管理システムの活用によって、ペーパーレスと業務効率化を同時に実現できます。
販売管理システム導入時の4つの注意点

販売管理システムは強力なツールですが、導入を成功させるにはいくつかの注意点があります。
本章では「導入したものの、うまく活用できていない」という事態を避けるための4つのポイントを解説します。
導入目的の明確化
「業務を効率化したい」といった漠然とした目的ではなく、具体的な目標を設定することが重要です。
目的が明確であれば、必要な機能もおのずと絞り込まれ、システム選定の精度が高まります。
具体的な目標例は下記の通りです。
- 見積作成にかかる時間を50%削減する
- 在庫の欠品率を1%未満にする
導入目的を明確化する際は、KPIを設定するのも手法のひとつ。
KPIを用いることで定量的な評価・分析を実現できるため、モチベーション低下防止にも期待できます。
販売管理システムの選定
販売管理システムはおもに下記の3種類です。
| 汎用型 | 販売管理システムの中でもスタンダードなタイプです。 多用な業界に対応しており、幅広い場面での業務効率化に有効です。 |
| 業種特化型 | 特定の業種に特化した機能をパッケージとして提供しているタイプです。 業界ごとの機能が整理されており、商習慣に対応できるものもあります。 |
| 小規模型 | 個人事業主や小規模事業者に導入されることが多いタイプです。 在庫管理機能が非搭載のシステムがある反面、低コストで導入できるのが魅力です。 |
販売管理システムは、上記にクラウド型かオンプレミス型かといった要素も加えて、それぞれの特徴を比較検討する必要があります。
無料トライアルなどを活用し、実際の操作性を試してみることも有効です。
導入・運用コスト
システムの費用は、機能や提供形態によって大きく異なります。
初期費用に加えて、月間利用料・サーバー維持費・サポート費用といったランニングコストも考慮し、長期的な視点で費用対効果を判断することが大切です。
例えば、オンプレミス型の販売管理システムを構築した場合は、サーバー維持費やサポート費用を自社で負担する必要があります。
なぜなら、サーバーやシステムの運用・保守は自社でまかない、社外に委託する必要がないためです。
しかし、オンプレミス型のコストを算出するには、IT人材にかかる人件費やサーバー稼働にかかる電気代などを考慮しなければなりません。
導入・運用コストは、自社が希望するシステムの導入形態を基本として考慮しましょう。
導入後の運用体制
高機能な販売管理システムを導入しても、使う従業員が定着しなければ意味がありません。
導入前に操作研修の計画を立てたり、各部署から推進メンバーを選出したりするなど、全社的に取り組む体制を整えることが大切です。
販売管理システムを従業員に定着させるためには、実際にシステムを使用している従業員から、状況や意見を聞き取ることも重要です。
何に不満があり・何を改善すべきかを把握することで、導入後の運用体制の安定を図れるとともに、システム定着の促進に効果を発揮します。
販売管理システム導入の成功事例

本章では、販売管理システムの導入によって課題解決に成功した企業の事例を見てみましょう。
自社の状況と照らし合わせることで、導入後のイメージがより具体化されます。
複数の販売管理システムを一元化して業務効率化
3つの販売管理システムを利用していたため管理業務が煩雑化し、情報も分散化していました。
この課題を解決するため、統合された販売管理システムを導入した事例です。
課題の具体的な内容は、システムが自動連携できなかったことによるデータの二重入力や登録分散などです。
企業が抱える業務が拡大する他方で、非効率的な業務が多くのデメリットをもたらしていました。
販売管理システムの導入後は、システムが一本化されたため、データの一元管理を実現されました。
システムそのものの管理が組織管理となり、属人化の課題も同時に解決できています。
独自化した管理手法を一元化して集計作業を効率化
業務委託先とスプレッドシートやチャットツールを使って実施していたやりとりの際に、過去のデータの煩雑化が進行し、業務の非効率さが課題の事例です。
過去データの全体像の把握も困難な状況で、データ確認のたびに多くの時間を要していました。
販売管理システムを導入したことによる効果は、データ管理の適正化・業務効率化・担当者育成労力の削減の3つです。
属人化が進んだスプレッドシートの管理がなくなり、担当者の育成とデータ確認業務が効率化されました。
さらに、データ管理が適正化されたため、ヒューマンエラーの減少にも成功しています。
データ転記を不要にして処理時間を短縮
非効率的なデータの転記入力を要する環境下で、ヒューマンエラーが多く発生しているのが課題の事例です。
転記入力作業は、入力ミス・見間違えなどが発生しやすく、遅くまで残業するケースも珍しくありませんでした。
販売管理システムの導入後は、転記入力作業が必要なくなり、業務の大幅な効率化に成功しています。
残業時間も短縮され、従業員の業務負荷も軽減されました。
紙とExcel運用をデジタル化
紙とExcelの運用が当たり前となっている中で、導入したシステムが業務にマッチせず、デジタル運用を定着できないのが課題の事例です。
販売管理システムの導入と定着を成功させた理由は、企業独自の運用ルールにマッチできるカスタマイズ性の高さのあるシステムとの出会いでした。
販売管理システム導入直後は従業員からの批判的な意見がありましたが、改善を繰り返す中でポジティブな意見が飛び交うようになりました。
もう一つの課題だった業務効率化も実現され、デジタル運用の浸透に成功しました。
カスタマイズで業務にフィットしたシステムを導入
スクラッチ開発を用いて、業務とフィットしたシステム導入に成功した事例です。
スクラッチ開発とは、既存のシステムやフレームワークを使わず、ゼロからシステムを開発する手法です。
本事例では、開発したプロトタイプをもとにブラッシュアップを繰り返し、フィット性を向上させています。
フィット性の高い販売管理システムを導入したことで、従業員への定着がスムーズで、継続的なシステムの拡張にも意欲的に捉えています。
販売管理システムのよくある質問

販売管理システムを導入する際に、ふとした疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。
本章では、販売管理システムのよくある質問を解説します。
生産管理システムや在庫管理システムとの連携は可能ですか?
販売管理システム・生産管理システム・在庫管理システムなどの連携は可能です。
API(Application Programing Interface)連携をはじめとした手法を活用し、さまざまなシステムと連携できます。
API連携とは、異なるソフトウェア・アプリケーションを接続して、データや機能を拡張させることです。
開発コストの削減・開発の高速化などのメリットがあり、多くの場面で活用されています。
ただし、API連携をはじめとしたシステム連携には、トラブル対応・セキュリティなどのリスクがあります。
信用できる提供元を探すと同時に、不安を解消しながら対応を進めましょう。
クラウド型とオンプレミス型はどちらを選ぶべきですか?
クラウド型とオンプレミス型の違いは下記の通りです。
| 型タイプ | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|
| クラウド型 | オンライン上のサーバーで提供されるサービスをインターネットを介して利用する形態 | 低コストで導入でき、保守・メンテナンスの負担が小さい。 インターネット環境があれば場所を選ばず利用可能。 セキュリティはベンダーに依存しやすく、カスタマイズが制限されがち。 |
| オンプレミス型 | 社内にサーバー・通信回線・システムを構築し、自社で運用する形態 | 情報が社内ネットワークから漏えいするリスクが低く、開発の自由度が高い。 ただし、導入コストが高くなりやすく、保守・メンテナンスの負担が大きい。 |
セキュリティやカスタマイズ性の高さを優先する場合はオンプレミス型、コストや外部での利用を視野に入れている場合はクラウド型、といったように状況に合わせて選んでください。
近年は、IT人材の確保・育成の難しさから、クラウド型システムを選択する企業が増加しています。
導入費用はどのくらいかかりますか?
導入費用は、導入形態によって、以下のように異なります。
| 導入形態 | 費用目安 |
|---|---|
| クラウド型 | 1~10万円程度(月額) |
| パッケージ型 | 100~1,000万円程度(パッケージ購入費) |
| セミオーダー型 | 100万円~ |
| スクラッチ型 | 500万円~ |
なお、上記は、あくまでも目安です。
実際には、販売管理システムに搭載する機能や導入規模などによって費用が変動する可能性があるため、注意が必要です。
無料トライアルはありますか?
販売管理システムの多くは、無料トライアルを提供しているため、積極的に活用しましょう。
販売管理システムの無料トライアルを活用する、おもなメリットは以下の通りです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 機能確認 | 販売管理システムに備わっている機能に不足がないかを確認できる。 |
| 操作感確認 | システムのUI/UXを、実際に確認でき、操作感を確認できる。 |
| 比較 | 無料で複数の販売管理システムを比較できる。 |
| 導入コスト削減 | 導入前に新規システムについての理解が深まり、導入時の育成コストの削減につながる。 |
無料トライアルは、複数の販売管理システムを比較する際に活用できるため、有無を確認してリストアップすると便利です。
なお、無料トライアルは試用できる期間・機能などを確認して、十分な確認作業ができるかをチェックすると安心です。
ERPとシステム連携はどちらにすべきですか?
ERPとシステム連携のどちらが適しているかは、企業の状況によって異なります。
例えば、ERPの導入により、全社的な情報の一元管理やDX推進といったメリットが得られますが、その一方でコストは増大しやすい傾向にあります。
一方で、システム連携を選んだ場合は、コスト軽減と情報の一元管理を両立できる場合もあります。
ERPとシステム連携のどちらを選ぶかは、企業を取り巻く環境や既存システムの寿命など、複数の観点から検討を進めることが大切です。
まとめ:販売管理と生産管理の違いを理解しよう

本記事では、販売管理と生産管理の違いや、販売管理システムの有用性を解説しました。
販売管理や生産管理は、生産性を向上するために欠かせない要素であり、違いを理解することでビジネスに対する理解を深められます。
また、販売管理はシステム導入による効率化で、多くのメリットが生じます。
この機会に、販売管理システムの導入を検討し、ビジネスの成長につなげてください。
WaGAZINE読者さま限定!
DX進め方ガイドブック
社内での