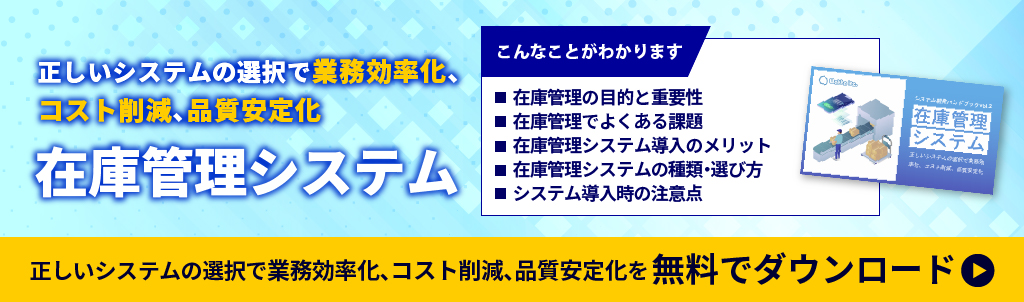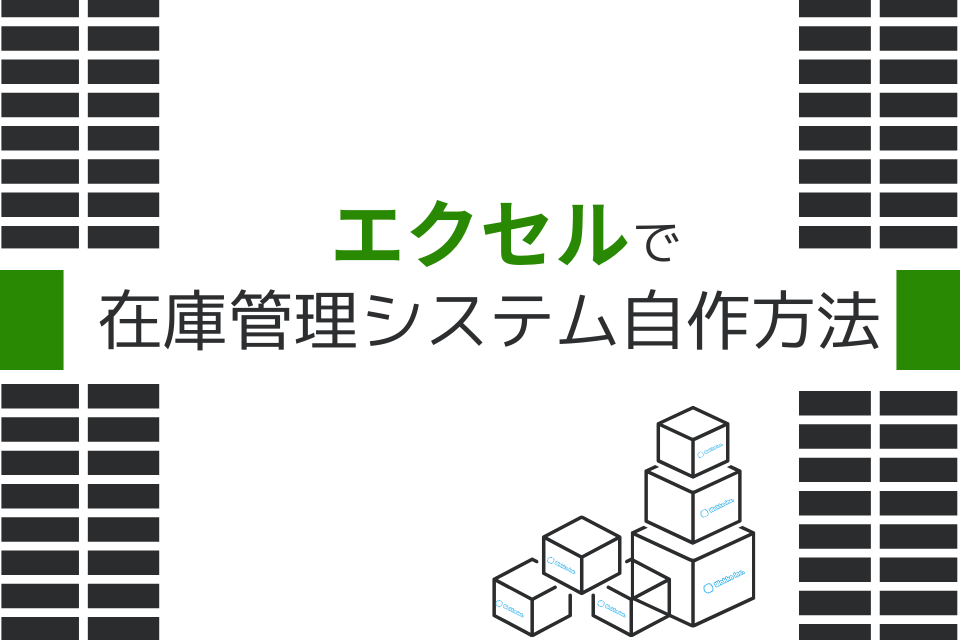商品管理システムを導入したい方は必見!種類と選び方を紹介

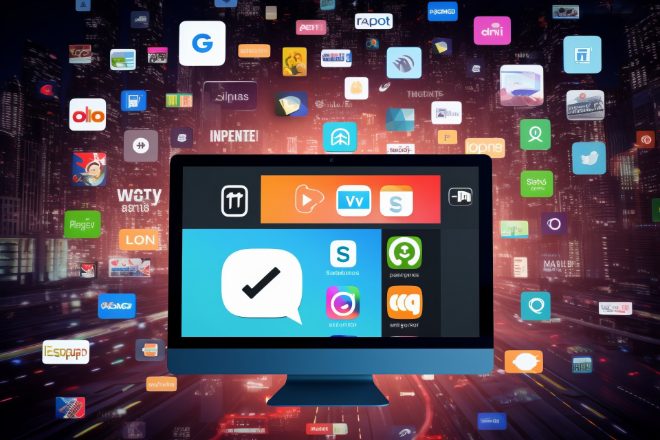
こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
商品管理システムは経営の中枢に関わるほど重要なツールです。
導入しているか、していないかでは業務効率やコスト削減などに差が生じます。
「商品管理システムを導入して、生産性を高め利益を増やしたい」
「商品管理システムの相場や選び方を知りたい」
とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では商品管理システムの種類と導入にかかる費用、選び方を解説します。商品システム選びの参考になれば幸いです。
「システム開発ハンドブックvol.2 在庫管理システム」では、商品管理を含む、コストと販売機会の効率化をはかるための在庫管理について、システムの選び方や導入時の注意点などを解説しています。ぜひ、あわせてご確認ください。
自社の在庫管理を最適化したい、在庫管理についてシステム化を計画している方
ぜひ下記の資料から最適なシステムの選び方もご確認ください。
コストと販売機会の効率化をはかるための在庫管理について、システムの選び方や導入時の注意点などを解説しています。
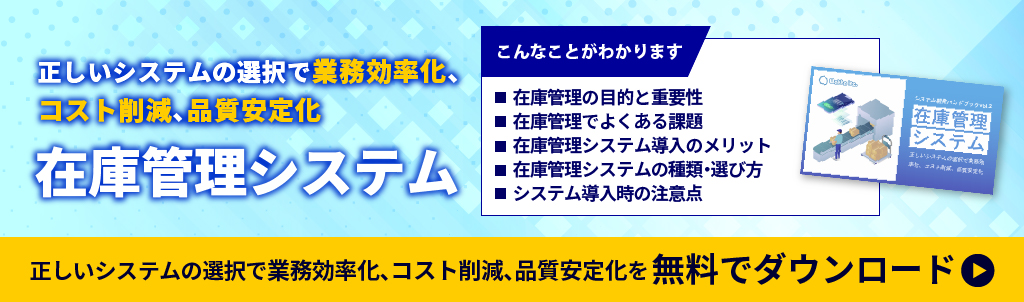
商品管理システムとは?

商品管理システムとは 商品の仕入れから販売完了まで物品の管理業務を一括で行うシステムのことです。
そのため経営の中枢として重要な位置付けとされています。
生産管理システムや顧客管理システム、倉庫管理システムなど他のシステムとの連携によって、より効率的な経営が実現できるのです。
商品管理業務は商品とお金の管理に分かれ、それぞれ以下に分類されます。
商品管理に分類されるもの
- 仕入れの管理
- 進を事務手続き管理
- 荷受
- 保管管理
お金の管理に分類されるもの
- 在庫管理
- 売上管理
- 棚卸し
これまでの商品管理は Excelが主流でしたが、販売が規模が拡大し商品数が増えた際に、管理が難しくなる背景から、商品管理システムが導入されているのです。
商品管理とお金の管理を統合し、可視化することで人為的ミス・商品不足・在庫過多などのミスを減らせます。
販売管理システムとの違い
実は商品管理システムが販売管理システムとも呼ばれているため、機能は似ていることがほとんどです。
違いを強いてあげるとするならば、販売管理システムは販売やお金の管理に重きを置いている点が特徴です。
いつ・誰に・何を・いくらで・いくつ販売し、支払いや入金がいつ発生するかなどを管理しているため、営業やマーケティングとの関連が強い側面があります。
一方、商品管理システムは、商品の選定や仕入れ管理など、商品の自体を管理する意味合いとして使われる場合があります。
在庫管理システムとの違い
在庫管理システムとの違いはカバーする業務範囲の違いです。
商品管理業務の大きな分類の中に在庫管理があります。
在庫管理システムは、製品の入出庫管理がメイン機能です。
機能としては以下があります。
- 在庫一覧
- 入出庫管理
- 検品
- 返品管理
- 棚卸し機能
上記の機能を活用し、販売前の資産を管理する役割があります。
商品管理システムは商品の入荷から販売までの全体を管理するのに対し、在庫管理システムは、商品の入出庫から販売準備までの一部を担います。
商品管理システムの主な搭載機能

商品管理システムは商品の仕入れから販売までを担うと説明しました。
具体的には次の機能が含まれます。
- 販売管理機能
- 購買管理機能
- 在庫管理・分析機能
上記の他にも、製品ごとに独自の機能を搭載しています。
自社の必要機能を明確にし、製品を選定しましょう。
販売管理機能
見積もりから売上・受注管理や請求管理まで対応する機能です。
商品の価格設定や数量を管理し、正確な見積もり作成を自動で行えます。
また、受注管理では受注した商品やサービスの情報を追跡し、在庫確認や納期管理を効率的にできます。
そして、受注情報を元に請求書の作成・売上管理・支払いの確認などを請求管理に関する業務も対応しているのです。
Excel・CSVへの出力や他のシステムからのデータ取り込みも可能です。
既存のデータをシステムに統合すれば、データ管理がスムーズにでき生産性も高まるでしょう。
在庫管理・分析機能
在庫管理は、入荷・出荷や棚卸しを行う機能です。
データと実在している物品の数が一致しているかどうかを把握するために使われます。
在庫分析機能は、在庫の数量や動向を把握するための機能です。
在庫の状況をリアルタイムに把握し、在庫の過不足や需要の増加を把握する役割があります。
この機能によって、在庫が過剰になったり足らなくなったりするのを防ぎ、業務コストを適切にコントロールできるのです。
購買管理機能
購買管理機能は、発注の管理から仕入や債務管理までを担う機能です。
発注が滞りなく行われているか、債権の回収漏れがないかを把握するために利用されます。
また債務にも漏れがないかも確認でき、債務不履行によって業務に悪影響を与える事象を防ぐ役割もあるのです。
経営リスクの把握や検知し回避するのにも役立つでしょう。
商品管理システムを導入するメリット
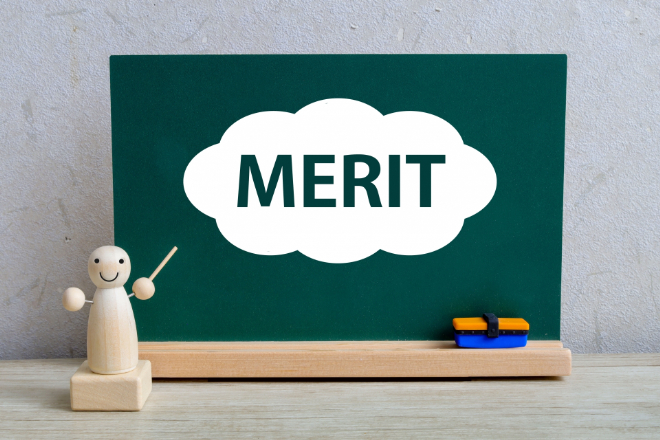
商品管理システムは前述したように、販売管理や在庫管理など複数の機能を備えているため、経営課題の改善につながるでしょう。
商品管理システムを導入すると、以下のメリットが得られます。
- 業務の正確性が向上する
- 複雑な業務を標準化できる
- 商品情報をリアルタイムで共有・確認できる
- 適正在庫の維持につながる
- コスト削減につながる
本章では、上記5つのメリットを紹介します。
業務の正確性が向上する
業種に限らず、自社の製品を販売している企業は商品管理が必ず発生します。
商品数や販売規模、取引先が増えると管理が難しくなり、作業ミスによる損失などリスクも増大するでしょう。
そのような状況の中、人が雑多な情報を整理し、正確に処理し続けることをするのは限界があります。
システムや機械なら、大量の商品データや取引情報の読み間違えや入力ミスがないため、正確に業務を行えるのです。
業務の正確性が向上すれば、入力の修正や見直しなどの時間も減り、効率化につながるでしょう。
複雑な業務を標準化できる
商品管理では複数の業務が連続的に発生します。
データを何度も確認したり、作業ツールを使い分けたりと業務が複雑になりがちです。
情報を整理するのが適切に把握し整理するのが難しく、業務マニュアルが機能しないケースも少なくありません。
システム化されていない業務は部署や担当者によって管理方法が異なるため、より複雑化しやすいです。
また特定の人しか業務が管理できなくなる属人化が発生し、効率が低下します。
ミスが起こりやすい業務を商品管理システムによって、人が行う作業を限定できるため業務フローを標準化できます。
商品情報をリアルタイムで共有・確認できる
商品情報をリアルタイムで共有・確認できることも、商品管理システムの導入によるメリットのひとつです。
商品の入出庫や在庫数・受注数などのデータが随時更新されます。
現在の商品情報を正確に把握できると、仕入れを増やすか減らすかなどの経営判断を瞬時に行えます。
また正確な情報が常に反映されていれば、販売戦略や計画の効果を検証するツールとしても役立つでしょう。
商品管理における無駄や無理を探し出して、取り除いて非効率な部分を改善できるのです。
適正在庫の維持につながる
商品在庫が過剰になったり不足したりするのは、以下が原因として挙げられます。
- 在庫管理リスクのサインを見逃してしまう
- 仕入数の見立てが適切に行えていない
- ヒューマンエラーによる発注ミス
商品管理システムには、在庫管理リスクを適切なタイミングで知らせる仕組みがあります。
商品管理システムを継続して使用すると、過去の売上データが蓄積されます。
過去の売上推移から在庫をどの程度仕入れると良いかや、急な発注により在庫が不足する恐れをシステムがアラートするため、在庫の過不足を未然に防げるのです。
また発注数の入力ミスをシステムや仕組みによって抑制できることが、適正在庫の維持につながります。
コスト削減につながる
商品管理において、非効率な作業や複雑な業務、在庫の過剰や欠品はコストを増大させる要因です。
実は、今まで解説してきたメリットはいずれもコスト削減につながります。
- 業務の正確さの向上は業務時間を短縮させ人件費の削減になる
- 複雑な業務の標準化は、ミスに起因の損失回避につながる
- 適切な商品の現状把握は、在庫の過不足をなくし、利益の最適化ができる
上記のように商品管理システムによって、コスト削減につながるのです。
また、商品管理システムは正確な情報が数字で現れるため、システム導入によってどの程度コストを削減できたかの確認もできます。
商品管理システムの種類と導入費用

商品管理システムを導入する際に、費用はシステムの種類によって左右されます。
システムの種類は大きく2つで、オンプレミス型とクラウド型に分類されます。
さらにそこから、オーダーメイド(フルスクラッチ)開発やパッケージソフトのように既製品をインストールするかなど、導入の方法によっても費用が異なるのです。
オンプレミス型
オンプレミス型は自社のシステムを構築する方法です。
自社でサーバーを設置し、構築・運用するためセキュリティ面でリスクが低いメリットがあります。
クラウド型のように開発側がサーバーやシステムを用意するのと違い、システムそのものを自社の業務に合わせてカスタマイズできるのが特徴です。さらに必要に応じて、機能を選べます。
しかし、システムを運用に必要なサーバー・通信環境を自社で用意するため、導入費用が高くなる傾向があります。
オンプレミス型でパッケージの導入した場合は、初期費用が数十万円〜数百万円、ランニングコストが月に数万円〜数十万円です。
フルスクラッチで外注する場合は、外注費が数百万円ほどします。
クラウド型
クラウド型は自社でサーバーを持たず、オンラインサーバーで提供されているサービスのことです。
開発ベンダーが、システムの設計から開発までを行うため、初期費用を安く抑えられます。
さらに社外アクセスが可能なシステムは、リモートで利用可能です。
また構築したサーバーに専用のシステムをインストールするなど、高度な専門知識が必要な作業がないため、初期設定の手間がなくスタートできるものが多いです。
しかし、オンプレミス型と比べるとカスタマイズ性や機能の拡張性が低いデメリットがあります。
クラウド型の導入費用は、初期費用が0円〜数十万円、ランニングコストが月に数千円〜数万円です。
自社の在庫管理を最適化したい、在庫管理についてシステム化を計画している方
ぜひ下記の資料から最適なシステムの選び方もご確認ください。
コストと販売機会の効率化をはかるための在庫管理について、システムの選び方や導入時の注意点などを解説しています。
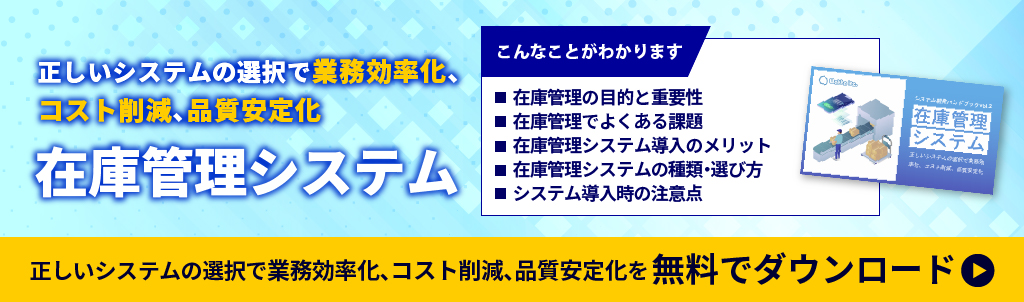
オンプレミス型・クラウド型商品管理システムの棲み分け
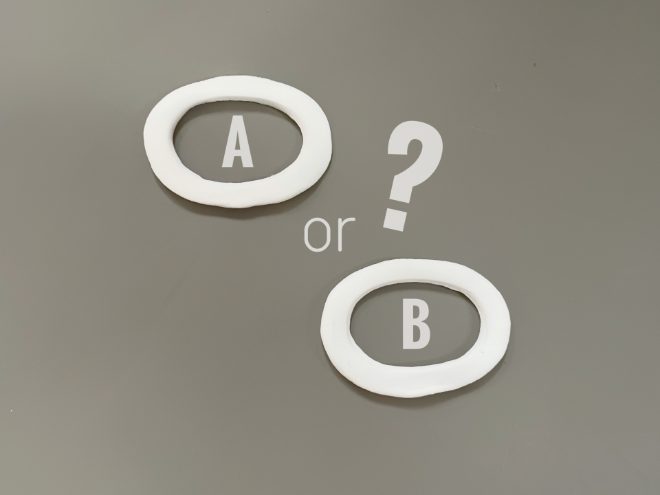
商品管理システムおいて、「オンプレミス型とクラウド型はどちらが自社に適しているのか?」と気になる方もいるでしょう。
両者はどのような企業に適しているか解説します。
オンプレミス型が適している企業
以下に当てはまる企業はオンプレミス型が適しています。
- 自社の業務に合ったオリジナルのシステムを導入したい
- 必要に応じてカスタマイズをしたい
- セキュリティを重視している
- システム運用管理を自社で行える
オンプレミス型は自社専用のサーバーを用意して、システムを運用するためシステムを運用する体制や環境が整っている、または整えられる企業が向いていると考えられます。
クラウド型が適している企業
クラウド型の導入は、次に当てはまる場合、適しています。
- 短期間で導入を進めたい
- 初期費用やランニングコストを抑えたい
- 保守やメンテナンスを外部に任せたい
クラウド型は、ベンダーがシステムを開発とメンテナンスをするため、導入コストを抑えたい企業が向いているでしょう。
オンプレミス型商品管理システムの開発ベンダーを選ぶ際のポイント
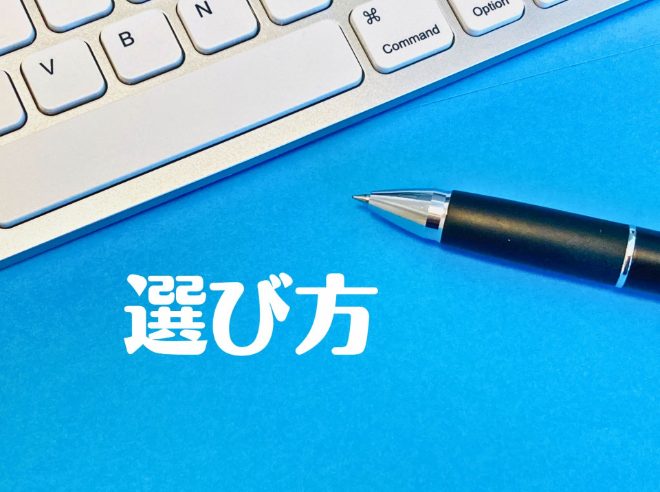
自社に適した開発ベンダーを選べるかは、商品管理システムの運用がうまくいくかに影響します。
オンプレミス型の商品管理システムを選ぶ際のポイントは次の通りです。
- 該当する業界で開発実績があるか
- 目的と課題を明確にして依頼内容を決める
- サポート体制が整っているか
- 複数社から見積もりをもらう
順番に解説します。
該当する業界で開発実績があるか
ベンダーが自社と同じ業種でシステムの開発実績があるかは、ベンダーを選ぶうえで重要です。
開発実績がない、得意分野が違う場合は完成品のクオリティが低かったり、想定外のものができたりする恐れがあります。
希望する商品管理システムに精通している場合、開発もスムーズに進むでしょう。
ベンダーを選ぶ際に得意分野や実績、開発言語などを調べておくことをおすすめします。
目的と課題を明確にして依頼内容を決める
ベンダーを選ぶ際には、商品管理システムを導入する目的と課題を明確にしましょう。
目的が不明確だとベンダーに意図が伝わらず、自社の業務に適していないものができてしまいます。
自社に合わないシステムを導入してしまうと、機能を十分に活用しきれず、導入自体が失敗につながる恐れがあるため、注意が必要です。
さらに目的が不明確の場合、開発の要件が定まりにくく納期が伸び、システムの導入タイミングに影響します。
また、依頼内容を決めるためには必要な機能の洗い出しが大切です。
目的や課題に対してどのような機能を実装すべきか、機能を1つひとつ洗い出し要件を定めましょう。
サポート体制が整っているか
商品管理システムの導入時には、管理や運用においてサポート体制が整っているかの確認をします。
特にオンプレミス型は、自社でサーバーを構築し運用するため、システムの運用や保守に関して専門知識が必要になるからです。
例えばオンプレミス型の商品管理システムは、開発後の運用や管理・メンテナンスを自社で行います。
たとえシステムがいかに優れていても十分に使いこなせなかったら、システム導入の効果が得られません。
したがってシステムを使いこなせるよう、サポートが必要です。
導入までの準備から、運用後の問題解決まで伴奏しながらサポートしてくれるベンダーはサービスの質が高い傾向があります。
サポート対応は内容によって有料の場合があるため、サポートの対応範囲も把握しておきましょう。
複数社から見積もりをもらう
商品管理システムは複数社から見積もりを依頼すると、予算にあったベンダーを見つけられます。
見積もりを依頼する会社が多いと、かえって比較が困難になるため、まずは3〜4社に絞り込むと良いでしょう。
ただ、ベンダーを選ぶ際は、価格のみならず実績やサポートサービスも考慮することが大切です。
価格が高くても、サポートが充実していたり、自社の要望を親身に聞きシステムに反映してくれたりするケースがあるためです。
そのため、価格を比較したうえで、提案依頼書を送り実際にコミュニケーションを取りながら判断するのが効果的です。
クラウド型商品管理システムの比較基準

クラウド型商品管理システムは種類が多く、どのシステムにするか簡単に決められないでしょう。
選定の際に、比較基準が明確にあると選びやすいです。
クラウド型商品管理システムの比較基準は以下の3つを参考にすると良いです。
- 自社の業務フローに適している
- 費用対効果が優れている
- 外部システムとの連携や拡張性を確認する
それぞれ順に解説します。
自社の業務フローに適している
商品管理システムは、さまざまな種類がありそれぞれ特徴や得意なものが異なります。
そのため自社の業務フローと適しているかがポイントになります。
例えば製造小売業の場合は、店頭と店舗倉庫の在庫管理、商品の入出庫、売上分析などの機能が必要です。
しかし業務フローとシステム機能がマッチしていないと、導入後に機能の追加などが発生し、余計なコストが発生してしまいます。
可能な限り業種に特化したシステムを選びましょう。
また自社の業種に特化したシステムがない場合、幅広い業界に対応している汎用タイプのシステムを利用するのも有効です。
費用対効果が優れている
クラウド型はシステムの導入費用が比較的抑えられます。
しかし、価格が安くても操作が難しく、トレーニングに時間がかかっては費用対効果が悪いです。
反対に、価格が高くても、ERPのように業務システムを統合して、全社管理ができれば費用対効果は高いです。
自社が商品管理システムを導入する目的が達成できるかが、費用対効果を判断するうえで重要なポイントといえます。
機能面だけでなく、サービスの充実さなどを確認して、総合的に見て判断すると良いでしょう。
外部システムとの連携や拡張性を確認する
クラウド型の商品管理システムは、機能の拡張性やカスタマイズ性が低いです。
そのため導入後に他のシステムとの連携ができると、機能を拡張でき、より使いやすくなります。
例えば商品管理システムに外部の連絡ツールやデータベースツール、AIの業務支援ツールなどと連携できると、業務の効率も向上するでしょう。
トライアルを実施して事前に試しておく
商品管理システムの機能が自社の業務フローと適しているとわかっても、実際に導入し業務で運用してみないと、本当に適しているかはわからない面もあります。
クラウド型のシステムは、一定期間であれば無料のものや機能制限付きで試せるものがあります。
システムを導入して得られる効果や業務フローの課題などを確認可能です。
無料プランで使えるか、一部の機能を利用できるかを公式サイトなどで確認し、テストで導入してみましょう。
商品管理システムを導入する前に準備すること

商品管理システムを導入し、成果を出すための環境を整えるには、準備が欠かせません。
事前準備をせずにシステムを導入しても、成果が出にくいです。
商品管理システムを導入する前に準備することは次の通りです。
- 業務フロー・課題の洗い出し
- 導入後の業務内容の変化を想定する
- 現場の従業員からも意見を収集しておく
業務フロー・課題の洗い出し
業務フロー・課題の洗い出しをしておくと、必要な機能は何か考えられます。
例えば「商品管理システムによって解決したい課題は何か?」「商品管理においてボトルネックになっているものはないか?」など1つひとつ検討します。
機能が決まれば、それに合ったシステムを絞れます。
システムの選定前に自社の業務フローや課題を洗い出しましょう。
導入後の業務内容の変化を想定する
商品管理システムを導入すると、業務が標準化されたり、簡略化されたりできるため業務内容が変化します。
業務の変化を想定できていないと、導入後に作業の動きを統率が取れず、かえって業務でミスが発生することも少なくありません。
どのように業務が変化するのか、業務の順番に変更はないかなど確認し、マニュアル化して従業員に共有すると良いでしょう。
また導入後の業務内容をシミュレーションする時間を設けると、商品管理システムを活用した業務が浸透しやすいです。
現場の従業員からも意見を収集しておく
システム導入前に現場の従業員からも意見を収集しておきましょう。
経営層やシステム導入担当者のみの意見で、システムの機能や業務フローを決めてしまうと、現場の従業員が困惑する恐れがあります。
現場が抱えている課題と経営層の考えに差異が生じるからです。
本格導入する前に、現場の課題を収集し、業務フローを変更する際に参考にして改善しましょう。
現場との差異をなくすと、システム導入後もスムーズに導入が進み、業務効率もあげられます。
自社の要件を明確にして商品管理システムを検討しよう

商品管理システムを導入すると、業務の正確性が向上し商品情報をリアルタイムに更新できるため、業務の効率や生産性が高まります。
システムを選定する際は、導入目的・自社の課題や機能、導入後の業務内容を明確にするなどの準備が不可欠です。
上記が不明確のためシステム要件が定まらないと、開発に着手できず導入までの時間も遅くなってしまいます。
またシステムの導入コストは、システムの種類によって異なるため、複数社に見積もりを依頼し、開発実績があり信頼できる企業を選びましょう。
自社の在庫管理を最適化したい、在庫管理についてシステム化を計画している方
ぜひ下記の資料から最適なシステムの選び方もご確認ください。
コストと販売機会の効率化をはかるための在庫管理について、システムの選び方や導入時の注意点などを解説しています。