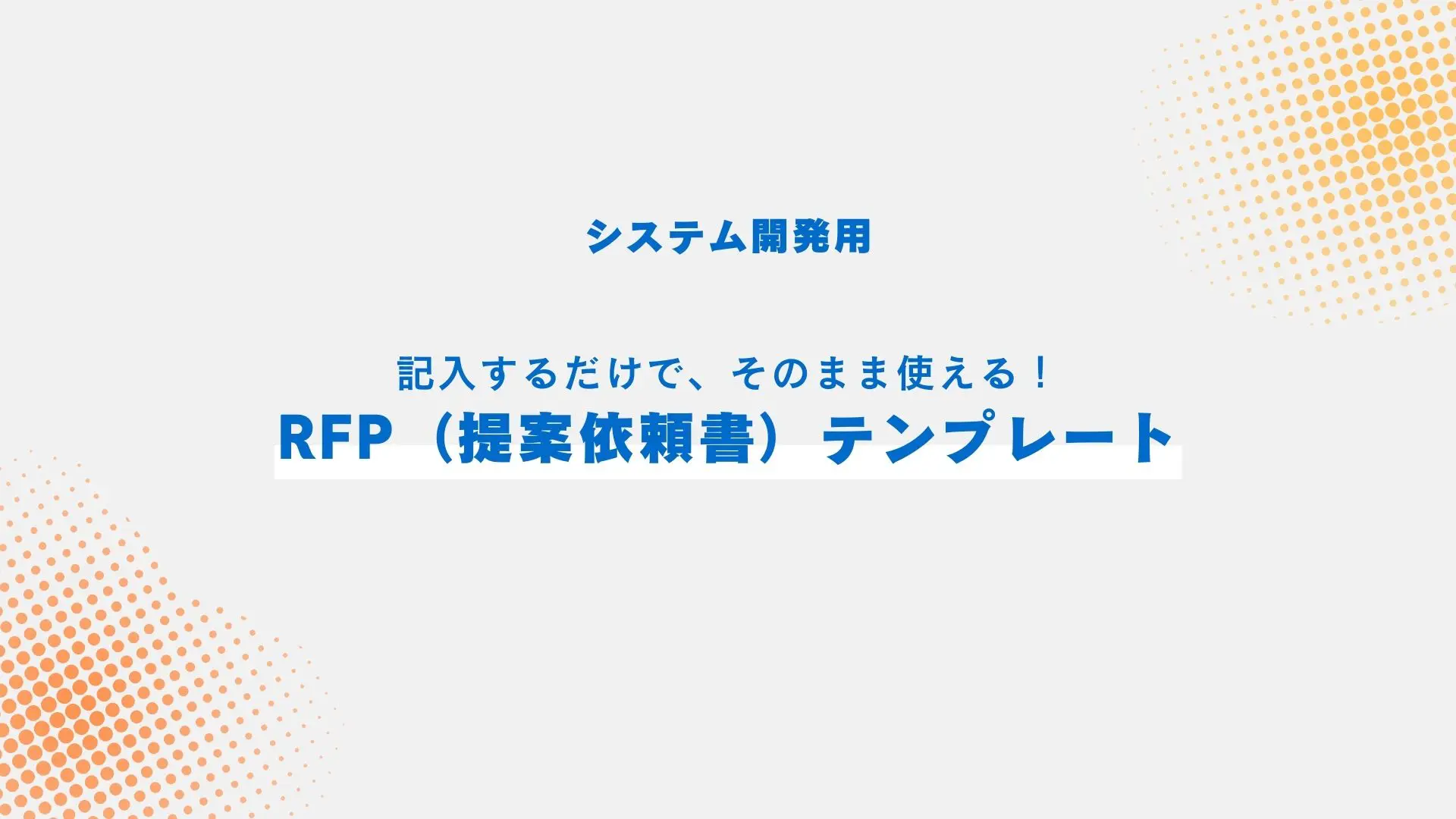イテレーションとは?スプリントとの違い・メリット・進め方を解説


こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。
「会議でイテレーションって言葉を聞いたけど、実はよく分かっていない」
「スプリントと何が違うのか、具体的に説明できない」
アジャイル開発のプロジェクトに参加し始めた方の中には、こうした悩みを持った人もいるかと思います。
専門用語の定義が曖昧だと、チーム内でのコミュニケーションに不安を感じてしまうこともあるでしょう。
本記事では、イテレーションの基本的な意味から、よく混同されるスプリントとの明確な違いを解説します。
また、具体的な進め方からメリットまで紹介するので、ぜひ参考にしてみください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
そもそもイテレーションとは
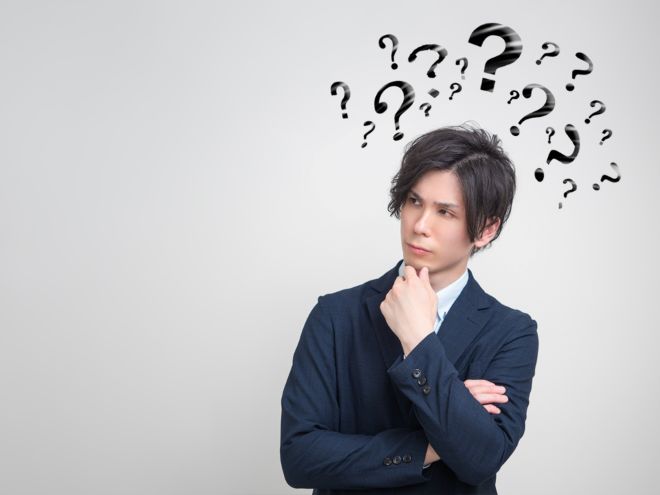
イテレーションとは、ソフトウェア開発などで用いられる反復的な開発サイクルのことです。
具体的には、(計画→設計→開発→テスト)といった一連の工程を、1~4週間程度の短い期間で区切って繰り返します。
この短いサイクルを何度も回すことで、少しずつ製品やサービスを作り上げていくのが特徴です。
大きな計画を一度に実行するのではなく、小さな単位で開発と改善を重ねることで、変化に柔軟に対応しながら質の高いプロダクトを生み出すことを目指します。
特に、アジャイル開発の考え方において、イテレーションは中心的な役割を担っています。
イテレーションとスプリントの違いとは

(イテレーション)と(スプリント)は、どちらも反復的な開発サイクルを指すため混同されがちですが、使われる文脈やニュアンスが異なります。
まず、両者の違いを以下の表で確認してみましょう。
※表は、横にスクロールできます
| 特徴 | イテレーション | スプリント |
|---|---|---|
| スコープ | アジャイル開発全般で使われる広範な概念 | スクラム開発フレームワークに特有の用語 |
| 目的 | 反復を通じて継続的に改善すること | 固定期間内に特定の目標を達成すること |
| 実装 | プロジェクトに応じて柔軟に調整可能 | スクラムのルールに厳密に従う必要がある |
イテレーションは、ソフトウェア開発などのプロジェクトにおいて、一定期間繰り返される作業サイクル全般を指す広い概念です。
計画・設計・開発・テスト・レビューといった活動が行われ、成果物が少しずつ完成していきます。
重要なのは、反復する考え方そのものです。
どのような手法を用いるか、期間をどの程度にするかなどは、プロジェクトによって柔軟に決定されます。
一方、スプリントはアジャイル開発手法の一つである「スクラム」で用いられる、特定のルールを持ったイテレーションです。
スプリントは、通常1~4週間の固定された期間で実施され、スプリントゴールと呼ばれる目標を設定し集中的に作業を行います。
毎日デイリースクラムと呼ばれる短いミーティングを行い進捗を確認したり、スプリントレビューで成果物を関係者に見せたりすることが特徴です。
また、スプリントレトロスペクティブで改善点を見つけたりするなど、スクラム特有のイベントが定義されています。
つまり、スプリントはイテレーションの一種であると言えます。
アジャイル開発におけるイテレーションの役割

イテレーションの考え方は、さまざまなアジャイル開発手法の根幹にあります。
しかし、開発手法によって、イテレーションの捉え方や呼び方、実践方法は少しずつ異なります。
本章では代表的な3つの手法である「スクラム」「エクストリーム・プログラミング(XP)」「カンバン」における、イテレーションの役割を見ていきましょう。
※表は、横にスクロールできます
| 開発手法 | イテレーションの名称 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| スクラム | スプリント | 1〜4週間 | 固定期間で、計画されたタスクの完了を目指す |
| XP | イテレーション | 1〜2週間 | 品質向上のための技術的プラクティスを重視する |
| カンバン | (明確な名称は存在しない) | 継続的 | 固定期間を設けず、タスクの流れを止めない |
スクラム開発
スクラム開発では、イテレーションのことを「スプリント」と呼びます。
スプリントは、1〜4週間の固定された期間内に明確なゴールを設定し、それを達成することが目的です。
スプリントの開始時にはスプリントプランニングで計画を立て、期間中はデイリースクラムで日々の進捗を確認します。
そして、スプリントの終わりにはスプリントレビューで成果物を評価し、スプリントレトロスペクティブ(振り返り)で仕事の進め方を改善します。
このように、スプリントは厳密なルールと一連のイベントがセットになった、規律ある反復開発サイクルです。
エクストリーム・プログラミング(XP)
エクストリーム・プログラミング(XP)でも、反復開発の単位として「イテレーション」の言葉が使われます。
XPのイテレーションは、スクラムのスプリントよりも短い1〜2週間で設定されることが一般的です。
ペアプログラミングやテスト駆動開発(TDD)といった、高品質なソフトウェアを作るための技術的な実践(プラクティス)と密接に結びついています。
XPにおけるイテレーションは、単なる反復ではなく、コード品質の継続的な向上を重視したサイクルです。
カンバン
カンバンは、スクラムやXPとは異なり、スプリントのような固定期間のイテレーションを明確には設けません。
目的は、作業の停滞を防ぎ、タスクの流れ(フロー)をスムーズに保つことです。
まず、カンバンボードで作業状況を可視化し、仕掛中の作業数を「WIP制限」によって管理します。
そして、リードタイム(タスクの開始から完了までの時間)などを計測しながら、継続的にプロセスの改善を行います。
固定期間で区切るのではなく、絶え間なく改善を繰り返すといった点では、カンバンもまた反復的なアプローチの一種とも言えるのです。
イテレーションの流れ

実際に「イテレーションを回す」とは、どのような手順で進めるのでしょうか。
本章では、一般的なイテレーションの進め方を4つのステップに分けて解説します。
以下の流れを理解すれば、あなたのプロジェクトでも具体的なアクションをイメージしやすくなるはずです。
ステップ1:計画(イテレーションプランニング)
まず、イテレーションの開始時にチーム全員で集まり、計画を立てます。
計画会議では、主に以下の3点を決定します。
※表は、横にスクロールできます
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 期間 | 今回のイテレーションを何週間で行うか(例:2週間) |
| 目標 | 今回のイテレーションで何を達成するのか(例:ユーザーログイン機能を実装する) |
| スコープ | 目標達成のために、具体的にどのようなタスクに取り組むか |
計画会議で重要なのは、チーム全員が納得し、合意した上で計画を立てることです。
そうすることで、チームは同じ方向を向いてイテレーションをスタートできます。
ステップ2:開発・設計・テスト
計画が決まったら、実際に開発作業に取り掛かります。
イテレーションの期間内には、設計やプログラミング、そしてテストまで一連の開発工程を行います。
ウォーターフォール開発のように工程を完全に分けるのではなく、小さなサイクル内ですべての工程を完了させることが特徴です。
期間中は、デイリースクラム(朝会など)を毎日行い、チーム内で進捗や課題を共有しながら作業を進めます。
ステップ3:レビュー
イテレーションの最終日には、レビュー会議を行います。
レビュー会議の目的は、完成した成果物(動作するソフトウェアなど)を、顧客やプロダクトオーナーなどのステークホルダーにデモンストレーションすることです。
実際に動作する成果物を提示し、具体的なフィードバックを受け取ります。
具体的に得たフィードバックは非常に重要で、次のイテレーションの計画に活かされます。
「イテレーションレビュー」と呼ばれる言葉は、以上の会議を指します。
ステップ4:振り返り(レトロスペクティブ)
レビュー終了後、開発チームだけで集まり、今回のイテレーションそのものを振り返りましょう。
こういった振り返りの会議を「レトロスペクティブ」と呼びます。
レトロスペクティブでは、成果物の中身ではなく、仕事の進め方に焦点を当てます。
※表は、横にスクロールできます
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 良かった点(Keep) | 次も続けたいこと |
| 問題点(Problem) | うまくいかなかったこと |
| 次に試すこと(Try) | 次のイテレーションで改善したいこと |
などを話し合い、チームとして継続的に成長していくことを目指します。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、
イテレーション開発のもたらす6つのメリット

なぜ、多くの開発現場でイテレーションの手法が採用されているのでしょうか。
理由は、プロジェクトを成功に導くための多くのメリットがあるからです。
「手戻りを減らして生産性を上げたい」「顧客に本当に喜ばれるものを作りたい」といった、現場の切実な願いに応える力がイテレーションにはあります。
本章では、イテレーションがもたらす6つの具体的なメリットを解説します。
品質の向上につながる
イテレーションは、短いサイクルごとにテストとレビューを繰り返す開発プロセスです。
こうしたプロセスによって、バグや仕様の認識違いといった問題点を開発の初期段階から継続的に発見し、速やかに修正できるようになります。
最終段階で大量の問題が発覚するのに比べ、小さな問題を解決していくことで、開発プロセス全体をスムーズに進められます。
結果として、プロダクトの安定性や使いやすさなど、最終的な品質が格段に向上するのです。
また、チーム全体の知見が蓄積されることで、次回以降の開発に役立つメリットもあります。
早い段階で問題が発見できる
ソフトウェア開発やプロジェクト運営において、問題の早期発見は非常に重要です。
品質の向上と関連しますが、イテレーションは技術的なバグだけでなく、さまざまな問題を早期に発見する機会を提供します。
例えば開発の進め方に関する非効率な点や、チーム内のコミュニケーション不足といった課題も、定期的な振り返りを通じて明らかにできます。
また、レビューでステークホルダーから「思っていたものと違う」といったフィードバックがあれば、プロジェクトの方向性を修正する絶好のチャンスです。
大きな手戻りになる前に、早い段階で軌道修正できるのは大きなメリットです。
顧客の要望に対し迅速に対応できる
ビジネス環境や市場のニーズは、常に変化するものです。
そのため、数か月〜1年単位の長期計画では、完成した頃には顧客のニーズが変化していることも少なくありません。
イテレーション開発では、短いサイクルで顧客からフィードバックを得るため、仕様変更や新たな要望にも柔軟かつ迅速に対応できます。
常に最新の顧客ニーズを製品に反映し続けられるため、顧客満足度の高いプロダクト開発が可能です。
このようなプロセスによって、開発全体の効率を格段に向上させられます。
開発メンバーが成長する
イテレーションは、開発メンバーの成長を促す仕組みでもあります。
特に「レトロスペクティブ(振り返り)」のプロセスは、チームにとって重要な学習の機会です。
レトロスペクティブでは、各イテレーションで何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかをチーム全体で深く掘り下げます。
チーム自身でうまくいかなかった原因を分析し、主体的に改善策を考え、実行するサイクルを繰り返すことで、個々のスキルだけでなくチーム全体の課題解決能力が向上します。
変化の激しい現代において、こういった自律的なチームは、プロジェクトを達成する上でも重要な資産です。
こうした継続的な改善こそが、プロダクトの長期的な成長を支える基盤と言えます。
手戻りリスクが軽減する
従来のウォーターフォール開発では、全工程が完了した最終段階で大きな仕様変更や問題が発覚し、大規模な手戻りが発生するリスクがありました。
手戻りは、スケジュール遅延やコスト増大の大きな原因です。
また、一つの問題が他の要素に連鎖的に影響を及ぼし、全体を巻き込む事態に発展する可能性もあります。
イテレーション開発では、たとえ問題が起きても、基本的に影響範囲は各イテレーション内に限定されます。
そのため、問題の連鎖を防ぎ、小さな単位で検証と修正を繰り返せることが大きな利点です。
結果として、プロジェクト全体を揺るがすような致命的な手戻りのリスクを大幅に軽減できるのです。
開発スピードが向上する
手戻りが減り、チームが継続的に学習・改善していくことで、無駄な作業が減り開発プロセス全体が洗練されていきます。
また、常に優先度の高い機能から開発に着手するため、ビジネスにとって価値のある成果をより早く市場に届けられます。
加えて、定期的なレビューや振り返りを通じて、潜在的なリスクや問題点も早期に把握できるのです。
結果として、チームは柔軟かつ効率的に課題に対応でき、プロジェクト全体の品質と安定性が向上します。
一見すると、計画や会議が多いように感じるかもしれませんが、長期的に見るとプロジェクト全体の開発スピードを大幅に早める効果があります。
イテレーションを成功させるためのポイント4つ

イテレーションは強力な手法ですが、単にサイクルを繰り返すだけでは、うまく機能しません。
効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。
本章では、イテレーションを効果的に活用するための重要な4つのポイントをご紹介します。
明確なゴールを設定する
それぞれのイテレーションでゴールが曖昧なままでは、チームはどこに向かって進めば良いのか分からず、作業が迷走してしまいます。
イテレーションプランニングの段階で、「ユーザーが〇〇できるようになる」といった具体的なゴールをチーム全員で共有することが重要です。
さらに、ゴールが明確であれば、進捗の確認や軌道修正も迅速に行えます。
また、ゴールに基づいた判断によって不要な作業や手戻りを減らし、開発効率を高められます。
明確なゴールがあることで、チームは集中力を維持でき、優先順位も判断しやすくなるのです。
チーム内のコミュニケーションを定期的に行う
イテレーションはチームで行う活動です。
メンバー間の認識のズレは、致命的な手戻りや遅延につながります。
デイリースクラム(朝会)のような短いミーティングを毎日実施して進捗や課題を共有したり、Slackなどのチャットツールを活用して気軽に相談できる環境整備などが重要です。
密なコミュニケーションこそが、問題を早期に発見し、チーム一丸となって解決するための鍵です。
こうした取り組みを継続することで、チーム全体の生産性と開発品質が向上します。
さらに、メンバー間で知見や改善策を共有することで、次のイテレーションにも高い効果をもたらします。
振り返りを必ず実施する
多忙なプロジェクトでは、つい振り返り(レトロスペクティブ)の時間が疎かになりがちです。
しかし、プロセスを改善する機会を失うと、チームの成長が止まってしまう恐れがあります。
うまくいかなかったことだけでなく、うまくいったことも共有し、チームの良かった点をさらに伸ばしていく視点も大切です。
形式的な報告会で終わらせず、チーム全員が本音で話し合える安全な場として、振り返りの時間を必ず確保しましょう。
振り返りの結果を次のイテレーションに反映することで、改善が具体的な成果につながります。
また、チーム全員が意見を出し合う文化を育むことで、協力体制が強化され問題解決のスピードも向上します。
作業を自動化する
テストやソフトウェアビルド、サーバーへのデプロイなど、開発プロセスには手動で行うと時間のかかる定型作業が多く存在します。
こういった作業をできる限り自動化することで、ヒューマンエラーを減らし、開発のスピードと品質を向上させられます。
自動化によって生まれた時間は、チームがより創造的で本質的な開発作業に集中する時間となるのです。
継続的インテグレーション(CI)や継続的デリバリー(CD)といった仕組みの導入は、イテレーションを成功させる上で非常に効果的です。
こうした開発プロセスの自動化は、チーム全体の効率と品質向上に大きく直結します。
まとめ:イテレーションを理解して、自信をもってプロジェクト推進を

本記事では、イテレーションの基本的な意味からスプリントとの違い、具体的な進め方やメリットまでを解説しました。
イテレーションとは、短い期間で「計画」「開発」「レビュー」「振り返り」を繰り返す開発サイクルです。
また、変化に柔軟に対応し、継続的に価値を生み出すための、アジャイルな働き方の中核をなす重要な概念です。
今回ご紹介した内容を理解し、あなたのプロジェクトで実践することで、チーム内のコミュニケーションがより円滑になり、プロジェクトを自信を持って推進できるようになるでしょう。
ぜひ、次のチームミーティングから、イテレーションの考え方を活かしてみてください。
WaGAZINE読者さま限定!
【無料】そのまま使える
システム開発の流れを知りたい方や、